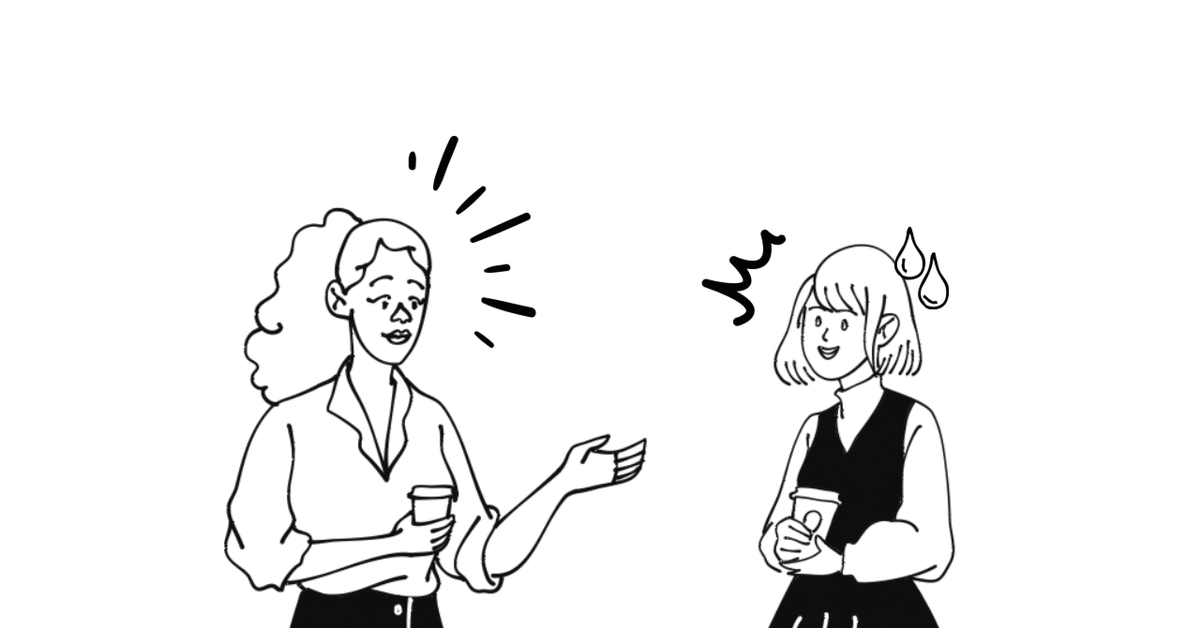
監査をコミュニケーションとして考えてみようという話
昨今では、ベンチャー企業で活躍する会計士の姿なども多くアッピルされるようになり、働き方改革や情報処理テクノロジーの導入など、実態はともかくとして良さそうなニュースがあるにも関わらず、監査法人はどうもあまり人気がないように感じる。この時期は、逃亡者のうわさに事欠かないので余計である。
しかし、監査という仕事はとても大事な仕事なので、おれとしてはBig4マンには(じゃなくてもだが)まだまだ頑張ってもらいたいと思っている。まあ、おれはとっくに監査法人からはいなくなっているので大きなことは言えないのだが、大手にいるとなかなか気づかない(であろう)監査の効果とか、それをうまく効かせるにはどうしたらいいかとか、そういうことについて、おれの思うところを書いてみようと思う。
監査とかがないとどういうことが起こるか
大手のスタッフとかが疑問に思うことのひとつに、「どうせたいていあってるような帳簿とか、死ぬほど見てもやっぱりどうせあってるし、なにやってるかわからない。それで、減損とか評価損とかは、なんかエライやつが会社とニギって怪しげな理屈で怪しげな処理を容認してたりして意味わからない。」といったようなことがあるだろう。これはおれの偏見だ。たぶん、昨今では後者みたいなことも、あまりないのかも知れない。
特に、おれが問題だと思うのは、売上高というものは、通常、会社にとってもすごく重要なので、まともな会社であれば、そうそうおかしなことは無く、要するに、死ぬまでバウチングしても、疲れるだけで、これと言って得ることが無いのが通常であるのに、なんか千本ノックみたいなことが実施されているとかそういうまことしやかな話をちらほら聞くことだ。
なんかとにかくやらねばならぬとかそういったマインドで、ひたすら沢山調書に書くこと、が目的化してしまって、かえって大事なことを見逃したりとか、そういうことが起こっているような気もしなくもないが、おれが話したいのは、そういうレベルのことですらない。
監査がない世界というものは、シャバで仕事を始めると死ぬほど目にするようになると思っているのだが、一部のごく善良な人を除いて、粉飾!脱税!投資詐欺!それまではいかないでも、税金優先で期間損益とかそっちのけ、カネを引っ張ろうと思って、背伸びし放題、といったようなことだらけだ。いわばアフター核戦争の荒野で、人の決算書とか信じたやつからまず死ぬ。そういった世界だ。
とりあえず、売上が欲しいやつは、
ソフトウェア/売上
とか、平気で仕訳してくるし、
なんか純資産がヤバいやつは、
のれん/資本金
とかも楽勝で計上してくる。
納税資金まで飲んでしまったやつは、なんでも前受金にしてくる。
まあなんかこの辺の処理は、上場会社でもそこそこあったような気もしなくもないが、そこは置いておこう。要するに、人はほっておくとものすごい勢いで粉飾をするというか、投資家から金を巻き上げる立場のやつを、自由にさせておくと、世界中の金がどぶに捨てられることになる(どぶはどぶで潤うのかもしれないが)というか。つまり、世の中には、バレなければ平気でインチキをするような奴は、めちゃくちゃたくさんいるのだ。
きっと監査論とかで習ったことだと思うが、嘘つきと付き合うのは結構大変で、いちいち、どれが嘘でどれが嘘でないか検証しないといけなくなる。大変なコストをかけないと、何が本当かわからないというようなことでは、実際問題人とは付き合えない。ものすごく面倒なことになる。
監査とかのあるこの素晴らしい世界
ところが、世の中には、監査とかいうナイスなものがある。世間じゃ、CEOの別荘が投資案件で云々みたいな難しい話とか、アメリカの原子力の会社の評価がどうとかそういう話もあって、なんか監査とかやってもしょうがないんじゃない?みたいな雰囲気も感じなくもないが、それは完全に甘いと断定できる。
監査があるから、あの程度で済んでいるのだ。経済事件で被害を被った善良な投資家からすると、あの程度とはなんだ!?という話になるかもしれないが、安心してほしい。おれも、事件発覚の前日に、ナントカ芝の株を買って、一夜で損切りせざるを得なくなった人間の一人だ。
そんなおれが言うんだから信じて欲しい。監査がないともっとひどいことになる。あと、ノーポジションと言う投資スタイルを甘く見るな、おれみたいに何かに突っ込んでないと気が済まないやつは、結局投資には向かない。
監査があるとどういうことになるかと言うと、まず稚拙な粉飾とかはあっという間に見つかって「ちょっと、これ。。。」みたいにされるハメになる。会社としては自分が嘘つきだとバレるみたいなのは相当バツが悪い。さらに、ちょっと意見がでませんみたいなことが明るみに出て、あそこの会社はちょっと自由すぎてヤバいんじゃないか、とか噂でもたてられようもんなら、あっという間にカネは引いていくだろう。なので、基本的に普通のやつはあまりインチキとかしないで済まそう、と考えるようになる。
そういう意味では、まず、まともな監査法人と契約している時点で、本来は発生していたであろう粉飾のザっと8割はすでに防止されている。これが大変な効果だ。誰が何と言おうと、その効果をおれは確信している。ただ、契約しても一日も帳簿をめくりに来ないとかであると、残念ながら、この効果はあまり得られない。それが次の話だ。
監査らしきことがなされるという警戒感
仮におまえが監査部屋で一日中youtubeとかしているような人種であったとしても、「ワンチャン、暇つぶしに帳簿とか見るかもしれない」と客に思わせた時点で、おまえは相当社会に貢献しているといえる。自信を持っていい。
悪事というのは、見つかるかもしれない、という意識があれば、相当抑止される。ただ、それには実際に摘発されるかもしれない、ということと、摘発されたら結構ダメージがデカい、ということが必要だ。
摘発された場合のダメージは、昨今何でも炎上する世の中なので、企業は当然警戒している。警戒しないやつはいずれ滅びるので、数に入れる必要はない。
ただ、見つかるかもしれない、と思わせることができるかどうか、という点はとても重要なので、よくよく考えてみる必要がある。
キレるやつとそうでもないやつ
今や古き良き監査ということになっているのだとしたら、若干悲しいことではあるが、監査人にはセンスの良し悪しとでもいう他ないものが相当ある。もう少し、学問的に追求すればセンスという言葉では済まされないものがあるのかも知れないが、おれは少なくとも「監査人のセンスの正体についての一考察」というような論文はみたことが無いので、たぶんあんまり研究されていないのだろうし、少なくとも有名ではなかろう。よって、ここではセンスと言っておく。
センスがある監査人は、会社にとって痛いところを必ず見てくる。おれならここでインチキをするなとかそういう鼻が利くやつはヤバい。バカなら何とかしようがあるが、それが賢いやつだと完全にお手上げだ。適当な説明とかしようもんなら一発でやられる。
件数をたくさん見るやつより、そういう一撃で会社の体質とか、特定のやんちゃな営業部門の体質とか、ガラの悪い取引先とか、社長の息子の道楽とか、そういうところに迫ってくるやつのほうが怖い。経理とかの管理部門もすべてをコントロールできているわけではないので、うすうす「あの部署の数字はちょっとアレだな。。。」とか思ってたりもするので、そういうところを突かれると、たとえその時は何もなくても、「アレちょっとちゃんとしとかないとヤベえな。」という気持ちになる。
こういうイケてるやつらは周到にプランニングとかリスク分析とかされてなくても、フラっと現れた現場で、会社がどういう商売をしているかとかちょっと聞いて、どういうところと取引をしているかとかみた時点で、大方どういう会社かわかってしまい、なんか雑談とかしていると思ったら、根本的に処理がアヤシイところとかを見つけてくる。また、話しても明らかに頭がいいのがわかると、別に大してクリティカルなポイントを見ていなくても、会社側は相当な警戒感を持つことになる。
一方、そうでもないやつはどういうのかというと、まず指定してくるサンプルにセンスがない。いやまあ、昨今ランダムにサンプリングしてとか、そういうのが盛り込まれているのはわからなくもない。しかし、どう考えてみても、大したことが起こりそうにないところとか、絶対に金額がヤバい事にならないところとかに、相当な時間を費やされると(おれは、銀行手数料のエビデンスを探して持って来いと言われたことがある)、ああ、こいつは中身を見ねえ奴だな、という気持ちになるのは仕方がないことだ。おれは、監査対応のバイトもよくやっているので、そのあたりはスゴイ感じる。
あと、何かを深掘りし始めるのは良いが、そのテーマ選びに絶望的にセンスがないやつも似たようなジャンルだ。ただ、ランダムにサンプリングするとか、あまり打率が高いと思えない手続きだけやって帰るやつよりかは、まぐれでもたまにヒットを打つ可能性がある分、まだマシとも考えられる。少なくとも打席には立っているからだ。
ただ、往々にして、そういうやつはあまり考える力がないので、適当な説明とかですぐ流される場合が多い。あとは、ぎりぎりまで一生懸命やった感を得ると、満足してしまって、結果はあまり気にしないというタイプが結構いる。よって、対応する側からすると、面倒なだけであまり脅威度は高くない。完全に興味で仕事らしきことをしているだけのタイプだ。こいつらは、何かをかぎつけているわけではないが、行動の予測が難しいという点では、多少やっかいではある。
つまり、与えられたサンプルを無言でバウチングしているやつとかは、監査を受ける側からすると、正直いてもいなくても同じような人間なので、わりかしどうでもいい。チェック係としては多少使えるかもな程度である。しかし、大して件数を見ていないのに、どういう商売なのかとか、どういう組織でどんな風に営業されているのかとか、商品のどういうところがウケているのかとか、そういうところを聞いてくるやつは恐ろしい。
ちなみに、世の中は粉飾だらけだと言ったが、さっきも言った通り、一応監査を受けている場合、監査法人に気づかれたらなんて説明しようかというマインドが多少は働くので、基本的なところはたいてい間違いがないように処理されているものだ。
そういう意味では、通常は別に何も発見しないという点では、両者にそれほど差は無いようにも見えるし、なんだったら最近は調書に沢山件数が載っているほうが、見栄えが良かったりするところもあるのかも知れない。
ただ、おれが現役だったころ、後者のやつの調書を見たことがあるが、その取引がいったいどういうものなのか、売上のタイプ別の特徴、取引先ごとのちょっとしたポイント、といったようなことが、文書でまとめられており、読むだけで何に注意して検討すればよいか、といった情報が伝わるような優れたものだった。それを引き継ぐことにより現場で秘伝のタレのような・・・まあ昔話はやめておこう。
今だと、プランニングの担当がそこまで手が回ればいいのかもしれないが、たぶん、最近の忙しさではそうそううまくはいかないだろう。
受け手に与える有効な印象
クライアントにとって恐ろしいのは、コイツはよくわかっている、という監査人である。そりゃそうだ。そういうやつは、他方、頼もしい存在でもある。悩ましいことを相談した場合に、色々な事情を踏まえてちゃんと考えてくれそうな気がするからだ。そして、そういうやつをクライアントは意外と裏切らない。お世話になった先生に迷惑はかけられないという気持ちが芽生えるからだ、そうなったら、極端な話、帳簿は一切めくらず、クライアントと談笑しているだけで監査は終わる。なぜなら、間違いはともかく、重大な問題の発生がそもそも(自主的に)抑制されるからだ。
おれは、とある初めて監査を受ける会社(買収した)で、一年目は、ものすごく棚卸立会でテストカウントをし、間違いを多数摘発した。二年目は、同じ担当者が出てきたので、ほとんどカウントしなかった。その時の担当者の表情を今でもよく覚えている「今年はすごい準備したのに・・・」。めちゃくちゃガッカリしていた。たぶん、気合を入れて頑張ったのだろう。いいぞ!ただ、おれが見に来なくてもちゃんとやれよな!
ただ、世の中コワいのは、そこをクライアントにうまく利用されて、なんだかんだのうちに片棒を担がされるような事例が無きにしもあらずということだ。ここは、ただただ物分かりが良ければいいというものではなく、クライアントの論理に飲まれずに、あくまでも客観的なジャッジができるかどうかということにかかっている。「そうはいっても重要な一線を踏み越えないように、適切にアドヴァイスしてくれるやつ」というのが最高峰だが、そこに到達するのはなかなか難しい。
なお、そういう客観的に見てうんぬんみたいな仕事は、審査員がするのではないかという話もあろうかと思うが、だいたい、見積もりとかそういうところを議論するだけで結構おなかいっぱいなので、審査に上がってこないような現場レベルの違和感とか、そういうところに客観的な目線を導入するのは、審査制度みたいな内部管理のシステムだけでどうこうするのは難しいのでは。。。余談だった。
ともかく、おれたちは見てるぞ、とクライアントに印象付けることが何よりも重要だとおれは考えている。そのためには、一つ一つのテーマを丁寧に咀嚼して理解して、理論づけていく、という作業をクライアントに見せつつ、行う必要がある。そういうチャンスを見つけたら、逃さずにクライアントと議論し、議論の蓄積を作っていくことが重要だ。
監査というコミュニケーション
初等教育で、
IR×CR×DR=AR
というような式を習うだろう。おれはちょっと忘れかけているので間違っているかもしれない。RMMとかまとめられたやつで習ったやつもいるのかもしれないが中身は大体同じだ。じゅうようなきょぎひょうじリスクか何かのことだ。
このモデルは、監査人がコントロールできるのはDRだから、リスクの水準を評価して、それに見合った監査手続きをやれというように説明されていた記憶があるが、おれは実際はもう少し複雑に物事が作用していると思う。今まで言ってきたようなことを踏まえると、このモデルはもう少し、いわば動的にとらえるべきでなのではないかというのが、おれの考えだ。
DRを低めるために、手続きの範囲をひたすら拡大するようなことではなく、おれが言ってきたように、一つ一つをそれなりに深く検討し、クライアントにインプレッションを与えてきたのであれば、RMM自体が下がるはずだ、というのがおれのアイデアの骨子だ。
監査がない世界では、誰も何も見ない、ということから無法地帯となっている。これは、虚偽表示のリスクは極めて高いので、ものすごく真剣に監査とかしないとどうにもならない。
ところが、良い監査人がいる世界では、クライアントは多少のことではすぐバレてしまうことを理解しており、くだらない粉飾とかはすぐに諦めてしまうので、虚偽表示のリスク自体があまり高くなくなる。質の高い監査手続きが、RMMを低下させるということだ。量じゃない。質だ。
監査人のアプローチはクライアントに影響を与える面がある。それを、もっとよく考えてみたらどうか、ということが、要するにおれの言いたいことだ。
おまえが実施する監査手続きは、クライアントに対する、ここをおれたちは検討しているぞ、というメッセージである。クライアントは、そういうメッセージを感じ取ると、絶対に検討されるような部分では(少なくともすぐバレるような)悪さはしないようになる。これを、ひとつのコミュニケーションだとおれは考える。
大きいレベルの監査人vs被監査会社というコミュニケーションのほかに、おまえvs担当者というやや小さいレベルのコミュニケーションがある。ただ、実際には、働いている人と人との間で物事が起こるので、こういった小さいコミュニケーションの積み重ねが、大きいコミュニケーションを作っていくと考えたほうが良い。
だから、おまえが何を検討し、何を検討しないかということのほかに、おまえがどういう人となりで、どういった能力を備えているかということを、クライアントにいかに理解させるかということが重要だし、より効果的であるためには、見せ方といったものにも配慮が必要となる。
そういう意味では、最近は監査法人が会議室にこもってPCと向き合ってばかりだ、とかいう悪口が出るのはとても深刻なことだとおれは思う。おまえの世界では、数字とエヴィデンスが世の中を支配しているのかも知れないが、実際の世の中はそうではない。
結局のところ、会社というものそれ自体はどこを探してもみつからず、あるのはなんか設備みたいなものと、そこで働く人間だけだ、ということを忘れてはいけない。その人間にどういう影響を与えていくかということが、極めて重要なことだ。そのうち、そこで働くAIとかも入ってくるのかも知れないが、それはもうちょい先の話だろう。
そもそも売上高とか本当に検討できるのか
最近、ロジカルに頑張っている人がすぐ怒り出すので、あんまり大っぴらには言わないようにしているのだが、普通の話として、超デカい会社の売上高とか、見れたもんじゃない。あれは検証できない。
牧歌的だったころは、売上高の調書とかは、なんとなく増減分析めいたものがあって、営業を仕切ってるやつとかと話し込んだ形跡とかが残されているだけで、よくわからないオーバーオールテストとか千本ノックとかは、一部の業種を除いてろくすっぽ行われていなかった。
分析的実証手続きとかいうのは、あらゆる方面にとって諸悪の根源であるようで、ある年には必須とされ、結局誰もできないことに気づいて、ほぼ翌年には分手実証はだいたい禁止になったとかいう、笑い話のようなことが起こった法人もあったと聞いている。
働き方改革以前には、ここはもうパワープレイしかないみたいな方向性の現場もあったようで、なんか死ぬほどサンプリングとかしたような話もちょいちょい聞いたことがある。
ただ、どっちにしろ、大した意味は無いのではないかとおれは思うし、たぶん、わりと多くの人がそう思っているはずだ。サンプル100件を1万件にしたところで、グローバル企業の売上高を十分検討したかどうかという点からすると、大した違いではないだろう。
ところが、売上高を検証することは、もはや不可能です、というのは、なんか、、こう、、言ってはいけないことらしい。おれは、だいたい事実だから、正直に無理というのは別にいいんじゃないかと思うが。
一応、歴史的なことを言っておくと、売上高をそれほど見なくてもいいというのは、論拠が無いわけではなくて、まず売掛金とかそういう残高の科目というのは、程度問題はあるが、頑張ればだいたい検証ができるはずである。
また、売掛金が回収されると現金とかになるわけだが、現預金の残高というのは当然がっちり見ているわけだし(銭勘定がアヤシイというのは、営利社団法人の根幹にかかわる)、売掛金の回収管理をまじめにやっているかということは、通常多くの監査チームで重要だと考えられているテーマであって、ちゃんとキャッシュになっているかということは、たぶん大体の現場で検証できていることだと思う。やってないなら、そこはちゃんとやれ。
売上原価とか在庫についても、話は同じようなことで、残高と、キャッシュ、これはちゃんと見れているはずである。
となると、なんかキャッシュが入ってくるようなことが起こった、というところまでは、偉大な複式簿記の力によっておおかた証明されているのだから、あとは、グロスネットの問題が残るぐらいのものだ、というのが、おおよそのところで、難しいのは、売上によるキャッシュインだとされているものが、実は借入だったとかそういう明らかにヤバいケースだけである。
まあ、細かい話をすると色々あるのは理解しているが、だいたいおかしいことが起こると、2~3年経てば、まあ隠し切れなくなるので、いずれわかるような話だとおれは思う。
その辺は、単年度で巨大なクライアントの全てを検討することがそもそも無理なんであって、4~5年監査してたのに1ミリもインチキに気づかなかったとかそういうひどいやつ以外は、多少大目に見てやったほうが良いんじゃないかとおれは思わなくもないが、まあそういう制度の話は賢いやつが考えるだろうから、おれはしゃべらないでおこう。
数字をつぶすことは果たして必要なのか
監査を、数字を検証する仕事だととらえると、色々と無理があるとおれは思っている。だが、クライアントに変な気を起こさせないようにするコミュニケーションのひとつだととらえると、おれはまだまだできることがあると思う。ただ、そこに本格的にリソースを投入するためには、今の監査のやり方というのは、あまり良くない面が多いのじゃないのかなあと、そういうことも思う。
数字を見なくていいというと語弊があるのだが、「数字をつぶす」ような事に多大な労力を費やすことは必ずしも監査の目的ではなく、社会全体で粉飾とかがあまり起こらないようになることが、本来の役割なのではないかとおれは考える。
そういう考え方で行くと、クライアントにどうやったらよい影響を与えることができるか、より適切な財務報告へと誘導できるか、ということがもっと真剣に考えられてしかるべきだし、そういう風に働けば、何より、監査が面白く、楽になるんじゃないかとおれは思う。
そういったような話を一回してみたかった。
誠にありがたいことに、最近サポートを頂けるケースが稀にあります。メリットは特にないのですが、しいて言えばお返事は返すようにしております。
