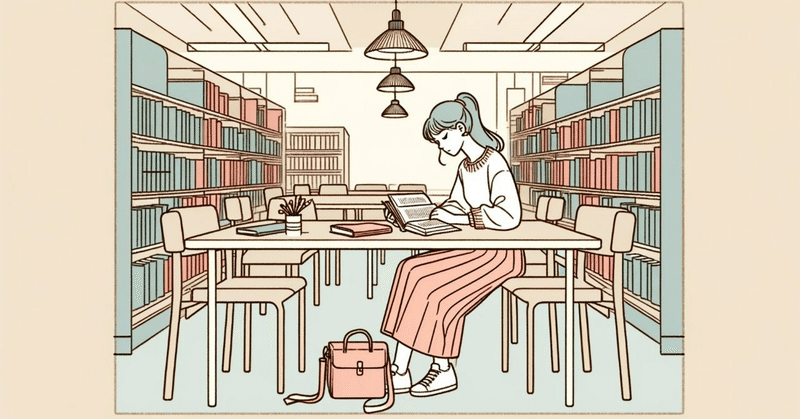
【エッセイ】〆切ヤバいを超えた先
「国語のテストに「この時の筆者の気持ちを答えなさい」ってやつあるじゃん。執筆中の筆者の気持ちなんて「〆切ヤバい」以外あるわけなくない?」
以前一緒にご飯を食べに行った知人の台詞だ。どうしてそんな話になったのかは全く覚えていないのだが、公教育の有様に疑問を呈するような話の一環で、そんな文句が飛び出した。
言わんとすることは分かる。国語のテスト、漢字の読み書き問題や慣用句の穴埋めならまだしも、筆者の気持ちを答えさせようとしてくる問題には若干の不毛を感じないではない。文章に対する解釈は十人十色であって然るべきだ。しかし、それにしても、「〆切ヤバい以外無い」は流石に言い過ぎじゃないだろうか……。
当時の高倉は塾講師として国語の教鞭をとることもあった手前、「わかる!そうだよね不毛だよあんなのはよ!」とも言えず、しかし教育の過程を一通り終えた社会人に「いやいや国語は大事でございますよ、学びなおしな」と言うのも余計なお世話に思われた。結果「そうかなぁ……そうかもなぁ……」と曖昧な相槌を打ち打ち、パスタをすするにとどめるなどしたというわけだ。
毎日noteを投稿するようになってから、「〆切ヤバい」の気持ちがちょっと分かった気がしている。
高倉の場合は〆切ではなく、日付が変わる零時に追われているだけだし、例え高倉が〆切を落としたとしても誰にも何の迷惑も掛からない。高倉の毎日投稿記録が途絶えるだけだ。それでも、「〆切やっべぇ……」の気持ちはかなり、結構、無視できない程度には大きい。まるで忍び寄る化け物から逃げるように、必死に文章を書いている。インターネットの片隅に駄文を放り投げるだけでもこんな強迫観念に駆られるのだ。国語の教科書に載るような文豪先生を追いかける〆切は、さぞや恐ろしい妖怪変化の姿をしていることだろう。
文章を書いている間、確かに「〆切ヤバい」に駆り立てられている。どんな言葉を選ぼうか、どんな構成にしようか、次はどうつなげて、最後はどうやって締めようか、を考える頭の片隅に「〆切ヤバい」はずっと居る。「このエッセイを書いた時の高倉は何を考えていたでしょうか」という問題があったとして、どのエッセイにおいても「〆切ヤバい」は正解だ。(正確には「日付変わるヤバい」かもしれないが。)
しかし、読者の皆様に「あぁ高倉のこのエッセイは「〆切ヤバい」って思いながら書かれたものなんだな」と思われながら読まれるのはちょっと、えー、悲しい。大前提として、読んだものをどう解釈するかは読者の自由だ。内心の自由は憲法で保障されている。それでも、だって、少なくとも高倉は、そういうことが言いたくて文章を書いているわけじゃない。
そもそも、全ての文学作品が〆切に追われて書かれたものだとは限らない。週刊誌や月刊誌の連載小説やアンソロジーであれば〆切に追い回されるシチュエーションがイメージしやすいが、例えば持ち込み作品とか、世に出されていなかったが死後屋根裏から見つかった原稿とか、そういうものの筆者の気持ちは「〆切ヤバい」じゃなかった筈だ。
それに、文豪先生は常に〆切に追われていそうなイメージはあるが、計画的に原稿を提出できる先生もいたのではないだろうか。〆切が化け物になって追いかけてくる前に「これが今回の原稿ですよ」と言って化け物退治をしてしまうような、勇者的文豪先生もいた筈で、その場合「〆切ヤバい」の感情は生まれない。
「〆切ヤバい」以外無い、というのは流石に暴論だと言えるだろう。「いやいやこの先生はいっつも〆切落としかけて編集に追いかけまわされていたんですよ、そういう記録があるんです」なんて話をし始めたら、それはもう国語ではなく歴史の話になってしまう。
そもそも、「この時の筆者の気持ちを答えなさい」という問題はどういう意図で問われるのだろうか。「「この時の筆者の気持ちを答えなさい」という問題を作った人の気持ちを答えなさい」だ。
筆者が何を思ってこの文章を綴ったのか、出題者は文章を読み込んで読み込んで解釈したのだろう。〆切に追われて書いたかもしれない文章、しかし文章はそんなことを言っているわけじゃない。筆者が綴った言葉は何を言っているのか。
文字は時代を超えて残る。明治の文豪の言葉を、令和の子供たちが音読しているのだ。文章は、死んだ人間とのコミュニケーション手段とも言える。
一般に、死者の考えを耳にするというのは、私たちが持ち合わせていない超人的能力のように思える。この超人的な能力はフィクションの世界にしっかりとどまっているに違いない(エドワードも含めて)。とはいえ、少し考えてみると、私たちは四六時中、死者の考えを耳にしている……たんに、文字を読むことで。表記法が発明されると、死者は突然、生者に語りかけられるようになった(逆方向のコミュニケーションは遅々として進まないが)。あなたにしてみれば、私は死者も同然で、あなたは今この瞬間、霊読の技能を行使している。偉い!
生きている間に活字を残しておきさえしたら、死して尚、人は生者に語りかけることができる。その声は人によって聞こえ方が違っていて、受け取るメッセージに正解は無い。それでも、じっと耳を傾けることが、読むということなのだろう。「この時の筆者の気持ちを答えなさい」という問題を作った人の気持ちは、きっと此処にある。
「この時の筆者の気持ちを答えなさい」の問題の正否には、きっと大した意味は無い。言葉には意図があるのだということ。耳を澄ませること。文章を読むにあたって、そういうことをしてほしいというのが、出題者の意図なのかもしれない。
因みに、このエッセイを書いている今の高倉の気持ちは「〆切ヤバい」を超えて「めっちゃお腹空いた」である。めっちゃお腹空いた。腹がぐうぐう言ってて眠るどころじゃない。時刻はもうすぐ零時、よりにもよってこんな時間にお腹空きたくなかったんだがな……とごちながら、実はチキンラーメンを茹でている。チキンラーメン独特の、香ばしい、ジャンキーな香りがキッチンに広がってゆく。これこれ、これですよ。夜中に食べるチキンラーメンほど背徳的で、美味で、明日の体重に響くものはない。
願わくば、未来でこの文章を読む誰かが、高倉と同じように夜中チキンラーメンの衝動に駆り立てられてくれますように。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
