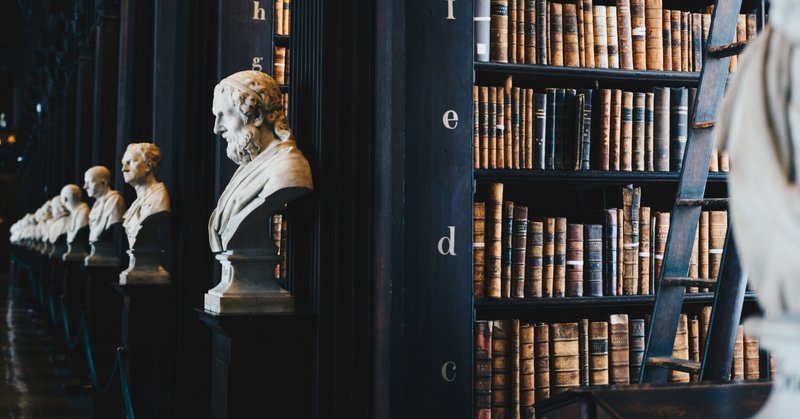
最強のチーム目指す人限定:インターナルブランディングはもう古い?社内の対話を促進するインターナルマーケティングでブランドを創ろう!価値共創型シン・インターナルマーケティングのすゝめです。
哲学クラウドさんとの対話から
Three Plus Six LLCのOpen Platform Partnerである哲学クラウドCEOの上館誠也さんと「対話」してきました。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが哲学クラウドは「考える」を習慣化するマネージメントプラットフォームサービスを提供している企業です。
働くことや所属している会社へのロイヤリティが低いと言われている日本企業。
どうやら「思考停止状態」に陥りがちの社員がたくさんいるようです。
「哲学」を活用して社員を活性化して、企業とそこで働くことをイキイキさせていくことを追求しています。
上館さんとはネットを通じた縁があって懇意にさせていただいております。
「考える」を習慣化するマネジメントプラットフォーム
テーマはインターナルマーケティング
今回の「対話」のテーマは社員活性化のためのインターナルマーケティング。
インナーブランディンやインナーマーケティングという言い方もあります。
ここではインターナル・エクスターナルで統一させてください。
最近日本市場でもよく聞きます。
かなり前から存在する概念です。
すでに実践されている方もたくさんいらっしゃいます。
以下参考です。
インターナルマーケティングって?
インターナルブランディングとの違いは?
日本ではインターナルブランディングという言葉の方が馴染みがあると思います。
Googleで単純に検索したインターナルマーケティングの情報量です。
Googleで単純にワード検索したいの表示件数の違い
(Three Plus Sixによる2023年8月24日調べ)
インターナルマーケティングとは?
約 165,000 件 (0.30 秒)
インターナルブランディングとは?
約 56,700 件 (0.30 秒)
インナーマーケティングとは?
約 5,630,000 件 (0.29 秒)
インナーブランディングとは?
約 1,060,000 件 (0.27 秒)
検索結果は正直思っていたことと異なりましたが、市場の興味がインターナルマーケティングに移行していることを感じ取ることができました。
インフレ下の優秀人材確保に頭を悩ませている北米を中心にインターナルマーケティングという概念がひと足先に活性化しています。
背景には
製造業のサービス業化が進んでいること、
過度な流動性の中で人材の確保に課題があること、
働き方の変化(リモートワーク)やDEIの普及による社員の活躍機会の最大化
などがあります。
個人的にはパンデミックの後、働き方や働くことの意味が問われていると理解しています。
上館さんとの「対話」を通じてインターナルマーケティングの定義をしてみよう!ということ、それを本稿を読んでいただくみなさんと共有し、新たな「対話」を起こしていこう!という事が今回記事をアップする目的です。
ブランディングとマーケティング
ブランディングとマーケティングについての定義は人それぞれみたいなところが日本の広告系ではよくあります。ブランディンとマーケティングの定義をThree Plus Six編としてして以下に書き出します。
マーケティングは4Pを統合して価値を顧客に提供して利益をあげること=経営そのものです。
ブランディングはマーケティング活動の一部です。
ブランディングサイクル
マーケティング4Pにおけるプロモーションで広告が果たす(べき)役割は以下のサイクルを創意工夫を持ってマネージメントすること
→ミドルファネルでの顧客とのインタクションを促進する行為、それによるユーザーの心にできた価値(それに基づく行動様式)がアイコンに昇華するプロセス、象徴されたアイコン(と行動様式)
→ブランド、ブランドはユーザーの中で「消費」されるのではなく、蓄積・連鎖される(ブランド・価値の生態系・ブランドエコシステムが生まれる)
→顧客がエバンジェリスト化する=自ら情報発信=テクノロジーと連携してUGCなどの活性化(普遍化する)
→(経営的に)LTV=レベニューに大きく貢献する=レベニューはマーケティング投資に戻る(永続的に回転する)
この一連のサイクルを価値創り(体験価値創造)をブランディングと定義します。
マーケティングはブランディングの上位概念ということが引き続きの前提ですです。
ブランディングではなくマーケティングについて語ろう!
マーケティング全体から考えよう!ここが上館さんとの「対話」の出発点です。
これからその対話によってインスパイアされた内容を書き出します。
ターゲットオーディエンスは大事な社員
マーケティングは顧客(外部)に向けた活動と一般的に認識されます。
時に(しばしば)顧客よりも大事な社員を対象にマーケティング4Pを実践していくことがインターナルマーケティングです。
特定企業のブランドをMVVで規定し、それを広報的に社内に流通させるのではなく、社員と一緒にブランド(体験価値)を創るという行為がThree Plus Sixのインターナルマーケティングにおけるブランディング活動です。
社員とのインタラクションをプロモーションの中心にすると…
インターナルマーケティングにおいてPromotion Targetから考えはじめます。
ターゲットを「社員」にして、「インタラクション」を「対話」に置き換えてみましょう。
例えば;
Productは会社が提供するハード&ソフトの成長機会
Placeはオフィス+全ての情報接点
Price=給与と経験(経験はキャリア=Pricelessに)
Promotion=社員を対象したブランディング活動
プロジェクト責任は経営者、リーダーはHR
4つのPを水平統合する責任者は顧客向けであっても社員向けであっても経営者です。
インターナルマーケティングは社長案件です。
コンダクターは人事のプロ、つまりインターナルマーケティングのリーダーはHR部門ということになります。
社員のモチベーションに対するコンサルティングを行っている哲学クラウドの窓口は人事部門が多いそうです。
人事部門は日本の企業では「バックオフィス」として引き続き位置付けられている事が一般的です。採用やトレーニング、そして社員ケアという仕事に従事するという認識を持つ組織です。
「社員」という最大の資産を運用するプロフェッショナルの役割が期待されています。
先進的な日本企業の中では人事部門の領域拡張(責任も増えてます)が進んでおり、労働力不足という課題を社内から解決するリーダーとしてのポジションに変革しています。
この流れを加速するためにも「インターナルマーケティング」という概念をしっかり日本市場で実践していきたいということが私たち(哲学クラウドとThrre Plus Six)で確認できました。
パーパス経営が解決策なのでは?
パーパスは企業の最終的な目的地を示しているという点では素晴らしいアプローチです。
企業の存在意義を明確にして、社員、顧客、社会と共有し前進していこうという経営アプローチです。創業理念がはっきりしている創業社長がいる会社であればその「意義」をシャープに規定することは可能ですし、社長のカリスマ性で人を束ねることができます。
日本企業においては「マーケティング」「リブランディング」「リポジショニング」とセットで「パーパス」が使われていますが、違和感を覚えることがよくあります。
企業の存在意義を追求する中で「人類の進歩」「愛」「平和」という非常に抽象的なものに昇華されます。
耳障りが良い言葉ばかりです。
企業は自らのパーパスを社員、顧客、社会と共に実現する必要があります。むしろその具体性の方が重要です。
パーパス経営やパーパスブランディングという言葉でピンとこないなーと感じてる方は(皮肉な問いかけですが)「何のためにパーパスを決めているのか?」ということに立ち返ってみてください。
パーパス達成までの具体性の欠如をいかに補うか
PurposeはSubjectiveになりがちです。
それはObjectiveなものに置き換えられることで、初めて外部とのインタラクションが可能です。
目的語は客観的な対象物を示します。
その対象についてどうアクションするかを考えて実践する=マーケティングするということになります。ブランディンはマーケティングを実践する上で一部の重要な要素だと僕は考えています。
実感を伴わない=ココロにエンゲージされない、ということでブランディングとしても昨日していません。
ぜひ、パーパスを言語化するだけにとどまらずに具現化すること、それを社員のココロに伝えていくことだけにとどまらず、エンゲージすることを目指しましょう。
その方法論は「対話」です。
「社員の体験価値」が大事:だからインターナルマーケティングに
従来のインターナルブランディングの責任部署は「広報部」でした。
言語化されたパーパスを成果物として社内報として社員に配布するということが成果(広告系では納品物)となりがちです。社員の手元には届いたけど(リーチはしたけど)、ココロの中までは届いていない(エンゲージされない)ということになってしまっている理由の一つです。HR部門の主体的な関与と活躍がこの状況を大きく変えていきます
インターナルマーケティングは「社員の人生」を中心に
ちょっと大袈裟ですが、「社員は人間であり、有限な時間(人生)の一部を会社に提供して対価(有形無形)をえている存在」としてみましょう…
社員の悩み=人間の悩みであるとしたら…
また企業側も終身雇用についてはかなり難しい状況になっています。
「社員を守る」ということ=「雇用を維持する」ということを持って人事マネージメントにおける経営上の解決策とされていました。「雇用機会を享受できる社員(人間)を育てること」を経営上人事マネージメントの課題と再設定してみてはどうでしょうか?
終身雇用+総合職=社内ジョブローテーションで解決ではなく、専門性の高い人間を適材適所+適切なリワード、に視点を動かしてみましょう。
そうなるとある会社の中だけで通用するキャリアプラン、キャリコーチ、スキル、Tipsをもたらすケーススタディの蓄積よりも重要なものが現れます。
社員と企業の体験価値の視点でまとめてみることをお勧めします。
最も重厚で洗練された「人間・生き様」としてのデータベース、人間学=哲学に注目すべき理由がここにあります。
哲学クラウドの上館さんと「対話」を続けて(モニターして深化していく)、私たちの考えをより体系化して、クライアントのみなさんにお届けしたいと思っています。
「哲学」の最もパワフルなメソドロジーは?
哲学データベースは人類の「対話」の蓄積であり、「対話」により「課題=ギャップ」を埋めていく。「価値」を創っていくメソドロジーが確立している
哲学と聞くとなんだか重た過ぎない?という方がたくさんいらっしゃいます。
広告系の僕が哲学を「圧縮して」捉えると、「対話の蓄積」=「対話のデータベース」ということになります。
哲学のスペシャリストがインターナルマーケティングのエージェントとして最適である理由は、人類の対話の蓄積が手中にある、それを「対話」を通じて適切なサービスパッケージとしてクライアントさんに提供できること、にあります。
社長との対話、社員との対話、社長と社員の対話のオーガナイズなどを社内にある全てのタッチポイントで実践し、価値を規定化、人事部門と連携して、価値の蓄積、連鎖を起こすノウハウを持ったスペシャリストたちと考えてください。
インターナルマーケティングと外部向けマーケティングとは「コインの裏表」
内側のマーケティング活動とそれによる具体的な価値創り(ブランディング)と外部の顧客との価値の連鎖づくりは同軸で行われる=社員(企業にとって最も大事なタッチポイント)が企業を代表する(エバンジェリスト)になる=企業人格を体現する存在:社内外の共通の価値観を持ち、その価値を連鎖させたい企業人格の体現者とエバンジェリストとしての顧客の存在が両輪となり企業が進歩していく。
リクルーティングは「人を採用する」ことではなく採用窓口の担当者が「(その企業固有の)価値を連鎖させる」ことになり、「入社してからの失望」が減ることに繋がります。
「宗教」ではなく何故「哲学」なのか
あくまで広告系のThree Plus Sixの視点です。
哲学クラウドとのコラボレーションをお勧めする背景です。
宗教家の方や哲学者の方の考えと異なることがたくさんあることを前提にさせてください。
宗教は救済で、哲学は生きる糧ということを僕自身は規定しています。
パーパス経営について少し触れましたが、パーパスは抽象化されたものになりがちです。
企業経営自体が宗教的なものに似てくるということは色々なところで言われています。
ある企業の(抽象化されていますが)絶対的な価値の追及ということがその理由と理解しています。絶対的な価値は時に他者否定に陥ります。(ココロの)救済を求めたはずが対立に加担してしまうということは会社経営やマーケティング活動においてはあってはいけないことです。
特に多様性の時代において(同じ方向・目的地を向いていることを全てにして)社員の個性が受け入れられないということに繋がり求心力・ロイヤリティの低下につながり、社員との共創を通じて企業を成長させる、ビジネスを永続的なものにするという課題を解決したことになりません。
対話が社員の意識が変わる
マーケティング(広告が責任を果たすプロモーション)においては顧客との体験価値づくりが重要になります。体験価値が言語化・象徴化されてブランドになります。
ブランドはその象徴のもとに共通の行動様式(culture)を取るようになります。十字架と十字を切る動作の関係です。ブランドは非常に宗教的な要素で捉えることができます。ブランドエバンジェリストです。
(カリスマ的な経営者がリードする企業を除くと)宗教的な要素を備えることが目的ではなく、マーケティングのプロセスで宗教的な側面が生まれてくると僕は理解しています。
何よりも対話を通じて社員のみなさんにも独自の働くこと、キャリアへの価値観が形成されることになります。社員の(恣意的な)思考停止がなくなります。自分ごととして企業にコミットする(働きがい、やりがいの発見、そしてロイヤルティへ)ことが可能になります。主体性の発揮が期待されます。
成長で同期する
経営者の立場では「人材の流動性」や「人材の確保」という課題設定になります。個人の立場では「キャリアの選択肢」だったり「キャリアゴールの設定」だったり…。
両者に共通する課題は「成長」です。成長への渇望で社員のみなさんと同期しましょう。
お互いの成長に向けて「哲学」というアプローチで解決に臨みます。
そのアプローチ自体に「創意工夫(Creativity)」があるという理解です。
僕が考える哲学は否定ではなく肯定的な行為です。
そこにあること(事実)を認識し、対立やバイアスを前提に当事者同士が話し合い、次のレベルの解決策をさがし、実践するものです。
そして、その方法が「対話」です。
テクノロジーをテコに
哲学をインターナルマーケティングに応用する上で、大事なことの一つが、ユーザーインターフェースです。
哲学クラウドはテクノロジーを活用してまずは中心的な組織であるHR部門との対話を可能にするノウハウを蓄積しています。分厚い「哲学書」に頼るのではなく、人類最大の学問(ケーススタディ)を彼らを通じてぜひ活用してみてはいかがでしょうか?
統合ブランディングは社内外で同期する
インターナル・エクスターナルのマーケティングの統合サービスについてはThree Plus Sixと哲学クラウドにお任せください。
人事の方とのワークショップやセミナー、研修などなどなどクライアントのみなさんの課題の顕在化からお手伝いさせていただきます。
哲学クラウドとThree Plus SixはOpen Platform Agency Partnerとして企業の体験価値創造を統合的に創っていきます。
ブランド創り(言語化、アイコン化+行動様式・culture)は社内外一体で(社内外を同期させて)進めるものです。
さあ、ブランドを創ろう!
統合マーケティングにおける企業スローガンの役割について興味がある方はぜひこちらもお読みください。
哲学クラウドの問い合わせ先はこちらです。ぜひ相談してみてください!
哲学クラウド連絡先: support@tetsugaku-cloud.jp
森へのお問い合わせはこちらまで:h-mori@threeplussix.com
【追記1】今回対談させていただいた哲学クラウドさんの記事です
彼らから哲学と対話の重要性を学びました。
おかげで【対話箱】というコンテンツサービスの着想を頂きました。
その哲学クラウドさんの記事がこちらに。
実務的な内容にも踏み込んでいます。
非常に具体的に彼らの仕事が理解できます。ぜひご一読をお勧めします。
【追記2】対話箱シリーズはこちらから
インターナルマーケティングについての質問をもとに議論しています。
みなさんの参考になりますので、ご一読を。
人事関連の記事はこちらにも。よかったら読んでください。
ヘッダーの写真はUnsplashのGiammarco Boscaroが撮影したものです。
よろしければサポートをよろしくお願いいたします! みなさまのお役に立てるようにこれからも活動を続けます! 今後ともどうぞご贔屓に!
