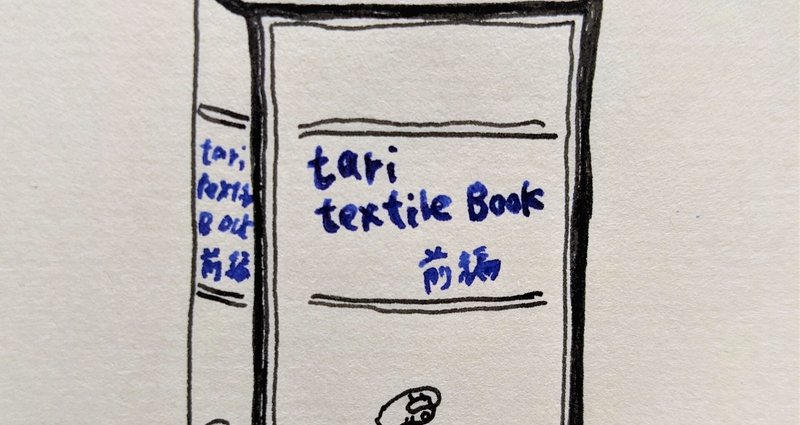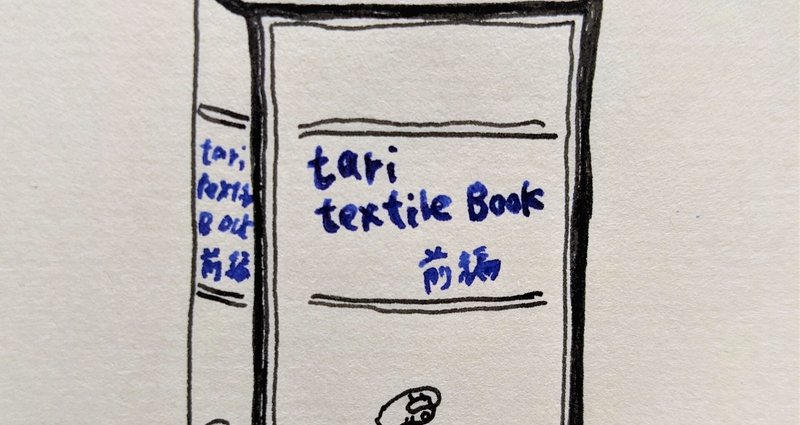tari textile BOOK 前編 第0章 「伝習生」
「伝習生」2016年4月~2018年3月
丹波布伝承館 長期伝承教室。私は、その第10期生として、2016年4月から兵庫県丹波市青垣町に移り住み、同町にある丹波布伝承館で丹波布という織物の技術を学んだ。この長期教室では、火曜日以外の平日、朝10時から夕方4時まで丹波布伝承館に通い、丹波布の技術を1から身につける。実技中心の授業で、糸紡ぎから染色、機織りまで一人で全ての工程を行えるようになることを目指す。1年目の基礎コース、2年目の伝承コースの2年間で1期となり、この長期