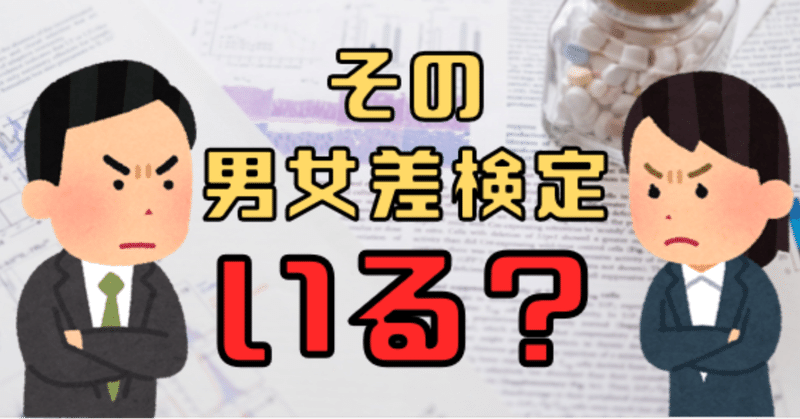
心理学研究で軽視される「男女差」検討の意義と問題
「とりあえず参加者の性別を聞いておこう」
「とりあえず各尺度得点の男女差を調べよう」
「男女差出たしとりあえず論文に書こう」
有名な雑誌に掲載された日本語論文であっても、男女差について十分な理由なく記述している論文は少なくないように見受けられます。
この記事では、男女差を扱う必要がある研究とない研究との違い、そして男女差を研究で扱うことの危険性について、私の持論を述べていきます。
心理学初心者の方や、心理学以外の分野でも人を対象とした研究に興味がある方にお読みいただければ幸いです。
【1】研究で扱われる男女差はほとんど男女差以外の概念で説明できる
例「女性は男性よりも周囲の人々に対して協調的である。そのため、女性は男性よりも外国人に対する態度がポジティブである(≒好意的である)と考えられる」

このような立て方がなされた仮説に基づいて、調べたい変数の男女差を検討する論文は非常に多いです。
しかしこの仮説の立て方は不適切です。少なくとも、男女差を検討する十分な理由が論じられているとは言い難いでしょう。
なぜ不適切なのか?
まず、この手の研究の仮説の構造について、一般化して考えます。
研究で調べたい要素、つまり目的変数をCとすると、「要素Aを持つ人ほど要素Bを持ちやすい。要素Bを持つ人ほど要素Cを持ちやすい。だから要素Cを持つ人とは要素Aを持つ人であるといえる」と言い換えられます。

このとき、要素Aと要素Cとの関連は「偽相関」に似た構造をしています。
偽相関とは、本来無関連である要素Aと要素Cとの間の、双方と関連する要素Bのせいで統計上検出されてしまった、文字通り偽物の相関です。
男女差を扱う研究の場合、要素Cを説明するための説明変数であるAの要素に「性」が入ります。
ですので、研究で調べたい目的変数である要素Cを説明する要因として、要素Aである性による差(すなわち、ここでは男女差)を扱うのは不適切であることがわかります。

要素Cを説明する要因を研究したいのであれば、その研究では要素Aにあたる男女差ではなく、要素Bに入る概念を説明変数として扱うのが適切です。
先の例に当てはめて考えると、要素Cである目的変数「外国人に対する態度」を調べるためには、間接的な関係がある要素A(=男女)を扱うのではなく、直接的な関係がある要素B(=協調性、共同性など)を扱うべきなのです。

ここまでをまとめた説明をもとにすると、例に示した仮説やその検定プロセスは、以下のような過程で修正すべきでしょう。
「女性が男性よりも外国人に対する態度がポジティブであると考えられる理由は、一般に女性の方が男性よりも協調性が高いからである。
しかし、協調性が高い男性もいれば、協調性が低い女性もいる。協調性が高い男性は外国人に対する態度がポジティブであると考えられるし、逆も然りだ。
それならば、外国人に対する態度を決める要因は、その態度の持ち主が男性か女性かということではなく、その態度の持ち主の協調性だと言える。
だから研究では、外国人に対する態度と協調性との関連や因果関係を調べる。」
以上のロジックで批判できてしまう男女差を扱った研究や研究計画は、残念なことにとても多いです。
ただし、このロジックに当てはめられないジェンダー研究や、ロジックに当てはめられるとしても意義のあるジェンダー研究もあります。その例外については次の章で説明しています。
【2】男女差を出すべき研究の3パターン
男女差を出すべき研究は、以下に示す3つがあると考えます。
(1)男女が質的に異なることを説明する研究
(2)ジェンダーの問題が背景として考えられる研究
(3)探索的な研究
まず(1)、男女間で変数の量的・平均的な差があることではなく、男女が質的に異なることを説明する研究です。
すなわち、「変数の男女差について男性または女性特有の要因による説明を試みる研究」です。
例えば、同性愛者に対する態度の(異性愛者の)男女差について、レズビアン・ゲイ男性それぞれの性的指向の対象であるかないかによって差が見られる、という仮説に基づき検討するなどです。
このような、男性と女性とで測定したい概念を構成する背景要因が異なる場合には、男女のデータを別々に扱ったり、態度得点の差を調べたりした方が適切な考察ができます。
次に(2)、ジェンダーの問題が背景に存在する研究です。
例えば、男性の育児休暇取得率の低さという社会問題を背景として、異性婚の状態にある子持ちの方を対象に子育てについての自己効力感を調べる研究などです。
男女差については子育てにどれくらい関わっているか、という要因に置き換えることが可能ではあるものの、背景にある社会問題にどのように対応していくかを考察するためには、男女差という形で結果を示しておく必要があります。
その際には、夫婦それぞれの就業状況などを要因に加えた計画が望ましいでしょう。
最後に(3)、研究全体としてまともな仮説が立てられないような探索的な研究です。
決して積極的な検討理由ではありませんが、男女差を出しておくことで、考察の材料とはなるでしょう。
以上に示した以外にも、私が気付いていない、男女差を示すべき研究のパターンがあるかもしれません。
少なくとも言えることは、議論なしにとりあえず男女別に結果を出したり、男女間の差を出そうとしたりするやり方は浅慮であるということです。
そういった研究は、あまり概念を詰め切れていないか、男女差について思考停止的であるかのどちらかでしょう。
そのことの何がいけないのかは次の章で。
【3】男女差の研究は偏見を助長し差別に利用され得る
最後に、研究倫理のお話です。
男女差をむやみに出すことは、たとえ研究者にその意図がなくとも、男性あるいは女性への偏見の助長に繋がりうるものです。
科学研究の結果は人々にとって道具です。
そして、世の中には男性のことを嫌う人、女性のことを嫌う人がいます。全ての人が見知らぬ他人に優しい世の中など幻想に過ぎません。
そのような人々は、研究者が渡した道具をちゃんと使ってくれるでしょうか。
たとえば、上に示した例の研究のように、女性が男性よりも外国人に対する態度がポジティブであることが示された場合。
男性のことを貶めたい方々の中には、この仮説が支持された研究成果を見るなり、こう喧伝する人もいるかもしれません。
「男性がレイシスト(差別主義者)であることが科学的に証明された!」
他にも、このような研究結果を鵜吞みにした(必ずしも害意が伴わない)会社の人事担当によって、男性が国際的な仕事から外されたり、逆に女性が望まない国際的な仕事に回されたりするなど不当な分業にも利用されかねません。
このような、個人の信念の確証や利益の追求のための、結果として特定集団に対する差別に帰結するような研究結果の転用、そしてそれに伴う風評を防ぐためにも、研究者は自身の研究を発信する際、考えを巡らせ、できる限り可能性を考慮し、あらゆる努力をすべきです(これは男女差に限ったことではありませんが)。
そして、ここではその努力とは、
・男女差を検出する意義を明確にすること
・必要のない男女差を検出・報告しないこと
であると考えます。
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
堀川佑惟(Yui Horikawa)
■Twitterで研究やジェンダーに関する情報や考察をツイートしています
https://twitter.com/The_Gender
■これまでの学会発表ポスターなどはこちら
https://osf.io/4en9h/
