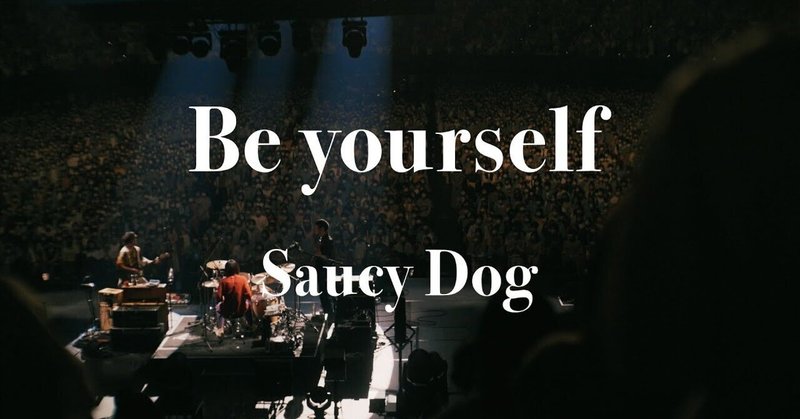
誰でも音楽が好きになる。Be yourself -Saucy Dog を聴いてほしい。
本日の内容
閲覧ありがとうございます。"ゆうひ"と申します。
本日はSaucy Dogの楽曲「Be yourself」について触れていきます。
大変魅力的な曲なので、もちろん第一に聴いて楽しんでいただきたいと思っています。ですが、大量の曲をスピーディに消化できてしまう現代の音楽環境です。敢えて1曲に対して詳しく掘り下げて考えてみることで、皆さんの中で音楽に対する向き合い方に変化があればいいなと思っています。
曲・歌詞の両面からアプローチして楽曲の魅力に迫っていきたいと思いますので、浅学+拙文ですが興味があればお付き合いください。
Saucy Dogについて
Saucy Dogはご存じですか。「シンデレラボーイ」とか、「いつか」といった代表曲を持つ、3人組の邦ロックバンドです(スリーピースバンドと呼んだりしますね)。
上記のヒット曲はいずれも恋愛ソング、それも失恋を取り扱ったものです。
彼らは恋愛の切なさややるせなさの描写能力に長けています。2曲それぞれ違った角度から恋愛を捉えていて素晴らしい曲なのですが、今回は説明を省略させて頂きます。聴いたことのない方は、是非聴いてみてください。
Be yourselfについて
さて、上項ではSaucy Dogについて、恋愛描写が巧みであると書きました。ですが、今回取り扱う「Be yourself」は恋愛をテーマにした曲ではありません。代表曲で失恋を扱っているSaucy Dogには暗い印象を持たれるかもしれませんが、この曲は寧ろ正反対の、背中を押してくれる曲なのです。
忙しくない方は、まずは一度聴いてみてほしいと思います。
勿論、先に本文を読み進めて頂いても構いません。
Be yourself -Saucy Dog
いかがでしょうか(聴いていない方もいるかと思いますが)。
私は、初めて聴いたときにかなり惹きつけられた覚えがあります。特に、曲調から好きになり次第に歌詞を理解していったという流れがありました。
やはり音楽ですから、曲調が看板となるのは当然のことではありますね。
では、「Be yourself」について書いていこうと思います。
曲調→歌詞の順で見ていきます。曲調については、少し音楽的側面が強くなりますので興味のある方に読んでいただければと思います。
曲調の面から捉える
まずは「Be yourself」の曲を見ていきましょう。
個人的には、歌詞をどんどん紹介していきたい気持ちもあるのですが、前述の通り音楽の看板は曲です。
この魅力的な楽曲を魅力的たらしめる要素は何かについて考えていこうと思います。まずは概要から。
4/4拍子
キー:Gメジャー
BPM114
この情報から得られる印象としては、ごく普通ですね。
敢えて触れるとするならば、キーにGメジャー(ファ#ソラシドレミファ#)を採用する曲の特徴として、力強さを感じる曲が多いというものがあります。
これはBe yourselfの曲のイメージとぴったりで、きちんと考えて調を選んでいることが伺えますね。勿論、曲を作る過程で自然(必然)と定まったということも考えられますが。
4/4拍子というのはごく一般的ですし、BPM114というのも邦ロックの中では一般的な範囲です。アップテンポな曲が流行しやすい現代では、比較的緩やかな曲と捉えることもできますね。次は、実際に聴いていきましょう。
特徴的なドラム
冒頭から耳を奪われるのは、何と言ってもドラムではないでしょうか。
勿論、人により感想はまちまちですので皆さんの抱いた感想を尊重して頂きたいのですが、ここではドラムについて触れていきます。
私自身ドラムに精通しているわけではないので深くは語れませんが……。
まず注目したいのが、ドラムの生み出している曲のテンポ感です。勿論、テンポ感の土台になっているのは曲の速度そのものであるBPMです。
しかし、同じBPMでもドラムの音数によってだいぶ曲のテンポ感の印象は変わってきます。具体的に言うと、音が細かくなればなるほど疾走感のある激しい楽曲になります。
改めてこの曲はどうでしょう。ゆったりとした印象を受けませんか?
試しに、この曲の冒頭に合わせて体をゆすってみてください。
……どうでしょう。
多くの人は2拍子ごとにリズムを取ったのではないでしょうか。(そうでなかったらすみません。)
1拍ごとに忙しなく体をゆするほど、すごくノリノリな曲ではないですよね(少なくともAメロは)。では、このゆったりとしたドラムは楽曲にどんな効果をもたらしているのでしょうか。
構成の都合上、先にもう一つの特徴について触れておきます。
それは頻繁なタムの使用です。タムというのは、ドラムセットの中の太鼓たちの一部ですね。「タムタム」「フロアタム」などの種類がありますが、音としてはポンポコした少し可愛らしい響きが特徴です。
この楽曲では恐らくタム1つとフロアタムが使われていますね。
Aメロ(歌が始まったあたり)を聴いていると、頻繁にタムの音が聴こえてくると思います。曲によりますが、タムは曲の場面転換の際のフィルインという部分に使われることが多いです。つまり、音の種類を増やすことで表情を付けて楽曲に起伏を与えているわけですね。
これを曲中のメインのビートに頻繁に取り入れるのは少し珍しいです。「Be yourself」は敢えてそうすることで、ドラムに独特な響きを加えて楽曲を盛り上げていますね。
しかし、先ほど申し上げた通りタムは本来場面転換に多く用いられる音になります。頻繁に使用することで曲に馴染んでしまい、逆に場面転換の際にドラムに表情を付けるのが難しくなってしまうと思いませんか?
そこで話を戻します。
話の流れを汲んで、もう一度ゆったりとしたドラムビートについて考えてみましょう。ここでは、大きく2つの役割が見いだせるのではないでしょうか。
音数を減らすことで特徴的なタムがより際立つ
音数によってドラムに表情を付ける余地がある
まず1つ目。タムが際立つという点です。この曲は8ビートで「ドッタン・ドドタン」といったリズムを繰り返しています。
少し音楽的に話すと、小節の最後(4拍目)に四分休符を挟むことが多いということですね。具体的には、「ドドタド」とせずに「ドドタン」で締めているということです。そうすることで、3拍目のタン!という音が耳に残りますよね。この「タン!」の部分にタムを当てることで、楽曲の持つ独特な響きが最大限にアピールされていると思います。
そして2つ目。ゆったりしている=音数が少ないということはすなわち、音数を増やす余地があるということです。これは先ほど述べた「表情つけにくい問題」のアンサーになっています。
曲の場面転換の際、具体的にはサビに入る直前など、ドラムに注目してみると音数が増えていますね。
こうすることで途端に曲が勢いづき、ここから盛り上がるぞ!となるわけです。
元からハイテンポな曲ですと、フィルインで音を増やすというのが難しくなってきます。そこでタムなどを使って表情を持たせることが多いのですが、「Be yourself」はその逆というわけですね。
「Be yourself」はタムのほか、サビ中にライドシンバルを使うなどしてドラムが非常にメロディアスに仕上がっています。
そしてその特徴的な響きを最大限に活かす構成にしていることで、ドラムの際立つ曲になっているわけですね。
もっと掘り下げたいところではあるのですが、主だったところは紹介させて頂きましたので次に移りたいと思います。
音の引き算
私が曲を魅力的にする上で欠かせないと考えているのがこの「音の引き算」です。引き算というのはつまり、意図的に音数を減らすということです。
前述のドラムにも共通する部分はあるのですが、この項では特にフォーカスしていこうと思います。
Saucy Dogはスリーピースバンドであることから、元々音数が少なくなりがちです。音数が少ないというのはすなわち曲の情報量が減ってしまいますから、複雑な響きがない分盛り上がりに欠けてしまいそうに感じますよね。
しかし人間というものはギャップに弱いものです。エアコンの効いた部屋から真夏の空の下にいきなり出ると、いつにも増して暑く感じますよね。
音楽も同じです。静かなところに音が一気に加わることで、その点にインパクトを与えることができます。
実際に曲中の一部を例に取ってみましょう。
やはり楽曲で一番インパクトを持たせたいところといえばラストのサビです。ここで盛り上がれるかどうかで曲全体の満足感は大きく変わってきますよね。
ではまず、ラストのサビの入りです。この曲では、ラスサビの直前に落ちサビと言われる静かなサビがありますね。ラスサビ前に静かなパートを持ってくることで、ラスサビがより華やかで盛大に聴こえますので、これもやはり音の引き算と言えるでしょう。
特に、この曲の落ちサビは強力です。音がドラムと手拍子のみになります。ここまで大胆に音を抜くことも少し珍しいのではないでしょうか。
しかし、手拍子というのはとてつもないパワーを持っています。例えばライブ会場でこの曲が披露されたら、観客はほぼ確実にここで手拍子をするでしょうね。手拍子というのは誰でも参加できるパートなので、聴こえてくるだけで自分も打ち鳴らしてみたくなるものです。
ここで、曲を聴くという本来受動的な行動を能動的なものに変換して、楽曲により引き込んでいると言えるのではないでしょうか。
そして落ちサビの終わりに「間違えていこう!」と歌が入りますが、この途中で音が完全に消える瞬間がありますよね。その後にドラムのロールが入り、楽器が全て加わるという運びになっています。
この、楽器が全て加わるタイミングがものすごく心地よく感じませんか?これこそが音の引き算のもたらす効果の最たるものです。
他にもラスサビの最後、「何度も何度でも進め」の直後に一瞬音のなくなるタイミングがあります。
こういった音の引き算はギャップにより盛り上がりを作るだけではなく、曲に躍動感を与えるように感じます。一気に楽器が加わる瞬間、なんとなく前に引っ張られるような感覚を覚えるのは、私だけではないと思います。
これはSaucy Dogの多くの曲に言えることですが、音の引き算によって"タメ"を作るのが非常に上手だと思います。バンドによってはギターが2本であったり、キーボードが加わることで音の情報量が増えることもあります。ですが、どんなバンドでも敢えて情報量を減らすことで盛り上げるという手法は有効なのではないかなと、私は考えています。
独特な曲構成
邦楽の多くは、曲を構成するパーツとして「Aメロ」「Bメロ」(「Cメロ」)「サビ」から成り立っています。この曲はどうでしょうか?
「Aメロ」は当然曲の開始から始まっています。ですが、「Bメロ」は一体どこでしょうか。
結論から言うと、この曲にBメロはないんじゃないかと思っています。そして、サビが2つあるという一風変わった曲です。
そんな曲あるの?と思いますが、前例のないわけではありません。
そもそもサビというのが「曲の聞かせどころ」というざっくりした定義なので、それなら複数あってもギリギリ不思議ではないですね。
曲の構成を文字にするなら
「イントロ」→「Aメロ」→「Aサビ」→「Bサビ」→「間奏(ソロ)」→「落ちサビ」→「ラスサビ」→「アウトロ」
といった感じでしょうか。
歌詞を読み込む
まずは歌詞をざっと読んでみましょう。
「それなりに生きるくらいなら、かっこよく死にたい。」
「普通でいいからさ、もう少し正直に生きたい。」
ココロとアタマが昔から噛み合っていないのさ
チグハグな僕を見ないでくれ
君にだけは知られたくない
Don’t let it get you down
君は君らしくいてよ
Don’t worry about it
自分の為に生きて良いんだよ
間違えていこう!
君がくれる言葉には
不思議な力があると思うんだ
明日ももう少し
頑張ってみたくなる
Don’t let it get you down
君は君らしくいてよ
Don’t worry about it
自分の為に生きて良いんだよ
間違えていこう!
Don’t let it get you down
君も君らしくいてね
Don’t worry about it
自分の為に生きて良いんだよ
間違えていこう!
何度も何度でも進め
テーマ
この曲のテーマはなんでしょうか?
ここは解釈の分かれるところではあると思いますが、私はこの曲のテーマが「恐れず前向きに、あなたらしく生きる」ことにあると感じました。
曲名の「Be yourself」は、和訳すると「君らしくいてよ」。歌詞に直結するわけですね。
ここについては下の項で詳しく話しますが、前述の通り解釈が三者三様な上、私のテーマとした言葉もだいぶざっくりしてますので参考までに。
登場人物
この曲の登場人物は"僕"と"君"の2人ですね。"僕"というのが作詞者の石原さんを重ねているのか、はたまた架空の主人公なのかはわかりませんが、ここで気になるのは"君"がいったい誰かというところです。
前向きに背中を押すような歌なので、最初は聴いている人を"君"と表現したのではないかと考えていました。ですが、「君にだけは知られたくない」「君がくれる言葉には不思議な力があると思うんだ」という歌詞にあるように、どうやら"君"は"僕"にとって何やら特別な意味のある存在なようです。
こうなると"君"とは特定の誰か、もっと言えば"僕"の家族や友人、恋人であると考えるのが妥当でしょう。
この曲は"僕"と"君"の対話であるとして読み解いていくと、すんなり入ってくると思います。
しかし、かといって聴く人に向けた言葉ではないとするのは早計です。
明確な根拠はないですが、この曲は明らかに"君"の中に聴いている人を内包しています。聴いている人に元気を与えたいという思いが強く表れている歌詞だと感じました。つまり、曲の中でストーリーができている一方で、メッセージ性は非常に強い曲というわけです。
Aメロ
「それなりに生きるくらいなら、かっこよく死にたい。」
「普通でいいからさ、もう少し正直に生きたい。」
ココロとアタマが昔から噛み合っていないのさ
チグハグな僕を見ないでくれ
君にだけは知られたくない
曲の冒頭です。"僕"の葛藤、矛盾を表現していますね。
「それなりに生きるくらいなら、かっこよく死にたい。」
「普通でいいからさ、もう少し正直に生きたい。」
これらは相反する考え方ですが、どちらも本音なのでしょう。実際、皆さんもこのような気持ちを抱くことはないでしょうか。
ここで、主人公が「誰かの目」を気にして生きている、と気づくのがこの後の流れにおいて重要になります。
「平々凡々に生き抜いて死ぬくらいであれば、せめて誰かの記憶に残るような劇的な死を遂げた方がマシだ。」というのは、他人の評価をとても重要視している考え方ではないでしょうか。または、「埋もれたくない」という主人公の反骨精神というか、他人と比べてしまう性格が表れていますね。
他方で、死ぬ勇気もない自分を認めています。「正直に生きたい」とは、直前の自分の考えを受けてそれが虚勢であると言いたいのではないでしょうか。
次に、ココロとアタマが噛み合わない、という表現があります。
あれ、と思わないでしょうか?ココロとカラダ、とかなら対比の対象としてすんなりわかるのですが、ココロとアタマというのは割と同じものを指しているように感じてしまいます。
しかしここでは、ココロが抑えられない衝動であるのに対し、アタマは理性的なものであるとして象徴的に描かれています。
具体的には、「それなりに生きるくらいなら、かっこよく死にたい。」はココロによる衝動的な言葉。「普通でいいからさ、もう少し正直に生きたい。」はそれを諫めるアタマによる、理性的な言葉です。
「本当は埋もれたくないし、誰かに評価されるかっこいい自分でありたい。でもそんなのが無理なんて少し考えればわかるだろう。平凡なままでいいから誠実に生きるべきなんだ。」という、あまりにも現実的で少し後ろ向きな考えですね。
現実が見えているというのは美徳とされがちですが、夢を失うということがどれだけ人の勢を削いでしまうのか、とてもリアルに描写されています。
そしてそのような矛盾を抱えている"僕"を、「君にだけは知られたくない」んですね。ここも、ダサい自分を他人に見せてはいけないという「他人の目を気にする」性格が表れています。
なぜ「君にだけは」なのか、というのは一考の余地がありますが、安直に考えるのであれば"君"がそれだけ大切な存在だからなのでしょう。弱い自分を知られたら離れていってしまうのではないかという、喪失に対する恐れのようなものなのかもしれません。
「見ないでくれ」と言っていることから、見られてしまってはいるのでしょうね。「見られちゃった、見ないで見ないで」といった具合でしょうか。
Aサビ
Don’t let it get you down
君は君らしくいてよ
Don’t worry about it
自分の為に生きて良いんだよ
間違えていこう!
これはどちらかというと、"君"から"僕"への言葉として捉えるのが妥当でしょうか。これが前述で"対話"とした理由です。
Don't let it get you downは、和訳すると「落ち込まないで!」となります。
Don't worry about itは「心配しないで!」ですね。
ここの歌詞は深読みすることは特にないくらい、とてもまっすぐな歌詞ですね。Aメロの流れを汲むと、他人の目を気にしてばかりの"僕"に対して、自分の為に生きてみようと呼びかけている様子が映し出されています。
そして「間違えていこう!」という力強いメッセージ。
これは歌詞に対する感想になりますが、「間違えていいよ」ではなく「間違えていこう」なのがとてもぐっと来ます。隣を歩んでくれているような温かさを感じる歌詞ではないでしょうか。
更に、積極的に間違えていいんだという、間違えに対する肯定的な姿勢というのは物事に挑んでいく心理的ハードルを下げてくれます。
そして、この部分がSaucy Dogとしても聴衆に対して最も訴えかけたい部分であることは明白です。貴方に向けたメッセージでもあるのでしょうね。
Bサビ
君がくれる言葉には
不思議な力があると思うんだ
明日ももう少し
頑張ってみたくなる
これは再び"僕"の言葉でしょうか。
Aサビの言葉を受けて、明日ももう少し頑張ろうと明るい気持ちになる"僕"の様子が描かれていますね。ここは歌詞以上の意味はないと思います。
が、主人公が"君"の言葉を受けて歩み始める様子を見せることで、この曲を聴いた貴方も同じように歩み始めてほしいという意思がこもっているのかもしれませんね。
そして曲の最後に「何度も何度でも進め」と繋がります。
これは、私は"僕"の言葉なんじゃないかなと思います。流れ的には"君"の言葉の後に来ますから、"君"の言葉のように思えますが、「進め」という強い口調の言葉が特徴的です。"君"が言うなら、なんとなく「進もう」という言葉を選びそうな気がしませんか?
ここでは、奮起した"僕"が「諦めるな、進め」と自分に言い聞かせているのではないかと思いました。正直、少し無理やりかもしれませんが、その方が胸が熱いので都合よく解釈しています。
歌詞の総括
歌詞を見ていきました。
ここで断っておきたいのは、「自分らしく」というのが横柄に振舞うということには決してならないことです。さらに言えば、他人の目を気にするその性格さえ自分らしさなのです。
だから「それをダサいと思わなくていい、それも自分らしさとして受け入れた上で、前に進もう」というとても肯定的な歌詞であると私は解釈しています。
社会で生きていくのであれば、他人の目を気にするのは必要なスキルであるとも言えますから、それを否定しているわけではないのですね。
誰かに見られて、評価されて、荒波にもまれて生きていくことは避けられない。でも間違えを恐れて縮こまる必要はない。間違えてももう一度進めばいい。貴方による、貴方の為の人生なのだから。Be yourself。
おわりに
最後まで読んでくださった方がいらっしゃるのでしたらありがとうございます。
この執筆を通して、この曲がより好きになったので私としても大変有意義な時間でした。
皆さんの音楽ライフがより豊かなものになれば幸いです。
ごきげんよう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
