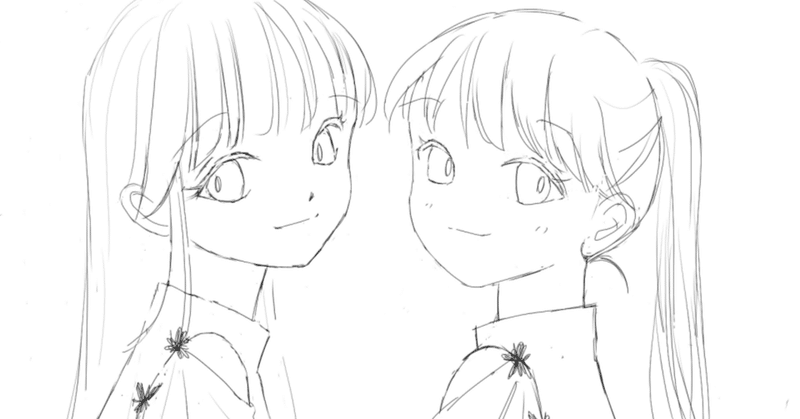
樹堂骨董店へようこそ24
1571文字あります。
イツキがどうやってレジを通らずに店からいなくなったのか那胡には全くわからなかった。店の奥から外に出ることはできないからだ。
ただ、今の那胡にはどうやっていなくなったのかということより…客がたくさん来る時間帯にいなくなったことの方が許しがたかった。
「パパから年末手当は時給の5倍くらいもらわないと割に合わないな…」
心の中で舌打ちしながらひとりレジ前に並ぶ客の会計をこなした。
冬場の昼は短い。夕方4時を過ぎる頃には日が傾き暗くなり始めた。標高の高い桜杜の空気はどんどん研ぎ澄まされてつめたく尖ってゆく。那胡は「りん」とレジを交代すると、りんが作ってくれたお汁粉をマグカップ二つに入れて、七緒の様子を見に行った。
神社の境内の隅には大晦日ということで無料で配布される豚汁と甘酒を作っている職員たちがいた。24時間営業になるため、参拝客や職員の寒さ対策として毎年行われている。わりと好評だ。
那胡は軽く挨拶を交わしながら通り過ぎて社務所に向かい、扉をノックした。
「那胡」
七緒が出てきた。
「お汁粉飲まない?」
そう言って那胡は七緒に渡した。
「あーしみるぅぅぅ」
七緒は熱々のお汁粉を一口飲むと目を閉じた。
「りんさんが作ってくれたんだ」
「美味しいね」
「うん」
以前のリリアの事件以来、りんは少しずつ社会復帰し始めていた。ほおづき屋や樹堂で仕事をするようになり、那胡たちともふれあうようになっていた。
「やっと休憩入れたね」
「毎年のことだけど大晦日は那胡のサポートが必要だよ。こんなん夜通しやってらんない…」
七緒がしみじみとお汁粉をすする姿に那胡は思い出した。
「そういえばパパが仕事サボってどっか行ったまま帰ってこないし」
昼間にいなくなってまだ戻らないのだ。
「んーイツキさんがいなくなるのはいつもの事だからなぁ」
七緒はあまり気に留めることもなかった。子供のころからイツキがフラッといなくなったり、唐突に現れたりするのをよく見ていたからだ。
ふいに、夕闇にまぎれて見覚えのある男性が本殿に向かって歩いてゆくのが見えた。
「…小林さん?」
七緒が目で追っている人影を那胡も見た。
「あ、あの人なら昼間にうちの店にも来たよ?パパの事聞かれてさ…こんな時間までいたんだ…」
「何聞かれたの?」
「元気にしてるかって」
「ふうん」
「小林って言うの?」
「うん。役員の人なんだけど…なんで年末にうちに来るんだろ。遠いのにわざわざ…」
「…七緒ちゃんすごくイヤそうな顔してる…」
「ちょっとね…やなんだ」
七緒にとってはイツキのことをコソコソと調べようとしているのが鼻につくのだ。会議の場で話すだけならともかく、実際にここまで来るのが気に入らない。年末はどこも忙しいから通例では出張は入れない。つまり、個人的な用事で来ているという事になる。
「なんなのあいつ」
七緒は観察することにした。
「七緒ちゃん顔がコワイよ…」
その時
「あっ、流だ」
那胡が境内をはさんだ向こう側の杉林に流が歩いているのを見つけた。こちらに向かって歩いてくる。
「流?誰?」
七緒は那胡の瞳の見ている方角を見るが、人はいない。
「誰もいないけど?」
でも、気配だけは感じた。強くて透明で研ぎ澄まされた空気だった。この敷地内でそんな気配を発している者はほかにいない。
「この気配は…人間じゃないね」
七緒には流という人物の姿は見えない。でも那胡には見えているようだ。
「七緒ちゃん、あの人「流」っていうんだ。目が赤いんだよ」
那胡の指さす方に人影は全く見えなかった。
「那胡、私には見えないよ。気配だけはわかるけど。すごく強いエネルギー…」
七緒は那胡の顔を何気なく見た。いつものぽやっとした目ではなかった。うっすらと赤みがかって見える。
七緒はふいに祖母が昔教えてくれたことを思い出した。
(桜杜には異形と人間の橋渡しをするものが必ず生まれる)
もしかしたら那胡はそれかもしれない。七緒はそんなことを考えた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
