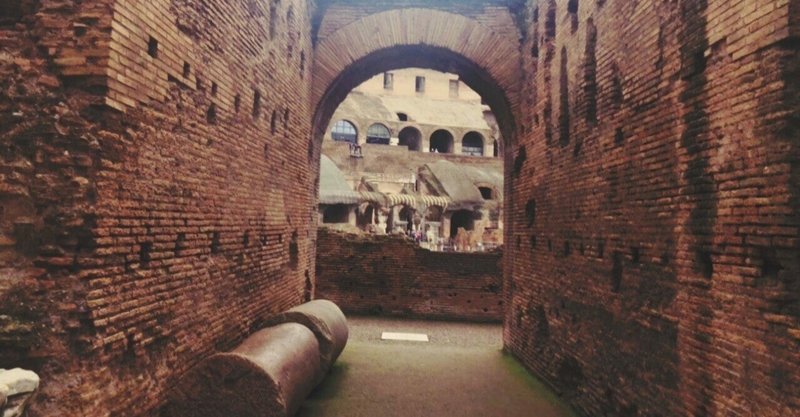
歴史嫌いに飲ませる薬 その二
前回からの続きです。前回記事のリンクは文末に貼っておきます。
時間に対する抵抗
ホメロスの『イリアス』には次のような言葉が出てきます。「つねに卓越をめざせ」。シーザーはスペインのカディスで、四十年も生きていて、まだ不滅の名に値するようなことはなにも成しとげてない、と嘆いたそうです。この卓越とか不朽という言葉に古代人のものの見方がよく表れているようです。
過剰な競争に倦んだ今日では敬遠されそうな言葉ですが、時代が違いますから受験や市場での成功を煽る言葉ではありません。先にお話しした古代の歴史観と関係があります。
ギリシア・ローマでは、五感で知覚できる世界というのは永遠なるものの表出であると考えられました。表出というのは直接知覚できない普遍的なものが見えるようになるという意味ですから、表出するものは表出されるものの一面にすぎません。その意味で、人間も含めすべては不完全です。
ですが、「不完全」には積極・消極の二方面があります。消極の方面は何かが欠けているという意味ですが、積極の方は完全なるものの理想がどこかにあるということです。それがなければ「不完全」という言い方は出て来ませんね。不完全ということは完全なるものが想定されている。
この理想が範型として目に見える形で世界に表れるものが美であり、そのひとつが偉大な行為や言葉である。それは不完全な人間が完全にもっとも近づいたものである。そのような世界観を古代のひとびとはもっていたようです。
手本となる偉業が幾世代にもわたって語り継がれるようにするのが、詩人とか歴史家の役割でしたね。しかし、そこには、そのような手本はけっして時代遅れにならない、という前提があります。
歴史的世界の制約から自由になって行動するときにこそ、人間は人間として完全になる。文字通り天空に上って星になったりする。神々の横に列することになる。なぜかというと、人間とは自由な動物であるからである。これがギリシア・ローマの人間観です。
古代における自由はわれわれの自由とはちがって、何か他の目的を達成するための手段ではないという点にあった。自由な行為や言葉は、それ自体において人間の偉大なものが輝き出るもので、結果は二の次であった。
だが、そのようなものは何もあとに残さないから、放っておけば忘却される。数学の公理や自然の法則みたいなものであれば、いったん忘れられても、また何度でも再発見される可能性が高い。人間の行為や言葉はそうではありません。いったん忘れられたら、おそらくもう二度と取り戻せない。
歴史は、その容赦のない時間の流れから人間存在というものを救い出そうとする営みから生まれた。生まれては死んでいくだけの人間の存在を時間の流れから引きあげようとする努力でもあったんです。
しかし、近代の歴史観というのは、まさにこのような考えを不可能にしました。歴史的世界においては、すべては時間のなかにある。であるから、時間の流れとともに相対化される。昨日までは手本であったものが、今日にはかび臭いものになる。ある時代に甲であったものは、次の時代では乙になる。万物は変転して已むことがない。
そうであるから、偉大なものの意味も時代とともに変遷せざるをえない。神々の領域たる「永遠の秩序」とか、普遍的に偉大な行為・言葉などというものが信じられなくなった今日では、今さら古代の歴史観に立ち戻れと言われても無理な相談です。ですから、今日の歴史家も詩人も自分の仕事をそのようには心得ていません。
現代における時間に対する抵抗
ですから、こんな古代の歴史観などというものが、なんの役にも立たない歴史の一例であるように思えます。そんな昔のことを知ったところで、ぼくらの生活にはなんの帰結も引き出すことができない。なぜそのようなことを思い出させられるのか。それが今日の歴史に対して向けられる問いですね。
だけども、時間の流れに圧倒されたような現代においても、それに抗しようという試みがあちこちに残っています。自分の気づいたところでは、現代の直面する問題について、古典を読み解くことによってなんらかの手がかりをえようとする思想家たちがいます。文献学と呼ばれるような伝統の継承者たちです。
具体的な名前を挙げると、これまでも何度かとり上げたニーチェとかガダマーとかアーレントとかいう人々です。なんだか古臭い古典ばかり読んでいる人たちなんですが、彼らの関心は必ずしも過去にあるのではない。そうではなくて、現在わたしたちが直面する困難な状況を理解するために古典に向かう。そういう人々です。
その前提としては、次のような考えがあります。「古典」とは、繰り返し読み継がれることによって、歴史の相対性を抜け出したテクストである。そこ`に書かれているのはそういう意味で、時間の流れから引きあげられた「偉大なことば」である。であるから、書かれた当時と同じように、現在でも無意味でもないし理解不能でもない。
ただし、テクストも表出である以上不完全なものです。それが生まれた時代の産物です。ただ古い言葉で書いてあるというだけではありません。書いてある内容そのものも時代の制約に縛られている。だから、そのテクストの背後にある「精神」を汲みとって、自分に時代に応じた意味を取り出してこなければならない。これが「解釈」と呼ばれるものです。そのような問題意識で古典を読んでいるわけです。
もう一つは、歴史学の内部でなされている反省です。個人の行為や言葉を軽視しがちなマルクス主義の唯物史観とかリベラル進歩史観に対する批判として、「自由主義史観」などと呼ばれるものが提唱されてます。ヘーゲル的な歴史の法則とかマルクス的な構造的要因といったものよりも、行為や言葉によって現われる個人の主体性を重視する立場のようです。
その背景には、歴史を作るのは個人であるという考えがあります。個人が行為や言葉によって歴史を作る。古代の理解とはちょっと異なる点もあるんですが、ヘーゲルやマルクスよりは近い。
残念なことに、日本ではこの自由主義史観はいわゆる歴史認識問題に絡んでいる。だから反リベラル・右翼的なものと見なされています。それに批判的な人たちはこれを「歴史修正主義」とも呼んでいる。自分はそうした論者のものをまだきちんと読んでいないので何とも言えんのですが、近代的歴史観の批判という一面もありそうなんです。
むろん、近代史学の恩恵は否定しえません。われわれは古人よりもより精確な歴史知識を豊かに保有している。これは近代史学の勝利です。覚えることが多いのはその裏面で、必ずしも悪いことではない。いくら効能がよくわからないからといっても、それを一切合切放棄するのは乱暴です。
だけども、得たものがあると同時に、何か失ったものもあるようである。詰め込まれた歴史知識を持て余してるぼくら自身が、どうもその証拠です。
近代が失ったもの
そこで、文献学的アプローチの範に倣って、古代の歴史観を写し鏡として、ぼくらが失ったかもしれないものの具体例をひとつ考えてみましょう。
前回お話ししたヘーゲル以後の歴史観においては、歴史の最先端である現在を出発点として歴史を遡って見ます。歴史とは現在にいたる必然の過程である、という前提で過去の出来事をつないでゆきます。
ですが、そうなると、何が歴史として書くに値するかを決める基準は成功です。結果的に成功した者たちがどのような因果関係によってつながっているかを追っていくのが歴史になります。敗れたものの経験は歴史のゴミ箱に捨てられる。だけども、この勝ち馬もまた新しい馬に追いこされていく。そうなれば、新しい勝ち馬の視点から古い勝ち馬の評価も書き換えられる。これを平たく言うと、「歴史はつねに勝者によって書かれる」ということになりますね。
しかし、わたしたちはこれ以外に何を歴史とするに値するかを判断する基準をもちません。真理が歴史において実現するのであれば、歴史の最先端である現在の真理が基準たらざるをえません。それに抵抗するものはすべて進歩に抵抗するもの、すなわち反動勢力です。であるから、その都度の勝ち馬に乗り換えていくという以外に方法はないわけです。
そうなると、歴史は党派的にならざるをえない。この党派性を避けようと思えば、たまたま史料の存在する事実を無意味につないでいくだけの不毛な営みになるかです。今日の歴史はどうもこの二極を往ったり来たりしている。
古代の歴史は異なります。ホメロスの『イリアス』を読んでも、勝者であるアカイア人の英雄の偉業も、敗者であるトロヤ人の英雄の偉業も、どちらも公平に書かれている。負けた方は絶対悪であり全否定しておけばよい、という今日ありがちな見方はしないわけです。それぞれが自分の投げ込まれた運命のなかで自己のベストを尽くしたわけで、たとえ歴史の敗者となっても、偉業は書き残され語り継がれるに値する、と考える。
それどころか、かえって敗者の歴史の方に深い意義を見てとることさえできるかもしれない。ギリシア悲劇というのは歴史ではなく文学なんですが、投げ込まれた運命に耐え、なおかつその運命に打克とうとし、それでもなお運命に呑みこまれていく人びとを描く。しかし、観客はそれを笑ったりしない。自分たち人間とはそういう存在であるという共感がカタルシスを生み、共に涙を流す。歴史はそのような人間存在の悲劇性を確認させてもくれるわけです。
これは受動的な運命論とはかぎりません。運命に耐え、できることなら打克とうとするところに人間らしさがある。それでも最後は敗れるんですが、そこで最初から「仕方がない」と諦めないところに、人間の偉大さが輝き出る。人間とはその有限性を自覚しつつ、それを乗り越えようとする唯一の存在である。それが歴史が保存する偉大なものである。
そして、そのような行為や言葉が歴史を変えることがある。というより、そうのように生きる人がいるから、今ここにないものが始まって、歴史という同じことの繰り返しではないものになる。以前にある記事で引用したマックス・ヴェーバーという人の言葉をもう一度引いてみましょう。
「人は不可能なことに何度も手出しするすることがなかったらば、可能なことを達成することもなかったであろう」
これがあまり身近に感じられないのであれば、変なところからもう一つ例を引いてきましょう。自分が子どものころの英雄(!)はマンガに出てくる矢吹ジョーというボクサーとキャプテン・ハーロックという宇宙海賊だったんですが、彼らに共通のセリフとして次のようなものがありました。
「男にはな、負けるとわかっていても闘わなければならないときがあるんだ」
性差別になりかねない部分を差し引いて、これを結果が成功であったか失敗であるかは偉大さには関係ない、と解釈すれば、古代から引き継がれてきた「偉大な言葉」が現代にもまだ通用している一例ともとれます。
これに対して、ぼくらの歴史的知識は古代においては想像もできないくらい豊かになったのですが、それが必ずしも教養につながらない。試験で高得点をとったりクイズ王になったりはするかもしれませんが、敗者を時代の流れに抗して散っていった愚か者として無視したり非難したりするだけで、そこからなにも学べない。
そして、「そんなことやってもムダさ、もう時代がちがうんだ」を万能の口実として重宝するようになる。以前にいちど書いたことがありますが、俗な言い方をすると、傍観者として勝ち馬に乗りがちで、自分たちが歴史のなかで生きている、歴史というのは自分たちが作るものである、という自覚に欠ける。
そうして、歴史というのは現在を正当化するかぎりにおいてしか意味がなくなる。そうなると、歴史から学べることはもうぼくらがとうに知ってることばかりですね。ただそれを補強するだけの材料にしかならない。
この偏狭な見方が歴史認識問題にどうかかわってくるかについては、長くなるのここでは省略しますが、いずれにしても歴史を知ることによって得られる教養とか効能というのがわかりにくくなったのは、この辺にも一因がありそうなんです。
効能のわからない薬を飲み続ける
ぼくらには歴史があって、その歴史をぼくらは学ばなければならない。この一見自明で不変の真理を表すような言明においてさえ、どれだけの歴史が背後に潜んでいるか。どれだけの解釈を施さなければ、その真の意味が理解できないか。さらに悪いことに、自明のこととして教えられている歴史の問題は、実はまだ未解決、現在進行形の課題である。今までの話をまとめると、そういうことになると思います。
じゃあ、専門家が問題を解決するまでは、歴史を義務教育や必須教養に含めるのはやめにしよう。そういう決定もできます。でも、おそらく歴史の問題が完全に解決されるということは、少なくとも近い将来にはありえなさそうなんです。だからといって、歴史という学問を捨て去る勇気をわれわれはもたない。
ですから、わたしたちは効能の怪しい学問の営みを続けていかないとならない。そうしながら、その学問の意義というものも同時に考えていかないとならない。バカげた話に聞こえるんですが、実はこれは歴史学に限られた問題でもありません。多くの学問というのはそういうものです。
こんな落ちのない長話を私になさしめるのもまさに近代の歴史意識という奴で、最後まで読んでくださった方には気の毒だったかもしれませんが、それがわたしたちが投げ込まれた運命、耐えるべき運命でもあるわけです。
だけども、どういうわけか、こういう話を聞いた後のほうが、歴史に興味が掻き立てられる。歴史というものが過去の無味乾燥な事実を機械的に記録・記憶していくという不毛な営為ではなく、人間の自己理解というものと深く関わっている。哲学や文学という分野とも密接な関係がある。そう悟らされるわけです(私のつたない文章でそれがなしえたか否かは別の問題ですが)。
タコツボ学問の弊害
もう6000字を越えてるんですが、最後にもう一点。少なくとも自分がここ一年くらい集中して勉強してきた近現代ドイツ思想では、歴史の問題は哲学上の問題として扱われています。というよりも、これが哲学のあり方を根本から揺るがす主要な問題のひとつと認識されているようで、主要な思想家はほぼ全員この問題に取り組んでいる。
ところが、ここ日本では、歴史学と哲学、文学の棲み分けがもっと明確で、同じ学部に所属しながらもあまり交流がないようです。学問の専門化が進んだためですが、それ以上の理由もありそうです。
かつて丸山真男という人が、日本の輸入学問はタコツボ型であって西洋のようなササラ型になっていない、と指摘したことがありました。ササラというのはお茶をかき混ぜる茶筅(ちゃせん)とも呼ばれる道具です。竹でできたブラシみたいのを想像してみてください。竹の先を細く切り分けて作るのですが、根元ではつながっている。
このササラのように、西洋では学問は専門化していくんですが、根っこに遡ればつながっている。だから哲学者が歴史を語ったり、歴史学者が哲学みたいなことに関心をもったりする。日本では学問が別々に輸入されてしまったために、タコツボのようにどこまで行ってもつながらない。そういう指摘だったんです。
だから、日本の哲学徒には、今日でも19世紀以前の哲学観を堅持して、歴史の問題を視野に入れない人が多い。そういう印象を受けます(あくまで印象論です)。だけども、歴史の問題、時間の問題を考えずには、ヘーゲル以降の近・現代思想というのはどうも理解できそうにない。歴史嫌いのつけは、必ずしも歴史を知らないということでは済まないようなんです。哲学や文学だけではなく歴史が人文的教養に欠かせないと言われることにも、やはり何か理由があるんですね。
前回記事のリンクはこちらです。
ここから先は
¥ 100
コーヒー一杯ごちそうしてくれれば、生きていく糧になりそうな話をしてくれる。そういう人間にわたしはなりたい。とくにコーヒー飲みたくなったときには。
