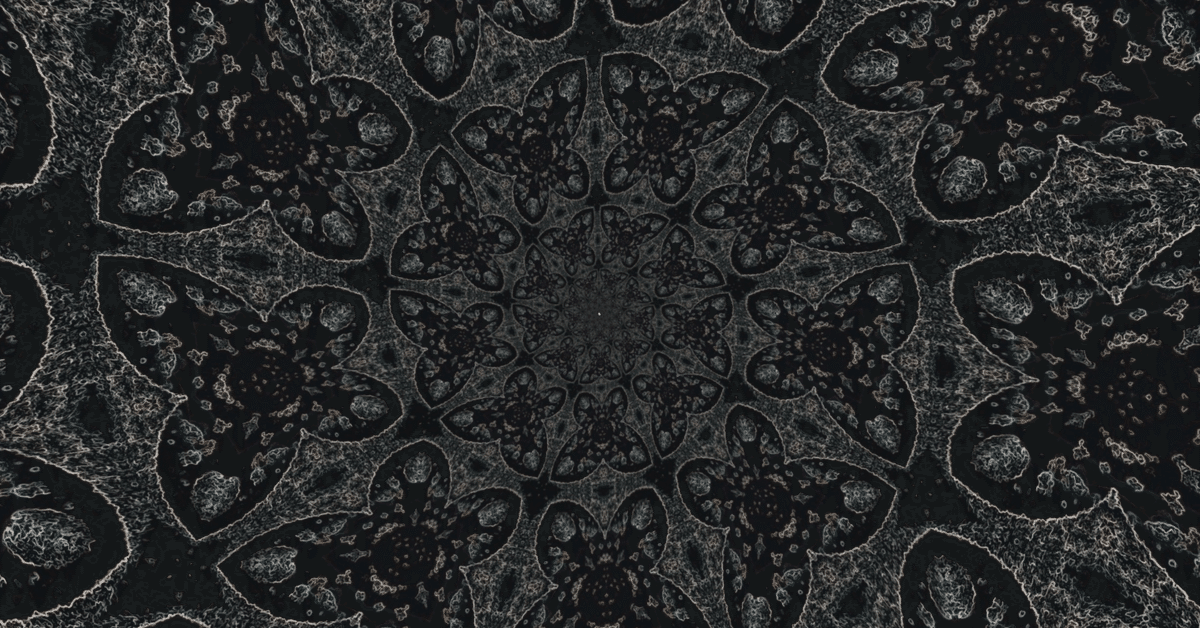
Photo by
cinemakicks
幾夜の孤独
わたしの声は、誰にも届いていない。
そんなのは錯覚だ、とわかっているつもりでも、その錯覚は毎日のようにわたしを襲ってくる。
そのたびに、わたしは孤独の底――地獄のように深い穴の底に突き落とされたような気持ちになる。
家族、友人、恋人、誰かがそこに蜘蛛の糸を垂らしてくれたとて、わたしはきっとそれに気がつきもしないだろう。
孤独は、・・・・・・いや、それにも満たないほんのちょっぴりの寂しさは、わたしからあらゆる感覚を奪ってしまうから。
やさしさ、ぬくもり、あい、いつくしみ、おもいやり、ゆうじょう、ゆめ、のぞみ、えがお、・・・・・・
そんな尊いもののすべてを感じ取るための機能は、ほんのちょっぴりの寂しさでいとも簡単に死んでしまう。
だからわたしは、わたしという女を盲信し、わたしの言葉をひとつも取り零さず受け止めてくれる、そんな都合のいい存在を頭の中で作り上げては、その馬鹿馬鹿しさに笑ってしまったり、ときには泣きたくなったりしている。
そのたびに、今夜一晩だけ泣き伏せばまた笑って生きてゆける、そんな期待に身を沈めて眠りにつく。
そんなやり方でしか、わたしは何百という苦しい夜を越えられなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
