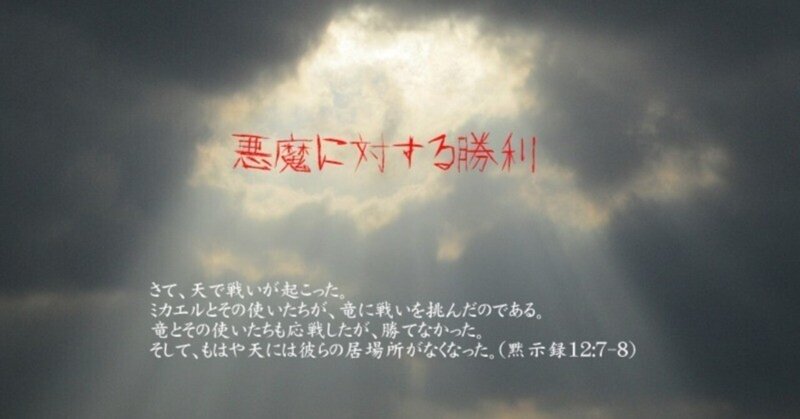
悪魔に対する勝利
黙示録の講解説教も12章まで来た。後半に入るわけだが、説教者はこの12章を、オペラ劇のようだ、とまず称した。芸術に疎い私には、もうひとつのその喩えがしっくりこなかったが、場面が変わるひとつの暗転のようなものは感じた。
女と竜が登場する。ここまでは、専ら神がイニシアチブをとって、ヨハネに関わってきたように見えたが、この竜が現れるとともに、神に対抗する勢力が立ち上がるような光景が目に付くようになる。必ずしも整然と、そこで起こる事件が展開するようには思えないが、次々と様々な出来事が目の前で展開するようになってゆく。
説教者は、最初に宣言しておく。これはこの世界のことであると読むべきである。否、これは私たち自身のことである、という姿勢が必要なのである。そして、いま自分が当たり前のように見ている風景を、新たな眼差しで見つめることが期待されているのだ、という。自分を、教会を、そしてこの世界を、違ったものとして経験しなければならないのである。それは、ハイデッガーが、凡庸なひととしてのあり方から、本来的なあり方へと移るためには、死というものを考えてそこで反射させた光の中でいまある自分を見ることを求めたことと類似するように見える。私たちは黙示録を通じて、いまここにいる自分の姿を捉え直さなければならないのである。
場面では、女が先に登場するが、今回の説教では、竜にまず焦点を当て、竜について長く検討する。「そして、竜は海辺の砂の上に立った」(18)という結びに、まず注目することから始め、いくつかの観点を指し示してゆく。
この「レスポンス」は、説教の再現を担うものではない。私の心にフラグを立てた点について触れ、私がそのフラグの周りをぐるぐる回ればそれで十分である。
ここのところ、各地の教会で、「黙示録」が比較的よく読まれているそうだ。そして、ここに出てくる竜が問題である。それはここで「悪魔(ディアボロス)」ないし「サタン」と呼ばれている。これを問う説教が、教会には欠けていたのである。ならば、教会がその危機に、無意識にでも何らかの気づきを得た、ということを表すのであろう。
悪魔とは何か。いまここはそれを研究する場面ではない。ただ、悪魔を問わない教会は、実は神を見失っているのかもしれない。また、罪を問わない教会は、悪魔を問わないことと等値であるかもしれない。聖書の中で、悪魔を退散させたのは、イエス・キリストしかいない。それもかなりの力を用いてである。私たち生身の人間にはできないことだろう。悪魔の言いなりになっている者が、悪魔など問題にせず、神はこんなにも優しいお方だ、というような詐欺を平気で行っているようにさえ思えないか。それはまた、人間でなんでもできてしまう、というような思い込みがベースにあるようなものであり、実際はサタンに操られている、ということであるに違いない。
説教者はまた、「時代精神」という言葉を今回多用した。どうしてもこの語は、ヘーゲルの「世界精神」や「絶対精神」の概念を思い起こさせる。その具体的な問題として、ゼノフォビア(クセノフォビア,xenophobia)という言葉があることが指摘された。未知のものに対する恐怖や嫌悪を意味する語だと思うが、懸念されている点としては、外国人やよそ者を嫌悪し排斥する気質を表すのであろう。異質なものの排除は、レイシズムにもつながるが、そのように大きな話題に上らなくても、日常的に私たちの周囲で見られる現象である。それどころか、私自身もまた、それをしている、あるいは無意識の中にそれがある、と考えたほうが妥当であろう。
キリスト教会だからそれから免れている、とは私は思わない。いくらでもあると思うし、自分の善意を前提しているようなあり方があったとすれば、それがいちばんよくないと考える。『福音と世界』誌には、ここしばらく「教会におけるマイクロアグレッション」が連載されている。いかにそれが根強くはびこっているか、白日の下にさらすようなレポートの翻訳と解説である。
12:7 さて、天で戦いが起こった。ミカエルとその使いたちが、竜に戦いを挑んだのである。竜とその使いたちも応戦したが、
12:8 勝てなかった。そして、もはや天には彼らの居場所がなくなった。
説教者は、この天における戦いに目を移す。竜は、勝てなかったのである。この後直ちに、竜は地上に投げ落とされた。そこから地上で暴れ始めるのであるが、竜はすでに天にその居場所を欠いているのである。
ここに大天使長ミカエルが登場する。ダニエル書12章に、その勇姿が描かれている。このダニエル書もまた、預言書というよりは、黙示書なのである。
人間は、どうしても人間的な「時間」の中でしか動けないし、思考できない。「永遠」にしても、人間のイメージからでしか捉えられないである。だから、竜とミカエルとの戦いについても、この黙示録の記事を、未来におけるものだと考えてしまう。だが、そういう「時間」を超えている神の次元においては、この戦いはもう、神の側の勝利が決まっている。奇妙な論理に聞こえるだろうが、このことを信じるというのが「信仰」なのである。
だから、イエスは「わたしは既に世に勝っている」(ヨハネ16:33)と告げたのであろう。それはまた、死に勝つということをも意味している。
これに関して、説教者は、初期の教会の情景を示した。もちろん礼拝堂などないが、カタコンベと呼ばれる、洞窟のような墓所に集まることがあったという。そこでこそ、聖餐をしたというのである。棺の上に、キリストの肉と血を象徴するパンと杯を置き、その命を受ける。死に対する感覚は、現代人とは明らかに違うものがあるものと思う。同じことをいま私たちがなすべきだということではないはずだし、できないだろう。だが、いまでも伝統的に、教会が聖餐の台をそのように見立てることがある。象徴的な形でしかなくとも、私たちは、キリストの死と復活を、全霊を以て経験しなければならない。
竜に先立って登場した女について、少しの時間だったが説教者は説いた。これを母マリアと解する人がいるのだという。だが、それを「教会」と読みたい、というものだった。しかもそれは、キリストの後に始まったものとは捉えず、旧約聖書の歴史の中から受け継がれてきた、神の民というものがつながる一筋の道だと捉えるべきだ、とするのである。キリストにしても、マリアから産まれた、という現象だけで口にしているならば、不十分である。天の川のように壮大に流れている、神の民の歴史の中に産まれたのではないか。
教会はそうして、イエス・キリスト以後2000年にわたって、その流れの中で受け継がれてきた。私たちのところにまで、それは届いている。私たちもまた、可能ならばそれを受け継いで、つなげていかなければならないだろう。神の時が完成するのを待ちながら。
あの竜は、私たちの中で働いている。見える形で暴れることもあるが、一人ひとりの人間にこっそりと忍び込み、潜伏したまま人間たちを操っているような気がしてならない。私もその危険から免れているわけではない。だが、その警告を与えるだけの知恵が、どういうわけか与えられている。逆に言えば、それくらいのことしかできないのだが、それくらいのことが、ミッションだということである。
説教者は、自らを「正義」と称する者たちの危うさについて、最後に触れた。「自分は正しい」と発する者や、そういう態度をとる組織である。彼らは、「罪」や「悪魔」については語らない。それ故に、「愛」や「赦し」が言えないのである。説教者はただ、「愛」や「赦し」を彼らは言わない、という言い方をしたが、それは不十分であったと思う。口先だけでは、いくらでも言えるのである。「愛」とか「赦し」とかを口にしているのでありながら、自らを含む人間の「罪」について触れない、あるいは「悪魔」の存在を隠し通す、そうした者と組織が、危ないのである。この点を強調しないと、「悪魔の存在が分からなくなっている」とか「私たちを操ろうとするものがいる」とか告げていた留意点が、蔑ろにされてしまう。
現代人は、最高の思想の中にいるわけではない。思想は進化するものではないし、新しい時代が最善であると単純に決めることはできない。「世界精神」のひとつの現れにすぎない。その証拠に、私たちが当たり前だと思いこんでいる世界観は、デカルトに端を発する考え方に大きく影響を与えられた空気の中で育まれたものであるし、その束縛から容易に抜け出せているわけではない。西欧文化の前提や枠組みの中に、あまりにも制約されているものであろうし、科学技術を生み、またそれから逆に規定された思考法に基づいてしか考えられなくなっている。
その意味では、私たちは自由を完全実現しているなどとは到底言えない。それなのに、私たちの世界観が最高である、というように思いなしている。そこに、悪魔の策略が簡単に忍び込むことができるという点を、なんとか警戒するだけでもしておかねばならないのである。
だから、説教者が告げるように、この制限された時代において、制限された私たちの能力や認識能力を頼りにするしかないままにも、「罪」を経た上での「愛」と「赦し」の言葉を、イエス・キリストから聴くようにしよう。そして天を見上げれば、神の国においては、すでに神の勝利が決まっており、私たちも勝利を確信した歩みを、一歩また一歩と踏みしめていきたいものである。キリストに似たはたらきを、ささやかながらでも、一人またひとりと、できたらよいと祈り続けていきたいものである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
