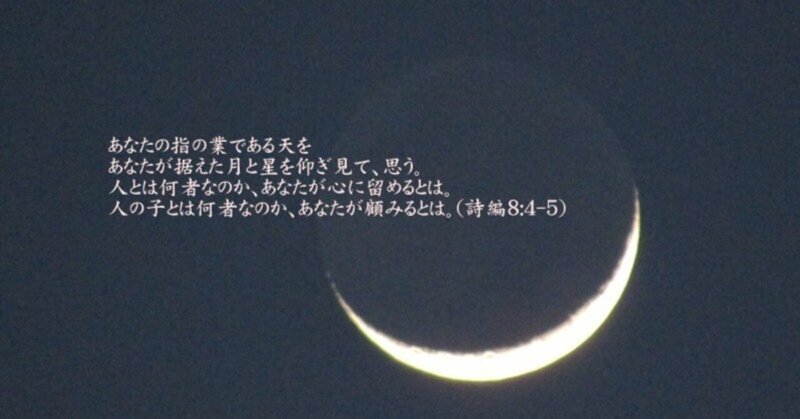
折り紙をしたことがない
ある事情があって、小学生たちのクラスで、工作をさせることとなった。しかし教材があるわけではなく、自分で考えてみることとなった。教会学校では毎回やっていたようなことだ。いけると思ったが、手近なところに素材がなく、思ったものが作れそうにはなかった。
確かこういうのがあった、とウェブサイトを探した。いまの時代はこうして情報が手に入るからいい。細長い紙1枚でできる。何度か同じように折っていき、最後に後ろ側に差し込んで、のり付けする。作業は、これだけである。
もちろん、今度四年生になろうという子たちにとっては、簡単ではないことは予想された。だが、作業工程が単純過ぎるので、なんとかなるのではないか、と考えていた。
甘かった。
うしろに折り入れるところがヤマかと思っていたら、とんでもなかった。まず、折れないのである。板書して、折り方を示し、折り目をつける、という図を明確に示していたが、指示の言葉がまるで通じない。折り目で三角が10個できたらそこで切ろう、と図示もしていたが、折り方が分からないと言ってきた子は、11個になっていた。
そもそも、辺と辺を揃えて折る、ということが、まるで分からない。いや、クラスにはそういう子が1人や2人はいるものだ――と思ったら、大半が分からない。1人か2人が、指示通り折れた程度であった。
折って折り目をつける、この意味が分からないような子が、半分くらいいた。同じ向きにそろえて真似してごらん、と目の前で模範を見せても、途中から勝手に方向を変えてしまうから、全く分からなくなってしまう。何度目の前で示しても、できない。
小学校低学年の子は、空間把握のレベルが非常に低い。立体図形を上から見たらどうなるか、ということの想像ができないし、立方体の見取図など、とてもとても描けやしない。それは、分かっている。しかし、辺と辺を合わせて折る、という折り紙の基本行為が、全く未知の世界のような反応をしているようにしか見えなかった。
それで、訊いてみた。「折り紙したこと、ある?」
すると、複数の子が答えた。「ありません」
したことがあっても、殆ど経験がないに等しい程度にしか、体験していないことが判明。
これでは、ボールを投げたことがない子と、いきなりキャッチボールをしようとしたようなものだ。かけ算九九を知らない子に、かけ算の筆算の勉強をしよう、ともちかけたようなものだ。
折り紙を、知らない。したことがない。これは、由々しきことである。折り紙は、空間把握のためにも素晴らしい営みだし、指先の力の入れ方や揃え方など、手先の技術を身に着けるにも適切である。手先指先の動きの器用さは、頭脳の働きにも関係がある、とも言われる。
そうだ。塾に来る子たちである。それなりに意識の高い子が多い。成績は様々だが、中にはかなり優秀な子もそこには混じっている。だが、折れない。折り方が分からない。
そう言えば、これまでもこの手先の問題には、気づいていた。六年生あたりに、1枚の紙を折って、正三角形を折れ、との問題を、時間があるときに出すことが私の趣味である。図形の難問を解く子たちが、全く折れない。三辺が等しい、という性質を考えれば、どうすればよいか気づく子が現れてもおかしくないのに、気づかない。そして、どこかに合わせて折る、という基本ルールを知らないし、折り目がきれいにつく子のほうが珍しかった。思い返せば、折った経験が殆どないような様相をそれは示していたのだ。
よく、日本の文化として、折り紙を外国人に紹介する、という場面の文章が教材に出てくる。中学生の英語ではもう常識だが、外国人から日本文化について質問されて、自分は答えられなかったから、これから日本文化に関心をもっていきたい、というような筋書きが英文で書かれている。あるいは、そういう対話が書かれている。このとき、折り紙というネタも使われることがあるわけだ。
それどころではなかった。折り紙で鶴が折れる子すら稀であるのに加えて、そもそも「折る」という経験をもつ子が少ないときた。文化と呼べるものではない。
このようなズレは、実は随所にある。草花の名を、あまりにも知らない。ツユクサなどというレベルではなく、レンゲソウを知る子はクラスに1人くらいしかいないのではないか。大人は、子どももこのくらいは当然知っている、という思い込みを、一度脳裏から消さなければならない。
生活環境の問題もあるから、一概には言うべきではないが、ともかく「お勉強」という、紙の上で文字を読み書くことだけで完結するかのような錯覚は、見直したほうがいい。見よう見まねでやる、ということさえしようとしない子どもが、権利主張ばかり覚えていく社会を、懸念する。悲観するばかりでなく、良いところも見ているつもりだが、それでもなお、心配である。
尤も、私たちの世代も、上の世代から見ると、同様に心許なかったであろうことは、ほぼ確実である。人類はこうして変化しながら、それなりに生き延びてきたのではあるのだろう。卓袱台を返すようで申し訳ないが。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
