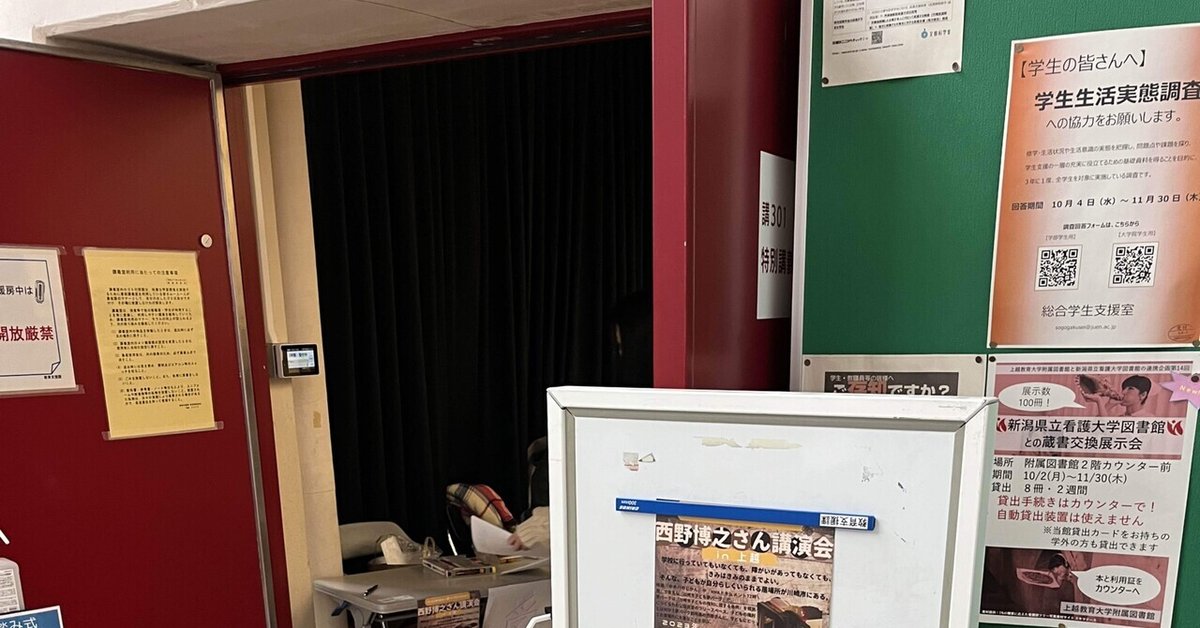
子どもはだんだん人間になるのではなく、すでに人間である。 西野博之さん講演会〜子どもの権利条約から夢パークができるまで〜
川崎市子ども夢パーク前所長 西野博之さんの講演会。
ゼミのキャナイによる主催。
少しだけだが、お手伝いさせていただいた。
4月に訪問させていただいた時も、お話を聞かせていただき、涙が流れる。
今回、二回目だが、また涙が流れる。鼻をすすりながら拝聴。
4月にも聞いた内容もあったが、書き出したメモが止まらない。基本的に話を聞いているのだが、2時間があっという間であった。
終わった後は、ディズニーランドの帰りのような感覚である。
不登校、引きこもりの支援を始めてから37年になるそう。
今でこそ、不登校が全国で約30万人というニュースが取り沙汰され、文科省も学校以外の学びの場の在り方へ推し進めている。
多くはこれから立ち上げよう、整備しよう、検討しようとしているのに、そのような居場所を30年以上前から運営されている。
我々が思い描く教育や社会の在り方をもうすでに具現化してしまっている。立ち上げ当初、住民の反対運動にあった話もあった、こういう方のことをイノベーターというのであろう。
そんな西野さんの話にはとんでもない重みがある。
・10~39歳の死因の第1位は自死
昨年度、小中高生での自死は514人。1日1人以上のペースで、全国のどこかで子どもが自ら命を絶っている。
コロナ禍の一斉休校から不登校の増加に伴い、この数は増えている。
コロナで亡くなった子どもは何人いるのだろうか。
当時の状況を鑑みれば、政府の対応を批判しても仕方ないかもしれない。
ただ、この変動は何によってもたらせているのか、あの期間に子どもたちの失ったものは何なのかは検証する必要があるのではないか。
不登校、引きこもりは命に関わる問題である。
・自己肯定感、自己有用感の低い日本
貧困、大人の過干渉による子どもへのストレスは計り知れない。
子どもの自信を奪うのは、大人の不安である。
自分の子どもには、人よりも勉強ができてほしい、スポーツができてほしい、友達を多く持ってほしい…など、子どもに価値を押し付けて、自分自身が正しい親として見られたいという大人の不安が子どもの自信を奪う。
早期教育の過熱は危険ではなかろうか。
幼児から、過度に読み書きやスポーツを習わせたりする風潮がある。幼稚園や保育園の中には、小学校へ適応させることを目的化しているところもある。そんなことよりも大切なことは何かを見失っているのではないか。
・子どもはだんだん人間になるのではなく、すでに人間である。(コルチャック医師、ポーランド)
生まれたときから一人の人間であり、権利の主体である。
子どもは未熟であるという思想は、職人の世界での半人前思想に由来する。
職人の世界で親方が見習いに「まだそんなこともできないのか!」と喝を入れるような場面。あの思想が家庭や学校に入り込んできた。
・川崎市子どもの権利条約(2000年)
1.安心して生きる権利
2.ありのままの自分でいられる権利
3.自分を守り、守られる権利
4.自分を豊かに、力づけられる権利
5.自分の決める権利
6.参加する権利
7.個別の必要に応じて支援を受ける権利
これらを具現化するために、どのような施設にするかを地域の子どもたち主体のワークショップの中で検討してきた。
模造紙を子どもたちが囲んで「ここに木を植えたら」「ここは広場にしよう!」といった具合で。
・いつでも、どこでも、だれでも学べる学校以外での学習権の保障、生活の中での学び。
現代では、多くの人が遊びや暮らしの消費者となっている。そうではなくて遊びや暮らしの生産者にならなくてはいけない。
人間は、火と道具を使って発展を成し遂げてきた。危険だから子どもに使わせないのではなく、自ら経験して学ぶ。その中で自己効力感、自己有用感を育む。
「ケガと弁当、自分もち」が基本。安心して失敗できる環境が必要。
・「何もしない」ことの保障
居たいように居られることが大切。
「正しい」だけで人が育つわけでは決してない。
現代では「やりたい」よりも「やらなくては」が優先されている。大人はこどもの時間を切り刻んでしまっている。時間を誰かの都合に合わせるのではなく、自分自身が主体となって生きる。
「ゆめパのじかん」はその意味を込めて「時間」ではなく「じかん」
「学校が安心・安全で、楽しく学べるであれば、学校に行きたい」
集団の雰囲気、教室のにおい、椅子を引く音など、感覚過敏の子どもたちには学校は辛い環境であることもある。
それに対して、行きたくても行けなくて苦しんでいる子へ「早く学校へおいで」という教師のマインドは改める必要がある。
行けない理由は、複合的で自分自身でもなかなかわからない。
朝起きれないのも、起きないようにすることで精神が崩壊するのを防いでいる人間の防御反応である。それをサボりだ、怠けだ、などは言えない。
・子どもからおとなへのメッセージ
「まず、おとなが幸せでいてください。
おとなが幸せじゃないのに、子どもだけ幸せにはなれません。
おとなが幸せでないと、子どもに虐待や体罰がおきます。
条例に、子どもは愛情を持って育まれるとありますが、
まず、家庭や学校、地域の中で、
おとなが幸せでいてほしいのです。
子どもはそういう中で、安心して生きることができます。
(川崎市子ども権利条約策定子ども委員会)
・ありすぎて止まらない、心に残った言葉
・「大丈夫」につつまれると、自分で歩みだそうとする。
・どうでもいいバカ話をできるところから始める。
・相談室ではなくて、お茶を飲みながら、菓子を食べながら、散歩しながら、ゴロゴロしながら。
・「To do(する、できる)」ではなく「To be(ある、いる)」
・「大丈夫!」の種を撒く。
・「そのまんまが素敵だよ」という人のまなざし
・試し行動は、「僕をみて、構って」を不器用な形で表現している。
・学力とは、出会いをものにする力ですかね(平林浩先生)
・大人は自分のものさしを疑ってみること。
・よくしよう!という大人のアドバイスが子どものやる気を奪っている。
・医学モデルではなく、社会モデルで考える。
・「困った子」ではなく、「困っている子」
・「学校不適応児」ではなく、「子どもに適応できない学校教育」
・SOSをキャッチできるアンテナを立てておく。
・われわれ人間のDNAには、本来、多動性が組み込まれている。多動性があるからこそ発展してこれた。ほんのこの150年で学校教育が始まり、席につく、前を向く、静かにすることが求められるようになった。
・伸びていく子どもの、成長の芽を摘み取らない。
もう、突き刺さる言葉に溢れて止まらない。
37年の経験から、発せられる言葉の一つ一つに重みを感じた。
一人ひとりのニーズに合わせて、多様な学び、育ちを保障…なんて軽々しく論じられることもあるが、次元が違うと感じる。学校の工業化ベースで考えていても大した答えは出ない。
次元をあげた知見から問題を捉え、先を見据え、活動し続けていこう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
