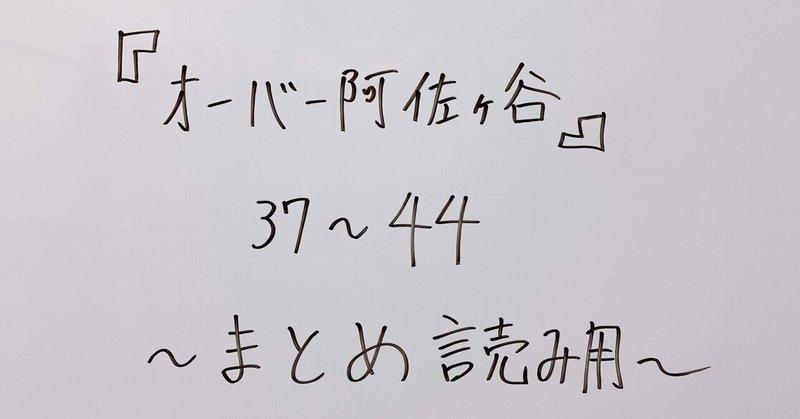
『オーバー阿佐ヶ谷』37〜44(まとめ読み用)
37.
一か月振りの北区だった。窓の外を流れる景色は廃団地群ディストピア。国がこの区を見捨てて久しいのかもしれない。軒並み割られた窓ガラスが無言のうちにそれを物語っている。廃団地群の反対側には寂れた工場跡地ばかりが目につく。すれ違う人間は皆年寄りで、この国の衰亡を予感させるには充分な光景だった。
サスペンションが用を為さない荒れた道路の先に一軒のコンビニがあった。低速で走る車がそこへと近づくにつれ、看板の名前に興味を惹かれた。
北区にしかその存在を許されていないような名前のコンビニだった。赤と緑を基調としたデザインはどことなく某大手コンビニを思わせる。他区からやってきた人間が間違えて入ることを期待してのことかもしれない。マーケティングを悪用し、情弱や生活保護受給者から金を巻き上げているような佇まいだった。ーーー悪を行おうとするならばそれは巨悪に対してが良い。その方が罪悪感も少なくて済む。
「おい。ここにしようぜ」と私は言った。
「サクッとやっちゃいますか」運転席の男(クルー)が答える。
足元にはたくさんの”道具”が積んである。人は言うに及ばず、家一棟は解体出来るほどの”道具”が。
真っ黒いワゴンをコンビニの駐車場に滑り込ませる。段差で弾んだ拍子に、ルームミラーが私の姿を映し出す。ペンギンが目印の量販店で買った黒のツナギ。深く被った目出し帽。どこの誰かなんて分からない出立ち。
太ももの上に置かれた”武器”。深呼吸をしながら、長年手に馴染んだその触り心地を確かめる。グズグズしている暇はない。どう贔屓目に見ても即通報されかねない出立ち。ことは時間との勝負だ。
クルーの踏むブレーキ音。すぐにでも発進出来るよう頭出しで駐車されたワゴン。
「オーケー。パーティーを始めようぜ」と私は言う。
太陽は雲に隠され、悪事を行うにはもってこいの天候だった。
手のひらが汗で湿っている。心臓のBPMは140を超え、陰嚢が収縮するような独特の高揚感。トリガーに指をかけ、これから起こる事態に想いを馳せる。これが上手くいけば懐は潤う。もし失敗すればーーー。止めよう。成功することだけ考えるんだ。
運転席から振り返ったクルーが身を乗り出し、「チャンスは一回きりです。打ち合わせ通り、一分以内にカタつけてせてズラかりましょう。ここまで来て、”ヘタこく”なんて許されませんからね」と耳打ちする。
目出し帽から覗く片目でクルーに向かってウィンクしてみせる。気分は上々。大金はすぐ目の前にある。私は煙草に火を点け、黒の革手袋に指を通した。
*
ワゴンのドアをスライドさせ、冷たく固まったアスファルトの地面に降り立つ。煙草を深々と吸いながら、コンビニの入り口までの距離を目視で測る。後は運転席のドアが閉じられる音を合図に作戦を決行するだーーー。
「ちょっと何してんの!」背後から聞き覚えのない声が聞こえた。
ーーークソッ。邪魔が入りやがった。仕切り直しだ。早くズラかろう。
私はクルーの方を見た。私に向けられたカメラが下ろされる。
「カット!カット!一旦、止めまーす」とクルー。
38.
別にコンビニを”タタ”いて、強盗襲撃メイクマネーを企ててやろうという訳じゃない。そもそも、わざわざトランペットを構えて強盗をする馬鹿もいないだろう?「さっさと金を出しやがれ!ピャーピャー!ピロリロ〜♪」そんな奴、三面記事にも載せてもらえないし、レジ側からベルの部分に一撃でも入れられた日には前歯が折れてお終いだ。「君、なんでこんなことしたのかね」と警官。「はひ。ふひまへん」と私。血に染まった胸元と二度と吹けないトランペットを片手に。
私にカメラが向けられているからといって、役者に転向した訳でもない。タトゥーだらけの三つ編みバッドガイに与えられる役回りなど月9に代表されるような地上波には存在しない。テレ東深夜でも無理だろう。Vシネマか低予算自主制作映画が関の山だ。ーーー映像関係に明るくない者でも分かる。それらは大金には程遠い。
出来るだけ広い敷地を持つコンビニ駐車場で無許可のゲリラ撮影を行うべく場所を探していた。コンビニのレジからは死角になるような場所と見つかった場合すぐに逃げ出せるように目の前が交通量の少ない道路。その条件に当てはまる場所は都内では北区か小笠原諸島にしかない。
邪魔さえ入らなければ、この駐車場でイントロのトランペット・パートを撮るつもりだった。工務店を継いだフッドの後輩にカメラを持たせて。
一向に跳ねない新曲にミュージック・ビデオを与えることが急務だった。映像さえあればSNS上でバズる確率も上がるこの時代。マイケル・ジャクソン『スリラー』並みの知名度とハリウッド映画クオリティを誇るMVに仕上げるつもりだ。ハローYouTube、グッバイMTV。合法メイクマネー、This is Real YouTuber Life.。
*
(話を前に進めてもいいかな、doggs?)
*
「ここは路上喫煙禁止だよ」という声が響く。
ーーーえ?北区なのに?と私は思った。北区と足立区は日本国憲法の範囲外、治外法権の地だと聞いていたのだが。
声の主たる近隣住民らしき老人は我々の前に回ってきた。私の姿に恐れ慄いているのか、目を瞬(しばた)かせてこちらを見ている。
ーーーまぁ当然だろう。目出し帽にツナギ、手にはトランペット。こんな格好、ギャングスタ・ビバッパーか狂人かのどちらかしかしないからな。
「あら、目出ぇ帽なんか被っちゃって。これから山でも登りに行くんかい?」と老人は言った。
年配の方にはこのギャングスタ・スタイルが登山家のそれに見えるらしい。
「リスペクト野口健です」と私は言った。
*
こうしてミュージック・ビデオのゲリラ撮影は中止となった。発射されることなく不発弾となったトランペット内の空気は外気によって急速に冷えていった。駐車場の隅では白銀の穂のススキが風に靡(なび)いていた。
39.
ーーー自分の夢にすら明確な形を与えられない人生ってのはどうなんだ?失敗か?
瓶の底に残る枯れ草は何も答えない。ーーー当たり前だ。LSDでもあるまいし、元々そんな薬効はないのだから。部屋に充満した煙の形に悪魔を見ることもない。
煙を指でなぞってみる。モーゼのように”雲”海を割るラッパー。煙輪を吐く代わりに書くリリック。
米国のケツに顔突っ込むのが大好きなこの国
あっちじゃとっくにビジネス
既得権益ボーダーレス
元々、自生してんだろ北海道
でもこればっかりはまだイリーガル
恫喝、圧力、絡み合う利権
モノマネ大国ここJapan
さっさと解禁しやがれYes,We can.
いちラッパーがリリックを通して声を上げたところでこの国は変わらない。棺桶に片足突っ込んだ奴らが握るハンドル。未来の舵取りを老人が行う矛盾に誰か早く気付けよ。
俺は持ってるぜ一票
米俵一俵よりも重要なのか
この紙切れ
マニフェスト、公約
口約束守れない奴が名乗る日本男児
切腹よりも斬首がお似合い
御立腹の桜吹雪
裁いてくれよ遠山の金バッジ
ーーー一体、いつになったら俺の本当の人生が始まるんだ。脳内と現実の乖離が酷すぎる。もし、この現実がホンモノの俺の人生だとしたら、脳内の俺は一体誰なんだ。
ステージ囲む聴衆
バックステージに溢れるパーフェクトレディ
棚にはヘネシー
テネシーワルツ流して吸う極上のブラント
預金通帳には
数えるのもうんざりするほどのゼロの羅列
まるで小室哲哉
TK a.k.a 馬龍丑。
*
怪物との遭遇、小牧亨の昔話、小石川真妃奈の独白。全ては一か月前に起こった寓話であり、もはや私の中では過去の出来事だった。相変わらず阿佐ヶ谷の街で飲み歩いているが、怪物の姿はおろか、噂すら聞くこともない。演出家殺害事件ですらこの町ではもう消費し尽くされ風化してしまっている。人間の記憶は随分と非情なものなのかもしれない。
鏡に向かって三つ編みを編む。目の下に出来た隈は睡眠時間と反比例するように、年々深くなっている。顔つきはーーーそうだな、生きる苦労をパイに載っけてぶつけられたような酷さだ。
ベルサーチのスーツに袖を通し、シャツの第一ボタンだけを外す。首元に覗くタトゥーは無事、完成した。”Black Letter”の字体を使って彫られた【The World is Yours】。私から全ての女達への愛の告白。
最近、原宿は表参道の地下にあるドープなアンティーク眼鏡屋で新調したサングラスを掛ける。テンプルやブリッジに彫金が施された1960年代のフランス製。ピンク色のガラスレンズ越しに見える世界は道行く女達全てがbitchに見える。
ーーーぶっ飛んでるだろ?安い細巻きを吸ったにしては。
時計の針が今宵、最初の酒を飲むべき時刻を指している。
ーーー行こうか。一夜限りの愛を探しに。DNAが仕組んだパズルをハメる為に。
40.
『ソルト・ピーナッツ』は住宅街と飲み屋街の境目にある。だから、私のアパートから一番最短の飲み屋はスターロードの果ての『ソルト・ピーナッツ』になる。だから口開け一発目、帰りしなの一杯は必然的にここになってしまう。だからこそ、泥沼に足を取られて朝を迎える日があるのも致し方ない。
今日もまずは『ソルト・ピーナッツ』で正体不明の酒を肝臓に流し込んでハイになり、そこからどこか別の店に流れようと思っていた。【酒場という聖地へ 酒を求め 肴を求めて彷徨う】酒場詩人 吉田類のように。
*
雪でも降りそうなほど寒い夜だった。クリスマスが近く、道沿いの一軒家の飾り付けはその浮ついたムードを煽っていた。毎日が金曜の夜みたいに。スーツの上に羽織るべきものを持たない私は「これも一つのスタイルだ」と自分に言い聞かせながら、凍える指先をポケットに突っ込んだ。【Style is Everything】それは絶対だ。
静かな住宅街を抜け、あと一つ角を曲がれば騒がしき歓楽街スターロード、という時だった。民家の壁や道路に反射する赤灯。それは一箇所を断続的に照らしている。私は足を止めた。財布と煙草の箱を取り出し、”所持”していないか入念にチェックを行った。OK。金は無いが”所持”もしていない。出掛ける前に消臭剤代わりのディオールの香水も身体中に満遍なく振りかけてある。抜かりはなかった。
角からそっと顔を覗かせる。人垣の奥に二台のパトカーが道を塞ぐようにして停まっていた。それはちょうど『ソルト・ピーナッツ』の目の前だった。
ーーーどうせ酔っ払いの喧嘩か何かだろう。
私は人垣に近づいた。鼻唄混じりに(何せ”所持”していないから幾らでも強気に出れる。カモン職質、いつでもウェルカムだ)。人垣はパトカーを囲むように二重三重にもなっていた。たかだか酔っ払いの喧嘩とも思えなくなってきた。
パトカーの奥で『ソルト・ピーナッツ』のドアが開き、二人の警官に脇を固められる形で店主が顔を見せた。俯き加減、ボサついた髪の毛。両腕を拘束する手錠は店のタオルで隠されている。どう贔屓目に見ても、その姿は下手人(げしゅにん)そのものだった。ーーーパトカーが来てるってことは脱税とかでは無いだろう。何かしらの事件には違いない。
特に抵抗する様子もなく神妙な顔でパトカーに押し込まれた店主はサイレンの音と共に連れ去られた。それに合わせて人垣も三々五々に崩落していった。私は今宵、飲む場所を失った。
41.
散らばっていく人垣の中に、未だ『ソルト・ピーナッツ』を見つめ続ける一人の老婆がいた。ーーー何か訳知りなのかもしれない。私は老婆に声を掛けた。若い頃はさぞかし男達を絶望の淵に追いやったであろう片鱗が覗く、その横顔に。
「夢のかけらでも探しているのかい?レイディー」
老婆は、まさか人生の最期に三つ編みのラッパーにナンパされるとは思ってもみなかった、みたいな顔をしてこちらを見た。街場のブティックで買ったような柄物のシャツがコートの隙間から自己主張激してくる。それは派手を通り越して奇抜だった。
老婆は何も言わない。ただそこにいて全てを見つめ続ける彫像みたいに。
「警官やらパトカーが凄かったけど、何があったか知ってる?」先の文言を打ち消すべく言葉を継ぐ。
「こんなことになるくらいなら、もっと早くに来てやるべきだったねぇ」と老婆は言った。
「なんだか当事者みたいな口ぶりだね」
彫像ではないことに安堵した。ーーーもしくは私にしか見えない幻覚でないことに。
「アタシはこれでも昔、女優をやっててね。舞台の」
「分かるよ。今でも充分通用するくらいに綺麗だから」
老婆は少し照れた。女性(レディー)の扱い方はアイスバーグ・スリムに学んでいる。勿論、反面教師として。暴力や脅しは使わない。使う必要もない。
「あいつらとはその頃からの腐れ縁なのさ」
「あいつら?」
「あら、あんた知らないのかい?この店の店主とこの前殺されたあの演出家、二人は元々同じ劇団の出身だったのさ。で、アタシがそこの看板女優だった、ってわけ」
老婆は何万光年も離れた星々を眺めるような目をしていた。そこにはもう輝くことを止めてしまった星々の欠片が転がっているだけなんだろう。
42.
〈ソルト・ピーナッツ〉と【演劇集団 暗愚裸座】を核として、逮捕された店主/殺された演出家/かつて二人と同じ劇団だったという元女優。小牧亨にしても(遥か昔に退団したにせよ)この劇団にいた訳だし、小石川真妃奈は現役の劇団員だ。そして、その不可思議な引力に引き寄せられてしまった哀れなラッパー。なんだか役者が勢揃いした感がある。
界隈に巣食う怪物の謎は残ったままだが、それすらもはや手の内にあるような気がする。
『バガボンド』一乗寺下り松・吉岡一門七十人斬りにて武蔵が真っ先に総大将 植田良平を斬ったシーンに倣い、いきなり核心へと切り込むことにした。
「”お姉さん”は怪物について何を知ってる?」ーーーお姉さん、とはいえ七十オーバー。お世辞にしては些かオーバー。
「あんたもそんなもん信じてるのかい?」
手答えがあった。刀が側頭部を削いだような手答え。
「教えてくれ。どんなことだっていい。それが怪物に関することならあんたの特殊性癖だって構わないから」
「怪物なんて、阿佐ヶ谷スターロードに根を生やしたロクでもない噂だよ」
「でも俺はこの目で見て、その背中に触ったんだぜ。リアルに」ーーーあの陰毛の如き手触りが蘇る。
「そうなんだね」老婆は溜め息をついた。私の手に残るかりそめの陰毛を吹き飛ばすように。
「初めは他愛もない冗談だったんだよ。そんな”もの”がいたら良いな、ってくらいの。仲間内で酒の肴さ。でも、それは次第に形を持ち始めた。酔っ払うたび何度も話すうちに輪郭が出来上がり、肉が付き、魂が宿る。そんなことって本当にあるもんだね。ある日、劇団の中の一人が『見た』って言い出したのさ」老婆の眉間に刻まれた皺。その一本一本から滲み出す記憶。「初めはみんな馬鹿にして信じなかったよ、勿論。だって作り話だったんだから。でもソイツはあっという間にスターダムにのしあがった。アタシ達に後ろ足で砂をかけるようにしてね。まるで猫のフンさ」
長くなりそうなので、煙草に火を点けた。「一本くれるかい?」と言われたので渡して火を点けた。ーーー本当は無性に”草”が吸いたかった。天下の往来で吸えるようになる日は生きているうちに来るだろうか。
「その後も何人か続くように、劇団内で『見た』って奴が出てきたのよ。明らかな嘘つきを除けば、『見た』って言った人間は例外なく売れっ子のスターになっていった。アタシらの目から見れば、何の才能もないような奴でも」
「ーーー嫉妬かい?」
「どうなんだろうねぇ。『忙しくなってきたし、阿佐ヶ谷から引っ越す』ってんで、手伝いに行った時のあいつらはでも全然幸せそうじゃなかった。テレビに映る姿は輝いてはいても私生活は空っぽのもぬけの殻。夢を追ってた頃の目の色とは全く違って乳白色の靄でも掛かってるみたいに見えたね」そこで言葉を区切った老婆は淡く笑った。「これが『売れなかった人間の嫉妬』って言われりゃ、それはそうなのかもしれないけど」
老婆はどことなく菩薩を思わせる横顔をしていた。慈愛と安心感と温もり。それはイッた男を幾多も包み込んできた女から滲む優しさだった。
43.
初めは他愛もない酒の席での話だった。しかし、いつの間にか”願望”という名の想念は実体化し、現実にその力を及ぼし始めた。老婆の話を要約すればそういうことになる。
才能のない人間の夢と引き換えにスターダムに押し上げてくれる装置、それが”怪物”らしい。生憎、私は才能の塊だったようで怪物の候補からは外された。というか、私の才能の輝きに気圧され怪物は自ら逃げ去った、とでも云うべきか。(ーーーまぁそんな具合に思うことで自分を慰めた)
「そいつらは夢を叶えた。死んだ目をしてようが成功者には変わりないだろ」
「成功ってのはそんなに大切なものなのかねぇ。たくさんのものを踏みにじってまで手に入れる成功なんて全然立派じゃないよ、あんた」老婆はフィルター間際、最後の葉の部分までゆっくりと吸い切った。「成功ってのは等価交換なんだろうねぇ。成功したいって思ったら色々なものを捨てる覚悟がいる。でもそんなの幸せなんかじゃないね。平々凡々で良いじゃないか」
ーーー平凡な幸せ。確か真妃奈も言っていたことだ。架空とはいえハードなシチュエーションを生き抜く芝居の世界に身を浸しているとそういう思考になるのか?
「何かを得るためには差し出すものが無くちゃならない、って考え方は嫌いでね」と私は言った。「俺は全部手に入れるつもりだ。金も女も人気も地位も名誉も権力すら全てを」
「若いねぇ。”手に入れる”ことだけが人生の成功じゃないよ。どちらかといえば”上手く手放す”ってことの方が大事なのさ」老婆は吸い切った煙草を指の間から落とした。「でもそういうことも、この歳になってようやく分かることなんだろうねぇ」
老婆が私を見る眼差しは稚児を見る目と大差なかった。
ーーー手放す気がなくても指の隙間からこぼれ落ちていった数々の宝物たちにレストインピース。
老婆は続ける。この歳に足を踏み入れた人間はよく喋る。まるでそれがこの世に於ける最期の自己表現だとでも云うが如くに。
「成功や失敗そんなものーーー云々」云々云々…。
私は話を手で遮った。このままいくと朝まででも喋っていそうだ。そうなると阿佐ヶ谷の路上に凍死体が一つ転がることになる。
「まぁ怪物のことは分かったよ。俄には信じられない話だけど、そういうこともあるんだろう。AB型の両親からO型の子どもが産まれるように」
「解決したんなら良かった。だったら怪物のことなんかさっさと忘れて堅実な毎日を送ることだね。せっかくこうして生きてるんだからさ」
ーーー堅実か。私の人生に最も足りていない要素なのかもしれない。
「最後にもう一つだけ」私は指を一本立て唇につけた。まるで幼な子が内緒話をする時のように。「あんた、さっき言ってたよな。『もう少し早く来てやるべきだった』って。ありゃどういう意味なんだ一体?」
「ケンちゃんとマサキさん、ーーーあぁこの店の店主と死んじゃった演出家のことね。あの二人を放っぽっとくべきじゃなかった、ってことさ」
ーーー【ケンちゃん】が店主で【マサキさん】と呼ばれる者が演出家のことだろう、多分。そのつもりで話を聞くことにした。
「あの二人は昔から仲が悪くてねぇ。主役をはれる人間の”さが”なのかもしれないけど、会えばいつもバチバチだったのよ」老婆は互いの人差し指をぶつけ合った。乾いた空気のせいで甲高い音が響いた。「最終的に、『このままだと劇団内の秩序を乱す』ってことで二人はクビになった。結局、それが原因でケンちゃんは演劇界から足を洗って、マサキさんはマサキさんで自分の劇団を立ち上げた。そこが二人の転機だと思ったんだけどねぇ」
『ソルト・ピーナッツ』を見つめる老婆の目には涙。街灯によって照らされたそれはジルコニアのような虹色の光を放っていた。
44.
老婆は流れ落ちる涙を拭った。私はそれを見ないふりした。生憎、差し出すべきハンカチは持っていなかった。
「もう少し早く来ていたら”止める”ことも出来たかもしれなかったのにね」
「ん?」
「マサキさんが殺される前の晩、ケンちゃんから電話を貰ったのさ。『もう限界だ』って」
「は?」
「そうだよ。マサキさんを殺したのはケンちゃんさ」
現実は怪物など意に介さないほど不可思議なことだらけだ。それは海を廻し、森を焼き、空を墜とし、時計を溶かす。
「でも、あいつ毎日のように『ソルト・ピーナッツ』にいたぜ?仲が悪かったら普通、飲みに来ないだろ」
当然の疑問だ。されて然るべき設問だ。カウンターに腰掛け、正体不明の安酒を前にした在りし日の演出家の姿が目に浮かぶ。
「関係を繋ぎ止め続けたかったのか、それとも贖罪のつもりだったのかねぇ、マサキさんなりの」
「贖罪?」
「劇団をクビになった後、しばらくしてからマサキさん言ってたんだ。『ケンの才能を潰してしまったのは俺の人生最大の汚点だ』って」老婆は亡き演出家の声色を真似て言った。それはとても似ていた。「馬鹿な話だよ。一言でも謝ればいいものをさ」
ーーーうむ。一言謝る。それはそうなのだろうが、男という生き物がもれなく背負ったプライドというやつが邪魔をしたんだろう。
「ケンちゃんも辛かったんだと思う。考えてもみなよ。自分がせっかくオープンに漕ぎ着けた店に自分が絶対に許せない奴が毎日のようにやってくる様を、さ」
「それを何十年も、か。行く方も行く方だけど、受け入れる方もなかなかに覚悟のいる年月だな」
ーーー赦(ゆる)す、という選択肢が頭に浮かんだ日はなかったのだろうか。ただただ歳月分の憎悪をたぎらせただけだったのだろうか。そうであったなら、人間というのはなんて愚かな生き物なのだろう。哀しい男たちの哀しい話だ。
「結びついて解けない、因果ってやつだったのかねぇ。マサキさんはずっと悔恨の情を抱えたまま通い続けて、ケンちゃんはケンちゃんで何十年もの間、ずっとマサキさんに対する殺意を握りしめていたのだとしたらあまりにも不憫で仕方ない。…アタシにはもう何がなんだか分からないよ」
ーーーその後の老婆の話を要約すれば、以下のようになる。
演出家が殺されて四十九日の昨日、再び店主から老婆に電話があったそうだ。曰く、「伝えたいことがある、明日店に来てくれないか」と。そして、地方に住む老婆は朝一の新幹線に乗り、ここ阿佐ヶ谷の地までやってきた。
「伝えたいこと」。そこには殺人の告白から演出家最期の言葉までパンドラの匣の如き内容が含まれていたらしい。底に残った希望は、それでも二人に出逢えたことへの感謝だったという。
老婆は店に備え付けられた電話で”110”を廻し、店主は当たり前のように逮捕された。集まる野次馬、飛び交う噂話。そこにやって来た三つ編みのラッパー。そして、今がある。
「色々と教えてくれて感謝するよ」と私は言った。
「あんたもさっさと三つ編みなんて切り落としてマトモになんなよ。殺されてからじゃ遅いんだよ、何もかも」老婆は私の三つ編みを軽く引っ張った。「老婆心ながらね。ーーー老婆だけに」
「笑えない冗談をありがとう」
『ソルト・ピーナッツ』の、多分もう開くこともないドアの前で我々は別れた。
*
“スター”・ロード。
どこまでも皮肉な名前だ。今までどれほどの人間が夢を追い求めるようにして希望と共にこの道を歩き、そして、この脆き道を踏み外すように脱落していったのだろう。
#阿佐ヶ谷 #飲み屋 #スターロード #ソルトピーナッツ #小説 #短編小説
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
