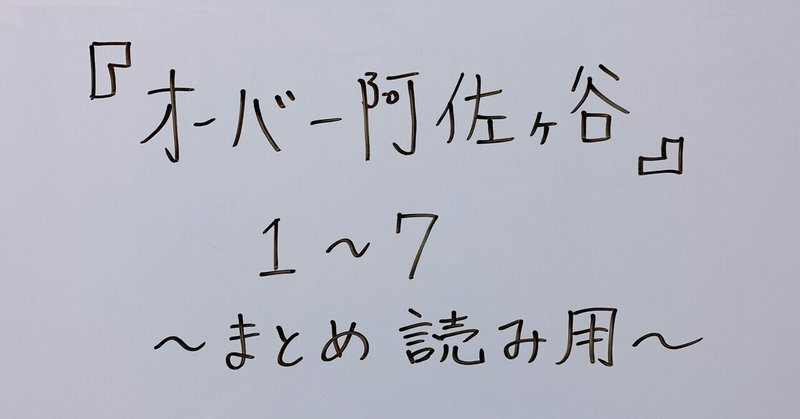
『オーバー阿佐ヶ谷』1〜7(まとめ読み用)
1.
阿佐ヶ谷スターロードのどん突きにあるバー『ソルト・ピーナッツ』で呑んでいる。縁が欠け、幾分汚れたグラスで酒を。
*
ちょうど住宅街と飲み屋街の境い目にある場末に空いた異界。はたまた中央・総武線で都心から戻り、ようやく家も近くなって気が緩んだところに待つ落とし穴。とはいえ、この店に来る客にサラリーマンやOLのような、まともな職業人はいない。サバンナに於いて自然と棲み分けがなされるような原理がこの街にも適用されているらしい。
通りに面して開かれた一つの小さな窓。そこから中を覗けば、バー『ソルト・ピーナッツ』が自分にとって相応しい店なのかどうか分かるだろう。その窓を通して見える景色は十九世紀の阿片窟を連想させる。それが故なのか、大体に於いて人々は素通りするか、そもそも視界にも入れようとしなかった。
掃き溜めに鶴、といった古語に期待してはいけない。掃き溜めには掃き溜めに相応しい落伍者がいるだけだ。もう誰からも引き上げられない腕を自ら掴むことで辛うじて生きているような人生の敗残者。”世間の目”からはとうにこぼれ落ちた透明人間。そのような者たち。
もし世捨て人や”何か”から崩れた人間を見たければこの店に来るといい。きっと数冊の本が書け、何本かのドキュメンタリーを撮れることだろう。
でも、【ミイラ取りがミイラになる】という話もある。近づく時は気をつけた方がいい。堕落は堕落を引き寄せる。その気がなくても足を掴まれ、ぬるま湯に引き込まれたらそれまでだ。怠惰に抗する程の力は人間には与えられていない。
*
ジャズトランペッター/ディジー・ガレスピーの名曲から取られたこの店名『ソルト・ピーナッツ』の名物はそのままソルトピーナッツだ。一度食べてみるといい。もう二度と他のピーナッツすら食えなくなる、トラウマ級の不味さだ。店名にまで冠したツマミがそのレベルでは他もお里が知れる。ピザはチーズが溶けておらず、ビーフジャーキーには黴が生えている。ホットドッグのソーセージは生煮えで、鮭とばはダイアモンドのような硬さを誇っている。
いつ開封されたか分からない酒瓶から供される酒達は熟成とは別の空気感を纏っている。ウィスキーは日本酒の味がし、焼酎からはビールの香りがする。
そんな酒に、ただ一つ言えることがあるとすれば”酔える”ということだけ。アルコールはアルコール。そこに嘘は無いらしい。
*
店の看板の下には【Since 1969】とある。1969。それはウッドストックやサマーオブソウルの年だ。そろそろ歴史書に綴られるような年代。火炎瓶や注射器が飛び交っていたような時代に産声を上げたこの店が何故、これほどまでの長きに渡って経営を続けていられるのかは誰も知らない。公衆衛生法を無視したツマミ類と表記から逸脱した味の酒を提供するこの店が。
でもこの店で飲む者、いや、この店でしか飲めない者にとっては、そんなことにそもそも興味すらない。
ただ店があって、そこに集う者がいる。資本主義の原初形態を保ちながら、そのバー『ソルト・ピーナッツ』は阿佐ヶ谷の片隅に今も存在している。
2.
店内には三人いた。カウンターの隅で潰れた男と私と、私の隣にもう一人。潰れている奴のことは知らない。ただ、よく見る顔だ、という以外に。
私の隣にいるのは小劇場を主戦場とする(にしか出来ない、と言ってもいい)劇団の演出家だ。勿論、自称。くたびれた襟首のTシャツを着ている。前面のプリントは掠れ、かつてそこにはミッキーマウスがいたことが、微かに残る白い手袋から推察出来る。
「阿佐ヶ谷に住んで何年になる?」と演出家の男が言った。
「二年弱くらいですかね」
「じゃあ、あの”怪物”の話は聞いたことあるか?」
男の目線は宙を泳いだ。何かを思い出しているのかもしれないし、それっぽく振る舞っているだけかもしれない。
「”怪物”なら毎日ここで見てますよ」
「ここにいるのは単なる夢の残骸だよ」と演出家の男は言った。Tシャツのミッキーマウス(の手袋)も同意している風だった。残された指先でサムズアップしていた。
私は焼酎を飲んだ。いつも通り、ビールの味がした。男の話す”怪物”になど興味はなかった。ただ、男は話したそうだった。きっと話を聞いてくれる者もいないのだろう。中年過ぎた、誰からも相手にされない哀しき男の末路。明日は我が身だった。話を聞くことにした。
「中央線の呪いみたいなものが働いているんだろうな。特に中野・高円寺・阿佐ヶ谷あたり一帯には。一度住むと温かい泥沼に浸かったような心持ちで肩すら出したくなくなる。そうして気付いた時には頭のてっぺんまでズブズブだ」と男は言った。
ーーーこの後、数分に渡って如何に中央線沿線が住みやすいか、についての講釈が行われたが、大して聞いてもいなかったので省略する。さて、本題だ。
「俺はこの町に住んでもう五十年近くになるけど、その間に両指くらいの人間が羽ばたいていった」演出家の男は指折り数えた。片方と一本でその動きは止まった。
「少ないっすね」
「で、羽ばたいていった人間達に共通するのは、その直前に『怪物を見た』と言ってまわってた、ってことだ」その口調は神託を授ける神官の厳かさだった。「『怪物を見た』と言った人間は次の日から、必ずこの店には寄り付かなくなる。で、あれよあれよという間にスターダムさ。雑誌やテレビに引っ張りだこになって、終いにはこの町からも出て行く」
男は具体名を挙げた。それは私も知っている人間達だった。もしかすると離島に暮らすアナコンダにだって知られているかもしれない。勿論、この話に信憑性はない。何せここは場末の飲み屋の中でも最低クラスの店だ。話の九割方はデマかガセで、突拍子も無さ過ぎるが故に裏の取りようもない。
「その怪物というのは、いわゆる都市伝説みたいなもんですか?」ーーー信じるか信じないかはあなたの知性と教養次第の。
「いや、伝説みたいな話じゃない。実際に会った人間もいるって言ってるだろ」男は手に持ったグラスをカウンターに叩きつけた。高音ではなく、鈍い低音がした。割れはしなかったことから考えられるのは、この店のコップはガラスに見せかけたプラスチック製ということだ。きっとかつて経営が傾くほど割れに割れた時代でもあったのだろう。
3.
スマートフォンで時刻を確認すると、既に次の日になっていた。零時を廻るか否かで心持ちは大分変わる。帰ろうにも男との話は佳境に差し掛かっていた。こうして人は”朝”という概念を忘れる為に更にと酒を呑む。
「で、その怪物に遭遇したらどうしたら良いんですか?」
当然の疑問を口にする。まさか見るだけで幸運がもたらされる訳でもあるまい。酒が語らせた戯言だとしても尚、そこに一縷の望みを賭けてしまう程にはこの人生、切羽詰まっていた。何者にもなれず三十を過ぎてしまった男のさが。
「怪物の前に回り込んで、こう言え。『俺をここから救ってください』と」
「なんか惨めっすね」
思っていたより哀れだった。いい大人が怪物にすがりついて『俺をここから救ってください』なんて憐憫を通り越して滑稽に近い。『人生は近くで見れば悲劇だが、遠くから見れば喜劇である』と言ったチャップリンのアレだろうか。
「この谷底から脱出したかったらそうするしかないんだよ、ボーイ」
ボーイ、と呼ばれる歳でもなかったが頷くしかなかった。
男はカウンター越しに手を伸ばし、勝手にウィスキーの瓶を取った。多分、中身は日本酒だ。店主の姿は見えない。私がこの店に来た一時間前からずっと不在だ。男は自分のグラスだけ満たして瓶を戻した。仕方なく、残り少ないビール味の焼酎を飲んだ。
「しかし、その怪物ってのがいるとして、そいつは一体何なんですかね。怪物なのに夢を叶える?まるで流行らなかったB級の御伽噺に聞こえるけど」
「夢破れた者達が生み出した願いの総体さ」と男は断言した。「それは空の星々を経由して、ある時、形態を伴ったんだ」
さすが自称・小劇場劇団きっての演出家。芝居じみていた。
「で、おじさんは見たことあるんですか?その怪物」これも私の抱くべき当然の疑問だ。
「もし見てたら、今こんな店で飲んじゃいないよ馬鹿野郎」
男はグラスの底に僅かに残った日本酒味のウィスキーに口をつけた。
潰れてテーブルの隅に突っ伏していた男が突発的に顔を上げた。現実のみならず夢の世界からも追い出されたらしい。
「そろそろ店じまいにするよ。勘定は各自置いていってくれ」
照明に照らされたその赤い顔は人々の希求する”健康な生活”とは程遠いように思えた。
適当な金額をカウンターに置いて店を出た。演出家の男は三百円払ったようだった。酒数杯で三百円。コスパ、と思った。
*
夜風が酔った肌に心地良かった。温泉から上がった後の散歩みたいに気持ち良い。夢という名のぬるま湯に浸った我が身を思う。怪物なんて見ることもなくこのまま浸り続けたい、とすら思う。夢は夢を語っている最中が一番居心地良いのだろう。
私は煙草に火を点けた。男が手を差し出したので、一本恵んだ。年功序列の通じない町・阿佐ヶ谷。
「おい。もし見つけたら教えた通りにするんだぞ」と男は言った。
「分かってますよ。後ろから蹴飛ばせば良いんですよね」
「馬鹿野郎。祟られて一生阿佐ヶ谷で暮らせ馬鹿」
我々は店の前で別れた。
4.
月の綺麗な晩だった。子どもの頃に友達の家で繰り返し観た、マイケルジャクソンの『スリラー』のPVを思い出させるような。雲間から覗く満月はきっとあちこちのアパートで性の宴でも催させているのだろう。全ての健康問題が煙草のせいにされるように、あらゆる過ちは月のせいにすれば良い。そうすればきっと誰も傷つかない。
予感はあった。
ーーー私はきっと怪物に出会える。
芸術家だけが持つシックスセンスがそう告げていた。今まで一度も的中することなく錆びついたシックスセンスが。
ただ、怪物と呼ばれるその”もののけ”の様相を聞き忘れた為、街ゆくどれが怪物なのかは判別のしようが無かった。全部といえば全部、怪物に見えるような気もするし、それは演出家男の頭の中にだけ存在する妄想の産物のような気もした。孤独は時に精神を蝕むものだから。
*
飲み屋街と言えど、深夜二時近いこの時間では開いている店も限られる。夜の町は静かに暮れていく。一軒また一軒と消える灯りは、冷え冷えとした月明かりをより輝かせる。私はただ照らされるに任せた。待てど暮らせど輝かぬこの身を。
終電は既になく、かといってこの町の在住者としては寝るにはまだ早い。酔った頭で路上に放り出された人間が考えることにろくなことはない。まだ開いてる店を探して更に酒を飲むか、家に帰って孤独を抱きしめるか。どちらの扉の先にも救いはなかった。
スターロードの直線を駅に向けて歩く。さしたる目的はない。酔い覚ましという名の時間潰し。貴重な人生の時間はこうして自ら潰しているに過ぎない。そうして気付いた時には何も持たない老人になっている。金も伴侶も優しささえも。縮んだ肝臓と黒くなった肺だけを抱えた、そんな老人に。
人の姿も声すら無い道は私に産道を連想させる。退却という選択肢はそこになく、ただ前に進むのみ。温かな居場所を振り切っての死の行軍。人生なんてその繰り返しだ。新しいことなんてない。巨視的に見れば、出産される道程を強迫反復しているだけだ。
ーーーこんなにも詩的に考えられる私が何故、売れないのだろう。
見る目のない大衆が住む世間という場所は、実に生きづらい。私が痛みの経験と引き換えに生んだアートは羊水すら拭い去られることなく、ネグレクトの憂き目にあっている。アートの水子、というものがいるとすれば、私の背中には数百万体は憑いているに違いない。どおりで身体が重い訳だ。体重から骨と筋肉と血液量を引いた値が”水子”分なんだろう。”アート水子”供養の寺社仏閣は何処(いずこ)?ライザップ?
*
自虐思索にも飽きた頃、高架下への曲がり角で見知らぬ背中が目についた。猫にしては大きく、人間にしては歪な形だった。二足歩行で歩むその背中は毛むくじゃらで、脱毛サロンのビフォーアフターに推挙したいくらいには目立っていた。
5.
「もし怪物に会ったのならーーー」男の声が蘇る。「ーーーすがりついてこう言え。『俺をここから救ってください』ってな」
ふむ。ーーー俺をここから救ってください、か。今の私にピッタリの台詞じゃないか。そのような想い、いつだって魂が叫んでいる。口に出すとしても、並の役者には負けないだけの迫力を伴って言えるだろう。少なくとも小劇場辺りでくすぶる役者風情には。実に簡単な話だ。
もし最悪、今目の前にいる背中が男の云う怪物でなかったとしても、単なる酔っ払いの戯言という形で収まりそうだ。シラフでやれば精神病棟は免れない案件だろうが、現に今こうして、おかげさまで良い感じに酔っている訳でもあるし。ーーー下戸じゃなくてよかった。心底、そう思った。
角を曲がった背中を追いかけた。自然と早足になる。なんだか気付かれてはいけないような気がしたので、出来るだけ足音は立てずに。その背中が近づいてくるにつれて、毛並みはよりはっきり見え始めた。月明かりに照らされ、銀色に輝いている。どうやら毛皮の服の類ではなく、皮膚から直に生えているように思える。ーーー間違いない。これが件の怪物だ(人間だとしたら大問題だ。毛の問題のみならず露出狂だ)。あとはこの怪物の前に回り込んでこう言えばいい。「俺をここから救ってくれ」と。
更に足を早めた途端、道端に突き出していたビールケースに躓き、大きな音が立ってしまった。クソッタレだ。きちんと収納しなかった居酒屋店員をレストインピースしてやりたい。静まり返った飲み屋街に響くその音は怪物の耳にも確かに届いたらしい。怪物の足も早まる。
「待ってくれよ」酒で腫れた咽喉は掠れた音を絞り出す。
声で制そうとした試みは無駄に終わった。今や怪物は四つ足に変わり、高架下をくぐり抜けて駆けていく。私は必死にその背中を追いかけた。今や目の前に現れた夢を掴むべく。
深夜の道路に私の走る足音だけが響く。怪物のそれは宙を駆るが如く無音だった。少しずつ距離が縮まる。火事場の馬鹿力とでもいうのか、人生史上一番のスピードを記録していると思う。目の端を溶けた景色が飛び去っていく。怪物の背中が目の前に迫る。私は手を伸ばし、その毛並みを掴んだ。
同時に怪物は後ろ足を使って飛び上がった。怪物の姿は大きな門扉の向こうに消えた。その先は釣り堀だった。閉められた門扉は私と私の夢を隔てる天の川だった。
赤の筆文字で『つり堀』と書かれた看板にもたれ、呼吸を整える。
ーーーいつだってこうだ。私は何も掴めない。指の隙間から全て零れ落ちていく。
いつのまにか月は雲に覆われていた。
*
指の間には数本の体毛が挟まっていた。月明かりに照らされていないと、まるで陰毛のように黒い。私は拳を握りしめた。夢の欠片を失くしてしまわないように。
もう一軒寄って帰ることにした。まともなラベルのまともな酒を飲みたかった。例えば、里の曙。ソーダ割。通称:里ソー。阿佐ヶ谷のソウルドリンクを。
6.
バーのカウンター席に腰を下ろし、改めて握った拳を広げる。指の間には確かに縮れた数本の黒い毛が挟まっていた。カウンターに一本ずつ並べてみる。合計四本あった。
「チン毛っすか?」とカウンター越しに店主が言った。「そういうのカウンターに並べられると困るんすけど、衛生上」
私は曖昧に笑った。これが私の陰毛ではないと証明すふ手立てはないし、かといって怪物のものだと言えば、それこそ『チン毛を並べた挙句、意味不明なことを口走る狂人』に認定されてしまう。私はただまともな酒を飲みたかっただけだった。四本の黒い毛は財布にしまった。店主の眼差しが痛かった。
カウンターにグラスが置かれる。透き通ったそれは炭酸を含み、上品な泡立ちを醸し出していた。里ソー。里の曙ソーダ割。奄美大島が生んだ黒糖焼酎だが何故か阿佐ヶ谷のソウルドリンク(阿佐ヶ谷のどの居酒屋にも大体置いてある)になっている。ここは『ソルト・ピーナッツ』じゃない。焼酎を頼めばきちんと焼酎の味がする酒が届く。そんな当たり前が有り難かった。
私は里ソーを飲みながら、先程の怪物のことを思い返していた。黒い(月明かりによって銀色に光る)体毛、はじめ二足歩行でスピードを求めて四足歩行に変わる形態、歪に盛り上がった背中。
アレが人間ではないことは確かだった。『月刊ムー』にでも出てきそうな雪山の主のような出立ち。そんなものが大都会新宿も近い阿佐ヶ谷のこの地に生息しているとはとても信じ難かった。ーーーでも紛れもなく、私は怪物と遭遇したのだ。この目で見、この右手でその体毛の数本をむしった。そして、その体毛は今も私の財布の中にある。現物より他に信じられるものなどなかった。
「なぁ。夢を叶えるのに他力本願ってどう思う?」と私は店主に尋ねた。
「ダサいっすね、それ」と店主は言った。
「私もそう思うよ。乾杯」グラスを掲げた。
ーーーしかし、これほどまでに努力を重ねても私に栄光の扉は開かれないままだった。閉じられた扉は冷たく、分厚かった。ノックしても返事すらない。他力本願になるのも無理はないだろう。
怪物にすがりついて夢を叶えることは、やはり本道から外れることになるのだろうか。でも、この世の中にはプロデューサーに抱かれるアイドルもいれば、社長に尻の穴を貸す二枚目俳優だっている。最終地点が同じなら、その時取れる最大限の効率を求めてしまうのが人間なのではないだろうか。たとえ痛む穴をさすりながら飲む酒が如何に不味かろうと。
酒が進んだ。脳がそれを求めた。まともな酒はやはり美味い。銘柄どおりのアルコールが提供される世界線は健全だ。でも、私は明日も『ソルト・ピーナッツ』に足を運ぶのだろう。人間の退廃ぶりを眺めるのが我が仕事だからだ。
7.
ようやく家に帰り着いた。煙草の香りがコロン代わりに染み付いた四畳半に。四時を回っていた。私の視界も回っていた。換気扇を回し、部屋にこもる煙草の匂いを追い出す。灰皿に溜まった吸い殻を捨て、固まって黒くなった灰の塊を蛇口の水で軽く洗う。そうしてからまた新たな煙草に火を点けた。世界はこうして清浄と汚濁を繰り返す。死と出産のメタファーが如くに。
一日の後半は酷い日だった。バーで隣り合った男の話から始まった怪物奇譚に巻き込まれ、より多くの酒を必要とする羽目になった。右肋骨の奥から不平不満が聞こえてくる。こんな夜は音楽が必要だった。虚像とリアルの入り混じるそんな音楽が。
レコード棚からN.W.A『”STRAIGHT OUTTA COMPTON”』を取り出し、ターンテーブルに乗せて針を落とす。スピーカーから弾き出されるコンプトン直送の爆音ラップ。私はさながらアイス・キューブだった。
「Fuck Tta Police」
「Fuck Tta Police」
「Fuck Tta Police」
♪。私も合わせて歌った。「ファカポーリース!」
中空に中指を突き立てると同時に、隣の部屋から壁をどつき回す音が聞こえた。鈍い連続音だった。それは地面に倒れた人間を金属バットで執拗に叩き続ける様を連想させた。薄い壁は今にも突き破られそうだった。安アパートに住む(にしか住めない)狂人はタチが悪い。ボリュームを絞った。
部屋の反対側から叩かれたであろう場所の壁には『スカーフェイス』のポスターが貼ってある。アル・パチーノ扮するトニー・モンタナが歯を剥き出しにしてマシンガンを乱射しているシーンを切り取ったそのポスター。顔の部分が凸凹に歪んでいた。内側からの攻撃にマシンガンは何の役にも立っていないようだった。
丑三つ時をやり過ごした今となっては、全てが非現実的で、怪物のことなど酔って見た夢のように思える。そうであるなら、なんの面白みもない夢だった。創造を主とする職業にしては致命的な。
ことの真相を確かめるべく財布の小銭入れを開くと、四本の陰毛が出てきた。ーーー陰毛?そうか。リアルか。
神棚代わりに使っているタンスの一番上に置かれたクインシー・トゥループ著『マイルズ・デイヴィス自叙伝』の真ん中辺りを開き、そこに四本の黒い毛を挟み込んだ。そこではちょうどマイルズが警官達に警棒でシバキ回されているところだった。
ページを閉じ、本を戻し、手を合わせた。多分、作法としてはこれで良い。自信はないが。
*
明日の朝は一件のアポが入っている。マネーをメイクする為の第一歩だ。それが三百六十五日分の一日だったとしても、二五億六千万五百分の一時間であっても、外せない重要案件だった。
ーーー怪物がなんだってんだ。俺は俺の手で勝ち取る。そしてその手でヘネシーを飲み、もう片方の手で弄る暗い茂み。
これから寝るというのに反比例するが如く屹立した竿を収める為、丸くなって眠った。
#阿佐ヶ谷 #酒 #飲み屋 #スターロード #小説 #短編小説
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
