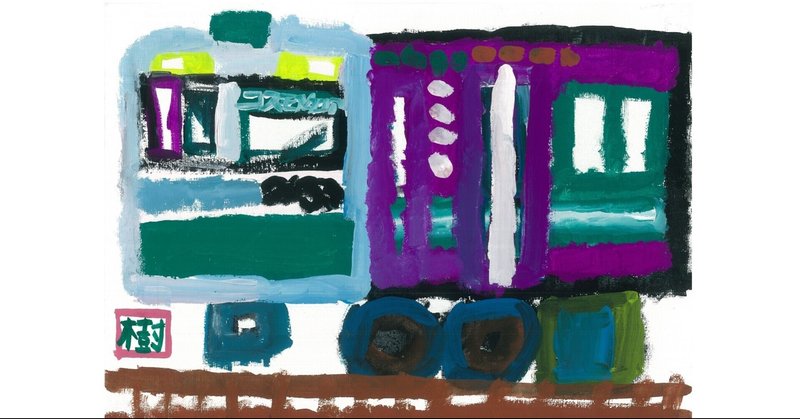
【A乳児院④】子どもにとって必要なのは「親」ではなく、「きずな」です
このnoteでは、女の子として生まれ、「ちいちゃん」と呼ばれて育ってきたかつての自分。男性として生き、「たっくん」と呼ばれ、福祉の専門家として働いている今の自分。LGBTQ当事者として、福祉の現場に立つ者として、「生」「性」そして「私らしさ」について思いを綴ります。
前回に続き、A乳児院で私が何を見て、何を感じたのかをお伝えします。
親は、子どもにとって絶対に必要な存在なのでしょうか。愛情を注げない、子育てができない親でも、子どもには不可欠な存在なのでしょうか。
愛着、つまり、子どもと養育者とのきずなは、子どもの成育には欠かせないものだと考えられています。「愛着障害」という言葉を聞いたことがある方も多いと思いますが、乳幼児期に養育者との愛着の形成ができないと、情緒面や対人関係の面での発達に影響が生じてしまうといわれています。
ただ、心のきずなを結ぶ相手は、親でなければならないというわけではありません。大切なのは、子どもが「いつも『この人』が自分を見守ってくれている」「何かあったときに『この人』が自分を助けてくれる」と信頼できるおとながいることです。
乳児院の子どもたちには親はいつも近くにいるわけではありませんから、「この人」の役割は、保育士が担うことになります。
私たち保育士が、担当する子どもと休みの日に一緒に外出したり、外泊に連れ出したりしていたのは、「いつもこの人が、自分を見守り、助けてくれる」と心から思え、おとなの愛情を独り占めできる時間をつくるためなのです。
心のきずなを結ぶ相手は、もちろん、多くの子どもにとっては親でしょう。しかし、重要なのはきずなの有無であり、相手は必ずしも親でなくてもよいのです。だから私は、「子どもには、親は必要なのか?」と聞かれれば、「必ずしも必要ではない」と答えます。
ただ、子どもには「自分のことを一番に考え、一緒にいてくれる」存在が絶対に必要です。その存在は産みの親でなくてもいいけれど、育ての親、あるいは保育士など、「だれか」は必要なのです。
あくまでも子ども中心に、子どもの育ちにとって何がよりよい状態かを考えたときに、「親でなければいけない」と親の存在にこだわるよりも、「親でなくても、その子のことを一番に考え、一緒にいてくれる」存在があればいいのではないか。乳児院でさまざまな親子と出会う中で、私の中にそんな確信が生まれてきたのです。
子どもに愛情を注ぐのが下手な親に代わって、子どもに愛情を注ぐのが上手な人が子どもを育てる社会。今、私が目指している社会について、次回もさらにお話しします。
【A乳児院の物語、ぜひ初回からご覧ください】
【あわせてこちらもご覧いただけますと嬉しいです】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
