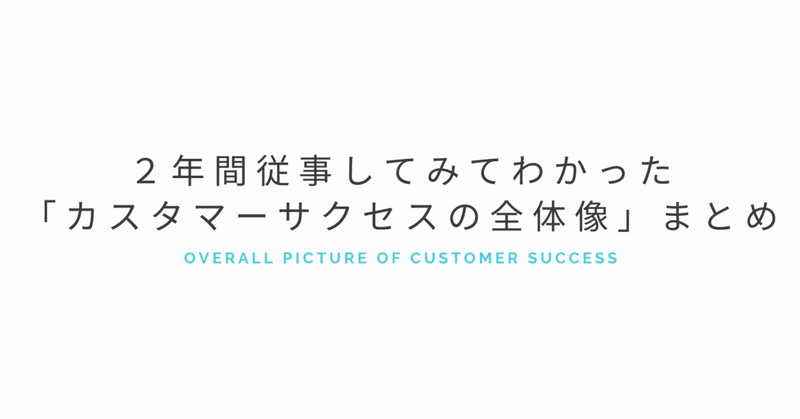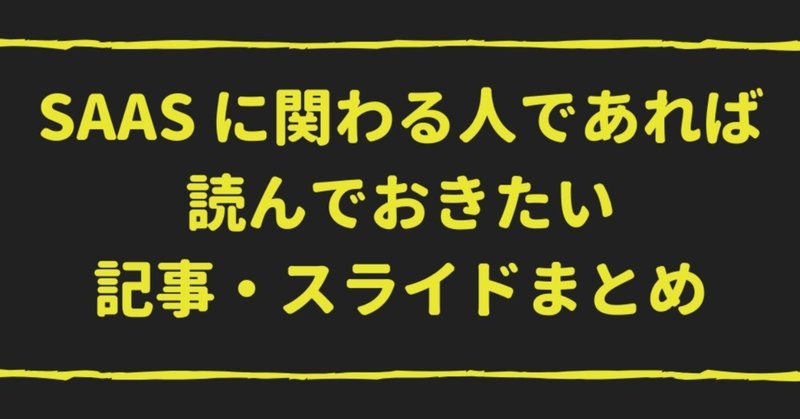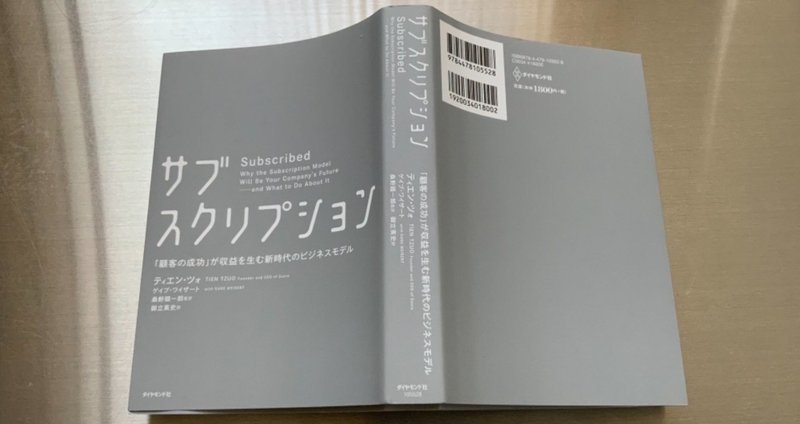SaaS企業でマーケティングを担当する うみみ( https://note.mu/umimi0425 )と竹前太朗( https://note.mu/tarotakemae )が…
- 運営しているクリエイター
#カスタマーサクセス
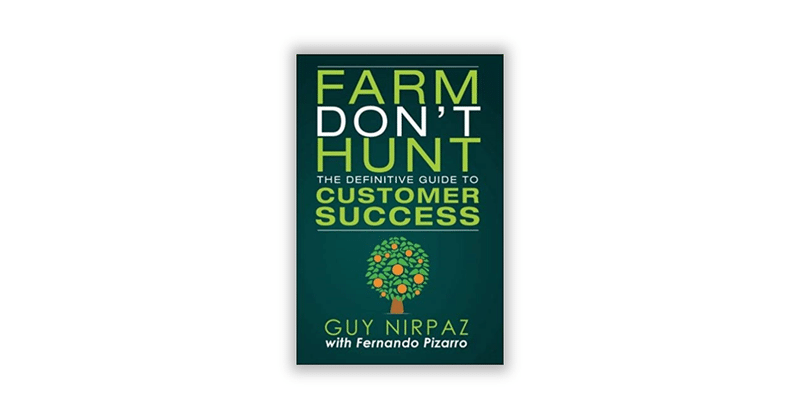
【読書メモ】Farm Don't Hunt: The Definitive Guide to Customer Success
みなさんFarm Don't Huntをご存知でしょうか? 5 Excellent Customer Success Books to Read にて紹介されている通り、「カスタマーサクセスの緑本」として非常に有名な書籍です。カスタマーサクセス本で1冊だけオススメ本を紹介するなら、私は間違いなくFarm Don't Huntを推薦します。※1 その理由は過去にRepro CS Blogでも紹介しています。 今となっては日本のCS界隈にとって既知の情報も多いですが、驚くべ