
「経済成長は不可能なのか?」名著です。
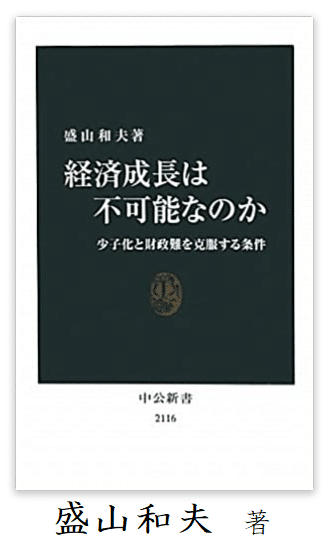
《一流の社会学者が本気で書いた!》
日本経済に関する本は吐いて捨てるほど出ています。
そんな中、東京大学大学院の、著名な社会学教授が書いたもの。
ちょっと「他にはない」面白そうな感じしませんか?
「はじめに」で著者はこう書いている。
『私は経済や財政の専門家ではなく、社会学者として、階層問題や社会保障制度あるいは雇用構造などの研究に携わってきたものだが、...日本社会全体に漂う暗鬱とした閉塞感がどうしても気にならざるをえなかった。
そして、その根源の一つに、1991年に始まって今日まで続く日本経済の長期不況という現実があった。不況からの脱却なくしては、雇用も、社会保障制度も、階層格差問題も、決して明るい未来像を描くことができない。』
『しかし、残念なことに、長期不況問題に関する経済の専門家たちの議論には、十分に納得のいくものは少なかった。
おそらく、専門家レベルでの議論の混迷こそが、現実の政治レベルにおける経済政策や財政での失敗や行き詰まりをもたらしている。』
『その道の専門家を頼りにすることができないとすれば、自分自身で問題の解明に乗り出すしかない。
それが、浅学非才をも顧みず、本著を記すことにした動機である。』
《どこが凄いか?》
「課題の整理」「問題の本質の捉え方」が素晴らしい。
10年前(2011年)に出された、この本。
経済学のイデオロギーや派閥、常識に囚われない立場から
日本経済・財政の問題点を整理する、
この本が提供する視点は10年たった今でもますます有益です。
これが常識となっていない現代日本に知性の劣化を感じざるを得ない。
Amazonのレビューから引用:
『社会学に忠実で、社会学の存在意義を問い続けてきた盛山和夫氏による
学問領域を超えた警告の書である。』
『経済学者でないからといって、そこはさすがにロジカルに丹念に整理をされており、その辺のトンデモ本ではありません。....1つの提言としては実に示唆に富むものと思えました。』
honto.jpでの書評:
『問題提起の仕方、問題の分析・整理の仕方、分かりやすい解説の仕方、
どれをとっても素晴らしいし、マクロ経済という一般的には退屈な分野の
話をとても面白く語ってくれている。』
『...本書は混迷する日本経済を見る視点として、読みやすく、わかりやすく、問題をすっきり整理できる良書であると思った。』
まったく同感です。
《日本経済の問題は四重苦の構造にある。》
その一部を紹介する。
【日本経済の問題】は「経済 と 財政 と 展望」の問題。
◉経済=①デフレ不況
◉財政=②財政難(社会保障などの歳出増)、③国の債務残高
◉展望=④少子高齢化
これらが相互に関連しあい、悪循環して問題解決ができない状況が続いている。
短期にすべての問題を解決することはできない。
だが、中長期には成長の可能性がある、と信じている。
【4重苦とは?】
①不況からの脱却なくしては、雇用も、社会保障制度も、階層格差問題も、決して明るい未来像を描くことができない。
つまりデフレ不況からの脱却は必須。
ということで①経済・デフレ不況対策を優先すると、当然需要拡大策として減税や政府支出増を取ることになる。
すると、財政②財政難(社会保障などの歳出増)が結果として起こり、その結果③国の債務残高が大きくなる、ということに。
=
では逆に、④少子高齢化にともない、医療や年金などの社会保障費の自然増が避けられない状況が続いているので②財政再建を最優先にしようとすると
②財政難を解決するために増税や政府支出減を行うと、今度は①経済・デフレ不況から脱却できない.... どちらにしても、④少子高齢化から抜け出せる展望が見えないということ。
=
どれかの問題を解決すると他の問題の原因になる、という「4つの課題が相互に絡まっている」四重苦だという全体像を前提として理解することがまず重要.....。
ではどう考えるべきなのか?
==シンプルに言うと、本著の主張は
②財政難は短期の課題でなく中長期的に解決しないといけない問題である。
よって
国の歳出増を行うには、国債の発行しかない。
しかし、そのこと自体が問題であり、③無限に国債増ができるものでなく、それ自体リスクがあり注意が必要である。
④少子高齢化は②財政難の主な原因であるだけでなく、①不況の原因ともいえるのではないか?
経済規模は人口減によって縮小するのが通常である以上、その状況で、企業の投資意欲があがるのは難しい。....
でも、まずは①不況からの脱出を最優先、そのためには②財政難・③国の債務残高は中長期課題として対策後回しにする...ということです。
(第一稿 10/13)
(*MMT後の議論として盛山先生がどう考えているのか?知りたいところです。僕自身はこのバージョンアップ版の考えをしている→別の記事で紹介したい)
《具体的な方策は「当たり前な内容」に落ち着く。》
すっごくシンプルに言えば
この本が「素晴らしい問題の構造を明らかに」した後の、
最終的な提案は当たり前なもの(?)に落ち着きます。
でも、この当たり前(?)な結論に、自信を持つことが出来ます。
honto.jpでの書評:
『...
まず増税ではなく、国債発行でデフレを乗り切る。
それから増税を。
何ら目新しいことはなかった・・・』
『....
素晴らしく面白い前半と、ややがっかりの結論。 ...』
* 個人的にはMMT等による知見が広がっている現在、財政再建についての著者の見解がどう変わっているのか?非常に興味があります。
そして
改めて思う。
藤井聡京大教授が涙を流して悔しがる、『2014年の消費増税をせずに大規模財政出動をしていたら、20年の不況から日本は脱することができたのに...』という話。本当にそう思います。
2011年に一流の社会学者が批判を恐れず、世間に示し、専門の経済学者たちに訴えた「当たり前の結論」をやっていればよかったってことですね。
それすら採用できない日本政府の愚かさって何だろうか???
《本著の本当の意味とは?》
最初に紹介した通り
◉一流の社会学者(当時、東京大学大学院教授)が
◉分野外である経済学について批判を覚悟で書いた
いや
◉『専門外の自分が、浅学非才をも顧みず、書かざるを得ない』と思ったほど、経済学者たちに問題があるのではないか!?
amazonのレビュー:
『…見事なまでに現在の低迷の原因(1980年代後半の過度な円高)を把握することに失敗しており、結果として的確な処方箋の呈示できない現在の経済学者の否定です。否定の仕方は鋭いものです。
...近視眼的な知性の殻に閉じこもり、意味のある政策論議を呈示できない経済学はまさに神学です。…神学上の教義にとらわれて、まともな政策論は存在せず、無意味な標語(無駄の排除と規制緩和)の乱発に終わっているというわけです。』
『呈示される政策の見事なまでの政治性です。神学上の教義論争にかかわりを持たない著者は...一群の工程表を呈示します。この工程表はリアリスティックなものです。...この程度のプログラムさえ提示できずに、仲間内での神学論争に労力を費やしている経済学者たち、どこか根本のところでずれています。』
関連リンク:
・アマゾン「経済成長は不可能なのか(中公新書)」
・honto.jp「経済成長は不可能なのか(中公新書)」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
