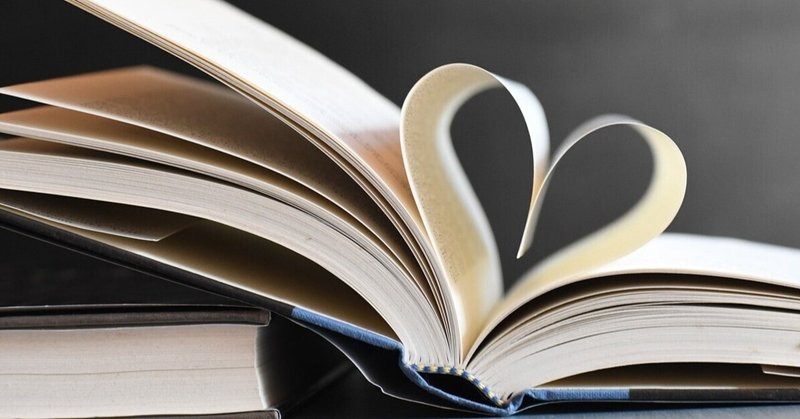
【小説】かっこつけた成績の上げ方
甘ったるい声の駒木先生が、あいうえお順に生徒の名前を呼び、英語の期末試験の結果を返却していった。
「倉本くん、百点!」
「おお!」
皆の前で点数を発表されるのは、百点満点の時だけだ。
俺は、首にマフラーを巻いたまま、寝ているふりをしていた。すると、一人だけ順番を飛ばされ、最後に名前を呼ばれた。
「新田くん」
不敵に聞き流した。
「こら! 新田大輔」
後ろの生徒に背中をつつかれてから顔を上げると、皆の視線を集めていた。教壇に立つ先生は、くりっとした目の幅を狭めるように、眉間に皺を寄せていた。
「はい?」
「後で職員室に来なさい」
呼び出された理由は、舐め腐った態度に加え、もう一つあると分かっていた。
授業が終わると、教室を出た駒木先生の後を追い、挑発的に横並びで歩いた。先生は、俺のにやつく顔を見上げず、怒っていると言いたげに、真剣な面持ちで前を見据えていた。階段を降りる際は、俺が少し後ろに下がった。
二階の職員室は、なごやかな雰囲気だった。すぐに怒鳴り散らす男――体育の長谷川先生を警戒したが、戻っていないようだった。
駒木先生は、窓際の自分の席に座り、大きなため息を吐いた。
「これは、どういうことなの?」
期末テストの解答用紙を突き返された。赤ペンの採点はなく、俺が名前だけ書いて提出したままだった。
「どういうことって、分からなかったので」
「そんなわけないでしょ。英語以外は八十点以上なんだから」
「ああ、正確に言うと、八十八点以上ですけどね」
ドヤ顔で見下ろすと、先生はもう一度ため息を吐いた。
「いつも英語だけ出来ないなんて、ふざけてるとしか思えない」
「いやいや、出来る必要がないです。なんで英語を勉強させられるんですか? 日本人なのに。それって戦争に負けたからですよね?」
先生を困らせようとしたが、俺を見据える目に力が宿り、臆する様子はなかった。
「英語は、世界で一番広く使われてるの。海外で仕事をするようになれば、英語は必須」
「俺は、外国に興味がないです」
「今はなくても、将来は変わるかもしれない。自分の可能性を狭めないで。新田くんには、世界で活躍してほしいと思ってる」
不覚にも、笑い飛ばせなかった。先生の大きな目が、少し涙ぐんでいるように見えた。途端に、胸が熱くなった。
「じゃあ、百点取るよ」
「百点じゃなくていいの。ちゃんと勉強してほしいだけ」
「やるからには、百点じゃなきゃ駄目だ。次のテストで、必ず百点を取ってやる!」
思いがけず、大きな声が出てしまったようで、先生たちの感嘆の声が上がった。強面の長谷川先生も、目を細めてこちらを見ていた。その傍らには、隣のクラスの生徒――薄笑いを浮かべる男は、質の悪い奴だった。
結果として、百点を取ると言い放ったことは、早々に広く知れ渡り、色んな奴に茶化されるようになった。俺は、そんなことに屈しないばかりか、売られた喧嘩は買うタイプだ。
ある時、しつこい奴に乗せられ、自分を追い込む宣言をした。
「二月の学年末テスト、英語が百点じゃなかったら、素っ裸で百回懸垂してやるよ」
休み時間の教室は、大いに盛り上がった。
「おい、本当だろうな」
「本当さ。もう一度言うから、誰か録音しとけ」
よほど自信があると思われたのか、たしなめる者はいなかった。
やるしかない俺は、決死の覚悟で取り組み始めた。学校では、そのような素振りを見せなかったが、弱小サッカー部の練習を適当に切り上げ、家にまっすぐ帰ると、勉強以外はなにも頭になかった。およそ三ヶ月後の決戦に向け、国語や数学も疎かにしなかった。英語だけ百点になり、他がガクンと下がったら、無理をしたと思われてしまうからだ。
風呂に入らない日もあり、食事中に英単語帳を開いていることもあった。当然、母親にそれを注意され、食事は出来るだけ早く済ませるようになった。
十二月のある晩、俺の必死さを感じ取った父親が、夜食の温かいうどんを作ってきてくれた。
「英語か。俺も随分勉強したよ。懐かしいな」
そして、誠に余計なことを教えてきた。
「英語が最も上達する方法は、イギリス人を好きになることだぞ」
「はあ、そうかもね」
全く心当たりのないふりをしたが、誰かを本気で好きになると、一生懸命になれることを痛切に感じていた。
勉強漬けの冬休みを過ごし――
新年のカレンダーは、二月二十九日があった。
年明けに会った駒木先生は、授業中にどこか寂しげな印象だった。かすかなブルーを帯びた甘い声は、色気を増して美しく聞こえた。その違いに感づいた者は、俺の他にいただろうか。
いつもの舐めた態度は取れないと思った。こっそり話しかける機会を窺った。
五日後のよく晴れた朝、校舎の中庭で紺色のダウンジャケットを着た駒木先生を見つけた。大きな箒を手にして、足元に点々と落ちている山茶花のピンク色の花びらを掃除していた。
「はようございます」
「あ、おはよう。今日は早いね。サッカーの朝練?」
「違います。でも、早く来てみた」
「そうなんだ」
先生は、優しく微笑んだ後、小首を傾げた。
「あれ? 疲れてるんじゃない? 勉強もほどほどにね。大事なのは、長く続けることだよ」
「先生こそ、最近元気ないですよね。なにかありました?」
先生は、深刻そうに口を閉ざした。――俺は、沈黙に耐えかねて笑った。
「なんだよ、男に振られたの?」
「私ね、三月いっぱいで教員を辞めることにしたの」
胸の内は、バクバクと鼓動したが、つとめて平静を装うと、憎まれ口がふいに出た。
「やっと気づいたんですね。教員に向いてないって」
「そっか。向いてないよね。皆にからかわれてばっかりだもんね」
「だからって、意味が分からない。逃げるのは良くないですよ。続けることが大事なんですよね?」
「ありがとう。でもね、結婚することになったから。逃げるわけじゃないの。色々と考えて、相談した結果だよ」
頭が、一瞬グラっと揺れた。倒れ込みそうになった。踏みとどまると、腹を抱えて大笑いした。涙が出てきた。
「おーい、めでたいじゃん。なにブルーな顔してんですか」
「ごめんね。学校に来ると、ちょっと寂しい思いが出てきちゃって。生徒の皆にも、そろそろ言わないとね」
「そうだよ。最後は明るく元気に、先生らしく、いい思い出作り。学年末テストも、楽しみになったと思いません? この前零点だった俺が、百点取るからさ」
「うん。楽しみにしてるけど、点数はいいの。気にしないで」
「百点だよ」
「新田くんには、一流の人間を目指してほしい。新田くんなら、きっとなにかで一流になれる。だから、一番じゃなくていい。百点じゃなくていい」
また、涙が込み上げてきた。笑ってごまかせなかった。空を見上げると、腹立たしいほど澄み渡っていた。
それから三日三晩、勉強が手につかなかった。
だが、気持ちをもう一度奮い立たせ、机にかじりつくようになると――
二月下旬のテストまで、息切れしなかった。出来ることのすべてをやり切った。英語に関しては、ありとあらゆる問題を想定した。やはり、百点を取りたかった。取りに行く姿勢が大事だと思った。
仮に失敗して、百点を取れなかったら、皆の前できちんと謝るつもりだった。一流の人間が、やるべきこととして。
テスト当日は、冷たい雨が降った。気をつけた体調は、万全だった。
冷やかしてくる奴らをあしらい、教室ではへらへらと笑っていたが、英語のテストの前は、気持ちを鎮めようとして、トイレにこもった。
教室に戻ったのは、チャイムが鳴ると同時だった。
試験官の長谷川先生の合図でテストが始まり、ふっと息を吐いた。まず、解答用紙に名前を書いてから、三枚の問題用紙に目を通すと、出題した駒木先生の人柄が現れていると思った。
一問ずつ、丁寧に答えていき――
制限時間の十五分前、手応えを感じながら見直しに入った。意地悪な問題は、最後までなかった。
その日の晩、手元に残った問題用紙をもとに、英語のテストを振り返った。
完璧だ!
と一度は納得したが、椅子の背もたれに寄りかかり、何気なく問題用紙を掲げてみると、二枚目のそれに目が留まった。
「ああ!」
思わず声を上げ、前かがみになった。嫌な汗をかいた。
そして、辞書を開くと、英単語のスペルを間違えたことに気づいた。わずか一点、あるいは二点の、減点になる。
急に体の力が抜け、情けない笑みがこぼれた。テストが返却された後、言い訳をせず、調子に乗ったことを謝ろうと思った。
次の英語の授業は、二日後の一時限目だった。
「Good morning everyone」
「Good morning Ms.Komaki」
授業は、お決まりの挨拶で始まった。
前の日に、誰かが駒木先生の結婚後の苗字を聞き出してきて、三月の最後の授業は、Mrs.Takashimaと呼ぶことをクラスの皆で計画していた。
解答用紙の返却は、いつも通りあいうえお順だった。あ行の時から、ちらちらと俺に視線が集まった。
「末松さん、百点!」
な行に入るまでに、百点が一人いた。席を立って俺の側に来る奴らがいたが、先生はそれを注意しなかった。
そして、中山が呼ばれた。次は――
「新田くん」
「おお!?」
「百点!」
「おおおお!!」
俺は、皆に頭を叩かれ、蹴飛ばされ、もみくちゃになった。
「こら!静かにしなさい」
手荒な祝福から抜け出し、解答用紙を受け取りに向かうと、すっかり明るさを取り戻した先生は、百点満点の笑顔を見せた。
翌朝、校舎の中庭へ行ってみた。花壇の前にしゃがみ込み、草木の手入れをしている人がいた。めずらしく毛糸の帽子を被り、分かりにくかったが、それは駒木先生だった。近づくと、日差しが眩しそうにこちらを見た。
「先生、テストはありがとな」
「おはよう。こちらこそ。本当にちゃんと勉強してくれて嬉しかった。ありがとう」
「分かってるからさ。俺、百点じゃなかったって」
先生は、一瞬驚いた顔をして、いたずらっぽく笑った。
「そんなの、教師失格じゃん」
「そうね。私は、三流の教師だね。でも、これからの人生の方がきっと長いから。私も、一流を目指して頑張るよ」
「一流の、奥さんですか?」
「将来、新田くんに会った時、恥ずかしくない私でありたいな」
「じゃあ、四年後に会おうよ」
「四年後?」
うるう年は、縁起がいいと思った。今年は、迫り来る別れを一日延ばしてくれるのだから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
