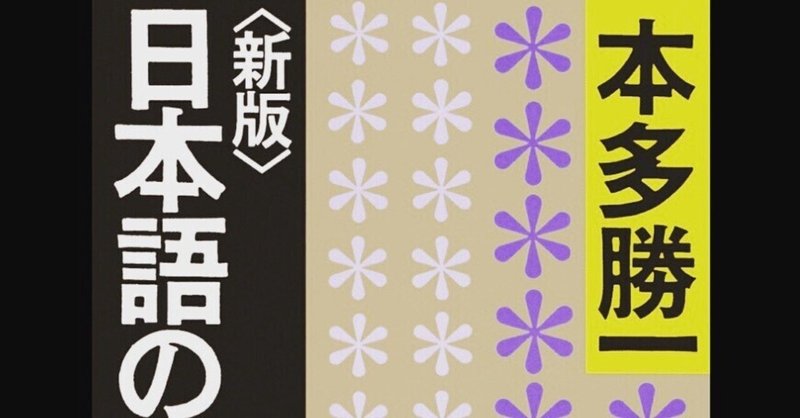
【読書メモ】 『#日本語の作文技術 』 本田勝一
読んだ。『日本語の作文技術』本田勝一
・本書の目的はただひとつ、読む側にとってわかりやすい文章を書くこと、これだけである。作文は技術だからこそまた訓練によって誰でもができるといえよう。
・言語とはすなわちその社会の論理である。また、いくら日本語が論理的であっても、それを使う人間が論理的であるとは限らない。
・修飾の順序
① 節(クローズ)を先にし、句(フレーズ)をあとにする。
② 長い修飾語は前に、短い修飾語は後に。
③ 大状況から小状況へ、重大なものから重大でないものへ。
④ 親和度(なじみ)の強弱による配置転換。
・句読点は字と同じか、それ以上に重要である。テンというものの基本的な意味は、思想の最小単位を示すもの。重要でないテンはうつべきではない。
・テンの原則
① 長い修飾語が二つ以上あるとき、その境界にテンをうつ。(重文の境界も同じ原則による。)
② 語順が逆順の場合にテンをうつ。
(+ 筆者の考えをテンにたくす場合として、自由なテン)
・漢字とカナを併用するとわかりやすいのは、視覚としての言葉の「まとまり」が絵画化されるため。
・助詞と助動詞は日本語の性格を決定する重大な品詞には違いない。日本語を正確に使いこなせるかどうかは、助詞を使いこなせるかどうかにかかっているといっても過言ではない。
・段落は、たとえでいうなら組織を集めて身体の小部分をつくることである。たとえば足という「章」でいえば、各部分の境の関節が改行である。 段落のいいかげんな文章は、骨折の重傷を負った欠陥文章といわなければならぬ。
・紋切型とは、だれかが使い出し、それがひろまった、公約数的な、便利な用語、ただし、表現が古くさく、手あかで汚れている言葉だ。 しかし、紋切型を使った文章は、マンネリズムの見本みたいになる。紋切型にたよるということは、ことの本質を見のがす重大な弱点にもつながる。
・ノダとかノデス・ノデアルの第一の用法は、その前の文を受けて説明するときである。文の頭に「ナゼナラバ」が付くような形の場合と思えばよい。第二の用法として強調や驚きの表現もある。
・筆者がいくら「美しい」と感嘆しても何もならない。美しい風景自体は決して「美しい」とは叫んでいないのだ。その風景を筆者が美しいと感じた素材そのものを、読者もまた追体験できるように再現するのでなければならない。
・体言止め(より広くは「中止形」)の文章はたいへん軽佻浮薄な印象を与える。読者を最後まで引っぱってゆく魅力に甚だしく欠ける結果、途中で投げ出して読まれなくなる可能性が高い。そうすると、結果的に「わかりにくい文章」と変わらなくなる。
・事実の過去でさえも現在形にしてしまう方が迫力がある。読者は筆者と一体になって舞台を同時進行するかのようだ。これはひとつの文体として確立している。また現在形の語尾は変化に富むので、過去形のように「た」ばかりがつづく「繰り返し」を避ける利点もあろう。
・目で活字を追いながらも人は無意識にリズムを感じ取っている。そうであれば、書く側がリズムに合わせて書かなければ読者の気分を害すことになる。自分の文章に固有のリズムが無意識に出るようになったとき、その人は自らの文体を完成させたのである。
いただいたサポートは旅先で散財する資金にします👟 私の血になり肉になり記事にも反映されることでしょう😃
