
大槌で『復興』を走る “ 旅先で『日常』を走る 〜episode9〜 岩手編 ”
前回のあらすじ
" 被災と復興の繰り返し。なんともやりきれないが、自然と共生するには、その恵みを享受するとともにリスクも引き受けなければならない、ということなのだろう。だけどこんなに胸が痛むのは、なんの花に例えられましょう? "
大槌で『復興』を走る
もう十年以上前になるが、私は2009年の春、ニコ生の放送枠がプレミアム会員に開放されて間もない頃からしばらく、いわゆる生主をやっていたことがある。放送内容はというと、ニコニコ動画に上がっている昭和のプロレス動画を放送画面上に流して、視聴者の皆さんと一緒に「あーでもない、こうでもない」と雑談するスタイルだった。

仕事が多忙だったため、放送する時間帯は終電で帰宅してすぐに始められる深夜0:30からにした。こんな時間帯の放送だったが、ほぼ毎日同じ時間に放送を繰り返して行く中で徐々に常連の視聴者が増えてきた。そんな常連のひとりにケロさんがいた。
ケロさんは生主である私にとって、とても助けになる視聴者だった。コメントが荒れそうになるとそれとなく軌道修正をしてくれたり、とにかくマナーが良く気遣いのある方だった。他の生主や常連さんのコミュニティをmixiに作り、ケロさんともマイミクになった。そこで初めて知ったことだが、なんとケロさんは北海道在住のお医者さんだった。
そうと知っても私は臆することなくケロさんを東京でのオフ会に呼び付け、一緒に屋形船でもんじゃ焼きを焼いたり、歌舞伎町でボーリングやカラオケに付き合わせたりした。ケロさんは少なくとも表面上は嫌な顔の一つもせずに、夜遅くまで付き合ってくれた。さらには、ケロさんから実家の畑で採れた新じゃがが我が家に送られて来たりと、なんとなく擬似親戚付き合い的な関係になっていった。
放送を始めてから1年が過ぎ、2010年になった。不規則な勤務体系で休みも少ない中、むりやり放送を続けていた私はさすがにスタミナが続かなくなり、徐々に放送の頻度が減っていった。ケロさんとも疎遠になっていった。
--------
2011年3月11日 14時16分、東日本大震災が発生した。続いて太平洋沿岸の広い範囲に想像以上の大津波が到来し、沿岸の町と多くの命を奪い、さらに原子力発電所の電源装置を破壊していった。
前回も書いたが、当時私が任されていた店も物理的に損壊し、休業を余儀なくされた。営業を再開してからも客足はなかなか回復しなかった。そもそも当時の上層部と折り合いが悪くなって干されていた状態だったので、これ幸いにとこちらから発案した売上対策はすべて却下され、人事考課では最低評価を付けられるという仕打ちを受けた。
12月に入り本部からおせち料理セット13,000円也のノルマが言い渡された。1店舗あたり31セット。とんかつ屋を営業しながら、『食べ物である』以外に関連のない物販をこなさなければならない。ちょっとなにを言っているのか意味がわからない施策だ。とはいえ、こちらにもプライドがある。なんとか自力でお客様やスタッフに勧めて、11セット買っていただいた。
ノルマ達成まで、あと20セット。タイムリミットは1週間後。周囲の店長たちはとうの昔にノルマ達成をあきらめている。しかしここは意地でも達成したいところである。熟考の末、ひとつのアイデアが頭に浮かんだ。
それは、『先日支給されたボーナスのほとんど全額をつぎ込んで、おせち料理セット×20(260,000円也)を買い占める。』という一種の富豪プレイであった。比喩的な自爆テロである。我ながら発想が冴え渡っている。世の中から発見されなかっただけで、もしかしたら天才かもしれない。
そうと決まれば話は早い。さっそく注文書を書き始めた。順調に書き進めていたが、『送り先』の欄で筆が止まる。狭いながらも楽しい我が家におせち料理が20セットも届いたら、部屋の中はどうなるのだ? せっかくの食べ物だから誰かに贈った方がいいな。方針を変更しよう。
しかし、20人も親しい友人知人がいるわけではない。精神的引きこもりの私。いっそのことどこかに寄付でもしようか? と思い立った。そこで思い出したのがケロさんだった。
ケロさんは震災後ほどなく、月一で岩手県大槌町までボランティアに通っていた。題して『お医者さんのお茶っこ』という、主に仮設住宅に暮らす独居老人を対象としたメンタルケアを行っていた。そのつてを頼って大槌町の方々におせち料理を送れないか?
善は急げ。すぐにケロさんに連絡した。

ということで、復元納棺士の笹原さんを紹介していただいた。
" 死と対話し、生と向き合う "
笹原さんのご尽力で、大槌町で年末年始も無休で任務にあたっている方々の元に、おせち料理セットが届けられた。不純な動機から始まった寄付ではあるが、それが少しでも被災地で戦っている方々の助けになったのであれば本望である。
この翌月、2012年1月に私は自分の店の前年売上を意地だけでクリアさせた。その足で会社に辞表を叩きつけた。
会社から退職金代わりにもらったものは、『おせち料理販売優秀賞』の賞金5,000円だけだった。
その後も、大槌町にはなんとなく親近感を覚えて、子どもたちの学習支援や東京での写真展の開催・写真集の発売など、折に触れて微力ながら支援を繰り返した。
--------
時は流れて2019年、ラグビーワールドカップが開催される。岩手県はその誘致に成功した。釜石市に鵜住居スタジアムが建設され、7月にこけら落とし、日本vsフィジーが開催されることとなった。これは、一度は訪れてみたいと思っていた三陸に足を運ぶ絶好のチャンスだ。さっそくサイトを開きチケットを確保した。行きの釜石行き深夜バスと試合当節の宿も確保した。あとは足を運ぶだけ。
しかし、出発まで10日を切ったある日、雨上がりの地元を夜走っていたところ、ぬかるみにはまって盛大に転び、手首を骨折してしまった。手術するために入院し、1週間も会社を休んだ。退院してすぐに貧乏旅行はさすがに体力的な負担が大きい。せっかくの三陸行きもキャンセルせざるを得なくなった。
とはいえ、そんなことくらいでは三陸行きをあきらめるわけには行かない。手首の骨があらかたつながったシルバーウィークの三連休、ラグビーの試合はないが仕切り直しの旅に出ることにした。待ってろよ、大槌!
旅行初日の朝、さっそく寝坊した。手首の機能を復旧させるために、見えないところでかなり体力を消耗しているようだ。幸いにも行きの交通機関は予約していなかったので、奮発して東北新幹線に乗った。
昼過ぎに新花巻駅に到着した。駅改札前に、花巻東高校出身の大谷翔平や菊池雄星を讃える展示があったので、とりあえず一通り眺める。すると、改札のあたりに人だかりができ始めた。ラグビーワールドカップために来日したウルグアイ代表の面々があらわれた。どうやら私と同じ新幹線に乗っていたらしい。
改札の中でプチ歓迎イベントが行われた。その後ウルグアイ代表メンバーたちは出待ちのちびっこたちとハイタッチをして、ロータリーに横付けされていたバスに乗り込み去っていった。
彼らは1週間後には鵜住居スタジアムでワールドカップ本戦を戦うのだ。
その日は新花巻で宮沢賢治関連の施設を回り(一部ランニングあり)、遠野に寄って市立博物館で遠野物語の世界を堪能してから、釜石駅近くにある復興作業員用とおぼしき宿舎に宿泊した。


————
2日目の朝、頑張って早起きし、釜石駅から3月に全面復旧したばかりの三陸鉄道に乗る。駅員さんのレコメンドで一日フリー乗車券を購入した。駅員の方の感じがとても柔らかく、初訪問の旅先で感じていた緊張がほぐれていくのを感じた。そういえば、先日キャンセルした旅行の際に三陸鉄道の三陸縦断夜行列車を予約しており、電話で事情を伝えて直前キャンセルをお願いしたのだが、その時も担当の方の対応がとても柔らかくて恐縮しきりであった。
では、生まれて始めて三陸鉄道に乗車し、いざ出発!

車窓から鵜住居スタジアムが見える。遠目から見るとかなり簡素な作りだが、もう少しすると、あの場所で世界トップレベルの戦いが繰り広げられるのだ。
そのまましばらく乗車していると、汽車は大槌に到着した。

大槌駅の改札を出てすぐ、右手に観光案内所を併設した駅舎があった。しかしまだ朝8時半過ぎだ。職員的な人もおらず内部はがらんとしている。幸いにもトイレとコインロッカーは開いている。手早く着替えを済ませ荷物を預けて走り始めよう。
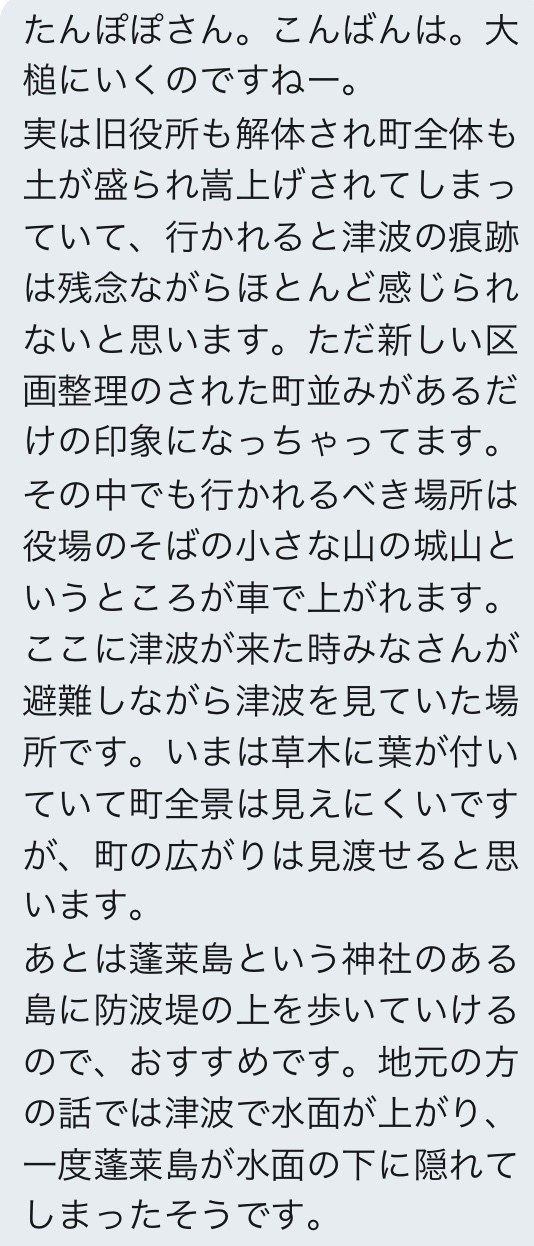
最初の目的地は地元で『ひょうたん島』と呼ばれる小さな島。昨日の夜、ケロさんにおすすめのスポットを聞いておいたのだ。
しばらく駅前の目抜き通りを進む。日曜日の朝なのにあまり人通りがない。駅回りには民家がちらほらと見受けられたが、少し進むと生活の痕跡が見当たらなくなった。目に入るのはブルドーザーやクレーン車ばかり。この辺りも復興工事真っ盛りのようだ。
突き当たりを右折する。工事車両が走るのにふさわしい、広くて凹凸のない新設されたとおぼしき道を走る。人も車もまばらだ。日曜日は工事も休みなのだろう。
右手には工事中の堤防がそびえ立つ。沿道にはLAWSONが一軒あるのみだ。陸橋のようなアップダウンを経て、ひょうたん島へと至る浜辺にたどり着いた。
まだ朝9時にもなっていないからか、浜辺には人影は見当たらない。ひょうたん島へ渡ろう。

浜辺とひょうたん島は堤防で繋がっており、堤防の上を歩いて渡れるようになっている。ゆっくりと周囲の景色を眺めながら渡る。絵に書いたような入江になっている。ほんの2~300mも歩くと、ひょうたん島に着いた。
遠目から見たら小さな島に見えたひょうたん島は、実際にその場に立つと、もっと小さく感じた。島というよりは、大きな岩に乗っている感覚である。ひとまず島の頂上に祀られている神社に参拝した。東日本大震災では、津波にこの島がすべて覆われてしまったそうだ。
参拝を終えて麓まで降りる。太平洋が眼前に広がっている。波音と浜風が心地よい。海の向こうから射してくる日差しは身を焦がすようだが、それすらも大地の恵みであるかのように思えてくる。先を急ぐわけではないので、岩場に腰かける。軽く水分を補給し喉を潤す。そのまま横になり、目を閉じてしばし休憩をする。

どれくらい目を閉じていたのだろうか? おそらく15分か20分くらいだと思う。こちらに誰かが近づいてくる気配を感じて、身体を起こした。なにしろ私は通路をふさぐかたちで寝ていたのだ。
休日で朝寝坊気味であった大槌の人々も、そろそろ活動を始める時間なのだろう。私も駅前まで戻るとしよう。
沿道のLAWSONで遅めの朝食をとりつつ、大槌の駅前まで戻った。次の目的地はここだ。

一面のクローバー畑。その中心に地蔵尊が立てられている。ここが旧大槌町役場だった場所だ。津波に襲われて多数の犠牲者を出した場所である。その建物の残骸を震災遺構として残すべきか、取り壊すべきかで意見が分かれ、長い間話し合いが続いていたが、結局取り壊された。
手を合わせて、犠牲者の方々のご冥福を心からお祈りする。
次の目的地は山の上だ。ランニングはここで終えるとしよう。
遠い昔に城が築かれていたという、城山に登る。かなりの急勾配だ。間違っても、ここを走って登ろうという場所ではない。
城山公園の入口まで登った。ここから大槌の町並みが一望できる。山の斜面いっぱいに墓地が並んでいる。特に震災の犠牲者を埋葬しているというわけではなく、昔から存在しているようだ。とはいえ、真新しい墓石も散見される。

山の下、駅回りの低地に建ち並ぶ建物は軒並み築年数が少なそうだ。大地の上に積み上げた目に見える歴史や暮らしは、津波がいとも簡単に奪い去ってしまったようだ。なにしろ、私が立っている場所から数メートル下に生えている樹ですら、津波に幹や枝葉を盛っていかれた形跡が残っているのだ。

————
今回、大槌の町を走って考えさせられたことが二つある。
ひとつ目は、『過疎の町における「復興」とは?』ということ。
大槌町が遠野と宮古を結ぶハブの役割を果たし、交通の要衝として栄えていたのは江戸時代のことである。この町の過疎化は年季が入っているのだ。大槌町自体は緩やかに町仕舞いをするしかない状況である。
その状況の中で復興すべきは昔ながらの町並みや賑わいよりも、長い間ここで暮らしてきた方々に対して、安らかに暮らしていける心の置き場所を用意することではないだろうか? そして、ここで育っている若者たちの未来を閉ざさないために、教育の機会を提供することではないだろうか?

これは自分自身が少なからず大槌の方々と関わってきた中で感じたことでもある。
そして二つ目は、『震災を忘れるべきか、忘れざるべきか?』ということ。
もちろん、震災があったという事実は残し、そこで起こったことは語り継いでいくべきである。しかし、過去の悲劇に囚われ続けている限りは、心は前に進めないのではないか?

私が出会った、大槌の被災者たちを支援している方々は、例外なく『残された人々の心を前に進めるため』に尽力されていた。
復元納棺士しかり、カウンセラーしかり、塾の先生や写真家まで、大槌に残された人々に希望の灯火をともすために。

だから市役所の跡地は解体して正解だと思う。ここは広島ではないのだから。
地震も津波も自然の摂理で起こるものであり、次の悲劇を減らすためには避難経路を整備するなどの物理的な対策が、なによりも有効だ。廃墟が視界に入る度に津波の記憶がよみがえっていたら、前に進むどころではないだろう。

今回は、大槌の町を考えながら走った。こうすることによって、明解な答えが導き出せるかはわからないが、新たな問いを立てることくらいは出来るのだろうか。
今後も考えながら走り続けたい。
※この旅はもう少し続きます。次回もお付き合いください。
次回予告
いただいたサポートは旅先で散財する資金にします👟 私の血になり肉になり記事にも反映されることでしょう😃
