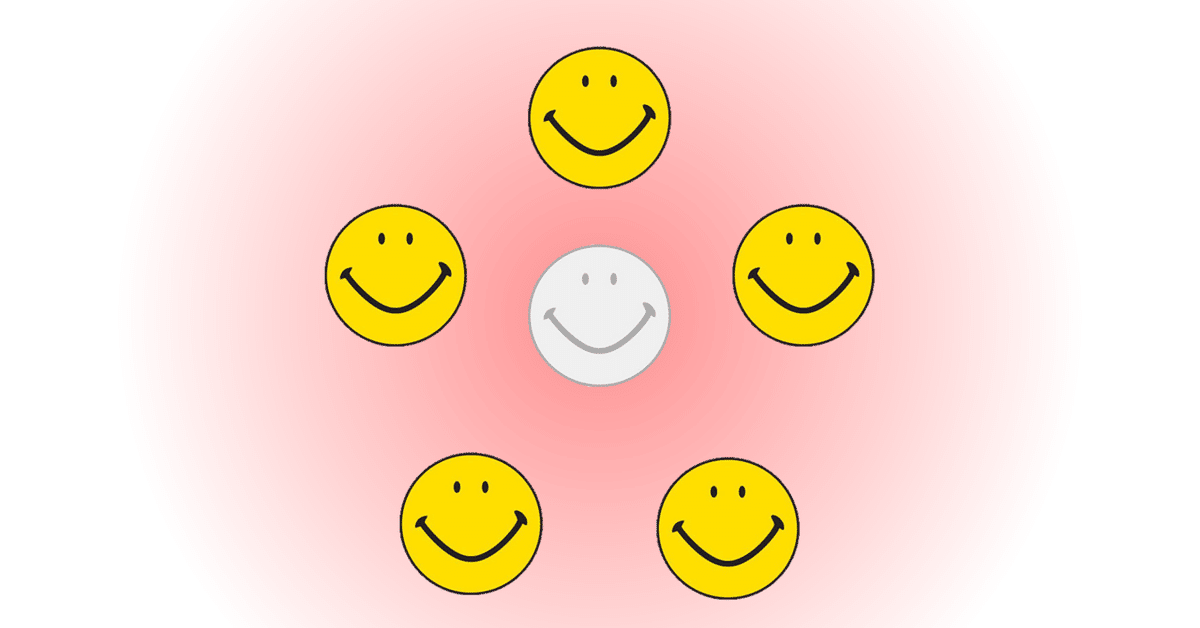
『介護と働く』 #03:寝たきり宣言-心を取り戻す-(1/2)
同僚の支え <助け合いの関係>
父が救急搬送された病院から帰宅した月曜日の明け方。心身ともに疲れ果てた上、入院の手続きや父の日用品の送り届けなども続くので、仕事を2,3日休むことに。
複数の業務を行なっていたが、それらに関わる全ての人に申し訳なさでいっぱいだった。ドタキャンばかりで迷惑をかけてしまう。
しかし、同僚やマネジャーたちは皆口を揃えて「仕事のことはなんとかするから、ご両親の傍にいてあげて」と心優しい言葉を投げかけてくれた。
その言葉は私の心に満ちた「ごめんなさい」を「ありがとう」に変えてくれた。
本当は私がやるはずだった仕事を急遽代わりにしてくれたり、調整してくれたり、バタバタしたと思う。
このことがひと段落したら、またこの人たちと頑張ろうと強く思えた瞬間だった。
ありがとう(ございます)。
家族の支え <笑顔の伝播>
父の病状が正式に分かるまでの一週間、母も弟も私も不安で不安でたまらなかった。
もしも意識が戻らなかったら、もしも身体を動かせないままだったら、もしも意思疎通をとれなかったら、と。
そんな日々が続いたある日、弟夫婦が子ども(私にとっての姪)とともに実家へやってきた。
弟は、沈んでいる母を少しでも元気付けようと、1歳半の我が子を連れてきたのだった。
姪は当然父が倒れたことを知らない(はずだ)。
まだ言葉を操ることはできないが、元気に走り回り、人懐っこくきゃっきゃとはしゃいでみせる。
そんな姪の姿に、私たちの暗い顔も自然と笑顔が覗くようになった。ほんと、姪の満面の笑みでどれだけ穏やかな気持ちを取り戻せたことか。
その笑みの先には明るい未来が続いていると感じさせる。まるで地獄にいるかのような心を持った私に、光を導いてくれる天使のようにさえ見えた。
ありがとう。
絶望の診断
ついに、医師から診断を言い渡される日。晴天の下、母と二人病院へと向かった。
コロナの影響で、重症患者が集まるエリアの面会室へは私ひとりで入り、医師と二人きりになった。
そして、医師は言いにくそうに、しかしはっきりとした声色で告げた。
「残念ですが、全身麻痺で身体を動かすことは困難です」
「もう言葉を通じて意思表明することは難しいと思います」
「意識レベルも回復するか…呼吸も自力でできない状態で…」
絶望した。
正直、父が倒れてから今までの一週間、言っても多少は良くなるよな、と根拠のない期待を巡らせていた。倒れた父の発見はそんなに遅くはなかったし、今までだってなんとかやってきたわけだし、それに父は悪いことなんかしてないし、と。
だから、医師の話を聞いている最中、血の気が引いていくのを感じつつ、夢か現か分からない精神状態に陥ってしまった。
信じられないし、信じたくない。
現実を受け入れられないまま、少しの間父の病室へ通してもらった。
いくつもの管を繋がれてベッドに横たわる父の姿。
声をかけても、触れても、揺らしても、父からは何も返ってこない。
堂々とした「おやじ」から変わり果ててしまったその姿に、「なんでだよ…」と途端に泣き声が漏れてしまった。
看護師からティッシュを差し出され、面会は一瞬で終わった。涙を拭いて、私はふわふわと母の待つ待合室へ歩いた。
苦しい告知
母は、看護師から買ってくるように命じられた日用品の入った袋を右手に持ち、俯きながら健気に立っていた。
「よろしくお願いします」と看護師に袋を渡す母。
これから父の病状をこの母に伝えなくてはならない。
あまりにも辛すぎる。母がこれから辛い思いをすると想像すると、悲しくて悲しくて居た堪れなかった。
そんな私の顔色を見て、母はなんとなく察したのかもしれない。
「どんな状況だって?」の声は少し震えていた。
そして、意思とは裏腹に、母の目を見た直後に涙が止まらなくなった。
私は、マスクの中をびしょびしょに濡らしながら、父の病状を母へ告げた。
正直、そのときのことはほとんど覚えていない。何をどんな風に言ったのか、そのときの母の表情はどんなだったのか、何もかも思い出せない。
いまだに現実感がないまま、私たち二人はしばらく会話もなく帰路に就いた。
さっきまでの晴天がゲリラ豪雨に変わっていた。なんだかやっすいドラマみたいだな、と心でツッコミながらも少しも笑えなかった。
友の支え<楽しさと苦しさに寄り添う温かみ>
どんなに苦しくても日々は過ぎていき、私も母も少しずつ仕事に復帰した。
コロナの影響で父との面会ができず、父に何もしてあげられない無力感の中、「働く」という社会とのつながりがあることにありがたさと喜びを感じた。
働いている間は、絶望が遠のいていく感覚を味わえた。
そして、この感覚が強くなったのは、なにより友人たちのお陰だ。
父が倒れてから少し経ったころ、私の状況を知る友人たちが食事に誘い出してくれた。
苦しさに真剣に耳を傾けてくれ、ときに共に泣いてくれながら、心理的にも実務的にも私を絶望から救い出してくれた。
なにより一番嬉しかったのは、今までみたいに、アホみたいな話をして笑いあえたことだ。
本当にこの温かさに助けられた。
そして私だけでなく、母も古くからの友人と喋るにつれ、少しずつ笑顔を取り戻した。
ありがとう。
つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
