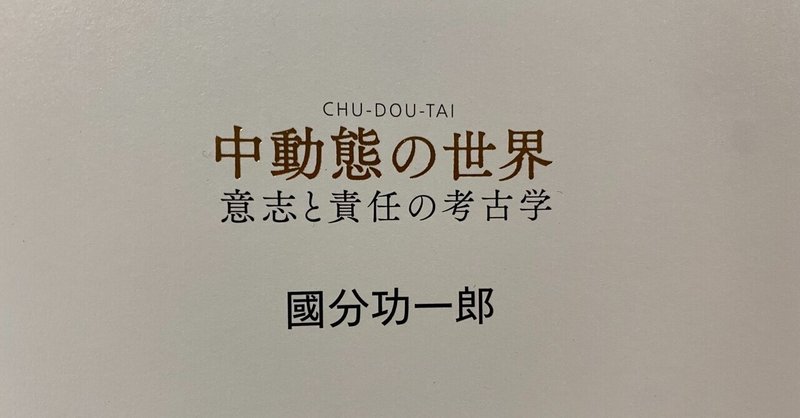
中動態の世界 意志と責任の考古学/國分功一郎
言葉は、人間の思考や行動、生活のあり方、社会の有り様を規定している。ゆえに用いられる言葉が異なれば、人びとの生き方も行動様式も、それらの元になる価値観もまったく違ったものになる。
つまり言葉というのは、ある種、人間にとっての檻なのだ。
だから、かつて存在したという中動態という動詞の態に目を向けることは、人間というものを見つめなおすにあたって、とても重要な観点となるのだと思う。
「かつて能動態でも受動態でもないもう一つの態、中動態が存在した」のだと、哲学者の國分功一郎は、『中動態の世界 意志と責任の考古学』で書いている。
この本では、失われた中動態に、人間の生き方の別の可能性が問われている。
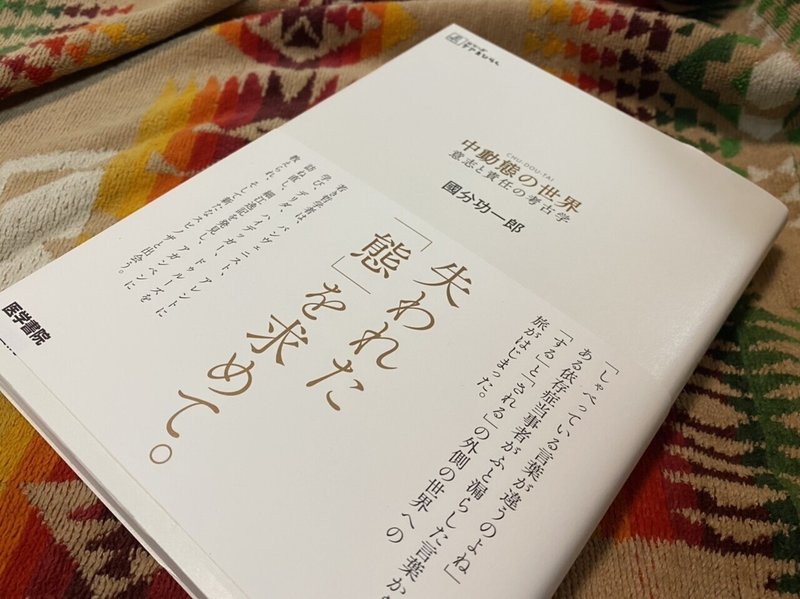
する/されるの外側
この本で問われているのは、中動態という態があった時代の人間の有り様がいまとはどう違ったか?ということである。
能動態と受動態の対立は「する」と「される」の対立であり、意志の概念を強く想起させるものであった。
と、著者はいう。
能動と受動が対立する言語の有り様のなかで、僕らはあらゆる行為を、自分の意思で行ったか、誰か(何か)にやらされたかを常に問われているし、自問したりしている。
「自分ごと化」や「やらされ感」なんて言葉が頻繁に飛び交うのは、まさに能動と受動の対立のなかで、行為の意志が重視されがちだからだ。
だが、この行為の意志をめぐる問いは少々息苦しくて、誰しもときにはそこから逃げだしたい気分になるだろう。意志には責任がつきまとったりもするからだ。
もちろん意志をもつのが大事で、責任をもって行動すべきこともたくさんあるが、かといって、そんなになんでもかんでも意志をもってやっているわけではないし、必要以上に責任ばかりを問われる毎日では息もできなくなる。
だから、ときどき息抜きをするためにも、僕らは逃げだしたくなる。
「する」と「される」の息苦しい対立の外側へ。
行為の過程の内にあるか外にあるか
著者が中動態に注目するのは、そうした視点からでもある。
われわれは中動態に注目することで、この対立の相対化を試みている。かつて存在した能動態と中動態の対立は、「する」と「される」の対立とは異なった位相にあるからだ。
かつて受動態というものはなく、あったのは能動態と中動態の対立だった。
受動態が登場しはじめたのは、古代ギリシアの時代、プラトンやアリストテレスが哲学していた頃である。その頃は、能動と中動の従来の対立軸に加え、受動がそこに加わり、新たな対立軸を生みだしはじめた頃であったらしい。
ローマの時代になり、そこで使われたラテン語になると、もはや中動態は消えてなくなり、いまと同様の能動態と受動態の対立軸に切り替わったそうだ。
プラトンやアリストテレスたちの生きた時代よりさらに前のまだ受動態がなかった時代、いまのような「する/される」の対立はなく、ゆえに行為の意志が問われることはすくなくとも行為の前提にはならなかったのでないか、と著者は問う。
能動に対して、中動はどのような対立関係にあったのか?と。
そこでは主語が過程の外にあるか内にあるかが問われるのであって、意志は問題とならない。すなわち、能動態と中動態を対立させる言語では、意志が前景化しない。
能動/中動の対立において問われるのは「主語が過程の外にあるか内にあるか」である。
中動態の動詞の例
主語が過程の内にあるというのは、どういうことかを考える上では、古代ギリシア語における中動態の動詞を具体的にみていくと、イメージができる。
たとえば、「欲する」という意味をもつβούλομαι(ブーロマイ)という語は、誰かが何かを欲するのは「心のなかからわき起こる欲望ゆえのことであり、この欲望によって突き動かされる過程のなかに主語はある」ことを示しているといえる。欲することはその人自身がすることであっても何かに突き動かされるようなところもあるので能動とはちょっと違うし、もちろん受動ではない。
あるいは、「できあがる」という意味をもつδύναμαι(デュナマイ)も、ものはできあがるとき、それはまさに生成の過程の只中にある。
「なる」という意味のγίγνομαι、「入浴する」という意味のλούομαι、「立ち上がる」という意味のἵσταμαιでも同様に、主語はその動詞で表された過程の内において、その行為の対象でもある。
それは「〜を言う」を意味するλέγω、「〜を送る」を意味するπέμπω、「〜を与える」などを意味するφημίなどの能動態の動詞が、その動詞で表された過程が作用するのが、主語の外側にあるものであるのとは対照的だ。
「使用する」という過程の内に
そもそも僕が、この本を読もうと思ったきっかけは、ジョルジョ・アガンベンの『身体の使用』で、まさに中動態が生政治による剥き出しの生に対する統治のあり方から抜け出すヒントとして扱われていたからである。
アガンベンは、そこで"chresthai"という「固有の意味がなく、コンテクストに応じてそのつど異なった意味を獲得している」中動態の動詞を紹介している。
強いて言うなら「使用する」という意味をもつ、その動詞はこんな風に意味を変化させるというのだ。
chresthai theoi 「神のものを使用する」=神託に伺いを立てる
chresthai nostou 「回帰を使用する」=郷愁を覚える
chresthai logoi 「言葉を使用する」=語る
chresthai symphorai 「不運を使用する」=不幸である
chresthai gynsiki 「女を使用する」=女と性的関係をもつ
chresthai te polei 「都市のものを使用する」=政治生活に参加する
chresthai keiri「手を使用する」=拳骨で殴る
chresthai niphetoi 「雪を使用する」=降雪に遭う
chresthai alethei logoi 「真実の話を使用する」=真実を言う
chresthai lotoi 「ロトス〔蓮〕を使用する」=ロトスの実を食べる
chresthai orgei 「憤激を使用する」=憤激する
chresthai eugeneiai 「良き出身を使用する」=高貴な血筋の出身である
chresthai Platoni 「プラトンを使用する」=プラトンと親しい
中動態が、主語がその行為の過程の内にあること、行為に巻き込まれていることを指すことをすでに知った僕らにしてみれば、これらのどの例も、主語が過程の内にあることを示すものだと気づくだろう。
中動態的に用いられる「使用する」という語が、外側の対象を「使う」ということを示す以上に、主語自らがその過程に巻き込まれていることを示すために用いられていることに気づく。
その意味では、「chresthai orgei =憤激する」はたとえ何かに憤激させられたのだとしても完全に受動的ではないし、とうぜん能動的に憤激したわけでもない。「chresthai niphetoi =降雪に遭う」も同様に、降雪に遭ったことを受け身で受け止めるよりも、みずからかその過程にあることを示している。だが、これも当たり前だが能動的に降雪に遭うようにしたわけでもない。
「chresthai theoi =神託に伺いを立てる」という行為さえ、神の意志に従うという受動的な姿勢というよりも、単に神の意志とともにある、その過程にあるというこを意味しているのだ。
つまり、ここには責任を伴う意志もないけれど、かといって、誰かに何かをさせられているから自分には意志も責任もないのだという受動的な思考もない。
そして、アガンベンが次のように書くように、
「中動態」の見方に立てば、"chresthai"という動詞の客体=目的語が対格ではありえず、つねに与格ないしは属格である理由も明らかになる。過程は能動的な主体=主語がその動作から切り離された客体=目的語へと移行していくのではなく、みずからのうちに主体=主語を巻き込む。そして主体=主語は客体=目的語のうちに引き入れられ、それに「与えられる」ことになるのである。
そのときには、わたしたちは"chresthai"の意味を定義することをこころみることができるようになる。それは、みずからとともに生じる関係、ある特定の存在者と関係しているかぎりでひとが受けとる影響を表現しているのである。(中略)そのときには、"somatos chresthai"=「身体を使用する」は、ひとつまたはいくつかの身体と関係しているかぎりでひとが受けとる影響を意味することとなるだろう。
自己と世界の使用者
あえて、もうすこしアガンベンの話を続けてみよう。
彼が「使用」あるいは「"somatos chresthai"=「身体を使用する」」ということにこだわったのは、そもそもアガンベンの本のタイトルでもある「身体の使用」という語が、まだ中動態が存在した時代を生きたアリストテレスの「『政治学』の最初で、奴隷の本性についての定義がなされている箇所に出てくる」からでもある。
アリストテレスはそこで「奴隷を《人間でありながら、その自然によって、自分自身に属するのではなく、他人に属する者》と定義」している。
この場合、奴隷を使用する主人の側がどういう立場で、奴隷との関係にあるかというと、僕らがそう考えがちなように「働かせる/働かされる」という能動態と受動の関係にあるのではなく、まさに「主人として奴隷の身体を使用している/奴隷がみずから奴隷の身体を使用している」という能動と中動の関係にあるのだ。
これは中動態を失い、そのように考える思考の可能性を失って久しい僕らにはなかなかイメージしにくい関係と言わざるを得ない。
だが、アガンベンが次に書くように、それは僕らが意志や合理性に基づく「製作と生産の領域」にどっぷり浸かりすぎてしまっているからだろう。
最初にあらかじめどうしてもやっておかなければならないのは、奴隷の「身体の使用」を製作と生産の領域から脱却させて、それを実践と生き方の――アリストテレスによると、定義からして非生産的な――領域に置き戻してやることである。
僕らはそうではない可能性を、中動態というものに目を向けることで再発見する必要がある。
そのことで、主人と奴隷の関係を、力によって他者の身体を統治しようとする者とされる者の関係というお決まりの生政治的なフレームワークのなかに置いてしまうのではなく、その檻から脱けだしたところで、自己と世界との不分明な経験的有り様(アガンベンいうところの〈生の形式〉)を記述できるようにしていく必要があるだろう。
詩人と同様、大工や靴職人やフルート奏者やわたしたちが神学的起源の言葉を用いてプロフェッショニスタと呼んでいる者たち、そして最後にはあらゆる人間も、なにかをおこなったり作ったりする能力の超越的な有資格者なのではない。彼はむしろ、自分たちの四肢と自分たちを取り巻く世界を使用するなかで、そして使用するなかでのみ、自己を経験し、自己を(自己と世界の)使用者として構成する生きものなのだ。
さまざまな課題が発生する過程に巻き込まれているなかで
さて、國分さんの本自体の話に戻そう。
國分さん自身が論じているのも、ここまでアガンベンの『身体の使用』について紹介したことと無関係ではない。
たとえば、國分さんは、次のような形で、権力というものを能動/受動の関係から、能動/中動の関係に置き換えて考えている。
権力の関係は、能動性と受動性の対立によってではなく、能動性と中道性の対立によって定義するのが正しい。すなわち、行為者が行為の座になっているか否かで定義するのである。
権力を行使する者は権力によって相手に行為をさせるのだから、行為のプロセスの外にいる。これは中動性に対立する意味での能動性に該当する。権力によって合意させられる側は、行為のプロセスの内にいるのだから中動的である。
つまり、権力によって何かを強いられてやらされたとしても、それが受動的な行為かというと必ずしもそうではないだろうということだ。もちろん、受動的ではないからといって、能動的に積極的にやった行為とは同じではない。権力に強いられて行った行為は、自分がその行為の過程に巻き込まれている限りにおいて、むしろ中動的と捉える必要があるということだ。
武器で脅かされて便所掃除させられている者は、それを進んでするの同時にイヤイヤさせられてもいる。すなわち、単に行為のプロセスのなかにいる。能動性と中道性の対立で説明すればこれは簡単に説明するできることである。
これは、民主主義における政治参加がなぜ必要か、日常的に仕事をする場合においても真に「やらされている」受動態的な仕事はないのだということにもつながってくるだろう。
必要以上に責任を問われる必要がない一方で、中動態的にみずからが過程に巻き込まれてあることを、その過程に巻き込まれているほかの人たちといっしょに見つめなおすことで、みずからがその過程に巻き込まれてあることを反省することはできる。
いま、さまざまな環境・社会課題が存在し、その課題の生じる原因に多かれ少なかれ巻き込まれてしまっている自分たちの有り様を問いなおすために必要なのは、そんな風に中動態的な見方で自分たちの活動を見なおしてみることではないだろうか?と思う。
まさに、そうしたサステナビリティにも関連した視点においても、「中動態の世界」に入りこんでみることが必要なのだと感じた。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
