
本を読めない病
このゴールデンウィーク、本が読めない病に陥った。
ほんと何年かに一度程度にしか起こらないことなんだけど、前に明確に記憶にあるのは、もう15年以上前だ。
普段、ごくごく自然に読んでいる本が突如読めなくなるので、それなりにびっくりする。焦る。
本に書かれたこととの距離が埋まらない
もちろん、文字が読めなくなるとかそういうことではない。その間もスマホでネット上の情報は普通に見ているからだ。そこに変化はない。いや、本を読まない分、時間にしたら多いのだろう。だから、文字を読めなくなるというのではない。
本だけが限定的に読めなくなるのだ。
もうすこし正確に言うなら読み続けられなくなる。普段なら数10ページは自然にまとめて読んでいたのが、ほんの数ページで読めなくなる。具体的には、書いてあることが頭に入ってこないということが起こる。
もちろん、普段でも読んでて内容が頭に入ってこないことはある。集中力に欠けていて、他のことに気を取られながら、本を読んでいるとそうなる。
それでも読み進めていくと、だんだんと本の内容のほうに集中できるようになっていく。書かれた内容に頭が集中しはじめて、読むことが自然になっていく。そうなれば、むしろ本に書かれたこと以外の他のことは気にならなくなる。
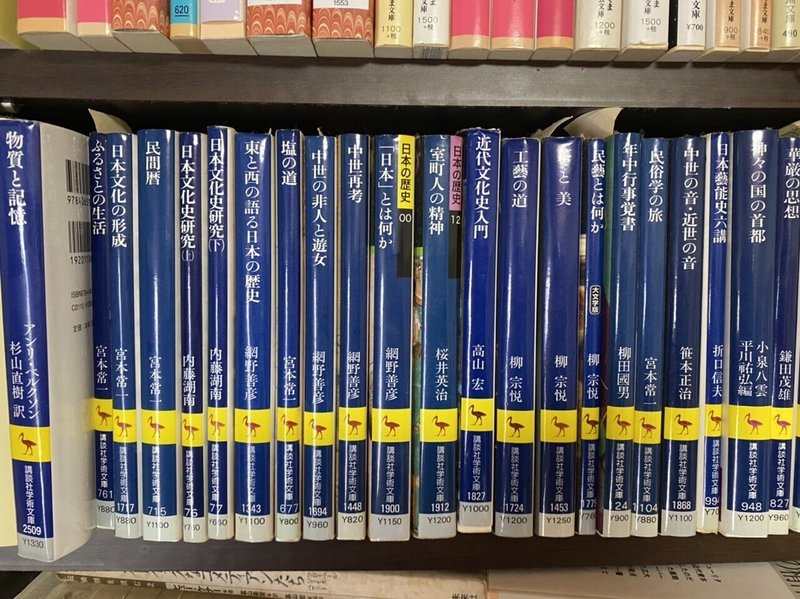
でも、このゴールデンウィークの数日間はそうならない状態に陥った。しばらく読んでも一向に書かれてあることが頭に入ってこない。読み続けるのが苦痛なくらい、書かれた内容が頭に入ってこず、本の世界と自分の思考のあいだの距離をうまく埋められなかった。
その状態だと、読書は続けられない。それに、そこで無理してまで本を読もうとは思わない。すこし読んでみて「読めないな」と感じたらあきらめた。本が読めないという人はいつもこういう状態なのかな、と思ったりした。
本の複数宇宙
前のときもそうだっただけど、本を読み続ける集中力が保てないのは、生活環境が変わるときだ。
前回なら数ヶ月間、仕事で名古屋で生活することになり、その最初の10日ほどだったか、本が読めない病に罹った。いつの間にか、病気は治って読めるようになったが、どうして治ったのかはよくわからない。たぶん、名古屋での生活環境に慣れたせいだろうと勝手に思っている。
生活環境が変わると、本のなかのこと以上に外部環境のほうに気にしなくてはいけないことが多くなるからだろう。それで本に集中しづらくなるのではないかと思っている。そういえば、旅行にいくときも、旅先で本を読もうと思って、持っていった本はほとんど読み進まなかったりする。読もうと思っても集中力が続かず、読み進まないのは同じような症状だ。

ある意味、マルチヴァースなんだろう。
現実の物理的環境のほかに無数の本のなかの宇宙がある。人はその宇宙のあいだを行き来はできるが、同時に、複数の宇宙には存在できない。なので、地球の地表上の物理宇宙に存在しているとき(この言い方はラトゥールの『地球に降り立つ』を意識。だから丸い地球がある宇宙とは日常の現象宇宙も別宇宙だ)、本の宇宙には入り込めない。本の宇宙に入るには、地表から離脱する必要がある。本が読めなくなる病気は、この複数宇宙間の移動に障害が発生している状態なんだろうなと思う。
薬はある
で、今回の生活上の変化は、明日に迫った引っ越しであるのは間違いない。いろいろ片付けしたり、新居の方の準備をしたり、廃棄したり、新たに購入しなくてはいけないものの準備をしたりと、地表上の物理的宇宙のほうでのやることがたくさんあったり、実際物理的にも部屋の環境が変わっていったりすることで、本の宇宙に行く余裕を失っているのだろうなと感じている。
まあ、読んでいた本が、ヘイドン・ホワイトの700ページ、しかも2段組の大著『メタ・ヒストリー』だったり、逆に小品ながらいつにも増して手強い内容のジョルジョ・アガンベンの『到来する共同体』であったことも無関係ではないだろう。
ヘイドン・ホワイトの次のような歴史学を詩学としてみる見方も面白いし、
歴史家は、歴史の場の史資料に表現や説明のための概念装置を適用する前に、まずその歴史の場をあらかじめ形象化しなくてはならない。つまり、その歴史の場を精神的な表象の対象として構成しなくてはならない。この詩的な行為は、歴史の場を特殊な種類の領域としていつでも解釈可能な状態にする言語的行為と同じことである。言い換えれば、ある領域は、それが明示的に解釈されうる前には、まず第一に、そこで識別できる形象を内包している基盤として解釈されなくてはならないのである。
アガンベンの「到来する存在はなんであれかまわない存在である」といい、「なんであれかまわない存在」という観点から、個別と普遍の関係を探っていこうとする視点もものすごく興味深い。
ここで問題になっている〈なんであれかまわないもの〉は、個物ないし単独の存在をある共通の特性(たとえば、赤いものであるとか、フランス人であるとか、ムスリムであるとかいったような概念)にたいして無関心なかたちで受けとるわけではなく、それがそのように存在しているままに〔ありのままに〕受けとるにすぎない。このことによって、個物ないし単独の存在は認識に個別的なものの言表不可能性と普遍的なものの可知性のいずれかを選択することを余儀なくさせる偽りのディレンマから解き放たれる。可知的なものとは、ゲルソニデスのみごとな表現によれば、普遍的なものでもなければ、ある系のなかに包含された個別的なものでもなく、《それがどんなものであれ単独の存在であるかぎりでの単独の存在》であるからである。
しかし、それらを興味深く感じ、それらについて深く知りたいと思いつつも、そのための具体的な活動としての「本を読む」という行為に入り込んでいけないのが、本を読めない病の症状だ。
というわけで、まあ、これは引っ越しが終わって、落ち着くまでしばらくは本は読めないかなと思っていた。
思っていた? そう、思っていたのだけど、変化が起こったのは昨夜のことだ。何気なく手に取って開いた高山宏さんの『アリスに驚け』を読み始めてみると、あれま、何のことはない、すらすらと読み進められ、おもしろく興味をひく内容にどんどん惹きつけられて、数10ページは読んでしまった。

高山さんは『不思議の国のアリス』の冒頭、「アリスは土手の上でお姉さんと並んですわったまま、何もすることがないので、あきあきし始めていました。一度二度、お姉さんの読んでいる本をのぞきこんだのですが、挿絵もなければ会話もないのですから、「絵も会話もない本なんて何になるの」と、アリスは思いました」を紹介しつつ、「ただ読むなどということはありえないのだ、といいたい」と書いて、この短い冒頭の文の背後にある壮大な文化史を読み解いてくれる。
ルイス・キャロルこと、チャールズ・ラトウィッジ・ドジソンが生きた英国ヴィクトリア朝時代になぜ人はアリス同様、退屈したのか、絵も会話もない本が17世紀なかばから生まれ、そのなかで演劇に変わって小説も生まれ、カトリックのミサの共同体的かつ体験的な宗教活動からプロテスタントの個々人が個室にとじこもって聖書を黙読するスタイルに変わったこと、などなど。
飽き飽きしたアリスが「絵も会話もない本なんて何になるの」と思うという一文が、大きな文化史という別の宇宙につながっていることを教えてくれる。
こんなマルチヴァースのつながりを、おもしろおかしく教えてくれる本が、僕の宇宙間の交通障害を解消してくれるクスリになった。
もちろん、『不思議の国のアリス』を読み返したくはなったのだけれど、それはもはや引っ越しのダンボールのなか。それこそ、アリスを読むのは引っ越しが落ち着いてからのことかな。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
