
田原総一朗は”あんがじゅまん”する。
昨年12月の某日。
落ち着いた午後のひと時、私たちは馴染みの喫茶店に集まった。
からんころんからん、ベルが鳴って扉が開く。
店に入ってきた白髪の老人男性は、ゆっくりとした足取りだが、背筋がすっと伸びて腰が据わった佇まいをしていた。

「どうもどうも、今日はよろしく」
老いを感じさせない声量と、元気な手振りを交えた挨拶に、店の空気が穏やかに昂揚する。にこやかに笑顔をふりまきながら、年季の入った椅子にゆっくりと腰を下ろした。
田原総一朗さんは87歳。長きにわたり活躍しているジャーナリストであり、深夜の討論番組『朝まで生テレビ』の司会を今もされている。
この日、田原さんが私たちと会った場所は、早稲田にある喫茶店「ぷらんたん」。創業70年の老舗であり、コロナ禍で経営がピンチに陥ったが、有志によるクラウドファンディングで危機をしのいだ。
卒業生の私も運営メンバーに入れてもらった。学生時代から居場所のように過ごしていた、思い出の店だ。
この日、田原さんからお誘いをいただき、ぷらんたんに集まった。
田原さんもクラファンに参加してくださった。早稲田大学の「特命教授」として教鞭を執られていた時期に、何度か訪れたことがあったらしい。
そのご縁で、応援メッセージの寄稿をお願いしたら、快く引き受けてくださった。「若い人が頑張っているならば」と、惜しみなく協力してくださったのだ。
クラファン終了後、「ぷらんたんに行って、ぜひメンバーと会って話したい」と私たちにオファーしてくださり、この日、特別に歓談することになった。

「今日はお越しいただきありがとうございます」
挨拶をしたら「え?」と聞き返された。彫刻のように刻まれた顔の皺が、眉間に向かって寄せ集まる。
すると傍らにいたマーネジャーさんが耳に手を当てて、穴のあたりに触れる。どうやら補聴器の具合が悪かったらしい。
颯爽とした存在感を放っていても、身体は確実に衰えている。つい忘れていたが、この人は87歳の高齢者なのだ。

「(店が)残ってよかったね。いくら集めたの?」
「750万円です」
「それはすごい。よかったよかった」
田原さんも早稲田大学の卒業生であり、私たちの大先輩だ。
ぷらんたんの創業は1950年。田原さんが在籍していた頃(1960年卒)、既に店はあったが、実際に訪れたかどうかは記憶が曖昧だった。
当時は街のいたるところに個人経営の喫茶店があり、学生のたまり場になっていた。スマホはおろか携帯電話さえ無かった時代、喫茶店にはノートが置いてあり、サークル部員や友人同士の連絡手段になっていた。
今では早稲田の街はチェーン店のカフェが台頭し、喫茶店は絶滅危惧種だ。そんな中で、ぷらんたんは半世紀以上にわたって「学生街の喫茶店」文化を受け継いでいる。

「当時は大学の講義なんて誰も行かなかった。今はみんな出るでしょ?」
「わりと真面目に勉強する学生が多いと思います」
「僕らの時は誰も出席しなかった。だけど、みんな難しい本を読んで議論してた。その頃は…」
田原さんは学生時代、作家に憧れて読書や執筆に明け暮れた。だが、同時代の石原慎太郎や大江健三郎を読んで「自分には才能がない」と挫折し、後にジャーナリストの道に進んだ。
穏やかな調子で学生時代の思い出を語る田原さんは、討論番組の時とはまるで違っていた。激しい口調で相手の話を遮るように追及するスタイルは、もはやお馴染みの話芸になっているが、この日私たちは「田原総一朗」の素の一面を目撃した。
クラウドファンディングでは、そんな過去の記憶を交えたメッセージを寄稿していただいた。
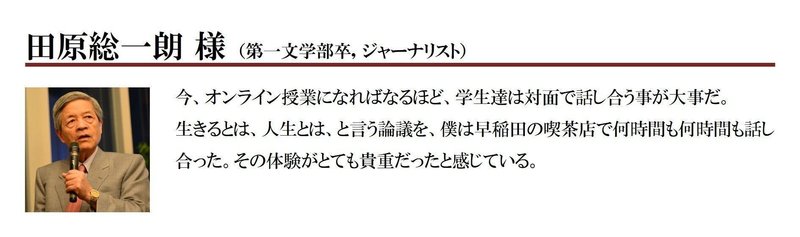
やがて話題はジャーナリストとして積み重ねてきたキャリアの話へと移った。
「僕は就職活動で、大手のメディアは全部落ちた。それで岩波映画という小さな会社に入った。そこは金がないから、大手の連中に(作品の質で)勝てっこない。それでどうしたか。大手じゃ出来ないような過激なものばかり撮った」
田原総一朗さんは元々は映像を撮る人であり、裏で作品を作る側の人間だった。岩波映画の後、テレビ東京の前身である「東京12チャンネル」に移籍している。
田原さんの取材に懸ける姿勢は、狂気を帯びたように凄まじい。作品を創るためなら、取材にこぎつけるまで手段を選ばず、取材前には相手のことを徹底して調べる。それが田原さんの変わらない姿勢だ。
かつてアメリカのマフィアを取材した時、「(取材したかったら)みんなが観ている前で(売春婦と)セックスしろ」と言われ、酒場のビリヤード台の上で本当にヤッてしまったという逸話もある。
歴代の権力者から、世間を賑わせたありとあらゆる人に論戦を仕掛け、「タブーに挑むジャーナリスト」「暴走する(人の話を聞かない)司会者」のイメージが強いが、その原点はドキュメンタリー制作にあったのだ。
マスターのダンが「少年を撮りたいか」と聞くので、「撮りたい」と答えると、今度は「ビリヤード台の上でやったら撮らしてやる」と言う。
仕方がないので、酒場にあるビリヤード台に上がった。お客たちが見ている前でズボンを脱ぎ、黒人の売春婦とコトを為した。またまた、酒場中の客から拍手喝采である。
ドキュメンタリーを撮るということは、要するに取材対象と関わることである。ディレクターの私を「世の中でいちばん信頼できる人間だ」と相手が思ってくれなければ、ドキュメンタリーなど撮れない。私を信頼するということは、言ってみれば精神的にも肉体的にも素っ裸になることだ。
「山下洋輔ってピアニスト知ってる?」
「すいません、分からないです」
「彼が「ピアノ弾きながら死ねたらいいなあ」って言うから、学生運動でバリケード封鎖しているキャンパスで演奏会を開いた。当時は、左翼どうしが内ゲバして火炎瓶を投げ合っていた。その中でピアノ弾きながら死んだらいいんじゃないかと思った。それで反戦連合っていう中核派から分かれたところのリーダーに話したら「おもしろい、やろう」となった。で、大隈講堂の地下から勝手にピアノをひっぱりだして、(敵対している)民青が占拠してる建物まで運んで、ほんとに演奏会をやった。そしたら、みんな演奏を聴いて、誰も火炎瓶なんて投げなかった。でそれを撮ったの」
「山下さんってどうなったんですか」
「まだ生きてるけどね、彼」
田原さんの話を聞いていると、「昭和」を生きた人間の生命力を感じた。
この日集まったメンバーは私を含め平成生まれで、昭和という時代は経験しようにも出来なかった遠い過去の話でしかない。敗戦も高度経済成長もオイルショックもバブル崩壊も、教科書でしか知らない。
大きな混沌の中で揺れ動き、渦巻く時代の波に押され、押し返し、日本の言論界をけん引してきた。そんな「田原総一朗」の原点ともいえる昭和が、すこし羨ましく思えたのだった。

「今の若い人たちは、どんなことに悩んでいるのか。何を考えているのか。それを知りたい。君はどう思う?」
自分ばかり話すのに物足りなくなったのか、田原さんからも私たちに質問を投げかけてきた。それまでの穏やかな空気が、瞬時に緊張した。混じり気のない目は、刃のように鋭く私たちに突き刺さる。
一人のメンバーが、おもむろに口を開いた。
「コロナでオンラインのコミュニケーションが増えて、うまくやり取りができなくなって自分を責めてしまうことが増えました。人と会う機会も減り、それがストレスになっています」
朝生のように「どうして!」と追及されるかと思いきや、物憂げな表情で彼女の話を聞き、噛んで味わうように頷いていた。
田原さんは、今の若者が置かれている状況に思うところがある様子だった。ご自身も、オンラインでの番組収録が増えたり、会食が無くなったりして、それが寂しく感じてならないらしい。
「僕が小さいころ、地域には共同体があって、助け合って生きてきた。だけど、今はどんどん独りでも生きていけるようになって、孤独になる人も増えた。コロナでもっとそれが激しくなった。宗教が共同体の代わりなんだけど、若い人は宗教にまったく関心がない。そこで聞きたい。なーんで若い人は…」
コロナ禍での「孤独」や「生きづらさ」をテーマに対話が進んでいったかと思いきや、いつの間にか共同体と宗教の話になり、日本における宗教の発展過程から「僕は三人の総理大臣を失脚させた」と政治講談に急旋回して、最終地点が見えないまま話が進んでいった。
記憶が次から次へと湧き出ている様は、脈絡がないように聞こえても、田原さんにしか見えない解があるのだと思った。

「君はどう思う?いまの世の中、何が問題だと思うの」
田原さんから私に質問が質問が飛んできた。
私にとって田原さんは10年来の憧れの人だ。
田原さんを初めて知ったのは高校時代、特集されていた「情熱大陸」を観た時だった。そこで田原さんの生き方をカッコいいと思い、自分も早稲田に入りたいと思った。

入学後は、田原さんが教鞭を執っていた講義「21世紀日本の構想」(通称:大隈塾)を履修していた。政財界の大物ゲストを交えて、バチバチのディスカッションをする講義。そこで何度かお話ししたことがあった。
それでも、お会いする時はいつも緊張する。意見を述べるのは得意ではないが、せっかく田原さんから質問をいただいたので、思うところを何でも言おうと思った。

「これだけコロナで世の中が大きく変わっても、先の衆院選で若い世代の投票率や社会への関心が大きく変わらなかったのが意外に思えました。どうして若い人は政治に関心がないのだろうって、思います」
「なんでだと思う?」
「…政治や社会問題の話は対立を生み出すと思います。意見の相違から論争が起きるものですが、なるべくそんな対立を生まないようにするのが生きていくうえで大事で、争うのを避けたいからではないでしょうか。私も議論をするのは得意ではありません」
「そうかな、論争は楽しいじゃない」
それはあんただけやろ、とツッコミたい気持ちをおさえていると「はあ」と気の抜けた返答をしてしまった。

「サルトルって知ってる?」
いきなり出てきた昔の人物名に、不意を突かれたような感覚になった。
「知ってますが、読んだことはありません」
「彼は”あんがじゅまん”と言った。すべての人間は社会変革に参加する責任がある。つまり自分の意見を持って政治に参加しろってこと」
”あんがじゅまん” が聞き取れなくて二度聞いてしまった。その単語を淀みなく口にした時の田原さんの表情が、87歳のジャーナリストではなく、20代の文学青年のような、得意気な爽やかさがあった。
「論争は楽しいよ。楽しいし負けてもいいのよ」
「はあ…」
「負けることで自分の考えの間違いに気がつくこともあるのだから」
論争は楽しいし負けてもいい。このセリフをこんなにも説得力と安心感を持って語ることができるのは、この国に田原総一朗しかいないのではないかと思う。
穏やかに、諭すように話す田原さんの顔が、まるで孫と接する好々爺みたいに柔和だった。

気がつけば、外の景色が薄暗くなっていた。「ではそろそろ」とマネージャーさんに促され、帰り支度を始められた。
”あんがじゅまん” について聞きたかったが、時間がきてしまった。それでもこの日、私たちは2時間半ちかく田原さんと会話した。
ひとまず田原さんと一緒に店を出て、帰りのタクシーをつかまえやすい大通りまでご一緒した。
ちょうど空車が一台交差点で信号待ちをしていて、青になったタイミングでそのまま乗り込むことができた。
「今日は楽しかった。また話したい」
ドアが閉まると、窓を開けて手を振ってくれた。車が見えなくなるまで手を振り返して見送った。

次の日、田原さんが突如として放った ”あんがじゅまん” の正体を知りたくなり、書店でサルトルの本と関連書を手にした。
前の日、誰もが知っている日本の政治家や文化人の名前ばかりを口にしていた田原さんから、突然出てきた外国の思想家の名前が頭から離れなかったのだ。

サルトルは戦前から戦後にかけて活躍したフランスの思想家であり、小説家や劇作家としても活躍していた。代表作に小説『嘔吐』などがある。
田原さんが言っていた ”あんがじゅまん” は、アンガージュマン(engagement)という仏語であり、「(約束や業務によって人を)しばる」「(人をあることに)参加させる」の意味がある。
このアンガージュマンの前提となる、サルトルの思想が「実存主義」と言われる。実存主義は「人間は自由である」という認識から出発する。個々の人間の本質(存在する目的)は、この世に生まれてから一人一人が世界の内で選んでいく。

例えば、ペーパーナイフは「紙を切るために使う道具」という目的があって(本質)、それから実際に作られる。しかし、人間は予め本質が備わって生を受けたわけではない。「人間はなんのよりどころもなくなんの助けもなく、刻々に人間をつくりだす」(サルトル『実存主義とは何か』)のが、実存主義の人間観なのだ。
これを「実存は本質に先立つ」と言う。実存は「現実存在」の略であり、「現実的具体的に存在する個々のもの」を指す。(松浪信三郎『実存主義』)
実存が本質に先立つとは、この場合何を意味するのか。それは、人間はまず先に実存し、世界内で出会われ、世界内に不意に姿をあらわし、そのあとで定義されるものだということを意味するのである。(中略)人間は、みずからそう考えるところのものであるのみならず、みずから望むところのものであり、実存してのちにみずから考えるところのもの、実存への飛躍ののちにみずから望むところのもの、であるにすぎない。人間はみずからつくるところのもの以外の何ものでもない。
サルトルは自由な状況に置かれた人間を「自由の刑に処せられている」と言い、「世界のなかに投げだされた」が故に「自分のなすこと一切について責任がある」とした。
この過程において人間は「孤独」であり「不安」をともなう。こうした状況のなかで、投げだされた世界に自分を拘束するのがアンガージュマンであり、「自由」は「世界」で拘束されたうちにしか出現しない。
拘束された状況のなかで、いかにそれを引き受け、自らをつくっていくか。それがが、サルトルの実存主義なのだ。
自由は、本来あるのではなく、歴史的状況のなかで得られるものである。
選択すべき出口はないのだ。出口は、発明されるのだ。そして各人は、各人固有の出口を発明しつつ、自分自身で自分を発明するのだ。人間とは、毎日発明すべきものなのである。
サルトルは当時の政治・社会問題に積極的に発言することで、自らアンガージュマンしていた作家だった。その影響は日本の作家にも及び、開高健や大江健三郎はサルトルと面会している。
学生時代の田原さんも一文(第一文学部)にいたころ、サルトルから大きな影響を受けた。
ショーペンハウエルやニーチェらの哲学書も読んだが、入学当初からずっと読み込んでいたのが、サルトルやカミュ、それにヤスパースら実存主義の哲学書である。要するに、世の中は不条理で、矛盾しているものだというサルトルらの主張に深く共感した。選んだわけでもない不条理な世界に投げ込まれた自分が、今度は自らを投げ出して関わるというのが実存的な生き方で、フランス語でアンガージュマンと言う。
一文の四年間で最も身になったことと言えば、サルトルやカミュの作品をまともに読めたことであり、その後の私の思想や行動にも相当の影響を与えている。
田原さんが言う「矛盾」とは、「人間は不自由な世界に身を置くことで自由になる」というサルトルの考えであり、自らを世界に投げだし(投企)アンガージュマン(自己拘束)することで、本当の自由を得られるということだ。
サルトルは決して神の存在を否定したわけではないが、「予め自分の運命は決められている」と信じる人を「卑怯者」と糾弾した。あくまでも、人間の存在は全面的な自由の下にあり、個々人の行為の選択がこの世界を形成している。
私がいおうとするのは、人間は一連の企図以外の何ものでもないこと、人間はこれらの企図を構成するさまざまな関係の総和、綜合、全体なのだということである。
田原さんとサルトルにとっての「不条理」の原点は、戦争体験にある。
田原さんは小学校時代に敗戦を迎え、それまでの「鬼畜米英」から「民主主義万歳」へと世の中の価値観が様変わりした。「君たちは国のために名誉の戦死を遂げるのだ」と言っていた学校の先生が、「戦争を起こした戦犯は悪いやつだ」と、まるで反対のことを言うようになった。
それが大きなショックで、大人のいうことを信用できなくなった。その時の不信感が権威への反抗心になり、後の取材活動につながる。
私は敗戦まで、天皇陛下のために軍隊に入り、天皇陛下のために出征し、天皇陛下のために死ぬのだと思い込んでいた。
敗戦後、初めて小学校へ行ったのは、夏休みが終わってからのことだ。ここから、教育現場でも戦後が始まったのだが、教師たちは「この戦争は侵略戦争で悪い戦争だった。日本の指導者たちはみんな間違えた。君らは今後、戦争が起きそうになったら体を張って阻止しなさい」と私たちに説いた。(中略)教師たちからは「自分たちも間違ったことを教えてきた。申しわけない」の一言も無かったので、私は「何言っているんだ」という気持ちになった。
田原さんは現役のジャーナリストとして太平洋戦争を経験した数少ない一人だ。それだけに、「戦争を知っている世代」として発言をすることを止めない。
令和になって、戦争を知らない天皇が登場した。そういえば、安倍晋三首相も、菅義偉官房長官も戦争を知らない世代である。
サルトルも戦争を経験した。1939年の第二次世界大戦の始まりとともに動員されたが、1940年の5月まで続いた戦闘休止状態(まやかし戦争)により、余暇を使って執筆活動にいそしんだ。
この時期に『存在と無』や『自由への道』といった作品を書いた。好き好んで従軍したわけでもないサルトルが、戦争という状況に自らをアンガージュマンし、自らの思想をつくりあげていったのだ。
たとえ、この地球がいつか粉々になってしまうべきものだとしても、この地球のためにもまた賭けねばなるまい。そのわけは、要するに、我々が、この地球上にいるからだ。
とにかく、世界は醜く、不正で、希望がないように見える。といったことが、こうした世界の中で死のうとしている老人の静かな絶望さ。だがまさしくね、わたしはこれに対抗し、自分ではわかっているのだが、希望の中で死んでいくだろう。ただ、この希望、これをつくり出さなければね。
もうこの世にはいないサルトルの著書に触れていると、今この世界に生きている田原さんにその思想が生きているように思えた。
人間はこの世界の内で、自由でありながら不自由な状況にある。どのようにして置かれている状況に自らアンガージュマンしていくか、それは自分自身が選択していくしかないのだ。
自分が生きている時代に、つねに自分を巻き込ませていきていく。そんな田原さんの生き方が反映された動画コンテンツがあった。
田原さんがひろゆき氏、成田悠輔氏と対談したこの動画では、田原さんへの批判的なコメントが目立つ。たしかに、田原さんは二人の話を遮ったり、「安倍さんって知ってる?」などと挑発するように質問したりと、まさに「老害」的な役目をしている。
だが、この動画での田原さんの言動は、終始無難な対談をするのではなく、あえて自ら悪役を演じることで、二人から本音を引き出そうとしていたのだと思った。
何より、それを見た若い世代に、体を張って日本を変えろというメッセージを伝えているとさえ感じた。
田原さんは『朝まで生テレビ』の本当の狙いについて、以下のように述べている。
立場を異にする論客たちが、ときには、いや、しばしば非理性的に、怒号、罵声まで交えて激論する。
この番組、一見論客たちの討論の激しさを売り物にしているようだが、この番組を企画したわたしの本当の狙いはそうではない。
標的は時代だ。時代との闘い、格闘技なのだ。
田原さんが起こす議論はいつも「時代」を念頭に置いている。
田原さんは自らの戦争経験がもとで芽生えた、権威への懐疑や反抗がジャーナリストの原点になった。就職活動で大手のメディアに落ちて、小さな映画会社で始まったキャリアでは「大手が作れない過激な作品」を撮り続けた。
前代未聞の深夜の討論番組『朝まで生テレビ』では、異なる思想の論客を集め、当時まだ触れられていなかったテーマを取り上げてきた。
そんな田原さんを「タブーに挑むジャーナリスト」と表現する人もいるが、そもそも田原さんにとって破ってはいけない規範も秩序もないのかもしれない。
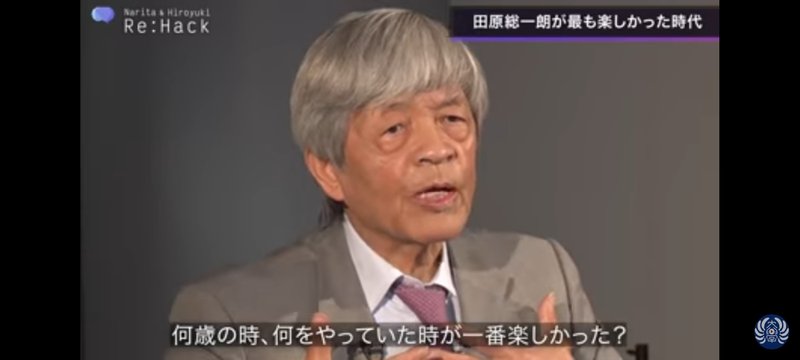
動画の終盤、ひろゆき氏と成田氏から「何歳の時、何をやっていた時が一番楽しかった?」と聞かれた田原さんは「今が一番楽しい!」と即答した。
コロナ禍の今に至るまで、田原さんは沈黙に身を置いて事態を傍観せず、時代の只中に自らを巻き込んで真相を見ようとしている。そして自らの言葉と行動を通して、日本社会を変えようとしている。
田原総一朗は、87歳の今も時代にアンガージュマンしているのだ。

先日、私たちは田原さんと再び会って話した。
ぷらんたんでの歓談がきっかけとなり、これから定期的に若い世代と対話する会を開くことになったのだ。その打ち合わせをzoomで行った。

早々に話すべきことを終えて、ぷらんたんで会ったときのように歓談した。
「田原さん、こないだ会ったときに「サルトルを読んだか?」と言われたので、読んでみました。すごくおもしろくて、田原さんの考え方や行動に似ているなと思いました」
「サルトルは、人間の存在は矛盾していると言った。僕は学生の頃サルトルばっかり読んでた。森鴎外も好きだ」
「田原さん、ひろゆきさんと成田さんとの対談動画でかなり白熱していましたけど、実際はどうでした?」
「ものすごく楽しかった。あれくらい自由に物を言える人がいないとダメだね。みんな無難なことしか言わなすぎる!」
今年で88歳。
まだまだ長生きして、アンガージュマンして、若い世代にメッセージを発し続けてほしい。
対話会が終わったら、続編としてnoteを書きます。
参考文献(順不同)
田原総一朗『塀の上を走れ 田原総一朗自伝』講談社、2012年
田原総一朗『田原総一朗的発想!』毎日新聞社、2012年
田原総一朗『戦後日本政治の総括』岩波書店、2020年
田原総一朗『原子力戦争』ちくま文庫、2011年
サルトル『サルトル全集 第九巻』人文書院、1964年
サルトル『サルトル全集 第十巻』人文書院、1964年
サルトル(鈴木道彦 訳)『嘔吐』人文書院、2010年
サルトル(伊吹武彦 他訳)『実存主義とは何か』人文書院、1955年
サルトル, レヴィ(海老坂武 訳)『いまこそ、希望を』光文社古典新訳文庫、2019年
松浪信三郎『実存主義』岩波新書、1962年
海老坂武『サルトル―「人間」の思想の可能性』岩波新書、2005年
いただいたご支援は、よりおもしろい企画をつくるために使わせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

