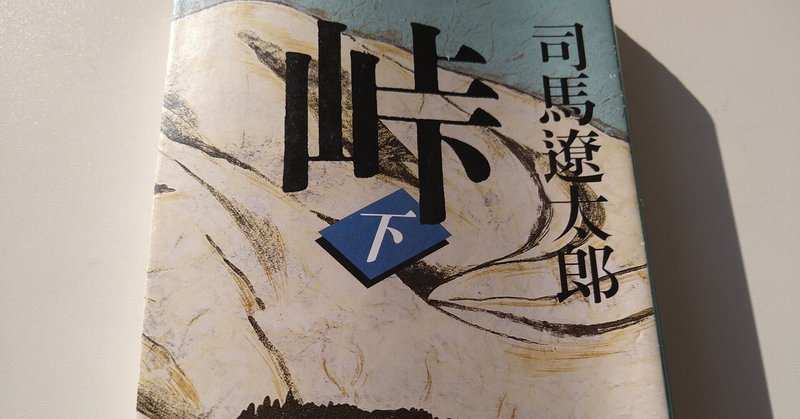
司馬遼太郎「峠」を読んで
今日はとある展覧会の受付をした。人があまり来ないので、一日中読書が出来た。
今回読んだ本は司馬遼太郎「峠」。
時は幕末、越後長岡藩という小藩に生まれた河井継之助は、明治維新という荒波の中で、藩の存立を守るために戦いに身を投じる。
山口でも一家揃って歴史好きの家に生まれた私は、子供の頃から司馬遼太郎が大好きだったが、彼の幕末時代小説における「佐幕贔屓」には若干辟易するところがあり、「燃えよ剣」を読んだあとは彼の幕末を題材とした小説からは遠ざかった。
が、この度書店で見かける機会があったので買ってみた。
司馬遼太郎の幕末贔屓には、彼の武士観が反映されている。河井継之助然り、土方歳三も然り。
いかに強い時流にも飲み込まれることなく、自我を仁王立ちさせて、抗い続け、最後には死ぬ。
これが武士である、と。
武士というより、男の目指すべき生き様というべきか。
これは本当に憧れるものである。
本を読み進め、文面が華々しくなっていくに連れ、私自身も熱くなる部分があり、次々と服を脱いでシャツ1枚になってしまった。誰もが見惚れる男の生き様、ロマンである。
受付中トイレに立つとき、ポケットに入れた財布やスマホを置き忘れるほど、読書の世界に入り込んでいた。
継之助が死に際し、自分の身体を燃やすための炎を見ているシーン。
腹は切らず、天命に任せているところに司馬遼太郎らしさを感じる。司馬遼太郎は、男の自決シーンを余り書かないように思う。
目線はなるべく客観的に書きつつ、湧き出す感情という主観へさりげなく思考を誘導していく。司馬史観というのは功罪があるが、読み物としてみると完成された美があり、読みづらさは一切ない。
読了する時には、日は西に沈みつつあった。私の住む岡山では、今日2月12日はサンサンと照る太陽の下に気温はぐんぐん上がり、晴れの国らしさを醸し出している。
うーんと背伸びをした。読書をする時はいつもこうだ。つい時間が通り過ぎていく。ましてや時代小説となれば、その時代に飛び込んでしまうから、時間の感覚はなくなっている。
結局3冊全部読み終えて、受付の仕事も終わった。
楽しい時間であった。
今度は、継之助が師事したという山田方谷の旧跡を訪ねに、備中高梁まで行く事にしよう。
春が待ち遠しい。
インターネットを渡り歩いてまだ6年、色々なカテゴリを楽しみ、「消費者」として生きています。 そんな文化の消費者の毎日思ったことアレコレを書いていきます。雑記。
