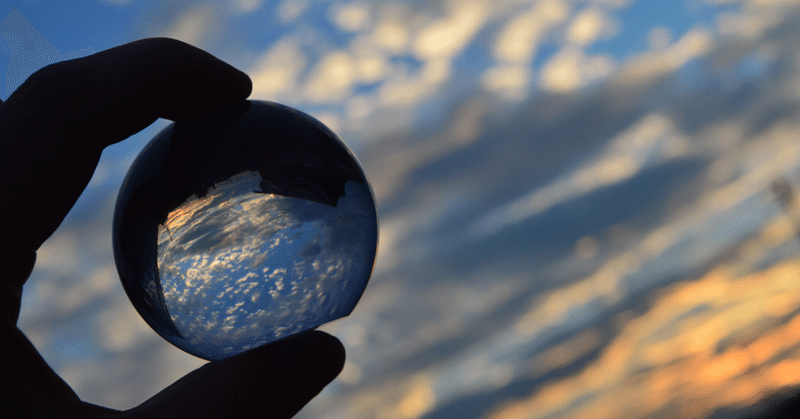
第7章 . 社会に溢れる不条理を知った19歳が思うこと(前編)
はじめに
悔しい。
なんで自分がこんなにも悔しいのかわからない。
社会はすごく不条理なことに溢れていると知った。
貧困、格差、すれ違い、戦争、生まれ育った環境、孤独、飢餓、依存、かなわない夢、報われない努力、権力、殺処分、死刑制度、勝ち負け、競争、マウント、必要以上の欲、憎しみ、怒り、やるせなさ、寂しさ、無力感、わからなさ、無知、恐れ、萎縮、命、支援、人道、宗教、学問、偏った思想、常識、普通、嫉妬、差別、性
あげたらキリがない。
なんの目的があるのかわからない。
だけど、今日も考えてしまう。
なんで社会はこんなに不条理なことに満ち溢れているんだって。
なんで解決できないんだろうって。
上に挙げたキーワードを全てカバーして考えを文章にすることは難しいから、もう少し抽象化して、四つの章に分けて、ぶつけるところがない思いを、noteに書こうと思う。
目次
>前編
はじめに
1. 社会問題
2. 支援
>後編
3. 無知の知(無知の恥)
4. 善意は正義にも悪にもなる
最後に
1.社会問題
例えばひとつの「社会問題」を解決しようとする時、どうやって解決すればいいのか考えようとする。
そのためにはまず、現状を把握し、誰がどんな問題を抱えているのか、社会全体的なマクロな視点でも事例に目を向けたミクロな視点でも捉える必要がある。
でも、その段階から壁にぶちあたる。社会は見えないところでいろんな因果関係をおこして繋がっている。その社会問題の実態を全て知ろうとすることは無謀なのだろうか。そもそも、ある社会問題は別の社会問題にも繋がっていたりするから、その枠組みだけで全貌を明らかにすることはできないだろう。
マジョリティの利益はマイノリティの不利益だってこともあるから、問題とされていることを安直に問題だとおもいこむのは危険だと思う。
知ることですら難しいのだから、解決することはもっと難しい。
ある問題を解決しようとすると、誰かにとっては利益・幸福・便利をもたらすことでも、他の誰かにとっては不利益・不幸・不便をもたらす。
物事は全て良い面も悪い面も表裏一体。
ジレンマとどう向き合っていくべきなのか。またまた考え込む。
解決したくてもそのための資源(知識や設備や土地や自然や材料etc.)や資金がなくてどうにもならないこともある。
その中で私が1番怖いと感じるのは、知識がないことだ。
課題にぶつかって、それを素通りせずに、解決したくて、表明したくて、どうにか行動を起こそうとする。
健全な感性と知性があるならば、道理も理屈も踏み外さないような健全な行動で解決に向かえるかもしれない。
でも、そうじゃなかったら、暴力でそれを訴えることしかできない人もこの世の中にはいる。テロだって戦争だって、まともに学べていれば、それが正しい手段だと思うはずがないと思ってしまう。でも、そういう機会や環境に恵まれなかった、という本人たちの意思ではどうしようもない偶然のせいで、知らない大人が知らない子供を育てる。負の連鎖はおわらない。
人の命を奪う戦士も、それが自分の意志だとは限らない。自分の身を置く環境の影響のせいか、圧力に抗うことができないからか、戦士としての使命を捨てたら生きる意味を失うからか。わからないけど、私はもはや誰も責めることができない。やり場のない思いを今日も背負っている。
平和ってなんだろう。
2.支援
2年くらい前まで、支援は歌が言うまでもなく正しい行動だと思っていた。
でも、支援って必ずしも正しい行動だとは限らない。
そのことを自覚せずに、支援をすることに危機感を覚えるほどに。
以前は、自分が困っている人のために起こす正しい行動のことを支援だと思っていたけど、無意識のうちに、支援って言葉に「支援する者」と「支援される者」という上下関係が含まれていたように思う。
だけど、正しい支援は対等な関係性にこそうまれるものだと考えるようになった。対等な関係性になるためには、「支援する者」としての主観を取り払うことが大切だと思う。向き合おうとしている人がどう考えるのか、どう変わりたいのか会話をして当事者目線で考えなければいけない。会話をしていく中で、そもそも当事者であるはずの人が問題意識を持っていない可能性だってある。仮にもしそれに気づいたのなら、支援自体不要ってことなのだろうか。
支援について考えると、ほかにも考えきれていない思考は山ほど出てくる。
・そもそも当事者ってどこまでをいうんだろう、支援者としてある問題に巻き込まれている人はもはや支援者ではなく当事者であるのだろうか。※
・問題を解決すること自体が生きがい・生きる意味となっている当事者がいるのなら、他者が足を踏み込んで勝手に解決することは、その人の生きがいを奪うことなのだろうか。※
・人は自分があたえられた環境で、たとえその環境が他の人から見て問題ありに感じる環境であっても、それなりに適応して生きている※
(※これは最近出会った人に言われるまで考えたことがなかった視点。)
・支援っていうより、サポートっていう方がなんかしっくりくる。
・自立を目指す支援ってなんだろう
・援助と支援の違いとは
・支援者はある意味では社会問題を原動力に生きているよな、、もし、この世から社会問題がなくなったら(そうなることは多分ないけれど)、人は生きがいを見つけにくくなるのかな。
・利他的だと盲信しているだけで実際は利己的なのだろうか、ただの自己満足なのだろうか。
ほんとにこういうこと考えるの難しい。正直ときどき途中で手放したくなる。
でも、だからこそ、逃げないで追求したいという野心が湧いてくるっていうか。
そうやって生きていると、今日もなんか頑張って生きてる心地がするっていうか。
言い換えれば、答えのない問いを考えることが自分の生きがいの一つとなっているから、手放したいと感じることはあっても、考え続けていたい。
後編に続く…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
