
感覚が良くなればスキルの上達は速くなる
こんにちは
サッカー・フットサルトレーナーの梅田です。
サッカーのスキルを高めるには、練習をたくさんすることが大切です。
しかし同じ量の練習しているのに、
うまくなるスピードが速い選手と遅い選手はがいます。
同じ練習量でも差が出る。
この差はどこから来るのでしょうか?
様々な要素が考えられますが、
その1つとして、感覚のレベルがあると考えます。
今回は、「感覚」についてまとめていきます。
1.そもそもスキルが上がるとはどうゆうことか?
スキルが上がるとは、大きく分けて2つ状態のことを指します。
1)今までできなかったことができるようになる
2)今までできていたことの精度が高まる(ミスが減る)
このように示すことができます。
例えばドリブルのスキルであれば、
練習を繰り返して、
今までできなかったドリブルのフェイントができるようになること。(1)
そして、さらに練習をし、そのフェイントの成功率が上がったり、相手がいても使えるようになったり、環境が変わっても使えるようになること。(2)
この2つの状態になれば、「ドリブルのスキルが向上した」と言えます。
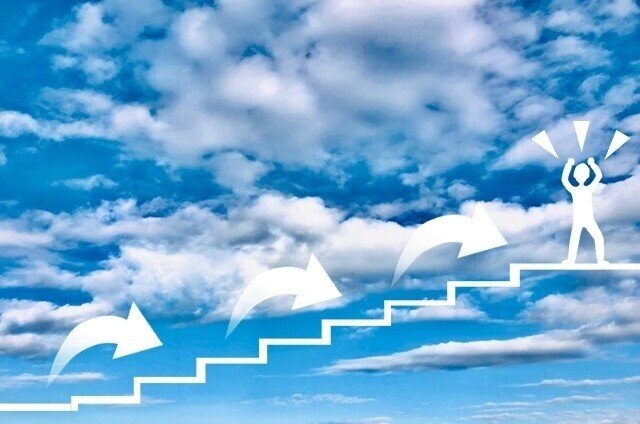
2.スキルが高まるとき、どんな過程をたどるか?
ではどのような過程でスキルは高まっていくでしょうか?
スキルが高まっていくときは、脳内で神経回路が作られていき、
運動パターンが強固になっていきます。
運動パターンが強固になると、そのスキルを実行しょうとしたとき、
無意識的にそれができるようになっていきます。
運動をするときは、脳内で「フィードバック」という機能が働き、これが運動パターンの習得の関係しています。
「フィードバック」とは、運動をおこなった後で
”これくらいの速さで運動がおきた” ”これくらいの力が出だ”
”こんな形の運動にだった” などと起きた結果を認識する機能です。

人は「フィードバック」を得ることで、自分の動きを修正していき、
運動パターンを強固にしていきます。
(専門的にいうと、フィードバックの他に、フィードフォワードという機能も、
運動パターンの形成に非常に大切ですが、こちらのブログでは割愛します。)
3.感覚を高めていくとどうなるか?
この脳内で起きるフィードバックは、
体の感覚(体性感覚といいます)や視覚が大いに関与しています。
つまり、自分の動きが「こんな形だった」「こんなスピードだった」「これくらいの力だった」というのは、自分の体の感覚を元にしてフィードバックされます。
体の感覚が正確であれば、
正確なフィードバックを得ることができますが、
体の感覚が、悪ければ、
フィードバックそのものの精度が下がってしまいます。

フィードバックが正しくなければ、スキルの上達(=運動パターンの形成)が
遅くなってしまいます。
つまり、体の感覚や視覚の精度が高まっている選手のほうが、
スキルの上達が速くなるということになります。
4.では体の感覚を高めるにはどうすればよいか?
どうすれば、体の感覚を高めていくことができるでしょうか?
抽象的な回答としては、幼少期、様々な遊びをたくさんすることです。
特に「自然の中での遊び」「いろんな体の姿勢での遊び」「道具を使った遊び」が有効です。
1つの例を上げると木登りです。
木登りをすると、右手左手の位置、右足左足の位置を正しく認識して、適切に力を加えなければ、上手く登ることはできません。
運動でいうと、四つん這いのポジションや高這いのポジションなどでトレーニングをすることが有効と言えます。

「体の様々な部位の様々感覚に目を向ける」ことや「体を繊細に使わないとできない種目の練習をする」ことが大切です
様々な感覚に目を向けるというのは、力加減や、動きのスピードの変化、リズムの変化などを伝えます。
私はしばしば擬音語を使います。
「トン」じゃなくって「ドン」だよ、や
「グッ」じゃなくって「スッ」だよ、などと。
こうすることで、自分の体の感覚に目を向けることができますし、
繊細に体を使うことを覚えていきます。
感覚が良くなっていけば、その後様々なスキルを上達させていく上で優位な状態を作ることができますでの、是非、小さいうちにやっておきたいことだと感じています。
余談ですが、スポーツ種目であれば
ダンスや体操などは体の感覚が高まります。
ジュニア年代は、1つの競技だけでなく、複数のスポーツをすることが進められていますが、それも上記のような理由も含まれまれています。
(これについてはまたブログを書きたいと思います。)
最後までお読みいただきありがとうございました。
面白い!良かった!と思いましたら、「スキ」や「フォロー」をしてくださると嬉しいです。
過去ブログはこちら↓
ジュニアサッカーの運動能力向上塾『トレ塾』はこちら↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
