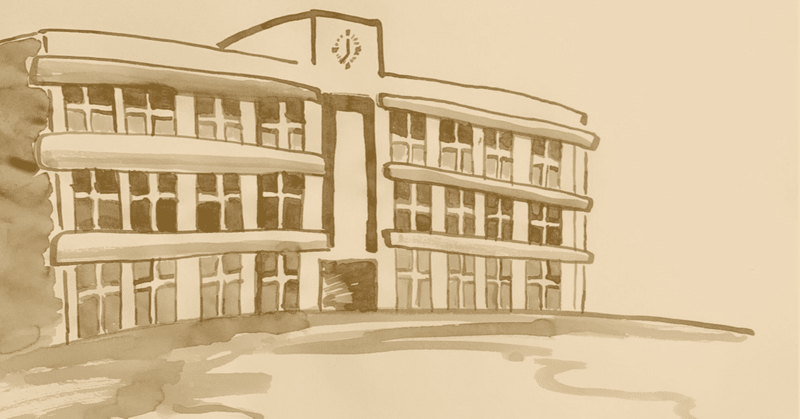
塾講師は大歓迎されて然るべき?
先日投稿したこちらの記事に対して、読者の方からコメントをいただきました。
それへの応答がコメント欄に残すには長すぎるので、改めて記事にします。
私からの応答
内容に入る前に、まずは私の拙い記事をお読みいただき、ご丁寧にコメントをくださったことに、深く感謝いたします。あまりコメントを頂くことは多くないので、こうしてコメントをいただけることが大変励みになります。本当にありがとうございます。下線以降がいただいた内容に対する私からの返答となります。
まず、「いま学校教育では、勉学を教える以外の、心理的思想的生活的な統制活動、また好ましくない人柄や家庭環境の者を摘発する活動に重きを置いている、と私は見ています。」および「今の学校が、勉強以外の、児童生徒への人格評価に狂奔し過ぎていた」について返答します。
確かにそのような「統制活動」「摘発」「人格評価」ばかりに偏って、本当に学校教育としての意味がそこにあるのかと問われざるを得ない教員もいるかもしれません。私自身も10年前は高校生で、そういう先生にストレスを感じていたことは事実です。しかし、それと同時に、そういった方向ではない学校教育の価値を生み出そうと努力している先生方も多くいらっしゃると思いますし、その可能性は誰にも否定しようがありません。(私もより良い学校教育を担える人を育てたいという思いがあって、学校教員を養成する仕事をしています。)
「…する活動に重きを置いている」主体を「学校教育」とするのは、さすがに主語が大きすぎて、一人ひとりの先生が実際に何に重きを置き、どのような思いのもと、どのような仕事をされているかは見えてきません。
その上で、(千葉県の施策そのもの以前に)この記事について私が第一に批判したいのは、この塾講師の方が授業をしたクラスの担任の先生という個人に対するリスペクトに欠けるという点です。これは学校教員をしていた一人の人間としての主観に過ぎませんが、そもそも授業に外部の人を招き入れることができる時点で、それなりに学級集団として適切に指導されていることの証であると考えます。そのような先生の日頃の仕事に対する尊厳を、当該報道が採用した子どものコメントは容易に踏み躙ることができてしまいます。それだけ教師にとって子どもの声は切実に響くものということであり、元のnoteにも書いたように伝え方・伝わり方次第では担任の先生への有意義なフィードバックにもなり得ました。しかし、少なくとも私の感覚では、あの記事・テレビ放送の構成では、担任の先生が尊厳を傷つけられたと感じる可能性が十分あるだろうと考えます。(我々に見えないところで、記者の方と担任の先生の間で何かしらの合意形成があったかもしれませんし、私がこうして話題にすること自体、その先生にとっては迷惑かもしれないという可能性は否定できません)
また、そもそも文部科学省や教育委員会から求められるあまりに多くの雑務によって(それも多くが「自主的にやっている」ということにされてしまうのですが)、教員が授業準備や授業力向上のための自己研鑽をする時間がかなり削られているという現状があります(という認識に同意いただけるか分かりませんが)。そうして授業の質を上げたくても上げることが現実的に難しい状況に行政の方から学校教員を追い込んでおいて、「授業力が低下しているようなので、授業に特化したスペシャリストを派遣します」と言って、授業という大切な仕事を譲り渡すことを強いているわけです。学校教員が授業改善以外のこと(コメントから拝借すれば「勉強以外の、児童生徒への人格評価」もその一つでしょう)に時間を勝手に使っているのだから、授業だけを専門的に極めている塾講師の方がありがたがられて当然だというのはあまりに学校教員にとって不条理であると、学校教員の仕事を取り巻く全体の構造を考えてみれば納得いただけるのではないかと信じています。
次に「児童生徒の人格形成を考慮せず勉強を教えるだけでいい塾講師、が学校に現れたら、大歓迎され学力向上につながるのは当然でしょう。」「たまたま現状においては塾講師が有効だった、ということでは?」についてです。まず、学校が外部人材を活用して何かしらの目的を(より良い水準で)達成することについては、その可能性を模索することに一定の価値があると、私個人としては思います。
しかしながら、塾講師が子どもから大歓迎され学力向上につながったとしても、必ずしもこの施策が「有効だった」とは言えません。公教育は子ども(=お客様)のニーズに教師(=従業員)が応えるという仕組みではありません。ですから、「塾講師の登場を子どもたちが歓迎するか否か」が、学校教育としての意義を評価する上で十分な判断材料にはなることは、まずあり得ません。(子どもの思いを無視して大人が正しいと思うことを押し付けることを推奨している訳では全くありません。念のため)
加えて、ここからは二つ目にコメントいただいた千葉テレビの実状にも関わります。私は確かに最初のnoteで千葉テレビの放送姿勢を批判しましたが、コメントいただいたように、県政の思惑に沿った報道をせざるを得ないという現実もあるのかもしれません。(それでもその現実を乗り越えてほしいという思いはありますが、私はそういうことの専門家とかではないのでそれ以上は立ち入りません。)むしろ、仮に千葉県への忖度によってあのような構成になっているのだとすれば、千葉県教育委員会に批判を投げかける必要があります。いちいち人格形成に関与されたくない子どもたちからしたら、単に分かりやすく算数を教えてくれる塾講師の存在はありがたいかもしれませんが、それはあくまでも子どもたちの個人的な感想です。一方で学校教育というのはその目的に人格形成を含みます。そして、人を(学校教育を受けなかったらそうならなかったかもしれない人格に)変えていくという営みには、当然ながら「どのような人格が望ましく、どのような人格が望ましくないのか」といった複雑な倫理的あるいは価値的判断が伴います。「どのような教育を目指すべきか」という価値観に基づくゴールが存在して初めて、そのゴールに対して効果的・効率的に機能する(そして別の目的の達成を著しく妨げたり、学校教育としての望ましいシステムや社会全体の望ましい秩序を破壊しない)施策を「有効だ」と判断することが可能なわけです。
子どもの声を素朴に受け入れ、「学校教育としてこれが望ましいのだ」という価値判断を千葉テレビが下し(忖度があるとすれば、千葉県教育委員会が下し)ているのは、学校教育が子どもの要望に応じるだけのサービス業ではないということを無視していると思いますし、また千葉県 が「効果を検証」すると言っていますが、ここには「そもそも学校教育とはどうあるべきか・何を目指すべきか・どのような方法で目指すべきか」といった価値判断が伴っていません。そのことへの批判が、元のnote記事において「『学校の先生』と『塾講師』を対置し、授業者としての専門性を塾講師の方に認めるかのような安易な構成」と書いた部分の意図です。
やや感情的な主張に聞こえるかもしれませんが、やはりこの施策および報道は、学校教育を担う学校教員の尊厳を踏み躙ったという点と、学校教育に塾講師を介入させなければいけない状況に陥らせた構造を無視しているという点において、特に厳しく批判されるべきであると私は考えます。
上に書いた通り、私は外部人材の活用自体を否定しません。学校教育の目指すべき姿を吟味し、現状の課題とそれを生み出している構造を理解し、解決への糸口を探る過程で学校教員・教育委員会・塾講師といった関係するアクター間で十分な合意形成がされた上で、塾講師の授業力を頼りにするというのであれば、そしてその合意形成の過程がしっかりオープンにされれば、私や他の専門家の方々も、そこまで強く批判することはなかったかもしれません。(もちろん、その合意形成の過程に問題が含まれている可能性もありますが)
いただいたコメントへの私からの応答は以上になります。
元のnote記事は、「流石にこのニュースは早めに触れておこう」と思って書き急いだ感もありましたので、コメントいただいて読者の方との問題意識のすり合わせや、私の前提となる認識の共有が甘かった部分があると思います。
考える機会をいただき、また改めてより具体的に主張する機会をいただき、感謝いたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
