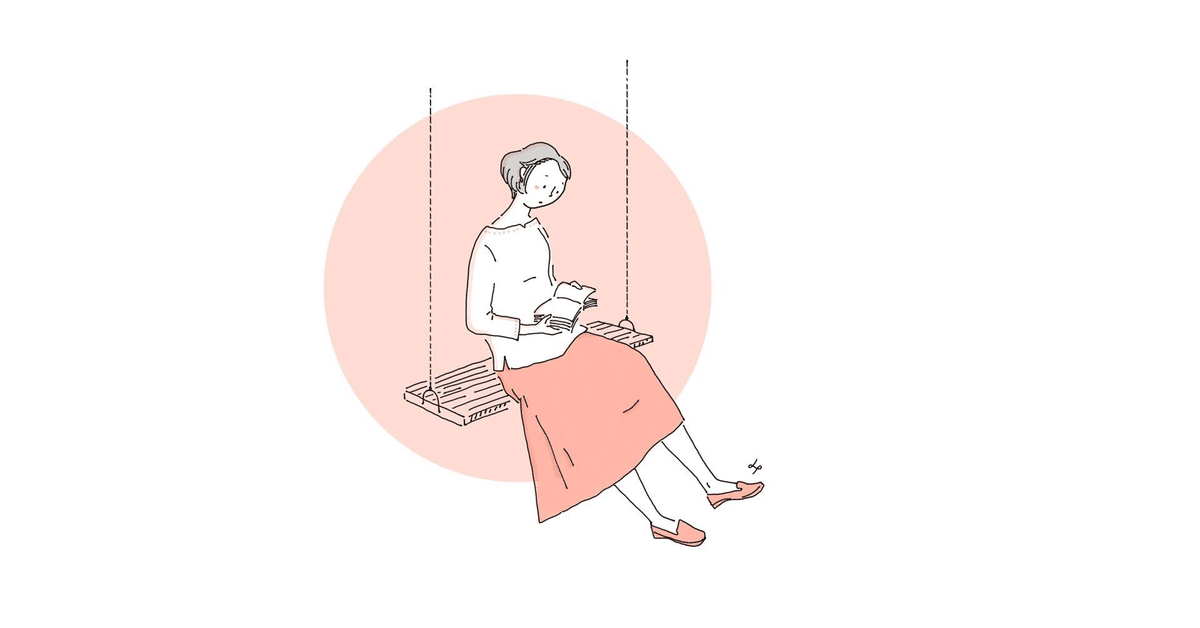
芸術である言葉 『光であることば』若松英輔
若松英輔氏の本を読むと大切なことをいつも思い出させてくれる。そんなことを感じる。なぜ忘れてしまうのか、それには色々と原因があるのだろうけれども、僕たちは何かを思い出すために生きているのではないか、と思う時がある。
わかるということは何か新しいことを発見するというよりも、まさに思い出すに近い気がするのだ。それは最初からそれを知っていなければ、僕たちがそれをわかることができないのではないのか、という理性と直感。論理的にだけではなく、知っているということを僕たちは直観しているのではないだろうか。だから、昔の人の言葉もわかれば、最初はわからなくてもいつしかわかるということが起きたりする。そして、わからないものはわからないとわかる。これこそが一番の不思議だ。なぜわからないとわかるのか。当たり前と思うかもしれないけど、わからないということがわかるということは、ある意味では何がわからないかをわかっていることだから。もっと言えば、何がの何がわかっているから、わからないと言えるのである、というパラドックスに行き着く。さて、なぜわからないとわかってしまうのだろうか。
若松氏の言葉にふれると、言葉の奥にある何かにふれることができ、そして何かを思い出すことができる。目では見えているのに、心眼では見えていないもの。耳では聞こえているのに、心耳では聞こえていないこと。そういうものがあることに気がつき、心の眼で、心の耳で、感じるように、その言葉にふれることで何かを思い出すことができる。魂の記憶。イデア。人はそれを色々な呼び方で呼ぶけれども、たしかにある何か。音楽家は音楽を通してそれにふれる。画家は絵を通してそれにふれる。そして、作家は言葉によってそれにふれるのである。人は直観的にそうしようとする。そうせざるを得ないと言った方が正しいのかもしれない。それが人間の本来の欲求。いや、魂の欲求と言った方がよいのかもしれない。自分の生活を顧みずに、それに没頭してしまう人をどう説明したらいいのか、それはもう人間という枠を超えているような気がするからである。
『光であることば』の中で、若松氏は「文学は言葉の芸術である」と語る。
文学は言葉の芸術である。色と線が絵を生むように、音と沈黙が音楽を生むように、言葉と余白が文学を生む。文学とは言葉のちからによって、この世に美を顕現させようとする試みにほかならない。
(『光であることば』若松英輔)
なぜか僕は、僕たちは、文学が言葉の芸術であることを忘れてしまう。なぜだろうか。言葉というものが色や音以上に当たり前なものとしてあると思っているからなのかもしれない。絵や音楽はすぐに芸術と結びつく、でも、言葉が芸術であると言われても、ピンとこない人もいるのではないだろうか。でも、たしかに文学というのもがあり、それはまさに言葉の芸術である。なぜそれを忘れてしまったのか。不思議である。こうやって毎日のように言葉を綴っているのに、それを忘れてしまうことがある。それくらい、言葉というものが当たり前のものになっているのだろうか。
でも、若松氏のことばにふれると、それが芸術だったことを思い出させてくれる。ことばの本来の姿を感じることができ、思い出すことができるのである。
「ことば」を身に宿す。それは「光」とともに在ることに等しい。
僕たちは「光」とともにあることによって、新しい何かを生み出すことができる。ことばの深淵にふれるとき、そこには、暗い闇を感じる。自分にはすくい上げることができないものを感じる。でも、たしかに光はあって、それをすくい上げることができるのである。それは女性が子どもを宿し、こんなにも大きなものが生まれてくるのか、と感じるように、その時はその大きさに驚くけれども、でも、ちゃんと時が経てば生まれてくる。僕たちもみんなそんな「ことば」を宿しているのではないだろうか。そして、いつしか生まれてくるのである。それを人は芸術と呼ぶのである。
この記事が参加している募集
A world where everyone can live with peace of mind🌟

