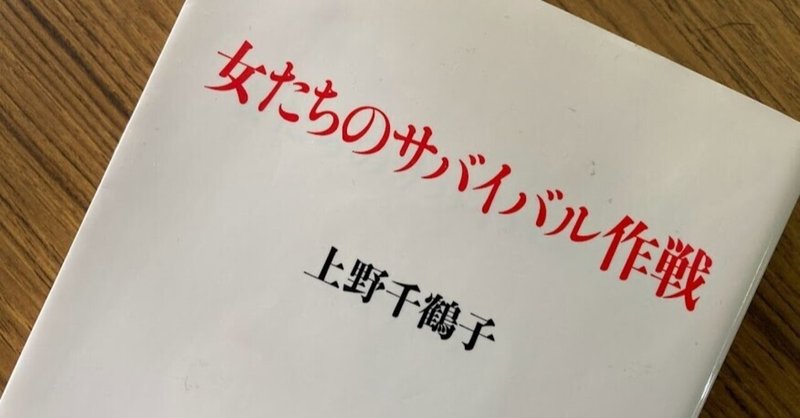
日本で女性差別がなくならない理由――上野千鶴子『女たちのサバイバル作戦』 (文春新書、2013年)評
多くの日本人にとって、現代の日本は、1985年成立の男女雇用機会均等法、1999年成立の男女共同参画社会基本法を経て、職場や社会の男女平等が成り立っている国だというのが一般的なイメージであろう。これらは小学校から高校までの社会科系の教科書で繰り返し姿を現し、暗記させられるものであり、それが上記イメージ浸透の理由であろう。だが、それが単なる建前で、実態はまるで異なる男女不平等、女性差別がなお横行する社会であるというのが、学齢期を終えた人びとの偽らざる実感であろう。
本書は、ジェンダー研究やフェミニズム運動の旗手として知られる団塊世代の社会学者が、その研究ならびに実践の集大成として、続く世代に向け、これまでの研究/実践の達成と積み残された課題とをまとめた総括の書である。そこでは、男女雇用機会均等法や男女共同参画社会基本法が、その背景に政府のネオリベラリズム(新自由主義)改革――市場原理を貫徹するため、規制緩和を進めていく――があり、結果として男女格差の拡大のみならず、女性たちの間にさえも分断と格差をもたらした事実とそれがひきおこされたメカニズムが丁寧に記述される。
ネオリベに順応して男並み=「社畜」となってバリバリ働くか、あるいはそうしたトラックから降りて非正規の補助労働力に甘んじつつ育児・家事・介護のシャドウワークにいそしむか。ジェンダー規範――生産労働を男に、再生産労働を女に割り振る規範――に変更がないままなされた上記の制度化が生み出したのは、大きくはこうした女性たちの生きかたの二類型であった。だが著者は、フェミニズムが求めたのはそのどちらでもなかった、と悔恨を込めてつぶやく。彼女がその失敗の教訓から後の世代に伝えるのは、ダイバーシティ(多様性)のすすめだ。
ダイバーシティとは、生きかたや働きかた、ライフスタイルをそれぞれが自由に選べ、しかもその選択の如何によって各自の間に不平等が生じないことだ。それを現実化していくためには、政府の政策レヴェルでは「同一労働・同一賃金」ならびに「配偶者控除廃止」、企業の慣行レヴェルでは「日本型雇用慣行の廃止」、個人の実践レヴェルでは「収入源のマルチプル化によるリスク分散」――それはかつての百姓のありように重なる――ならびに「共助け」ネットワークの構築が必要、と著者は結論づける。
著者のイメージや本書のタイトルからは、この本を「女性向け」――とりわけ「フェミニスト向け」――のそれと受け止め、手にしないでおこうと考える人も多いかもしれない。だが、日本の会社や労働の世界というものがその根底に性差別を埋め込み、そうすることで成り立ってきた構図が存在する以上、ジェンダーを起点にそれをまなざすことは、その本質を理解するのに不可欠である。耐用年数をとうに超えた「男たちの社会」を理解し、変革していくためにこそ、本書は読まれる必要がある。(了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
