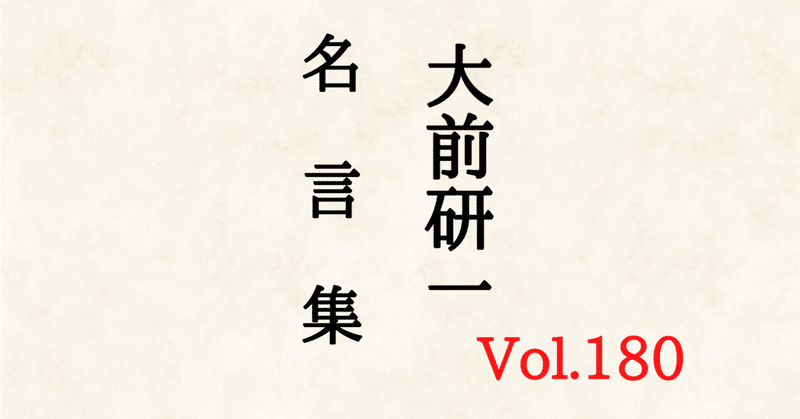
大前研一 名言集 『サラリーマン再起動マニュアル』(32)
『サラリーマン再起動マニュアル』(32)
今回から『サラリーマン再起動マニュアル』から名言を取り上げます。
大前研一氏は、私にとってメンター(師匠)であり、グールー(思想的指導者)の存在でもあります。
大前氏の著作を読んでいつも感じるのは、物事の本質を捉える、ずば抜けた能力です。
凡人である私は大前氏の足元にも及びませんが、不断の努力を怠らず、一歩でも彼に近づきたい、と思っています。
『サラリーマン再起動マニュアル』
目次
[イントロダクション]志のあるサラリーマンは、きつい仕事を厭わない
第1章[現状認識]なぜ今「再起動」が必要か?
第2章[基礎編]「再起動」のための準備運動
第3章[実践編]「中年総合力」を身につける
第4章[事業分析編]“新大陸エクセレントカンパニー”の条件
第5章[メディア編]「ウェブ2.0」時代のシー・チェンジ
[エピローグ]新大陸の“メシの種”はここにある
✅ 小学館 出版年月日 2008/9/29
「中年総合力」が要求されてくる年齢層を30代後半~40代とすると、その年代のビジネスマンに私が勧めたいのは、自分の年齢プラスマイナス15歳の人を研究することだ
「中年総合力」が要求されてくる年齢層を30代後半~40代とすると、その年代のビジネスマンに私が勧めたいのは、自分の年齢プラスマイナス15歳の人を研究することだ。
35歳であれば上が50歳で下は20歳、45歳であれば上が60歳で下は30歳の人である。
このうち15歳上の人は“反面教師”として研究する。
つまり、会社の中を見渡せば「ああなりたくないな」と思う15歳上の人、我が身に置き換えて「15年後になりたくないモデル」が必ずいるはずだ。
そこで、その人がこれまでどのように仕事をしてきたのか、ということを研究して、同じ轍(てつ)を踏まないようにするわけだ。
ただし、より大切なのは15歳下の人たちである。
彼らが自分とは違うどんな能力や価値観を持っているのか、ということをよく研究しな ければならない。
とくに新入社員の研究は、どの年代の人にとっても重要だ。
➳ 編集後記
『サラリーマン再起動マニュアル』 はタイトルから推測すると、マニュアル本のように感じられたかも知れませんが、いわゆるマニュアル本ではありません。
私たちが身につけるべき、本質的な事柄やスキルを具体例に即して大前氏が述べている普遍性のある本です。
🔶 大前氏は自分で考え出したことを自ら実践し、検証しています。仮説と検証を繰り返す行動の人です。
Think before you leap.(翔ぶ前に考えよ)という諺がありますが、Leap before you think.(考える前に翔べ)もあります。
あれこれ考えて、難しそうだからとか面倒くさそうだからやめようでは成長しません。
まず、やってみるという姿勢が大切です。
大前研一氏は、常に物事の本質を述べています。洞察力が素晴らしいと思います。
私は、ハウツーものは、その内容がすぐに陳腐化するので読みません。
➔ 大前氏の言葉は、いつでも私たちが忘れがちな重要なことに気づかせてくれます。
🔷 私は現在59歳(この記事を最初に投稿したのは2014年)で、6月には60歳(還暦、2022年現在67歳)を迎えます。
大前氏の考え方を当てはめれば、15歳下の人たちは44歳(2022年時点では52歳)くらいの人たちが該当します。
その人たちの言動に注目しなくてはならないことになりますが、私はもっと若い人たち、つまり20~30代の人たちの言動に注目しています。
この年代の人たちは保守的な傾向を持っている、といわれていますが、私から見ますと、考え方の違いや価値観等で注目に値します。
今後も、定点観測をして彼らの動向を観察し、研究していこうと思っています。
もしかすると、あなたにお会いすることがあるかもしれません。
その際には、よろしくお願いします。
🔷 大前研一 高齢者のマインドを変えれば、日本経済は飛躍的に伸びる
恒例によりまして、大前研一氏のウェブサイトから今回の投稿記事に関係がありそうな内容を抜粋します。
大臣の顔ぶれをみると、安倍首相の悲願である憲法9条を変えるのに都合のいい「お友だち」だけを集めた感は否めない。この内閣でデフレ脱却? それならアベノミクス失敗の反省から始めるべきなのに、誰もそれを言い出せないようでは、まず無理だ。まあ、首相を筆頭に、閣僚内に現在の日本経済のことをわかっている人間が一人もいないのだから仕方がない。
上記の発言はいつのことだと思いますか。2016年8月3日、第三次安倍再改造内閣が発足した後の2017年3月24日のことです。
その当時から安倍晋三元首相には誰も意見する人がいなかったことが分かりますね。独裁者だったということです。
安倍首相は、先の参院選で「この道を。力強く、前へ。」と威勢のいいスローガンを掲げて大勝したものだからすっかり気をよくし、さらに新しい三つの矢を出してきて、このままアベノミクスを推し進め、一億総活躍社会を実現すると息巻いている。いくら前に進めたところで、政策そのものが間違っているのだから、結果など出るはずがない。そういう指摘をきちんとしないマスコミにも責任がある。
大前氏は時の権力者に対しても歯に衣着せず、正論を述べていました。
安倍首相は参院選の前に、ノーベル経済学賞受賞者のポール・クルーグマン教授をわざわざアメリカから呼び寄せて、自分の経済政策の正しさを裏書きさせようとしていたが、私にいわせればまったく無意味だ。いくらノーベル賞経済学者だといっても、欲望社会の研究をしてきたクルーグマンに、低欲望社会の日本がわかるはずがないのである。実際、彼は自分が異次元の金融緩和を提言していながら、「想定している以上に量的緩和の効果が出ない原因は、本質的かつ永続的な日本の需要の弱さに根差している」と、米紙『ニューヨーク・タイムズ』(2015年10月20日付)に敗北宣言ともいえるコラム(「Rethinking Japan」)を寄稿している。
ヘリコプター・マネーが、余っているお金ならまだいい。しかし、日本でこの手のばらまきをやるとなると、原資はすべて次世代からの借金にならざるをえない。では、15年後、20年後の人がこの借金を、喜んで払ってくれるのか。税金の担い手は勤労世代。だが、日本のデモグラフ(人口動態)をみれば、今後勤労世代の人数は確実に減っていく。払おうにも払いようがない状況が訪れるのは明らかだ。だから、将来に負債を先送りするような政策は、政治家としてもつべき倫理からいっても、絶対にやってはいけない。そういう意味でもヘリコプター・マネーは、まともな経済政策とはいえない。
安倍首相は連合の集会に行って、労働者の賃金を上げろとやっていたけど、いかにも的外れである。いまの日本では企業が無理して賃金を上げたところで、労働者はその分を消費ではなく貯蓄に回すだけだから、一向に景気回復にはつながらない。そういう認識が安倍首相の頭の中にはないのだ。経済学者はなぜ給料を上げてもGDPが上がらないのか、せめて謙虚に分析すべきだ。同一労働同一賃金、というまともに定義もされていない意味不明の言葉が独り歩きして政策の中心になっているが、中国で日本と同じ労働をしている人が物価を通じて(同一賃金になるまで)日本人の賃金上昇を阻害しているのだ。
いまの高齢者は、年金、貯金、生命保険という三重の投資で老後に備えている。それで年金が支給されるようになっても、その3割を貯金に回して死ぬまでお金を増やし続けるのだ。なんでそんなことをするのか尋ねると、彼らは口をそろえてこういう。「いざというときのためです」。だが、働き盛りのサラリーマンならいざ知らず、いざというときというのは、いったいいつなのか。想定外の長生きや大病だというが、長生きして貯金が尽きたところで年金はもらえる。それに、歳を取って大病をしたら、そのときは寿命だと思って腹を括り、それまでは人生を楽しむことに専念しよう、とすれば景気は爆発的に良くなる。
大前研一氏が素晴らしいと思うことは、批判するだけでなく、必ず代案を提示することです。しかも根拠を示した上で具体的に説明することです。
安倍首相が「いざというときは国が責任もって面倒見るので、安心してお金を使ってください」というメッセージを発信する。
次に、こういう人生の楽しみ方があるというのを、政府が国民に紹介し、国民運動にまで高めていく。
振り返ってみますと、安倍元首相が自分の懐を肥やすことばかり考え、実行していたので、大前氏のような考え方はできなかったのでしょう。
森友問題や加計問題、桜を見る会の疑惑さらに東京五輪において汚職疑惑で暗躍していた可能性が高いことを考慮すると、安倍氏の横暴を周囲の人間は誰も止めることができなかったと言えます。
止めたのは、母親が旧統一教会の信者で、莫大な寄附を強要され自己破産し、それが原因で家庭を崩壊させられた息子による銃撃でした。
この事件が発端となり、旧統一教会と自民党の深いつながりが公になり、東京五輪の汚職疑惑の中心人物であった元電通の専務で東京五輪組織委員会の元理事の逮捕に至りました。
この事件の背景には、首相歴任者数名が関わっていたという疑惑が浮上しました。その中に安倍元首相が含まれていたと見られています。
話の内容が少し逸脱してしまったことをお詫びします。
⭐ 出典元: 大前研一 高齢者のマインドを変えれば、日本経済は飛躍的に伸びる PHPオンライン衆知 WEB Voice 2017年03月24日 公開
⭐ 関連書籍
🔶 大前研一氏と私とは年齢が一回り違います。大前氏は1943年2月21日生まれで、私は1955年6月30日生まれです。
大前氏は、私にとってはメンター(師匠)です。もちろん私が勝手にそう思っているだけです。
🔶 大前氏は評論家ではありません。言うだけで自分では何もしない人ではありません。大前氏は行動する人です。だから大前氏の提言は説得力があるのです。
大前研一オフィシャルウェブ
このウェブサイトを見ると、大前氏の出版物一覧を見ることができます。
私は、大前氏の全出版物の半分も読んでいませんが、今後も読んでいくつもりです。
⭐ 出典元: 大前研一 オフィシャルウェブ
大前氏は1995年の都知事選に敗戦後、『大前研一 敗戦記』を上梓しました。
🖊 大前氏の著作を読むと、いつも知的刺激を受けます。
数十年前に出版された本であっても、大前氏の先見の明や慧眼に驚かされます。
『企業参謀』(1985/10/8 講談社)という本に出会ったとき、日本にもこんなに凄い人がいるのか、と驚嘆、感嘆したものです。
それ以降、大前氏の著作を数多く読みました。
『企業参謀』が好評であったため、『続・企業参謀』( 1986/2/7 講談社)が出版され、その後合本版『企業参謀―戦略的思考とはなにか』(1999/11/9 プレジデント社)も出版されました。
🔶 大前氏は経営コンサルタントとしても超一流でしたが、アドバイスするだけの人ではありませんでした。自ら実践する人です。有言実行の人です。起業し、東京証券取引所に上場しています。現在は代表取締役会長です。
大前氏の本には、ものの見方、考え方を理解する上で重要な部分が多くあります。大前氏の真意を深く考えなくてはなりませんね。
この元記事は7年前にAmebaブログで書きました(2015-02-08 19:36:17)。
「新・大前研一名言集(改)」はかなりの量になりました。
私にとっては、いわばレガシィです。
その記事を再編集しました。
✑ 大前研一氏の略歴
大前 研一(おおまえ けんいち、1943年2月21日 - )は、日本の経営コンサルタント、起業家。マサチューセッツ工科大学博士。マッキンゼー日本支社長を経て、カリフォルニア大学ロサンゼルス校公共政策大学院教授やスタンフォード大学経営大学院客員教授を歴任。
現在、ビジネス・ブレークスルー大学学長、韓国梨花女子大学国際大学院名誉教授、高麗大学名誉客員教授、(株)大前・アンド・アソシエーツ創業者兼取締役、株式会社ビジネス・ブレークスルー代表取締役社長等を務める。 (Wikipedia から)
大前研一氏の略歴補足
大前氏は日立製作所に勤務時、高速増殖炉もんじゅの設計を担当していましたが、原発の危険性を強く感じていたそうです。
その後、世界一の経営コンサルティングファームのマッキンゼーに転職。
マッキンゼー本社の常務、マッキンゼー・ジャパン代表を歴任。
都知事選に出馬しましたが、まったく選挙活動をしなかった青島幸男氏に敗れたことを機に、政治の世界で活躍することをキッパリ諦め、社会人のための教育機関を立ち上げました。BBT(ビジネス・ブレークスルー)を東京証券取引所に上場させました。
大前氏の書籍は、日本語と英語で出版されていて、米国の大学でテキストとして使われている書籍もあるそうです。
⭐ 今までにご紹介してきた書籍です。
⭐ 私のマガジン (2022.08.18現在)
サポートしていただけると嬉しいです。 サポートしていただいたお金は、投稿のための資料購入代金に充てさせていただきます。
