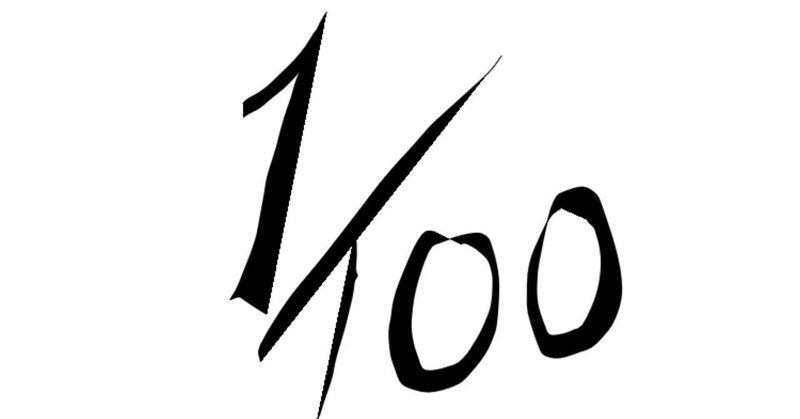
小説「100分のイチ」
0.1%の真実
100分のイチの確率で発症する病がある。100人にひとりが発症する可能性がある「統合失調症」である。幻覚や幻聴。脳のシナプスの繋がりとドーパミンの多量分泌による社会認識の欠如が起こる。
薬物療法による治療で症状を抑えることができる。この症状は程度の差はあるにせよ、誰にも起こりうる。100人にひとり。この1%の真実は知られていない。絶望と希望を持ち続ける人々に伝えたい。
「キミたちは狂っていない。キミたちを薬で抑えるより、この社会を、キミたちも生きられるようにほんの少しだけ変えよう」
これが私からのメッセージである。もし親や兄弟姉妹、夫婦や子、あるいは大切な誰かにこの症状が発症したら、この話を思い出して欲しい。
1.遅刻した朝
1997年。カラオケが流行り、女子高生が時代を創っていた。その時代の隅っこで、シワのついた紺色のブレザーに曲がっているえんじ色のネクタイをつけて、山田優一はイケテナイ高校生活を送っていた。
小田急線の大和駅を降りて、改札を抜ける。駅の時計は8時50分をさしている。
「優一」
後ろから声をかけられる。三上大輔がいけている姿で立っている。
「なんか用あるか」
優一が尋ねる。大輔が白い歯を見せる。
「カラオケ行こうぜ」
「いや。学校にいく」
「なんで」
「単位たりねぇし。眠いし」
歩き出す優一。
「マック、奢ってやるよ」
大輔が追いかけてくる。
優一が仕方なさそうに答える。
「なら、昼休みから、抜けようぜ」
大輔が優一の肩に手を乗せる。
優一には、学校はつまらなかった。部活もやらず、友達もできなかった。自然に放課後たむろしたり、遅刻してくる大輔たちと仲良くなっていた。
どうして、大輔たちのイケてる子が自分とつるむのか、優一も最初は不思議だった。
大輔の彼女の川上陽菜が理由を教えてくれた。
「ブスと一緒にいると可愛く見えるでしょ」
優一はダサいから、大輔がかっこよく見えてくる。大輔が隣で聞いていて、割り込んできた。
「ちがうよ。こいつには気を使わなくていいから、楽なんだよ。楽しいし」
「それ、ぜんぜん褒めてない」
陽菜が言った。
なめられているだけかもしれないが、少なくともブス理論ではない、と大輔は釈明をしたかったようだ。
大輔と陽菜と、優一はよく放課後にカラオケやマックで遊ぶようになった。たまに大輔と陽菜が盛り上がり、先にいなくなると、優一はひとりで残された。数は少ないが、友達ができて、彼女はいなかったが、友達の彼女を見ながら女の子を知っていった。
そして、忘れられない高校生活二度目の夏が訪れる。
2.優一と優紀
優一には優紀という中学生の弟がいる。彼らの父は優と言い優しいという字を書く。弟が生まれた時、父は「優二」にしたかったのだが、母は「勇紀」にしたかったのだそうた。母の名は紀子である。父と母の協議の結果「弟」の名は「優紀」になった。女の子みたいな名前で、身長も中学一年までは低くて髪をボブにしていたので、よく女の子と間違われた。
優一と優紀は小学生の頃はよく近所で一緒に遊んだ。裏山に行ったり、沢にカニをとったり、近所の寺の霊園を夜中に忍び込んで、肝試しをしたりした。
さすがに優一が高校生になってからはつるむこともなくなっていた。優紀は女の子とよく遊んでいたから、オシャレであった。イケテナイ高校生の兄の優一を優紀は少し恥ずかしく思っていた。高校二年になる頃には優一は優紀と会話をしなくなっていた。
3.優と紀子
優一の父、優は市役所に勤めていた。母、紀子は介護福祉士であった。いわゆる競争社会とは縁のない家庭に育っていた。
朝8時から夕方5時までの仕事で、日々同じ場所に行き、仕事をする職域である。共働きなので、優一も優紀もカギっ子である。優一は塾には通ってないから、ふらふら外に遊びにいく。優紀は陸上部に所属し、県大会に出場するほどの実力だった。
優紀が中学二年になると、急に身長が伸びて、優一を追い越した。
家族の食卓は、たいてい夜の6時45分から始まる。ダイニングテーブルに家族四人が座る。
鳥のから揚げに、サラダ。味噌汁と御飯。スーパーの総菜の和え物。いつもの食卓だった。「いただきます」と手を合わせ、食事をする。男三人が話すこともなく黙って食べていると、紀子が口を開いた。
「優紀、来週の日曜日の県大会、応援いくわよ」
「いいよ、誰も親は来ないよ」
優紀がそっけなく返すと、紀子は勝ち誇ったように言う。
「嘘言わないの。実里ちゃんのお母さんと連絡とったわよ」
「あっそ」
優紀はため息まじりに肩を落とした。
「優一は受験勉強は大丈夫か」
優が優一に話をふる。
―いい加減にやめようよ。
優一はそう思いながら、不器用に笑う。
「ごちそうさま」
優一が箸をおき、立ち上がる。優紀が優一の皿を見て呟く。
「兄貴、から揚げも残してる」
「やるよ」
優一は二階へかけていく。部屋の扉が閉まる音がした。
紀子の目元に戸惑いが見える。優紀が優一のから揚げをとり、食べる。
「大学受験、兄貴の高校だと、厳しいんじゃない?」
優が優一の皿を片付ける。
「中央、明治、立教あたりを狙っているんだよ」
「MARCHね。実力は、日東駒専あたりじゃないか…?」
優紀が呟く。SSランクの東大・京大の次に、Sランクの早慶、AランクのMARCHと呼ばれる明治・青山・立教・中央・法政があり、その次がBランクの日東駒専。その次はCランク、Dランク、Eランク、Fランクくらいまで偏差値で分けられる。卒業する大学で就職先が決まるため、競争社会にいる親は子供に必死に受験をさせ、いい大学へ送る。
優一の家は違った。役場勤務と介護士の両親から競争原理は働かず、人並みに幸せになってくれたら、そう願っており、大学は卒業して人並みの生活を送ってくれたら、御の字と思っていた。
すべてが壊れる、あの日までは、家族4人とも普通の人生があると思っていた。
4.破綻する夏
夏の陽射しに、蝉が鳴く音。優一は学校帰りの地元の駅からの帰り道を歩いていた。ぺしゃんこの鞄に半袖のワイシャツ。グレーのスラックスを着ている。汗でシャツはベトベトになっている。
このままどこかへ行きくなる。
海でも、山でもいい。
空を見上げる。夏の太陽がまぶしい。
「バード!」
優一と同じ制服の南高校の男子生徒がふたり自転車になり、坂を下ってくる。「バード」とは優一につけられたあだ名だ。バードウォッチングのようにウォッチングされているからバードと名付けられた。
優一は、ひとりを殴る。自転車が横転し、男子生徒は頭から落ちる。血がでている。もうひとりのスポーツ刈りの少年が少しおびえている。
優一が小さくつぶやいた。
「救急車呼ぶか?」
血がでている少年は、頭を抱えながら、
「なんもしてねーだろ、いきなり殴るな」
と言い、優一を蹴りあげる。ふたりがかかりでぼこぼこにされる優一。
少年ふたりはうずくまる優一を見て、にやにやと満足そうに自転車にのり、去っていく。
優一は、ふたりが去るとすくっと立上り、歩き始めた。
この頃、優一の心と体はボロボロだった。学校には大輔以外に友達はおらず、ほとんど誰とも話をしない生活だった。ネクラな人種だとクラスメイトには思われていた。ただ顔はまともなほうだったので、ニヒルなイメージであったかもしれない。不良仲間には入らずに、シラケながら大学をめざしている、そういう生活であった。『いじめ』にあっていたが、優一自身は気にしていなかった。それよりも自分の人生がどのように展開されるのか、見当がつかなかった。
ある日、優一は満員電車にのっていた。体が密着する車内である。一瞬、何かの危険を感じたが身動きはとれない。次の瞬間、腕を掴まれ、
「この人、痴漢です!」
女性が声をあげていた。
警察で優一は、触ったかもしれない、と真実を伝えた。昔の警察の調書は筋書きがある。痴漢の容疑者は、たいてい「ムラムラしたので、つい触ってしまった」ということになる。よほど意志が強いか、免疫がある人でないと、調書から解放されたいために、この筋書きの通りになる。現在はこのような単純な筋書きではなく、えん罪を防ぐためにも、裁判をする流れができている。卑劣な痴漢犯罪は許されないし、不用意に満員電車にのってしまった落ち度はある。最近はそこまでの満員電車は少なくなっている。盗癖と同じように、この行為は病気に繋がってくる。その環境に行かないことがひとつの対策になる。不可抗力でも触れないように対策しておくことが双方の自衛につながる。
紀子が身元引受人として優一を迎えにきて、ようやく釈放された。
警察署からでると優一に何かの声が聞こえた。
「なんか言った?」
優一が紀子に尋ねる。
「ん? どうかした?」
紀子が尋ね返した。
「なんでもない」
優一は答えた。
『おまえは悪くない』
男か女かわからない声が優一の頭の中で響いた。優一は悪いか悪くないより、不快にさせたことは悪いと思っていた。故意ではないと理解してほしかったが、それは誰も認めてはくれず、大人の解釈では、「少年の夏の気の迷い。二度しないで』ということで解決された。
頭の中の声は優一にどんどん語り掛けてくるようになっていった。
『おまえははめられた。誰にだと思う?』
「うるさい」
優一は部屋にいるときは聞こえてくる声と会話をするようになった。
優紀は一階の部屋を使っていたので、優一の独り言が聞こえてくる度、首をかしげていた。
窓の外から入る陽射しは、次第に弱くなり、蝉の声もいつしか聞こえなくなっていた。
5.夏の声
「声が聞こえるか」
優一が部屋に入ってきた優紀に尋ねた。
「誰の声だ?」
優紀が怪訝な顔して、扉を閉めた。
あれが世に聞く『妄想』ではないか。
優一がひとりで部屋の中でつぶやく声が優紀に聞こえてくる。
夏休みはあっという間に終わった。そのほとんどを優一は部屋の中で過ごした。外から聞こえる風の音と鳥の鳴き声、子ども歓声、奥様方の噂話も風に乗り、時々、二階の優一の部屋まで届いた。
『お前は何になりたい?』
太い男の声が聞こえる。幻聴だ。優一は頭の中を整理する。事件の前から何度か、幻聴のようなものはあった。相手への気遣いはできたから、相手の気持ちや非言語コミュニケーションをとれたので、そういうものではないことは理解していた。
「お前は誰だ?」
心の中でつぶやいていると、誰が何を言っているか、わからなくなる。そのため、口に出して小さく呟いた。
『私はマーズ。神の使いだ』
「バカげている」
優一はマーズの声に反応した。
「なぜ日本語を話す。なぜ神ではない」
呟きながら、優一はおかしくなり、笑ってしまった。
『私はお前だ。だから日本語を話す。そして、神ではない』
おかしなことになってきた、と優一は考えた。こいつの正体がわからない以上、自分は何もできない。大学受験が唯一のやることではあったが、今はそれもどうでもよくなっていった。この得体の知れないマーズなるものの正体を知りたい。それが強く芽生えた。
『お前の肉体に入る』
「は? なんだって?」
『私がお前の肉体に入る』
マーズの声が優一の身体中に響く。底知れぬ恐怖を感じた。体を乗っ取られているような感覚だった。幸いにも頭はクリアだった。
『脳は活かしておく。お前のこと知らない。私がこれからお前になる』
「ちょっと、意味がわからない」
『お前の人生は終わった。私がお前になり、お前の人生を歩む』
「なぜ?」
『苦しんだろ。楽になれ。お前の脳は生きている。お前の意志は生きている。お前の意志に従い、私達がお前を動かす』
「それ、俺が自分で体を動かしていることと変わらないじゃん」
『それでいい。しかし抑えが効かないとお前の意志通りに体は動く』
優一は深く呼吸をした。何がなんだか、わからない、と思った。
『わからなくていい』
マーズの声が聞こえる。明らかに自作自演ではなく、別の人格が物語を創っている。思考するだけで優一の言葉はマーズに捉えられる。
優と紀子が優一の異変に気付き、すぐに精神科を受診することになった。となりの市内にある病院に通うことにした。市内だと近所の目も気になる。そういうこともふたりは配慮していた。
山本クリニックの山本博医師は50代後半の短髪のおだやかな先生だった。
「優一くんに聞こえる声はそのマーズだけかね」
山本が尋ねると、優一は答える。
「最近は別の子がでてくることがあります」
「別の子?」
「小学生くらいの話し方をする女の子です」
「姿は見えるのかい?」
「いえ、ただ存在は感じます」
「ありがとう」
山本が言った。紀子が優一の後ろで不安そうに見ている。
「先生」
紀子が思わず、声を出した。
「今は薬物療法と作業療法、優一くんは幻聴の次に、幻覚も見えてきています。ドーパミンをおさえる薬を出します。定期的にきちんと服用してください。半年ほどでゆっくり感覚を取り戻しましょう」
「はい」
紀子は力なく答えた。
「優一くん、質問はあるかな?」
優一はしばらく考え込んで、口を開いた。
「先生はなぜ生きているの?」
山本は静かに笑みを浮かべる。
「きみを助けるためだよ」
と山本は優しく言葉にして、優一の肩を触った。
紀子の目に涙が溢れてきた。
6.白い病院
藤沢にあるその病院は白い壁に囲まれ、近くを川が流れている。優一はその病院に入院させられた。
医師の名は山本喜一。
「君の名前は」
山本が尋ねた。
「山田優一」
と優一は答えた。その後、いくつかの質問と何かのテストのようなものをさせられた。これからここに数ヶ月閉じ込められるのだと優一は直感した。窓の外に雨が降り出した。病院はコの字型に中庭を囲むように建物が建てられていた。
味気ない病院の食事のあと処方された薬を飲むと気分は落ち着き、優一はすぐに眠くなった。体中の筋肉が緩み、よだれが自然と出てきてしまう。薬を飲んだせいだとその時は思っていた。しかし今考えると、なるほどあぁそうか、と思うことがある。人間のエネルギーを様々なことに使うことができる。医師はある状態の人間に対して治療を行う。人間の思い込みとは大したものだと思う。社会通念上適正と思われることを常識と言う。この常識の範囲外にあるものを異常と呼ぶ。つまり想定される受け答え以外の問答に関しては全て異常である。統合失調症。以前の名前は分裂病だ。『24人のビリー・ミリガン』など小説の中に出てきている症状である。多重人格の症状もあるし、躁鬱の症状もでる。何が正常で、何が異常なのか。そのことを決めるのが社会である。正常と定義される行動をすることさえ覚えれば、統合失調症の状態であったとしても人間は異常と呼ばれずに済む。
7.優一のノート
優一の入院中に優紀は優一の部屋に入った。ふと気になったのである。なぜ優一が病院へ連れて行かれたのか。
優一の学習机の上にノートが一冊あった。ミミズの這う文字で、『本人以外は見てはならぬ』と書かれていた。優紀はノートを開いた。
ノートにボールペンでびっしり文字が書かれていた。優紀は開いたノートを手にして、食い入るように読み込み始めた。
ー通常と呼ばれる日常生活を送ることを早々に諦め、それでも人間として尊厳ある生活を送りたい。
最初にそう書かれていた。
優紀はページをめくった。
* * *
私は社会通念は時代とともに変わると考える。なぜなら神様であった天皇陛下は一夜にして人間となり、敵国だったアメリカは友好国となるのである。
私の目に見えるものが見えると言うと、頭のおかしい奴と思われる。
21世紀は神を信じながら科学を研究することができる。しかし19世紀のヨーロッパでは神を信じながら科学はできなかった。所詮常識は時代とともに変わる。
つまりその時に異常と言われたものが正常になり、正常と言われたものが時代遅れの古い知識となり非常識と言われるのである。太陽の周りを地球が回っていて、さらに地球自身も回転している。
統合失調症の症状は幻聴や幻覚、つまりドーパミンの多量分泌。これを抑えるのがハルシオン。私は経験者としてあくまで主観的に記録している。病の症状と改善について主観的に書くと、脳内麻薬を自身で出し、自身で分泌をコントロールするのである。多幸感、不思議な高揚感、全能感、これらのことが自身の体に起こると通常はその快感や全能感から再び体験をしたくなるものであるが、これらは経験により抑制ができる。経験がないとそれこそ「薬」で抑えないと均衡を保てなくなる。
幻聴の不思議な言葉の声に従い、体中をみなぎる全能感で何者かわからないものと対話をし、感じたままに言葉を出し、行動する。この歯止めのかからない状態で、外に出た場合に悲惨な事件につながっている。
では、どのように理解をすればその状態の人間が社会の規範をルールとして覚え、以前の状態ではないにせよ、人間としての尊厳を持ちながら社会の一員として暮らすことができるのか。そのことについての実践的な実験をしてみたいと思ったのである。
* * *
優紀はノートを机に置いた。ゆっくり閉じて元あった場所に戻した。
ー兄貴は狂ってなかった。
8.30年前の君へ
2027年、優一は47歳になっていた。古いノートを横目にパソコンのキーボードを叩いた。画面に文字が次々に並んでいく。
タイトル
「30年前の君へ」
と文字が光る。
9.30年前の君へ
もしも今、君が幻聴や幻覚で苦しむなら、社会に対しての違和感を感じ通常の仕事につけないとしたら、それはキミがおかしいわけではない。幻聴や幻覚はおかしなことではない。昔から日本には幽霊もいたし妖怪もいた。さらに人間同士であっても以心伝心、気が合う合わないなど言葉にせずとも相手の周波数を感じ思っていることがわかるものである。
統合失調症の幻聴に関してはこの周波数の帯域の広さをコントロールすることで改善できる。また幻覚に関しては認知症の症状と同じであり、既存の社会認識の壁が壊れた状態なのである。
人間の記憶とはつながっているようでいて、つながっていない。匂いや体のポーズ、その場所などでバラバラに記憶されていて、トリガーを引いたら想起される。写真を撮るときに光を計算して撮影をする。要は光と影である。ものが見えると言う事は光があり、その光が屈折し、瞳に入り、脳が認識するのである。つまりその存在に触ることができるのであればそれは実存する。しかし触ることができないのであれば、それは光の屈折あるいは影なのである。それは幻覚などではなく、脳の認識の問題であり、脳は実存しなくても実存しているもののように存在を作ることができる。
わかりやすく言えば、その存在をたった1人が信じているとしたら、それは妄想となる。その人間は異常者となるのである。しかし全人類の過半数がもしその存在を信じることができたとしたら、それは妄想ではない。つまり異常が正常かを決めるのは医学ではない。多数派とコミュニケーションが取れるか取れないかではないか。
最初は無意識であったがすぐに意識的に私は無意識の状態になるようになっていた。どういうことかと言うと肉体を動かすときに無意識で動かしているのだ。しかしあまりに無意識に動かしていると自分の感覚と言うものが次第になくなっていくのである。私の場合は5年ほどかけてこの状態になってしまった。どこでどうなぜと言う事はもう今更なので考えない。もし読者の皆様の中で体の不調やどうしても治らない癖などがある場合、今はADSL、ADHDなどの名前があるが、それまでは説明がつかず、ある集団ではこれは妖怪の仕業であり、別の集団では悪魔の仕業であり、また別の集団では「魔」であると言われる。そのような説明を受けた場合にあなたはどう思うだろうか。
シンプルに表現すれば、集団心理の中で日本人は物事を複雑にしてはいないだろうか。
ところで君は神様を信じるだろうか?
日本人の多数派は神社で神様に感謝し、寺院で仏様に手を合わせる。これらは徳川幕府、そしてGHQの政策である。神を信じ、仏を信じているのが日本人である。
ところで、神様に会えた人はどれほどいるだろうか。仏様に会った人はどれほどいるだろうか。
社会の認識は時代とともに変わる。だから必要な体験は自身が存在する社会の認識をすべての共同体の構成員が共有することである。その時に正しいとか間違っているとか言う事は考える必要はない。ただそのようなものだと思えば良いのである。これは物差しのメモリだ。このメモリがあるから自身の考えと他人の考えの違いや距離感がわかるのである。
自分に見えるものが他人に見えない。
辛くともそれで良いのである。それを他人も同じように見えないとおかしいと思うことにより、双方の認識に差異な起こり、争いになる。そして多数派の意見が正常となり少数派の意見が異常となるのである。
ある集団がその集団の中でだけの常識を競い合う文化があるとする。それは他の文化からすると滑稽に思える。しかしその文化の中で大切なことであるから当然尊重されるものである。これが集団ではなく個人と置き換えて文脈を読んで欲しい。集団であれば尊重されるべきこと、なぜ個人では尊重される事は無いのであろうか。
もちろん社会生活を行えないほど制御が効かなくなった状態であれば危険回避と言う名目で隔離する事は必要であろうが、拘束する必要は無いであろう。また制御が効かない状態と言うのは制御を聞かせることもできるのである。
どのように制御するか。
一時的には薬で活動量を抑えることである。脳内物質を自身でコントロールしだすことができるので、それを抑えることもまたコントロールできるのである。これには訓練が必要であり、訓練をしないとできないのである。しかし訓練をすれば薬に頼ることなくコントロールをしていくことができる。難しいことではなく特殊な事でもない。
1つは規則正しい生活。そして運動。食事。そしてもう一つ欲求に頼らない生きがいである。マズローの欲求については、本質的なものではないと思っている。社会の意味付けとして、行動のモチベーションをどこにどのように結びつけるか、その研究の結果ではないかと考えている。
「生きがい」と言う言葉が今私には1番しっくりとくる。生きがいがあれば仕事はなくとも人は生きていける。マズローの言う自己実現の欲求と言うものは教育によるものではないだろうか。つまり教育により人は生きる意味を覚え、社会の構成員として殺し合わずに生かし合うように育てられているのではないだろうか。その教育がなければ、人類は仲間のために他のグループを支配し、仲間のために防波堤を立て、仲間のために領土を奪う。教育がなければ、人類はそのように行動するのではないだろうか。人類は社会を作ったことにより、動物的なグループの構成とは少し異なる価値観を持った。しかしその教育がなければたちまち原始的な本能によるグループを形成する。身体的につよいものが生き残る、そういうグループである。社会があることによって、そのような原始的な中では生きられなかったものがたくさんの命を育んでいる。それは先人の知恵であろう。
生かし合う社会を作るために教育が必要である。そのことに異論は無い。これから日本は「生きがい」をモチベーションとして社会を構成していったらどうだろうか。超高齢社会を迎え、生産性が落ち、GDPの成長は望むべくもない。経済大国を目指す無理な筋書きを止め、精神的な成熟を目指してはどうだろうか。
人間は知識や経験により、文字通り人としての幅が広がるのである。許容できる社会そのものも広がるのである。
説明が必要であれば簡単な説明ができる。鎖国をしていた日本には海外からの人は数えるほどしかいなかった。開国した後、海外の文化が入ってきた。西洋の文化を知り、日本の文化を改めて感じたに違いない。同じように他者を知ることで自分自身を改めて感じるのである。他人を評価する前に自分自身を見つめてみてはどうだろうか。
私は社会性そのものを否定しているのではない。幻覚や幻聴があったとしても、社会の物差しに基準を合わせ、他者とのコミュニケーションを取ることができれば何ら問題がないのである。私自身の経験から言うと、そのことが大変なストレスになることもある。そのため人間との接触を極度に避けるようになるのは致し方のないことである。ただそのことが社会性のない人生を送ることになるとは思わないのである。
都市の生活者においては、社会性はさほど必要ではないが、群衆の中での立ち振る舞いはとても求められる。電車の中や街中での立ち振る舞いである。カラオケボックスで大声で歌ってもおかしな事は何もない。しかしスーパーマーケットの中で大声で歌っていたらおそらく警備員が飛んでくる。優しく他のお客様のご迷惑になりますのでお控えください。と言われるのだろう。ちなみに道路では注意される事は無い。あまりに1カ所で大きな声の場合、迷惑行為として警察の注意を受けることがあるだろう。しかし悪意なく鼻歌がちょっと大きな声になってしまったレベルであれば注意を受ける事は無い。しかし私はこのような人を見たら、陽気だと思う反面、群衆の中では好ましくない行為である。
それが社会性と言うものである。誰かに不快な思いをさせる、そこが分岐点になる。ところが正常と思われる多数派の行為も少数派の人にとってはとても不快になっていることがある。そのため、倫理や快不快の基準では抑えることができないのである。だからこその教育であり、「生きがい」なのである。
集団が尊重されるべきものであるならば、またひとりの個人も尊重されるべきものである。
思想の自由
行動の自由
言論の自由
これらは日本国憲法により保障されている。冷笑や視線に対して、怒りをあらわにする事は何らおかしいことではない。なぜか現代社会において、それぐらいの事は我慢しなさいと教育されている。もし戦争があり、お互いに銃を持つ距離だとした場合、あなたはその銃を持つ人間に冷笑をするだろうか。
その瞬間に銃口を向けられ打たれる可能性がある。私ならなるべく関わらないように距離を取る。日本の電車や駅、カフェなどで冷笑や視線を感じることがある。彼らの常識については時間をかけて学んだので何となくはわかる。しかしなぜ自分たちが安全だと思っていられるのか私には不思議でならない。これだけ事件が起きて、これだけ命が失われ、これだけわかりやすいことが起きているにもかかわらず、まだ認識が改まらないのかと思う。これはおそらく集団の中の教育の問題ではないだろうか。特異な教育ではなく他者と自己の差分を社会で共存する教育が行われておればおそらくこのようなことにはなっていないのであろう。しかし、こぼれたミルクである。きれいに拭き取り、次にいこう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
