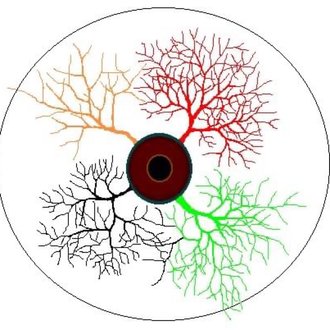★我楽多だらけの製哲書(22)★~夜な夜な開かれる奴らの集会と夏目漱石~
日本に戻って来て1年以上経つ。
シンガポールのときも、ラオスのときも、夜の散歩が日々のルーティンになっていたが、日本に戻って来てからもできるだけ続けるようにしている。
散歩は気分転換であったり、軽い運動であったりと、それ自体に価値はある(これを価値Aとする)。そして副産物として、授業展開のイメージやアイディアを膨らませたり、考察的投稿の構想を練ったりという「脳内の活性化の機会」という付加価値も生み出していた(これを価値Bとする)。
さらに異なる付加価値、もしかしたらこちらの方が重要な価値だったかもしれない(これを価値Cとする)が、シンガポールやラオスでは、散歩の途中、明りに照らされている場所に集まる虫を狙うヤモリを捕まえることを楽しみとして積極的に散歩していた。
日本に戻って来てからも、暖かい時期にヤモリと遭遇した場合には、捕まえるようにしていたものの、シンガポールやラオスにいたときとは比べ物にならないくらい少ない捕獲数であった。
そのためこれまでA+B+Cであった散歩の価値が、日本に戻って来てからはA+Bとなっていたのである。この失われた価値Cの埋め合わせをせんがため、日本での散歩ではヤモリに代わる対象に私は関心を持っている。
奴らは夜な夜な集会を開いていた。
初めのうちは、その集会を遠くからしばらく眺めて、通り過ぎていた。
そのうち、奴らともっと関わりたくなって近づいてみることにした。
奴らは人間に慣れているようで、私が近づいてもそこまで警戒心を示さなかった。
だからといって、親密な関係になっていくかというとそうではなく、さらに一歩踏み出してコミュニケーションを取ろうとすると、奴らは私なんか興味ないというような素振りでどこかへ行ってしまう。
奴らにとって人間は珍しいものではないらしい。

「吾輩は人間と同居して彼等を観察すればする程、彼等は我儘(わがまま)なものだと断言せざるを得ない様になった。」
どうやら、奴らは普段、私たち人間を注意深く観察し、そして人間をわがままな存在と見切ってしまっているため、既に興ざめし、夜の集会に近づいてくる私など眼中にないということなのである。
この言葉は、奴らの中の一存在が述べたものである。
そして、この一存在は名を持っていないらしい。名を持っていないことを次のように自ら説明している。
「吾輩は・・・名前はまだ無い。」
ただ、奴らの全員が名を持っていないわけではない。
「奴らに名前付けるのはとても難しいことなのです。信じられないかもしれないけれど、奴らには3つの名前がある。まずは『普通に使われる名前』、あなたが気楽につける名前、ピーター、ジェームス、フランク、トム。平凡すぎてつまらない。もっと『素敵な名前』もある。貴族的に凝ってみると、クレオパトラ、メディア、エリザベス、シーザー。これもやっぱり平凡です。奴らは『独特な名前』を求めている。もっと威厳のある名前を。誇り高くいられるために、顔を上げて生きるために、こうした名前もあげておこう。マンカストラップ、コリコパット、ボンバルリーナ、ジェリーロラム。少し個性が出てきたけれど、『本当の名前』は残されたままなのだ。『最高の名前』はかくされたままなのだ。人間にはこの名は見つけられない。人間の能力では発見できない。」
これは私が好きなミュージカルの冒頭の一節を少し加工したものである(ミュージカルのDVDも持っている)。このミュージカルでは、たくさんの奴らが登場する。奴らは様々な名前を持つ。
グリザベラ、ジェリーロラム=グリドルボーン、ジェニエニドッツ、ランペルティーザ、ディミータ、ボンバルリーナ、シラバブ、タントミール、ジェミマ、ヴィクトリア、カッサンドラ、オールドデュトロノミー、バストファージョーンズ、アスパラガス=グロールタイガー、マンカストラップ、ラム・タム・タガー、ミストフェリーズ、マンゴジェリー、スキンブルシャンクス、コリコパット、カーバケッティ、ギルバート、マキャヴィティ、タンブルブルータスなど、個性的な名前である。しかし、奴らの『本当の名前、最高の名前』は隠されたままで、人間ではそれを見つけることができないらしい。
さきほど紹介した名を持たない奴らの中の一存在に話を戻すが、この一存在に代弁させる形で、人間社会について持論を展開した人物が夏目漱石である。彼は次のような言葉を残している。
「自己の個性の発展をなしとげようと思うならば、同時に他人の個性も尊重しなければならない。」
奴らが行う夜の会議の公平・公正に比べ、人間が行う様々な会議がいかに不公平・不公正であるか、それは夏目漱石が生きた時代も、現代も変わっていないように思える。
民主主義は人間が発明し、上手に使いこなしている原理のように錯覚しているが、人間よりも自然界に近い奴らの方がよっぽど民主的に互いの個性を尊重していて生きているように思える。本来、人間が作り出す原理・仕組みといったものは、調和や循環を成り立たせている自然界のそれに新たな要素を加えて、調和や循環を崩すことによって、特殊な偏りを生み出し、強引にその果実を利用しようとする人間の傲慢さそのものではないだろうか。
(以下、考察は続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?