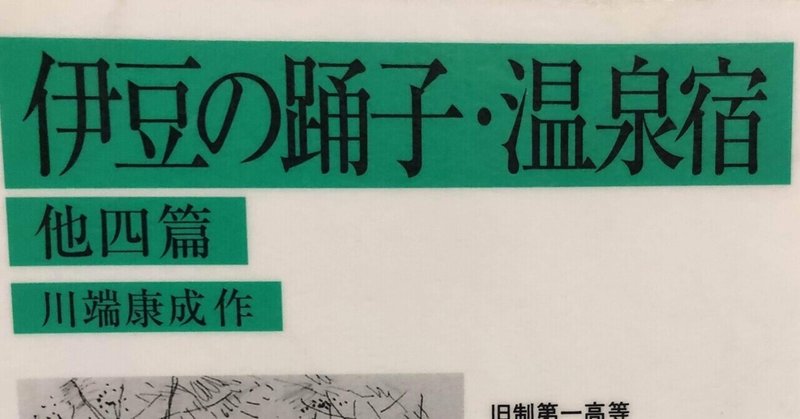
伊豆の踊子(川端康成、1926) 読書感想文
伊豆の踊子・温泉宿 他四篇(著:川端康成、岩波文庫、1952) より
伊豆の踊子(1926年発表) 感想文
道がつづら折りになって、いよいよ天城峠に近づいたと思う頃、 雨脚が杉の密林を白く染めながら、すさまじい早さで麓から私を追って来た。
出だしでもう作家志望の人々の心をへし折っていくかのような名文だと思う。景色が目に浮かぶとはこのことである。物理的な景色、心象的な景色がサラリと書かれている。
川端自身の回想によると、22歳の時に書いた草稿から、踊子の思い出の部分だけを1926年、26歳の時に書き直したものだという。早熟である。
しかし川端康成の小説は読んでいてまるで文章の壁がどさりどさりとやってくるようで読んでいて混乱する時がある。あらゆる語彙がだだっとやってきて軽い気持ちで読むと痛い目に遭う。
ととんとんとん、激しい雨の音の遠くに太鼓の響きが微かに生れた。私は掻き破るように雨戸を明けて体を乗り出した。太鼓の音が近づいて来るようだ。雨風が私の頭を叩いた。
冒頭の雨のリフレインである。雨が太鼓になって響いていく。叩く太鼓の音、「私」の頭を叩く雨風。雨と太鼓の叩く音が響き合い、
「ああ、踊子はまだ宴席に坐っていたのだ。坐って太鼓を打っているのだ。」
太鼓が止むとたまらなかった。雨の音の底に私は沈み込んでしまった。
その太鼓の音の正体である踊子の存在に浮かれ、しかしその音が止んでしまうと「雨の音の底」に「私」は沈み込む。川端は音の表現が詩的である。音の表現だけで臨場感を出すのだからすごい。
この後も「太鼓の音」が「私」を感傷的に襲うことになる。
窓閾に肘を突いて、いつまでも夜の町を眺めていた。暗い町だった。遠くから絶えず微かに太鼓の音が聞えて来るような気がした。わけもなく涙がぽたぽた落ちた。
この文が最後の展開とも響き合う。涙の音が最後にリフレインするのである。
雨から始まり涙に終わるという、まさに水々しい一作であった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
