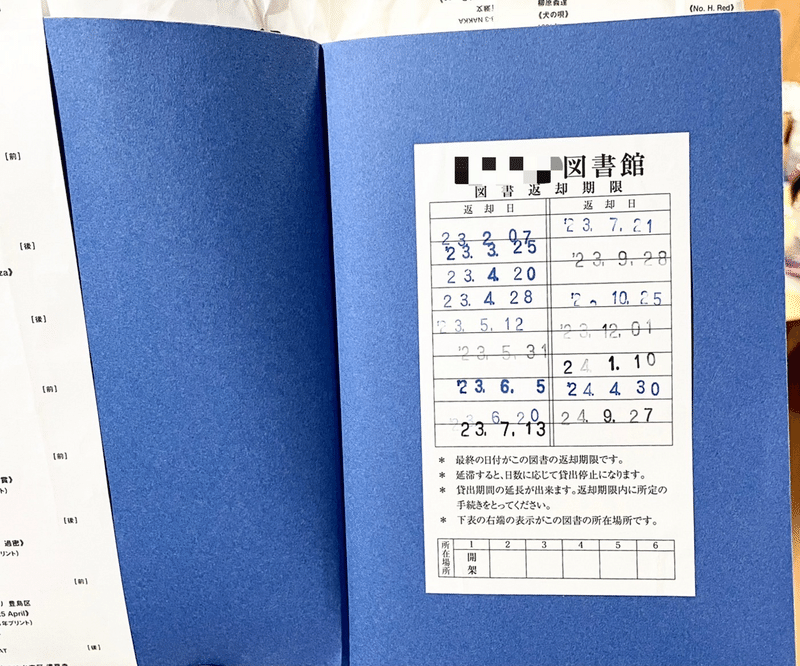pocoria
マガジン一覧
ゆるゆる図書室で暮らしてく
図書室・図書館で過ごした日々でふわふわ漂う思考の海をゆるゆる記す フィクション込
Thought✰つぶやき
ちょこちょこっとつぶやいたのをソートかけたくて
たまには
心にうつりゆくよしなしごとを、そこはかとなく書きつくれば
わたしの随録
美術館・博物館、展示会巡りの記録をまとめたくなったとき。それらに付随して頭に浮かんだことを記録しています。
わたしの読書memo 𐰶𐰶𐰶 ブクログ
ブクログに載せてる感想たちの一部、長くなったものとか残しておきたいもの