
Books, Life, Diversity #20
きょうはまた一つ、素敵な書店を発見しました。そういう発見があると、大変なことばかりの毎日も、なかなか楽しいじゃない、と思えます。その書店についてはまた後日ご紹介するとして、区切りの良い第20回。
「新刊本」#20
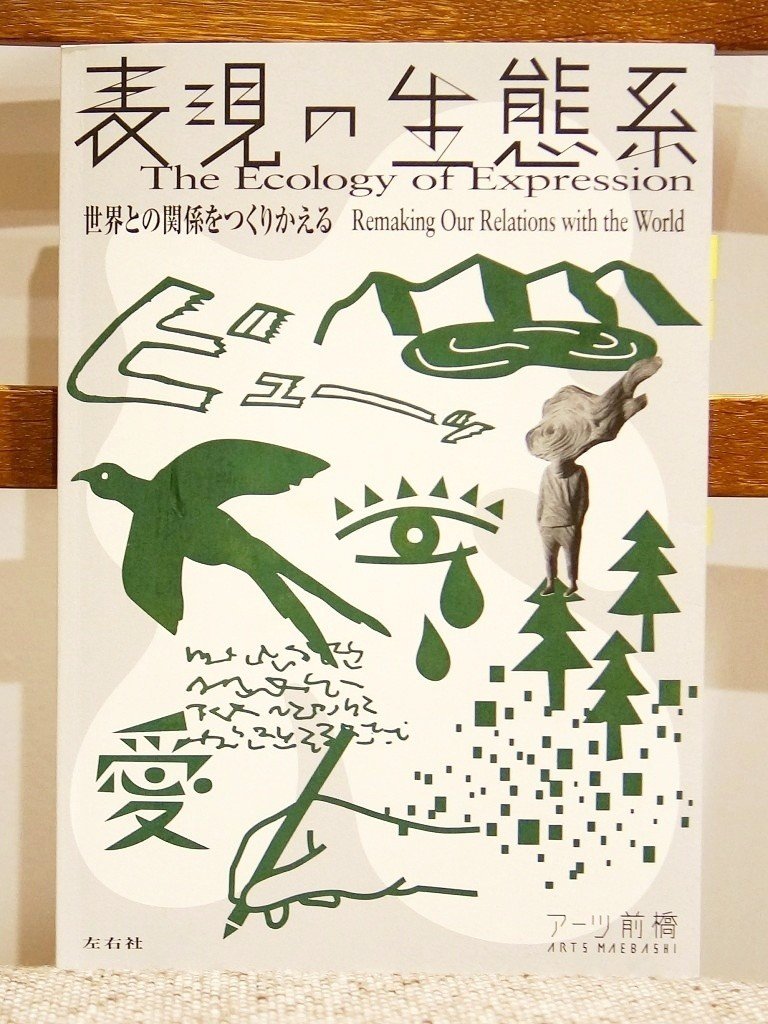
アーツ前橋編『表現の生態系 世界との関係をつくりかえる』左右社、2019年
2019年10月から2020年1月にかけ、アーツ前橋にて開催された展覧会「表現の生態系 世界との関係をつくりかえる」の図録です。
図録とはいえ、論考も充実しており、メディアアートやパフォーマンスアート、パブリックアートさらにはコミュニティアートなど、ちょっと一括りにはできないのですが、個というものの問い直しを試みるものや地域共同体と感応しあう中から生まれてくるもの、つまり境界線に揺さぶりをかけ無効にするようなアート(アートにはもともとそういう機能があると思いますが)に関心がある方には特にお勧めです。残念ながら私はつい最近この展覧会のことを知ったため実際には見ていないのですが、現代の作品だけではなく、デュビュッフェやアンリ・ミショー、さらには出口王仁三郎の作品まで、点数はそれほどありませんが非常に幅広く展示されていたようです。第18回で紹介した『たぐい』(亜紀書房、2020年)や『Cosmo-Eggs 宇宙の卵―コレクティブ以降のアート』(torch press、2020年)の石倉敏明氏、そして『ラインズ 線の文化史』(2014年、左右社)や『メイキング 人類学・考古学・芸術・建築』(2017年、左右社)で知られる人類学者ティム・インゴルド氏も寄稿しています。左右社さん、面白い本を出版なさっていますね。
私は美術史にも芸術にも疎いのですが、それでもこういった本を眺めたり読んだりすると、自分自身のテーマと通底しているものを感じますし(哲学にせよアートにせよ、私たちが生きるこの世界を説明しようという点では共有するところがあるはずなので当たり前かもしれませんが)、あるいはそうでなくても、突拍子もない想念が湧いてきてそれもまた楽しいことです。そんなところから次の研究テーマが生まれたりもします。例えばアーティストのブブ・ド・ラ・マドレーヌ氏による節「人魚の領土と脱皮」では次のように書かれています。
人が互いの身体の表面である肌に物理的に触れる時、そこでは何が起きているのだろうか。なぜ、ある人たちは私の肌に触れようとするのか。親しさや好意の表現。傷や悲しみの手当て。性的な動機。あるいは征服欲や攻撃欲による場合もある。また、私はどうしてある人の肌に触れたいと思うのだろう。他者が私に対して抱くであろう感情や欲望を、私もまた他者に対して抱く可能性をもつ。人間と社会とその関係の複雑さにおいて、人は人に触れたいと欲することがある。私たちの体の表面は何か価値のあるもので覆われているのだ。(p.16)
あるいは社会学者の山田創平氏は次のように書いています。
私は一見、何らかの区分や分類、境界のある世界で生きているが、それらの「線引き」は、本当は存在しない。例えば、私の皮膚は私の身体と、身体の外の世界を分かつ、ひとつの境界であるように思われるし、普段、実際にそのように考えながら日常を送っている。だが、その皮膚や角質も日々剥がれ落ち、内から外へと代謝されている。また皮膚の表面からは常に水分や気体が排出され、また逆に水分や気体を吸収もするという意味で、皮膚は極めて透過的な存在である。私とは、どこからどこまでの範囲をもった存在なのだろうか。(p.28)
いまはソーシャルディスタンスが叫ばれるばかりの状況ですが、けれどそもそも、私たちは他者や環境と不可分な形でしか生きられない存在です。「私」「他者」「環境」という、ある意味極めて近代的な幻想を超えて、在るということそれ自体を問おうとするとき、この強迫的なソーシャルディスタンスの状況を経験したということが、思想を屈折させて面白みを与えてくれるのではないかなどと感じたりもします。漠然としたこういう妄想を脳の片隅に降り積もらせておくと、あるときそこから何かが芽吹いたりして、それもまた楽しいのです。
「表紙の美しい本」#20
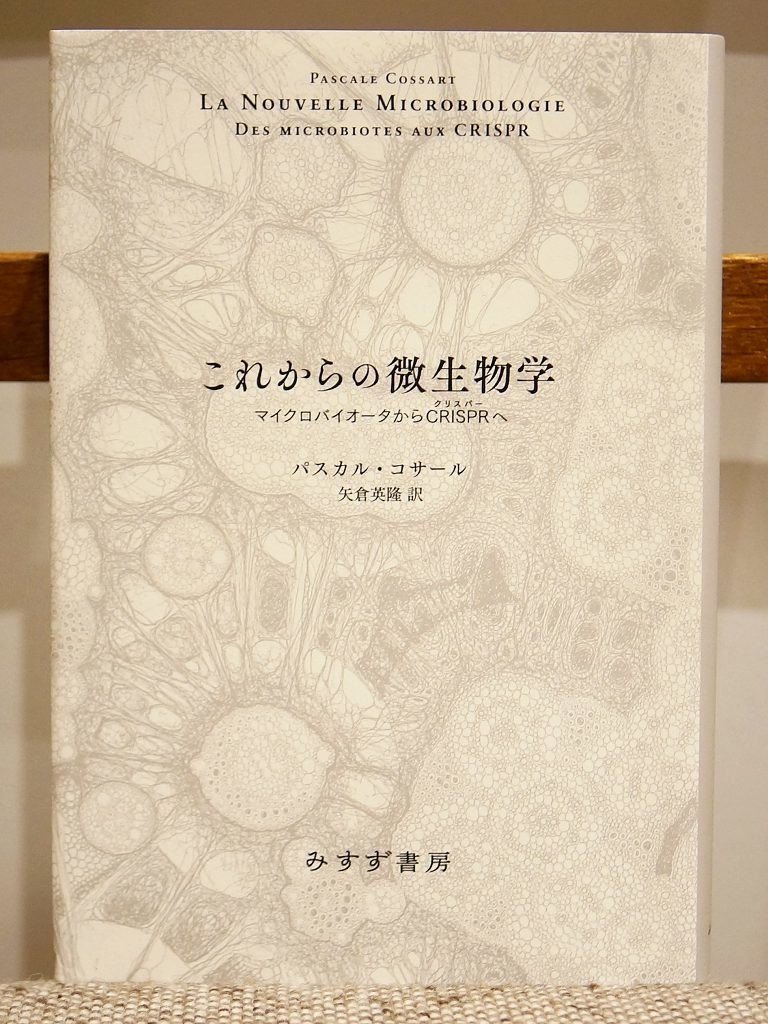
パスカル・コサール『これからの微生物学 マイクロバイオータからCRISPRへ』矢倉英隆訳、みすず書房、2019年
これは購入したまままだ読んでいないのですが、次の論文に向けて読むべき本の最上位グループに入っているものです。「21世紀は生物学の世紀になるだろうと言われた。それは間違いなく微生物学の世紀である」(p.7)とあるように、微生物学の歴史からその驚嘆すべき最先端技術までをまとめています。ちょっと、私の研究ジャンルって何ですかというと私自身も適切に言えなくて、表向きは環境哲学/メディア論を名乗っていますが、じゃあ環境哲学ってなあに、とさらに突っ込まれると、環境倫理も含むけれど、コミュニケーション論も含まれるし、それは民主主義についての議論にもつながるし……、などとごにょごにょして、なかなか一言では語りにくいものです。ともかく、この本の中ではクオラムセンシング(一部の真正細菌が生息密度によって特定の物質の生産量を調整したりすること)などはコミュニケーションだし、だとしたらこれって辿っていくと絶対民主主義の話に行きつくよな、とか、研究仲間の間でこんな話をしたらぜったい心配されるようなことを考えてニヤニヤしています。研究って楽しいよね……。
磨き上げた化石に文字を彫り込んだような端整な装丁は大倉真一郎氏によるもの。美しいイラストレーションはEpi2mic。いまちょっと調べてみたらこの方(グループ?)はストリートアーティストっぽいです。いいですね……。先に大山エンリコイサム氏を紹介したときに書いたように、ストリートアートもいまの研究の重要なモチーフなので、こういうところでコインシデンタルなものを、あるいはシンクロニシティを感じるようなときが、いや全然こじつけかもしれないけれど、でもそれが研究のもっとも楽しいときの一つではないかなと思います。研究って楽しいよね……。お金にはなりませんけどね……。
「読んでほしい本」#20
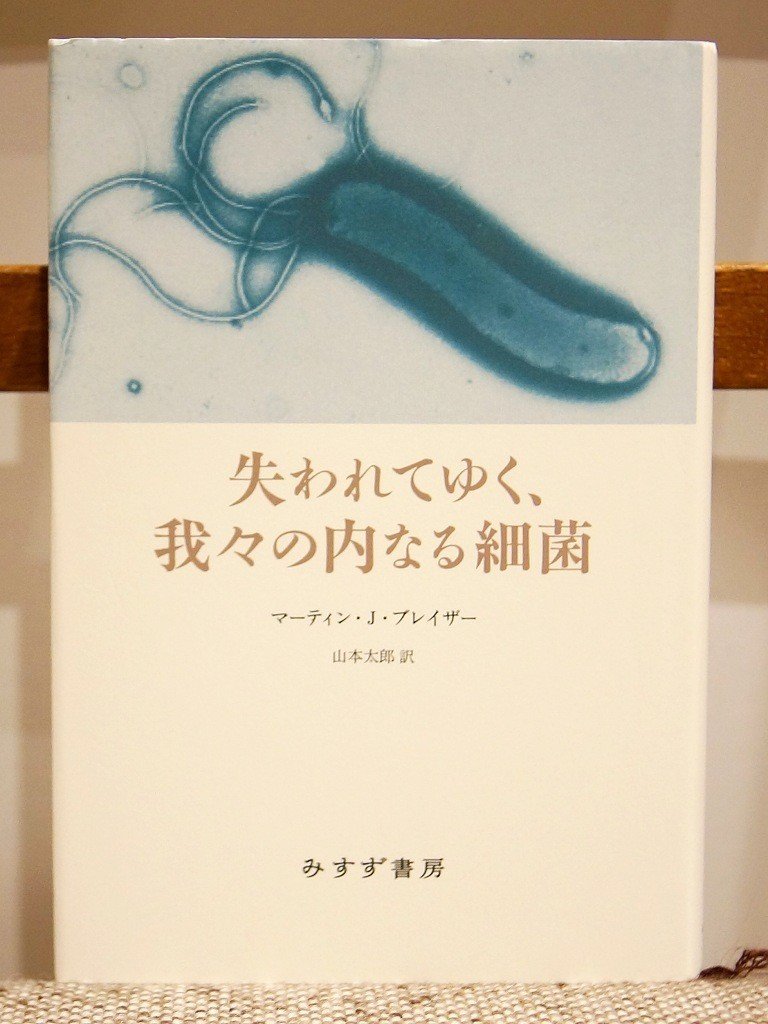
マーティン・J・ブレイザー『失われてゆく、我々の内なる細菌』山本太郎訳、みすず書房、2015年(2刷)
米国の微生物学者でマイクロバイオーム研究の第一人者であるブレイザーによる、ヒト・マイクロバイオームがいま直面している危機についての警告の書です。ブレイザーは研究者ですので、無暗にその危機感を煽るようなことはしません。そしてそれだけにいっそう、私たちの内なる生態系がどれだけ抗生物質の過剰な使用によって破壊されているのか、その怖ろしさがひしひしと伝わってきます。これまでに紹介してきた本とは異なり、胸を打たれるとか、そういったことはないかもしれませんが、無自覚的に抗生物質漬けな生活を送っている私たち現代人にとっては、そもそも生命/生物とは何かを問い直すために非常に重要な本だと思います。類書でロブ・デサール、スーザン・L・パーキンズ『マイクロバイオームの世界 あなたの中と表面と周りにいる何兆もの微生物たち』(斉藤隆央訳、紀伊國屋書店、2016年)があり、これも読みやすくて良い本です。

本書の方がより専門的ですが、一般向けに書かれたもので、門外漢の私も面白く読めました。ここに書かれている内容は衝撃的なものばかりなのですが、その根本にあるのは、「私」というものが単純にひとつの生命、ひとつの意志によって構成されたものではないという端的な事実です。「ヒトの体は三〇兆個の細胞よりなる。一方、ヒトは、ヒトとともに進化してきた一〇〇兆個もの細菌や真菌の住処でもある」(p.28)。だとすれば、近代以降私たちを強力に規定してきたこの「私」という観点を超えて、皮膚という境界すらを超えて拡がる〈私〉という複層的で開かれた生命体に心を馳せることも必要でしょうし、それはきっと、あらゆるものを簡単に支配しコントロールできるという驕りに対する、ポジティブな対抗力にもなってくれるでしょう。
余談ですが、皮膚の細菌叢を素材/コンセプトにしたバイオアートを作っているオーストリアのアーティスト、ソニア・ボイメルの作品などは、ここまで書いてきたようなぼんやりとしたアイデアに一つの焦点を与えることができると思います。(下記リンクの「辰」は文字化けですね。正しくは「ä」です。)
そんなかたちで、普段からぼんやりした表情ばかり浮かべている私ですが、何かそういうメディア論って良いよねと、やっぱりぼんやり考えたりしているのです。
この一連の記事では、出版支援として以下のプロジェクト/情報へのリンクを毎回貼らせていただきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
