
鉄道と労働|絵本でよむ蒸気機関車の近代
プロテスタンティズムの倫理と蒸気機関の精神
鉄道と労働は語呂が良いだけでなく、相性もまた良い。
特に蒸気機関車の勇姿は、労働者の働く姿を擬人化したものとして頻繁に表現されてきました(※1)。蒸気を上げながら貨車・客車を引っ張り、石炭や水が無くなると走れなくなる機関車は、いわば汗をかきかき懸命に働く労働者の姿を彷彿とさせるのでしょう。
こどもに大人気のTVアニメ「きかんしゃトーマス」もそうした鉄道擬人化の代表例として知られます。そんな「きかんしゃトーマス」を見ていてナルホドなぁと思うことの一つは、そこで描かれる群像劇が徹底した階級社会を反映しているということ(舞台である架空の島ソドー島がある国はイギリスという設定なので納得)。
トーマスと仲間たちは雇い主であるトップハム・ハット卿へいかに忠誠を尽くすのかに腐心し、ミスをして叱られることに異様なほどの恐怖を抱いています。物語にはトップハム・ハット卿が口癖のように「混乱と遅れが生じた」と叱るシーンがほぼ毎回のように登場するのが印象的。
トップハム・ハット卿の不快感は、ちょうどW・シベルブシュが『鉄道旅行の歴史:十九世紀における空間と時間の工業化』(1982、法政大学出版局)の中で、蒸気機関の動きが「均一性、規則正しさ、思いのままの継続性と思いのままの速度の増大」と指摘した事実に対応しているのです(※2)。
さて、先にも触れましたが、トップハム・ハット卿とトーマスを筆頭とする機関車の立ち位置は資本家と労働者の関係に対応しています。そして、さらに労働者=機関車のなかにも格付けがあります。機関車の格下に貨車が位置づけられていることを感じさせるエピソードも随所に。
そんな状況設定のもと、TVアニメ「きかんしゃトーマス」は労働の意味や誇りを毎回のエピソードの基調に据えた内容となっています。
例えば、「きかんしゃトーマス」のテレビ絵本『トーマスとフォグマン』(2003)のエピソードは、資本家と労働者の間にある葛藤を克明に描いており秀逸です(図1)。
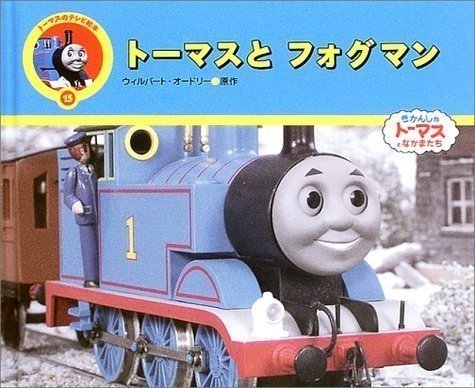
図1 トーマスとフォグマン
トップハム・ハット卿が導入を企てた装置フォグホーンが、いままでその役割を担っていた技師フォグマンを失業させる危機に直面。あわや解雇というところで、装置が崖崩れを誘発した事故が発生し、フォグマンの首切りは阻止されるというお話。なんだかマルクス主義の啓蒙絵本みたいなストーリーが衝撃的です。
少し気になったので『機関車トーマスと英国鉄道遺産』(秋山学志、2010)を通読してみました。そのなかで興味がわいた事実として、原作者ウィルバート・オードリー(1911-1997)が聖職者であったということが挙げられます(※3)。
イギリス国教会の牧師として活動した彼が、もはや労働者のメタファーとしか思えない機関車たちの働きぶりを丹念に描いた(実際、彼はリアリティを追求したという)と知ると、なんだか「天職への献身=プロテスタンティズムの倫理」を連想させるに十分。そう思うと、トーマスたちのやけに前向きな言動や、怠惰や失敗について自責する姿に深みが出てくるではありませんか。(※4)
熱烈な鉄道ファンでもあったオードリーは、自身の信仰心と鉄道をどのように結び合わせ、労働者のメタファーとしての機関車にいかなるメッセージを託したのか。ソドー島を舞台にしたトーマスたちの物語とマルクス、ウェーバーを結ぶことで見えるものは何か。
そんな問いをもって、我が家で無限再生される「きかんしゃトーマス」を眺めていると、楽しみの時間になります。「ここがソドーだ!さあ跳べ!」。
トーマス、ちゅうちゅう、それぞれの労働観
『きかんしゃトーマス』のエピソードは総じて「役に立つ機関車」であろうとする気持ちが空回りしてトラブル発生→すったもんだの挙げ句、他者とは比べようのない「特別な仕事」を担うことの意味を再確認し「誇らしく」思う、という定型の展開が用意されています。このある種の説教臭さは、わたしたちにカルヴァン予定説からくる「天職への精励」を連想させます。
トーマスの生みの親オードリー作『機関車トーマス』(1946)を見てみましょう(図2)。

図2 機関車トーマス
血気盛んな若きトーマスが「客車を引きたい=より重要度の高い仕事を任されたい」と願うものの、その思いが先走って失敗ばかり。でも最後には「役に立つ機関車」として褒められるというお話です。
すでにシリーズの初期段階で、働くことの意味が説かれる物語展開を確認することができます。いってみればトーマス絵本は将来の中間階級へ向けたキャリア教育読本なのかもしれません。
イギリスが生んだ鉄道絵本が『機関車トーマス』だとすると、アメリカが生んだ鉄道絵本の名作といえば『いたずらきかんしゃちゅうちゅう』(福音館書店、1937)(図3)。

図3 いたずらきかんしゃちゅうちゅう
作者は『ちいさいおうち』(岩波書店、1942)で知られるバージニア・リー・バートン(1909-1968)。翻訳は村岡花子。トーマスに約10年先行するものの、機関車が若気の至りで失敗する展開はよく似ています。
主人公ちゅうちゅうは、ある日、重い客車を引くことに嫌気が差し、ひとりで疾走したいという欲望に取り憑かれます。ところが廃線に迷い込んでしまい立ち往生。手痛い失敗を経て、仕事から逃げても面白くないと悟るちゅうちゅう。任された仕事を着実にこなすことの意味を再認識するというお話です。
トーマスとちゅうちゅう。ふたつの絵本は両方とも鉄道、特に蒸気機関車を労働者として描き、与えられた仕事へ奉仕することの意義を高らかに謳う点で共通しています。
「近代」の象徴ともいえる蒸気機関ですが、この絵本が刊行された頃には、次第に鉄道の電化が本格化していく時期にあたっています。鉄道絵本に登場する蒸気機関車の姿をより深く読解するためには、ディーゼル機関車や電気機関車といった他の動力がどのように登場してきたのか、そして、それらの力関係はどうなっていたのかも見てみないといけません。
蒸気機関車の戦前・戦後
『きかんしゃトーマス』や『いたずらきかんしゃちゅうちゅう』といった1930~40年代に描かれた蒸気機関絵本には、勤労を奨励するメッセージが込められていまいた。それと同時に、衰退する蒸気機関車へのノスタルジックな視点もはらんだものでもした。
それでは、電気機関車の台頭に伴い蒸気機関車たちはどんな境遇に直面したのでしょうか。そのあたりの経緯を描いた絵本があります。それは『きかんしゃやえもん』(阿川弘之・岡部冬彦、岩波書店、1959)(図4)。

図4 きかんしゃやえもん
年老いた機関車やえもんは、若かりし頃に活躍したプライドにしばられて、時代がレールバスや電気機関車へ移行している現実を受け入れられません。
電気機関車やレールバスに嗤われたことに業を煮やしたやえもんは、煙と火の粉をまき散らして走り、それが稲むらに引火してぼや騒ぎを起こしてしまう。怒った百姓たちは蒸気機関車の打ち壊しを主張して大騒ぎ。
仕事を外されたやえもんは、その後、博物館で展示されることになります。最後は子どもに囲まれて余生を過ごすものの、時代の変化の中でなかなか上手くポジショニングできなかった主人公の騒動劇はなんだか寂しくもあります。かくも歳をとるのは難しい。
やえもんが経験したであろう戦前・戦後の激動をより丹念に描いた絵本が小風さち・藍澤ミミ子『はしれきかんしゃちからあし』(福音館書店、2008)です(図5)。

図5 はしれきかんしゃちからあし
主人公ちからあしは、戦前は重い貨物を引いて活躍するも、戦時中には軍需物資の運搬にたずさわることに。同僚だった客車専門の蒸気機関車の戦死(空襲による炎上)も目の当たりにするなどの苦難を越え、戦後復興へ向けた食料や建材の運搬に活躍します。とはいえ、やはりディーゼル機関車や電気機関車の台頭を受け、蒸気機関車は都会を走れなくなる。
でも、ちからあしのその後は、やえもんのそれとは展開が異なります。周囲から認められない憤懣からトラブルを起こしたやえもんとは違って、懸命に仕事をこなし実績を積むちからあしは観光向けに客車を引く仕事を任され、皆に愛されることになったのです(※5)。
やえもんに比べると、ちからあしは仕事を選ばない点において労働に対して極めて受動的に感じらなくもない。でも、与えられた仕事を懸命にこなし、時代が移り変わっても自然と次の仕事を与えられていく過程はとても印象的です。自分の持ち味は他者から与えられる機会によってにじみ出る。「キャリアのドアにはドアノブがついていない」ことを痛感させられる絵本。
ナチス・鉄道・労働
さてさて、『きかんしゃトーマス』や『いたずらきかんしゃちゅうちゅう』、『きかんしゃやえもん』などの鉄道=労働絵本を導き糸にして、鉄道と労働、機関車とキャリア教育の関係について考えていくと、どうしても避けられない論点があります。それは「近代」のメカニズムであり、その副産物としての「ナチズム」の問題。
特に安西水丸『がたんごとんがたんごとん』(福音館書店、1987)は、ほのぼのとした画風でありながら、いや、ほのぼのとした画風だからこそ一層深刻に問題を浮き彫りにする問題作といえます(図6)。

図6 がたんごとんがたんごとん
「がたんごとん」と機関車が走ると「のせてくださーい」を動物たちが呼び止める。そしてまた「がたんごとん」と走っていき・・・これをリフレインしながら走り続け、最後は「しゅうてんでーす、みんなおりてください」の号令のもと、飲食物・ネコ・ネズミが下車。
ラストシーンは女の子の食卓に飲食物が並び、ネコ・ネズミが相席するシーンと「がたんごとん、さようなら」の文章で締めくくられます。子どもに読み聞かせると嬉々として「もういっかい!」とせがむので、無限ループに突入しますが、内心とても複雑な気持ちに。
鉄道も労働も、ともにテクノロジーやモダニズムを蝶番にして極めて「近代」的な対象ですが、その「近代」の暗黒面として「ナチズム」を捉えてみると、一見したところほのぼのとした絵本『がたんごとんがたんごとん』の蒸気機関車は、アウシュビッツへと向かうあの悪名高い「家畜用貨物列車」へと姿を変えます。
ネコは「カポ」 (囚人でありながら看守の親衛隊員が就任する労働隊指導者の下で労働隊の他の囚人の監督を行う役職)であり、女の子はホロコーストを主導したドイツ親衛隊中佐「ルドルフ・アイヒマン」にみえてくる。
リンゴやバナナや牛乳は第三帝国の生存圏(Lebensraum)を維持するために動員され、そして解決(=大量虐殺)されていった。だとすると、絵本の最後のフレーズ「がたんごとん、さようなら」は全く別の顔を見せることになる。
もちろん、安西さんがそうしたメッセージを込めたわけではないだろうけれども、質が高く、でも表現がシンプルなまでにそぎ落とされた名作絵本は、創造的な誤読の余地をもたらしてくれます。
近代化の申し子としての鉄道、そして、それを下支えした労働を巡る歴史は、私たちに豊かな生活を与えてくれました。それと同時に、数多くの問題・課題を残したこともまた事実。本当に豊かで自由な生を全うするためにも、残された問題・課題を深く考え、学ばないといけません。
自由のために学び・働き・生きる。ナチスが強制収容所の入り口に掲げたスローガン「働けば自由になる(Arbeit macht frei) 」は、その問題・課題の複雑さ・難しさを指し示して余りあります。
(おわり)
※1 特に蒸気機関車が発する音や振動、匂いなどが懸命に働く姿として擬人化を促したのだと思われる。アメリカの「労働歌」には鉄道労働者たちに関係するものも多くあるそうで、そうした文化との関連もみえてくる。
※2 W・シベルブシュ『鉄道旅行の歴史:十九世紀における空間と時間の工業化』法政大学出版局、1982、p.12。また、労働を下支えする労働者の観念=労働観が近代に至ってどのように形成され、どのような問題があるかについては、今村仁司『近代の労働観』(岩波書店、1998)が参考になる。
※3 秋山学志『機関車トーマスと英国鉄道遺産』集英社、2010。聖職者であり、かつ、鉄道マニアでもあったオードリーが、実際の鉄道から物語の着想を得ていただけでなく、鉄道遺産として保存する運動にも尽力していたことを紹介している。
※4 こうした「プロテスタンティズムの倫理」がさらに進化した様態がフレデリック・W・テーラーの思想になる。「純粋培養されたプロテスタンティズムの権化、宗教的内実を喪失した禁欲倫理の体現者として、テーラーはアメリカ合衆国のなかから登場したといえよう」(桜井哲夫『「近代」の意味:制度としての学校・工場』日本放送出版局、1984、p.199)
※5 蒸気機関車が観光目的に再利用されるのは、たとえば大井川鐵道の動態保存が有名。ただ、赤字続きの大井川鐵道がその対策の一環として手がける「きかんしゃトーマス号」は楽しい企画であるとともに、いささか複雑な心境になる。蒸気機関車の動態保存を存続するために、まさにその保存対象たる蒸気機関車にトーマスの顔を張り付けるなどのデコレーションを施さなければいけないのだから。
サポートは資料収集費用として、今後より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。スキ、コメント、フォローがいただけることも日々の励みになっております。ありがとうございます。
