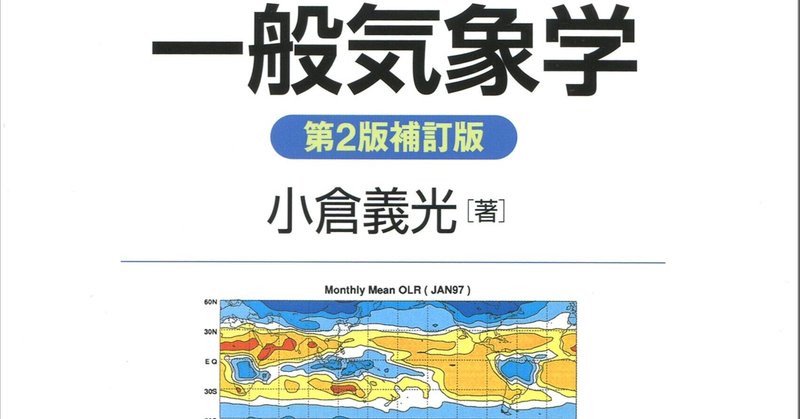
気象予報士試験のバイブル『一般気象学』を読み解く①
気象予報士試験合格を目指す本連載(第一回はこちら)、今回から小倉義光『一般気象学』(東京大学出版会)を読んでいきます。
全体確認
本書は現在(2021/09/26)紙版のみで、序章があって第1章から第10章まで、全11章。大学の講義で、初回はガイダンスで、十数回の講義があって、最後はテストかレポートで、一学期の講義のためのテキストとしてはぴったりの構成です。
なので半年かけてゆっくり読みたいところではありますが、来年2022/01/30の気象予報士試験をひとまず目指していますので、今回=今週含めて、全6回=6週間で読み進めます。
序章
第1章 太陽系のなかの地球
第2章 大気の鉛直構造
第3章 大気の熱力学
第4章 降水過程
第5章 大気における放射
第6章 大気の運動
第7章 大規模な大気の運動
第8章 メソスケールの気象
第9章 成層圏と中間圏内の大規模な運動
第10章 気候の変動
ページ数的には、序章から第2章までで30ページ、残り八章が平均30ページと少しで、目次などもあって合計320ページです。つまり読むべき30ページのかたまりが九個あるということで、6週間でどうやって割るかなと思いつつ、まずは本をめくってみます。
はしがきと序章
1984年に書かれた初版はしがきも収録されていて、そこには「イリノイ大学での講義は1学期約42時間ある」とあって、3時間×14週なのかなと想像しつつ、その少し下には「ふつうの教科書とは少し形態を変え」て、「多少読み物的な要素を入れた」とあって、なるほどということで、序章に入ります。
序章冒頭から読み物的というか小説家的には非常に参考になるフレーズが書かれています。
「気象学がもつ2つの特殊性」
→①「気象学は入りやすいが奥が深い学問である」
→②「気象学では基礎研究と応用研究が重なり合っている部分が多い」
①の特殊性〈入りやすいが奥が深い〉については、A=天気観測が小学生の夏休みの宿題であることと、B=カオス理論の提唱者であるエドワード・ローレンツが気象学者であることから語られています。
カオス理論は──個人的には物理学科のゼミであつかっていたこともあり──本書で最後に扱われていてそこにたどりつくのは楽しみです(オチがあるのも読み物的!)。
②の特殊性〈基礎と応用の重なり〉については、数値計算と環境問題が例として挙げられていて、ぼくとしてはその2つ──特に後者=環境問題──に関心があって、気象予報士試験を受けようと思っているので、ますます励まされる次第です。
本書の数学や物理学のレベル
序章に明示されていることとして、本書は中級=大学教養レベルであって、微分・積分を使うのは上級とのこと。本書は──(微積を使わない)熱力学やニュートンの運動の法則を使って──「気象学をできるだけ統一的に体系的に、高等学校卒業程度の物理学と数学と化学で記述する」ことが目標ということで、
関数電卓が欲しくなる
理工書ではよくあるパターンで、本書にも練習問題があり、これまたよくあるパターンで(全問ではなく)いくつかの問題には解答がついているとのこと。そして「できれば三角関数や指数関数などの初等関数の計算ができるポケット電卓」を使うことが推奨されています。
ここで「初等関数の計算ができるポケット電卓」とは〈関数電卓〉のこと。大学の自然科学系の学部1年生が入学すぐ買うように言われる定番ツールです。このあたりの記述は、このバイブルあるいは気象学が人文科学系の学生も受けることを想定しているのかなと推測します。
気象予報士試験には関数電卓は持ち込めず、なんとなればアップルウォッチも持ち込めないのですが、それはそれとして試験用文房具は連載のどこかで書くのでお楽しみに! そしてこの関数電卓も──ちょっと調べると色々面白く関数電卓上でAIも作れそうな予感もしまして──近日中にnoteで書きますので少々お待ちください!
確認:本連載と本書の文字数換算の公式
本連載は1記事5,000字を目安としていまして、なので公式化すると〈本書10ページ=1,000字〉くらいにすると良いのではないかと思ってきました。なので、章終わりでちょうど記事が終わることはあまり追求せず、第3章は熱力学が出てきますので──ぼくの趣味的にも物理はやりたいので──2回に分けたほうが良いであろうということで、今回は第3章前半までやります。
第1章「太陽系のなかの地球」(10ページ弱)読解
大気中のほとんどの運動が直接間接に太陽と関係しているということで(なるほどー)、太陽概説から。
太陽では「毎秒4×10^26W」のエネルギーが作り出されていて、さっそく数式なので簡単に解説を。「10^26」とは黒板では10の肩のうえに小さく26を書くもので、「10の26乗」と読んで、意味としてはゼロが26個並ぶ、頭の1を入れて27桁の数字を示します。10^3は10の3乗で1000になります。頭の「4×」はそれの4倍ということで「4かける10の26乗」と読みます。
Wは「ワット」と読み、物理量のひとつ〈仕事率〉です。1Wは、1秒で1J(ジュール)という仕事率を示していて、WもJもイメージしにくいかもですが、たとえばLED電球は7W前後なので、毎秒7Jずつ電気を使っています。あるいは本書には広島型原爆約5兆個とあり、それだけのエネルギーが毎秒作られていることになります。エネルギーの一部は太陽風となって──物理的には粒子と光(電磁波)で──地球に届きます。
光/電磁波について
小中高のどこで習ったのか記憶が定かではないですが、まず〈光と電磁波は同じもの〉です。光/電磁波の一部は、人間に見えるということで可視光と言います。
電磁波はその名の通り〈波〉で、波は波長で分類することができます。長い波長のものは普通に数キロメートルにも及び、たとえば潜水艦のアンテナは海中で何キロにも広げて受信するようです。電子レンジに使うのは波長10センチほどの電磁波、オーブンではもう少し短い波長の遠赤外線を使います。
さらに波長が短くなりマイクロメートルになると見えるようになってきて、0.77〜0.38μmくらいが可視光で、もっと短い遠紫外線になるとまた見えなくなります。
地球の大気の独特さ
「1960年ごろまでは、金星は地球の双生児と思われていた」という興味深い記述もあったりしながら、〈太陽も星間ガスも水素が主なのに、なぜ地球大気は独特なのか〉という、言われてみればなるほど確かに謎だと思う問題が追求されていきます。
このあたりは活発に研究されているとのことで、もしかするとさらに新しい説が出ているかもですが、ひとまず本書によれば、原始地球に初めにあった大気(それはもしかすると水素メインだったかも)は、特に地球形成期に強かった太陽風によって吹き飛ばされて、今の大気はそのあと、固体部分の地球から噴出したガスからできたものであり、そのガスは今の火山ガスの成分とも近いもの(二酸化炭素や窒素や硫黄や鉄や塩素など)だとのこと。なるほどです。
噴出ガスあたりの事情は火星や金星と同じだったはずですが、唯一地球が違うのは海があるということ(地球だけに海があるのは、太陽との距離が幸運な〈ハビタブルゾーン〉にいるから)。
海は亜硫酸ガスや塩酸ガスを溶かし込みまずは酸性に。その後の降水によって陸上からの金属イオンによって海は中性化し、そこにさらに二酸化炭素が溶け込んでいくと(窒素は水に溶けにくいのでそのまま)。
地球大気の二酸化炭素は火星大気に比べるとぐぐっと少ないのは、海のなかで難溶性の炭酸カルシウムとなって石灰岩などになったから。
最後にこれまで出なかった/地球大気の主成分のひとつである酸素は、これはもちろん光合成反応から。H2O+CO2→CH2O(炭水化物)+O2に従って、植物というか初期の酸素を必要としないバクテリアが酸素をいわば廃棄物として生成して、それが溜まってオゾン層となり、オゾン層は紫外線を吸収するので、生物の繁殖につながり、ますます光合成反応をする植物が増えていくという正/生のスパイラルが生じたのでした。
こういうのは小説に書くと冗長になりがちですが、地球史は久々だったのでちょっと丁寧に。ペース配分を考えつつ次の章へ!
第2章「大気の鉛直構造」
言われてみればが多い気がしますが、言われてみれば「数千kmも旅をして北極圏にいかなくても、わずか10km上に昇れば、そこは気温が零下数十度」に。ということで、大気を垂直方向に見ていく章のようです。
全部メモっていくのは回避して、面白いと思ったところだけメモで。
まずぼくたちがいる大気の一番下の層は〈対流圏トロポスフィア〉。厚さ11km。その次が成層圏で、成層圏の名前の由来がなかなか面白く、成層圏が発見されたのは19世紀のこと、そのときには成層圏は(対流圏と違って)上下の対流などのない安定的な領域だと思われていて、だとすれば空気は重い順に「層を成している」であろうということで付けられたのでした。しかしこれは科学あるあるというか、間違った推測で、成層圏にも激しい上下の運動があることが今ではわかっているとのこと。
地上から100kmくらいから上には〈電離層〉があり、その名の通り窒素や酸素が紫外線によって──光が原子のまわりの電子を弾き飛ばして──電離しています。なぜ地上100kmかと言えば、それは太陽からの紫外線が地球大気とぶつかって分子を電離しつつどんどん吸収されていって、地上100kmにたどりつくころには「かなり弱くなっている」から。逆に言うと上層ほど紫外線が強く、また電離された電子も多く、あるいは太陽面での爆発があれば電離層は活発に。これを〈デリンジャー現象〉と言いますが、最近は人工衛星通信もあるので通信への影響は少なそうです。
第3章「大気の熱力学」
さて今週の目玉なのか、熱力学です。この3章は11節まであるので5節まで行って今日の勉強は終わり(なんだか久しぶりに超勉強しています)。
そして熱力学と言えば〈気体の状態方程式〉。体積Vで重さmで圧力Pの気体があるとすると、それはある比例定数(気体定数)Rを使って、〈PV=mRT〉という関係が成り立つという、よくよく考えると不思議な式があるのです。これが気体の状態方程式。混合気体でもmを工夫すると基本的に成り立ちます。とりあえずここはこれくらいで次節に。
静水圧平衡
大気がなぜ地球にまとわりついているかと言えば、それは重力があるから。なので地表に近いほど大気の密度は大きくなり、気圧も高くなります。では気圧は高さによってどう変化するかという式が〈静水圧平衡の式〉で〈Δp=−gρΔz〉。ここでΔは微小変化を表していて、ΔpやΔzでひとかたまりで、Δpは微小な気圧変化であり、Δzは微小な高さ変化。gは重力加速度、ρ(ギリシャ文字ロー)は空気の密度を表します。
ここで密度ρは、重さmを体積Vで割ったものに等しく〈ρ=m/V〉と書けます。ここで、さきほどの気体の状態方程式を変形したもの〈P/RT=m/V〉を合わせると、ρ=P/RTとなり、静水圧平衡の式は〈ΔP/Δz=−Pg/RT〉と変形もできます。なかなかマニアックになってきた気がしますが、これを普通に使って、高度変化Δzに応じた気圧変化ΔPが算出できるのです。
なぜこのような式を考えるかというと、山岳地帯にある測候所での気圧の値を、海面上で測った気圧と合わせて、正しい気圧の等圧線を引くためです。これを〈海面補正〉と言って、上の式あるいはその微積バージョンを使います。※微積を使ったほうが正確です。
熱力学第一法則
熱力学と言えばのもうひとつはこの〈熱力学第一法則〉。数式的にはもろもろ変形して〈ΔQ=ΔW+Δu〉。熱量Qが与えられると、それは仕事Wと内部エネルギーuの増加に使われるという意味です。
面白かったのは気温のポテンシャル=位置エネルギー的な〈温位〉です。数式は〈θ=T(P0/P)^R/Cp〉で与えられるもので、たとえば「地表面にあり温度は30℃」の空気塊Aと、「高度10kmにあり温度は−50℃」の空気塊B、どちらが暖かいかということで、Aを高度10kmまで持ち上げると−68℃となって、実はBのほうが暖かいのでした。すなわち温位とは、その空気がもつ本質的な温度的位置が見えるというもの。領域における温位の変化から、上昇気流や下降気流の存在が見えてきます。
今回のオチ──次回に向けて
以降は〈3章後半と4章〉〈5章と6章前半〉のように1章半ずつ進めていけばちょうど全6回で終わるということで、ペース的にはこれで良いのかなと。
書く内容としては、今回やってみてぼく個人は結構楽しかった+久々の勉強のような新しい取材のような感じで狙いとしては大成功な気もしつつ、noteとしてはもっとピンポイントにしたほうが面白くなるはず。あと、数式については別の記事として、練習問題をやったほうが良さそうです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
