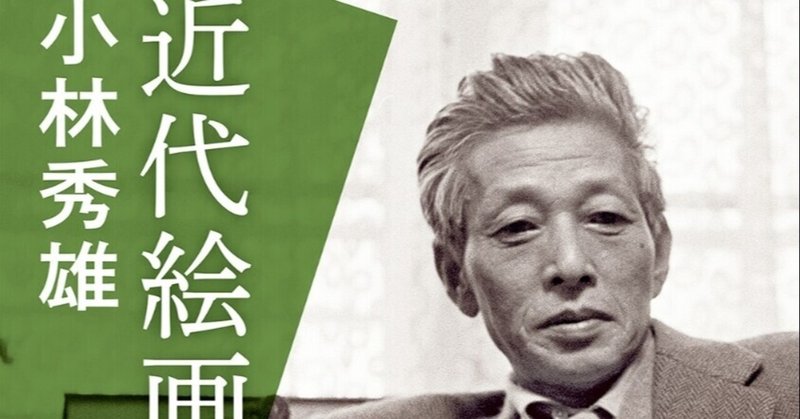
Etude (11)「理想人とは、実現不可能なことに賭ける人」
[執筆日 : 令和3年3月19日]
ゴッホの弟テロに宛てた手紙を基に「ゴッホの手紙」を描いた小林秀雄は、後に発刊された「近代絵画」でもゴッホを取り上げています(ゴッホの他には、詩人のボードレール、モネ、セザンヌ、ゴーギャン、ルノワール、ドガ、そしてピカソを扱っています。)。小林は、ゴッホの手紙を「没我のうちになされた告白文学」のように捉え、彼は、
「何んと告白好きが、気楽に自分を発見し、自分を軽信し、自分自身と戯れるしか出来ないでいるかを考えてみればよい。正直に自己を語るのが難しいのではない。自己という正体をつきつめるのが、限りなく難しいのである」「優れた告白文学は、恐らく、例外なく、告白者の意志に反して個性的なのである。彼は人々とともに感じ、ともに考えようと務める、まさに其のところに、彼自身を現して了うのである」
「彼の表現力は、強く豊かで、天賦の才を示しているが、もっと驚くべきものは、彼の天賦の無私であろう。彼の無私が、彼の個性的な一切の性癖を透過して言葉を捕える様に見える」
と述べています。
ゴッホは文学者としてもそれなりの作家になれたであろうと小林は評価しておりますが、ゴッホの場合、絵と手紙には共存的な関係があるようで、お互いが切磋琢磨して成長しているような、そんな存在となっていたと分析しています。これは、仕事と趣味との関係にも似ていますが、ゴッホは自己分析の人でありましたので、彼を知る(画家としてというよりも人間として)上では、手紙は貴重な情報を含んでいます。手紙を「告白」文とすると、私のこの徒然も、確かに告白的なものではありますが、ゴッホのように、無私の人間にはなりきれていないので、虚構が入ります。
ゴッホは、「僕は、自分に振られた狂人の役を、素直に受け容れようと思っている。丁度、ドガが公証人の役を演じた様に」「要するに、常に誠実である様に努力するのが、恐らく僕の病気を防ぐ唯一の道であろう」と述べておりますが、ゴッホは、自らの使命を意識していた人間で、その絵は、ミレーに大きく影響されているようです。貧しさ、悲しみを背負う不運、不幸に対峙する人々への限りない愛の溢れた絵がそこにありますが、最後に彼の死を看取った医者のガッシュは、「芸術に対するゴッホの愛というのは当たらない。それは信仰、殉教まで行った信仰だったと言うべきだ」と言っております。ゴッホの絵は、小林からすると、セザンヌもそうした面はあるが、違うのは、絵の仕事は人間ゴッホを呑み尽くすことが出来なかったと述べています。
ちなみに、小林は、ロシアの文豪トルストイの言葉「理想とは達する事の出来ぬものだ」を引用し、達せられるかもしれないような理想は、理想と呼ぶ価値はない、ゴッホはレンブラントに対する畏敬の念をもっていたが、レンブラントはスピノザの嫡子で、スピノザは「神を愛するものは、神から報酬を期待する事は出来ない」と述べているとして、スピノザ、レンブラント、トルストイ、ゴッホの4者に存する、無限なもの、究極のものへの飢渇の存在を指摘し、そうしたものへの渇望が絶えずゴッホを駆り立てていたのである、こういう類の大理想家達が、キリスト以来、例外なく、人間世界の鋭い、仮借ない観察家であったことは、興味あることであると、述べています。
神を愛する人は報酬を期待できないというのは、これは大変な覚悟になりますが、そうなると、神を愛せないから、そして理想を求めないから、私は駄目なんだと思ってしまいます。
小林は、ゴッホにとって、絵を描くということがどういう目的の為の手段であったかをゴッホ自身、明答出来なかったであろうけれども、目的とは、神から期待出来ない報酬だったのであろうかと自問しております。それは人生に何か報酬を期待して生きるのが良いのかどうかという哲学的な思考にもありますが、絵はどこかしら哲学的なものがあるでしょうし、本と同じで、作者からの解答はなく、それを見る人、読む人が解答を出す存在かもしれません。
「人生とは、実に呆れ返った実在だ。僕等は、みんな、こいつに向かって何処までも追い立てられる」として、手紙を書き、並行的に絵を描くゴッホでありますが、彼はアルル以降、黄色が顕著になります。我々には黄色に見えますが、何故彼が黄色を使ったかについてはまさに色々と言われております。黄色は黄金色ということのようで、「赤と緑によって人間の恐ろしい情熱を表そうとした」ということですが、ドラクロアによって、色彩に関する考え(「自然の色から出発するな。自分の色調の調和から、自分のパレットの色か出発せよ」)を触発されたゴッホは、色は光の分析によって現れるものではなく、内的な感情の動きに結びついた色が動揺するのであるという考えであったということです。そして「絵画における色彩とは、人生における狂気の様なものだ。これを番するのは並大抵のことではない」と述べています。
小林によれば、この色彩の狂気を抑え込むために、デッサンがあった、抑止効果的なものとしてあったと言うことのようで、デッサンが色彩という狂気の番人であったということです。セザンヌは、絵の制作の柱心観念を「感覚sensation」と呼んでいますが、ゴッホの場合は「感情」「情熱」と呼ぶものであろうとし、ゴッホの絵は、色とデッサンの格闘によるものであったと。小林は「ゴッホの手紙」を書くこと機縁となったゴッホの最後の絵の原画を後に見ることになります(1953年ゴッホの百年祭、ロッテルロにあるクレーラー・ミュラー美術館で)。かつて見た絵(1947年東京美術館「烏のいる麦畑」の複製画)は、複製であって、絵としてはむしろ複製画の方が良かったとしながらも、原画の色の生々しさは、堪え難いもので、これは絵でない、彼は表現しているというよりも、寧ろ破壊しているという感想を述べています。そして、レンブラントの自画像は、レンブラントが影の背後に身を潜めているであろうが、ゴッホが最後に描いた自画像は、明るい緑の焔の中にいる、彼自身が隠れる場所はもはや画面になかった、ゴッホは、未だ崩壊しない半分の理性をふるって自殺したのだと締めております。
確か西郷隆盛のことを無私の人と誰かが評していましたが、理想的であることは諸刃の剣というか、純粋しすぎることは周りにも迷惑であり、理解され難いものです。しかしながら、こうしたゴッホのような大理想家がいるからこそ、世界は前に進むことが出来る訳です。ゴルフで例えると、理想とは100を一度も切ったことのないヘボゴルファーが70台を夢みることとは本質的には違いますが、理想を抱かずに進歩はないでしょう。ゴッホを鏡とするかは別にして、実現の可能性が限りなくゼロに近い事に挑戦するのも、人生ではないかと思いますし、そういう人(パスカルもそうですね)を知り、学ぶのも大事なことだと思います。(了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
