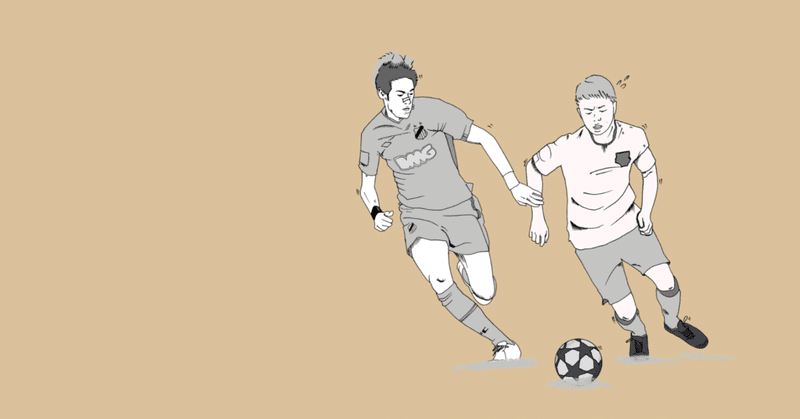
東大8年生、"外国籍選手"としてピッチに立つ
今回は、全国発売中の著書『東大8年生 自分時間の歩き方』(徳間書店)の未収録ストーリーをお届けするシリーズの第2回です。
メキシコ留学から帰国し、学生生活最終年の8年目を迎えながらも進路が定まらず悶々としていた中、YouTubeで初めて観たネイマールのドリブルに触発され、当時住んでいた寮で突然でボールを蹴り始めた上にブラジル移住まで志すようになったことは本書の中に詳しく書きました。この時、本格的にサッカーがやりたくなって大学内のあるサッカーチームに入ったことにも少しだけ触れましたが、その詳細を綴ったストーリーは収録しませんでした。
今回はその話をお届けします。お楽しみいただければ嬉しいです。
YouTubeで観たネイマールのプレーに受けた衝撃に導かれ、何年ぶりかも思い出せないくらい久しぶりに思い切りサッカーがしたくなった僕は、寮の狭い自室や廊下でドリブルしているだけでは満足できなくなり、どこかで本格的に練習や試合をしたいと思うようになっていた。そんなある日、同じ寮で暮らしていた大学の先輩ウギョンさんがサッカーのユニフォーム姿で食堂に現れたのを見て、彼が学内のサッカーサークルに入っていることを知った。サークルの名前を聞いてみたたころ、僕が入るのはちょっと難しそうな印象だったけれど、ダメ元で相談したところ、意外と普通に仲間に入れてもらえることになった。
こうして僕は、東京大学韓国人留学生会サッカー部の一員になった。
言うまでもなく韓国人でも留学生でもなかったのに、快く迎え入れてくれた皆さんには今でも感謝している。
ちなみに当時よく一緒に過ごしていた友人で在日韓国人の李くんも同じくサッカーをしたがっていたので、彼も誘って2人で入れてもらった。韓国人学生しかいなかった集団に、日本語ネイティブが同時に2人加わったことになる。とはいえ李くんは生まれ育ちこそ日本ながら、国籍とパスポートは韓国だったし、韓国への留学経験があって韓国語も話せた。なので結局、僕がこのチームにおける唯一の(そしておそらく初めての)完全なる「外国籍選手」ということになった。
もちろん考えようによっては本来、僕以外の皆さんの方が「外国籍」ということになるのだけれど、純粋にその場の状況的な話をすれば、誰がどう見ても僕の側がそれに当たるのは明らかだろう。練習でも試合でもピッチを飛び交っていたのは韓国語で、その場で唯一、僕だけがその共通語をほぼ理解できない状況だったのだから。事実、試合に出た時のハーフタイムでも、コーチの話を聞いて僕が拾えた単語は「洪明甫(ホン・ミョンボ)」と「カリスマ」の2つだけだった。(確かに時の洪明甫選手はカリスマ的存在だったなーと思って聞いていた)
ともかく、いずれにしても、自分の国にいるのに完全に一人だけ「外国人」という立場でコミュニティに加わった経験は、なかなか得難く貴重なもので、とにかく楽しかったし面白かった。
ほぼ全く韓国語ができなかった僕には皆さんいつも丁寧な日本語で話しかけてくれて、本当に有難かった。休みの日のサムギョプサルパーティーにも混ぜてもらったり、揃いのユニフォームも買って試合にも出させてもらったりと、一緒に楽しい時間を過ごさせてもらった。学内のグラウンド使用許可を勝ち取るために夜中のキャンパス内で一緒に順番待ちに並んだ時は、寒さの中、狭いテント内で身を寄せ合いながら互いの将来や両国のことなどを深く語り合ったりもした。
長い学生生活のわりに、いわゆるサークル活動にまともに参加した経験がほとんどなかったので、卒業を控えた在籍8年目という最後の最後で、思いがけず楽しい「キャンパスライフ」を過ごさせてもらった気分だった。
そんなやっと出会えたキャンパス内の居場所が「留学生サッカー部」だったというのも不思議な話だけれど、僕自身ある意味で鳥取という異郷からの留学生みたいなところもあったので、「他所から来た」という感覚が自然の前提になるような場が、かえって居心地が良かったのかもしれない。
(実際、各国出身の留学生の友人達の輪に入れてもらっていた時には、冗談で「トットリ共和国からの留学生」と呼ばれていた)。
こうして、思いがけず入団した「海外チーム」で、最初から最後まで楽しい時間を過ごさせてもらった。やがて大学卒業と同時にチームの活動から離れた僕はブラジルに渡り、当時ネイマールが所属していたサントスFCを飛び込みで訪問し、広報部スタッフの一員となる(詳しい経緯は本をご参照)。
それっぽく言えば、所属チームでの選手生活に区切りをつけて、別チームのフロントに入ったということになる。元々プロでも何でもない上、サッカーも生涯スポーツになると思っているので、「現役引退」という言葉は使わなかった。
改めて、韓国人でも留学生でもなかった僕を快く、そして温かく受け入れてくれたチームの皆さんには感謝している。
いつかまた、一緒にボールを蹴る機会のひとつでもあれば嬉しいなと思う。昔からやろうやろうと思いながら全然身につけられていない韓国語も、その時までにはさすがに何とかしておきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
