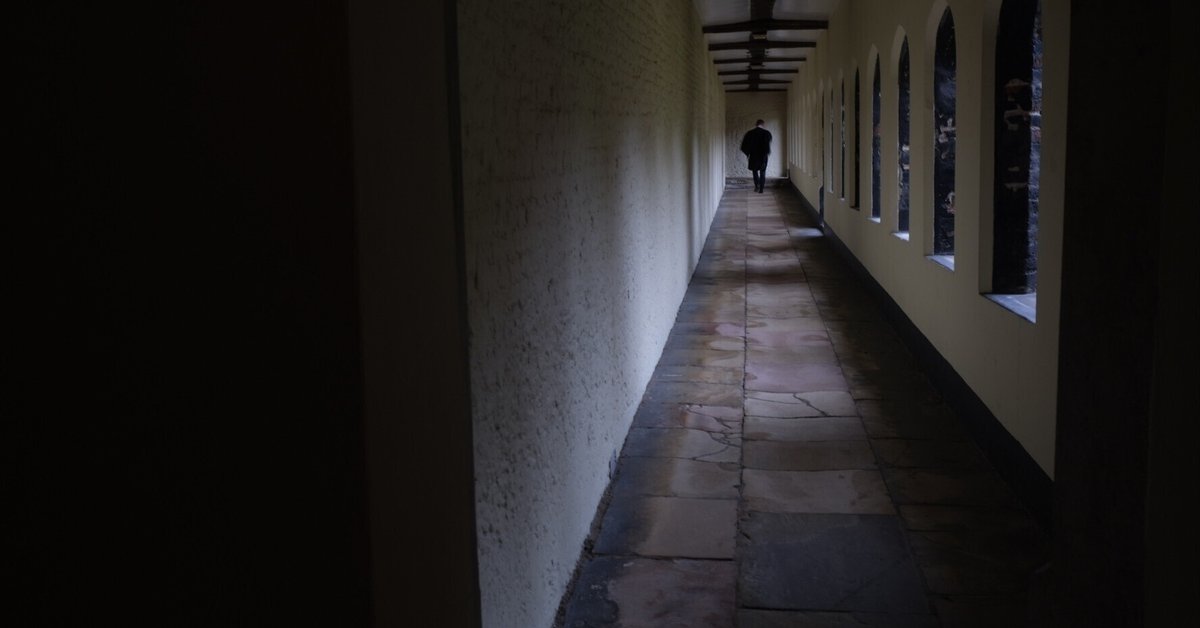
2年間の社会人生活から脱サラ院生への道
さて、2016年3月に大阪大学大学院を修了して(一応、研究科総代!)、4月から神戸に配属されて営業マンとしての仕事がはじまった。結果としてぼくの社会人生活は2年間だけだったのだけれども、まぁ体力的にも精神的にもなかなか鍛えられた2年間だった(=かなりキツかった)。ちなみに、大学院の最後の月に行きつけの美容院のおっちゃんが勢いで、アシンメトリーのツーブロックにしてしまい、左だけ刈り上げているというなかなか攻めた髪型での初出社。上司は僕のことをしばらく香港人だと思っていたらしいw
配属されたのは、交通インフラの海外営業の部署で主に東南アジアや南アジアを中心に事業を展開していた。実は後からわかるのだが、ここの部署はなかなか厳しい職場で、若手がどんどん辞めていく部署だった(ぼくもone of them)。ぼくが来る前も若手の人が辞めていき、ぼくが辞めた後もすっぽり若手が辞めたw この辺りの話はまた需要があれば別で書くことにするが、問題の所在は優秀すぎるプレイヤーがマネージャーになってしまったことに幾分か起因する気はしている。
入社してすぐにマレーシア・インドネシア担当になり、現地の道路事業者や官公庁とかによく営業にいった。日本ではJICAや開発コンサル、総合商社やNEXCO、国土交通省あたりがうちのステークホルダーだった。インフラの営業というのは、一般的に言われる営業とはかなりイメージが異なるものだった。いわゆる飛び込み営業とかはなく、外回りもなく、そして個人の営業目標とかも明確にはない。では営業は何をしているかというと基本的にお客さんに会うために月に1回くらいの頻度で海外へ出張する以外は、社内の調整業務が主な仕事。「お客様より社内」というのが弊社の(非公式しかし事実上の)モットーだったので、とにかく社内調整での能力がすごく求められる。仕事ができる人とは書類の決裁を早い人であり、誰もが納得できる文章を簡潔かつ明瞭に書ける人だった。
文章の書き方は日本語も英語も徹底的に叩き込まれた。ビジネスのライティングというのは、アカデミックのライティングとは全く性質が異なる。いかに簡潔かつ明瞭に1枚紙にまとめられるかというところに、営業担当は命をかけている。誰がこの書類を読むのかを想定したり、事前に根回しをしたりもしながら、美しい書類を作るのに一喜一憂するのがうちの営業マンだった。こう書くとすごくインテリっぽく聞こえはいいが、その反動で夜の飲み会は業界でも有名なほどやばい。
ということで、インフラの海外営業というのは、意外と地味な仕事が多い。もちろん海外出張もあるし、海外の政府高官や大臣向けにレターを書くみたいな謎の仕事もあったのだけれども、基本的に入社して数年はいかに良い文章を書けるかというところが重要視された。それ以外は大体社内調整。。こういう仕事を日本の厳しい上司とマレーシアにいる厳しくて偉〜い上司の間に挟まれながら進めていく2年間だった。
まぁ厳しいながらもいろんな経験をさせてもらった会社だったのだが、働いてみた結果、自分は調整業務というものがいまいち向いていないのと同時に、研究の方がよっぽど向いていることがわかり、大学院への「入院」生活へと戻る覚悟ができた。こうして、一旦阪大に出戻りになり、1年間をかけて海外博士留学に向けた研究計画書の作成に取りかかることになる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
