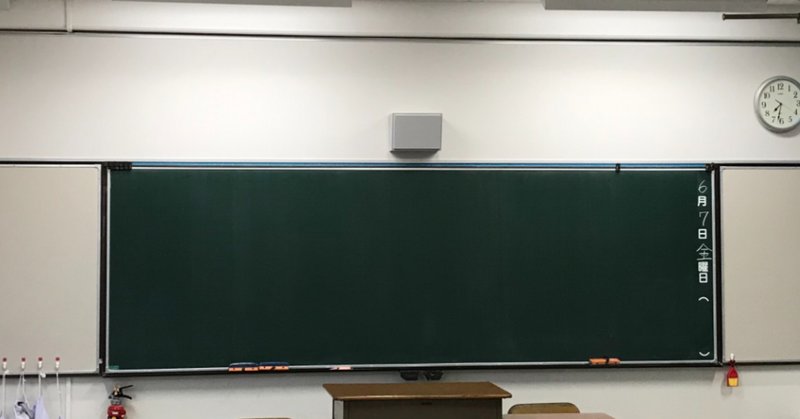
”非凡”な才能を持たなかったとしても、きっとできることはある
始まりは”非凡”な先輩に囲まれていたことだった
初任者のころ、私のまわりには素晴らしい先輩方がいらっしゃって、色々な話を聞かせてくださった。それこそこれまでの実践をお話して下さる方もいらっしゃれば、その時の私が躓いていることを見抜いてアドバイスをくださる方もいらっしゃった。私は特に、先輩方の”非凡”な実践の話を聞くのが好きで、いつかは自分もそんな素晴らしい実践がしたいと思ったものでした。
今思うと、その時に聞いていた実践というのは、誰にでも真似できるものではなかったように思います。それらの実践はそれぞれの先輩方の唯一無二のパーソナリティに基づいているものであって、取り立てて何の取り柄もなく、ただ教育の世界で生きていきたいと飛び込んできただけの自分とは、歩んできた道のりの深みが圧倒的に違ったのです。
ここでぶち当たったのが、「”大した人間ではない自分”に素晴らしい実践ができるのか?」という壁でした。教育を行う以上は、教員自身も素晴らしい人間性を持ち合わせているべきで、個性的なエピソードを語ることができなければいけないのだと、悩みました。結局私には、語るべき自分も、人に誇れるような長所も、まわりから突き抜ける実践を行う度胸も、勇気も持ち合わせていないのでした。勉強だけはそこそこ真面目にやって来てはいたものの、私よりも勉強ができる人間なんてそれこそいくらでもいるし、これまでの自分の歩いてきた道には何の価値があるのだろうと真剣に悩んだ時期でもありました。
初任校では訳も分からないまま3年間お世話になりました。教員としての基礎をつくるべき時期に、尊敬すべき先輩方に出会うことができ、その実践を間近で見ることができたことは、本当に幸運でした。私にとっては”教員としての故郷”ともいえる場所になりました。つらいこともあったし、きつかったことも沢山ありましたが、それらすべてが今の自分を形作っていると、今ならば胸を張って言うことができます。
”非凡”にも匹敵する自分の武器を発見
初めての転勤を経験します。現在もお世話になっている市=自分の出身地に帰ってくることができました。3年間の武者修行を終え、先輩方に背中を押してもらい「よく成長したな!!」と送り出してもらえたからか、すでに一人前気分でした。ところが初任校で通じたことが転勤した先では通用しませんでした。3年間曲がりなりにも卒業生を送り出し、「自分はそこそこやれるようになった」と根拠のない自信を持っていたのです。それが間違いの元でした。たった3年間、それも先輩方の厚いフォローがあってこそやれている気になっていただけであったことが、分かってきます。中々クラスの子達と打ち解けることができない。クラスに上がるのが憂鬱で、嫌だなと感じることが多くなっていきました。
そんな中で新しい出会いがありました。実は現在でもこっそりマネをさせていただいていることが多いのですが、新しい職場でも素晴らしい実践をしている先輩に出会うことができたのです。この先輩の学級経営の仕方を勉強できたことが、私にとって大きな転機となりました。
初任校で私を悩ませていた”非凡であること”について、一つの解答を示してくださったのです。それが”平凡”を突き詰めることでした。誰にも真似できない実践を行うのではなく、誰にでもできる”当たり前”のことに徹底してこだわることで、学級組織を創り上げていくという手法でした。
たとえば、下駄箱の履物を揃えさせることなどが挙げられます。学校の下駄箱というのは、上下二段になっており上の段には上履きを、下の段には下履きを入れるようになっているのですが、上段の方が狭く入れにくいのです。子どもたちは部活に急ぐ時や、下校の際には急いでいますからわざわざ上履きを上段に丁寧に入れたりはしないわけです。でも、少し注意すればだれでもできることです。それをクラスとして1学期の最初にこだわるのです。大抵は、学級開きの日にそんな話をすると、その日の下校時にはみんな気を付けて入れてくれます。そして、そこをすかさず学級通信に書くわけです。「まさか、初日からみんなができると思わなかった!」と。そして、上履きを上段に入れなければならない理由を書いてやります。(私は生徒たちに、外の汚れを校内に持ち込まないためだと説明します。下履きと同じところに入れると外の汚れが上履きについて校内に持ち込まれてしまう。そしてその汚れは自分ではない誰かが掃除をする事になる。自分のやった行動の結果を誰かに後始末をしてもらうのはカッコ悪くない?と問いかけてやるのです。)すると多くの場合、2日目の下校時にも子どもたちはちゃんとやってくれるのです。もちろんやってくれていない場合もあります。その場合は、やってくれている人の数を数えて、「期待していたよりも沢山の○○人の人がちゃんとしてくれていた!」と報告すればいいのです。そして、それを粘り強く言い続けることで、子どもたちの方が折れて全員ができる日が来るのです。そうなったときには、大げさに喜び一杯の学級通信にします。
以上の例は、私が最初に実践させていただいた、先輩の実践です。先輩のアドバイス通りに実践するとものすごく効果がありました。上履きを上段に入れて帰るくらい大した行いではありませんが、それをクラスみんなで実践するということで、クラスの始まりに弾みをつけられます。この成功体験が今の私の基礎をつくっています。つまり、”平凡な事でも突き詰めれば素晴らしいものになる”ということです。
”非凡”でなかったことに感謝!
私は今では、何かずば抜けた能力を持っていなかったことに感謝をしているほどです。確かに何かの天才的な才能があればもっと人生は違ったものになったかも知れません。でも、私が出会う生徒たちの多くは”非凡”な才能など持っていない子がほとんどだと思います。(どの子もかけがえのない存在であることは疑う余地はありませんが・・・。)私自身が平凡な能力しかもたず、その他大勢に埋もれてしまう道を歩んできたので、そんな自分でも”非凡”な人たちに負けず劣らず、何かを成すことができるのだと示すことができるなと思っています。たとえ”平凡”であったとしても、とことんまで突き詰めていけば、きっと”非凡”にも負けないことを成し遂げることができると信じられるようになってからは、随分楽になりました。特別な事を成し遂げられなくたって、素晴らしい実践ができなくたって、誰かのマネだってかまわないのです。まずは”当たり前のこと”を”当たり前に”できることが大切なのだと気づくことに気付かせていただいたことが、今もまだ教員として現場に立っていられる最大の要因かも知れません。本当に、感謝しかありません。
果たして自分なんかが書く文章を読んでくださる方がいらっしゃるのかは分かりませんが、もしも最後まで読んでいただいた方がいらっしゃったとしたら、ありがとうございます。自分自身の文章力の向上と、実践記録のために書いている文章なので、読みづらい部分も多いかと思います。ご指導いただければ幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
