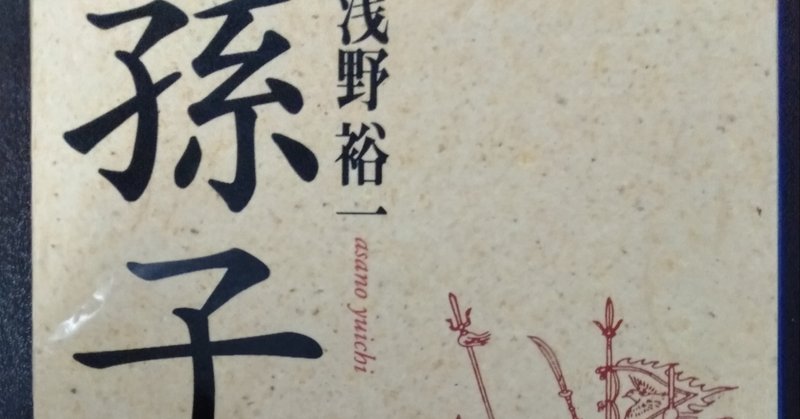
孫子の兵法を卓球にフル活用しよう! ③「謀攻」篇 ~戦わずに勝て~【後編】
③「謀攻」篇 ~戦わずに勝て~【前編】では、
「戦うな!」
「作戦で勝て!」
という話をしました。
今回は謀攻篇の後編です。
勝つために何をすべきか、知っておきましょう!
勝つためのポイントは5つ!
「勝を知るに五有り。」
勝利を得るのに5つの要点がある。
戦うべき時と戦うべきではない時を見極めること
攻撃すべきときと、そうでないときを、しっかりと分けましょう。
相手の返球をイメージできているときが、攻撃をするときです。
「バック前に横上を出すと、クロスにツッツキが浮いてくるから、回り込もう」
というように、相手の返球の癖を見抜くことで、攻撃が可能になります。
逆に、イメージができていないうちは、癖を探す作業をひたすらします。
「フォア前に巻き込みを出したら、クロスに返ってくるかなぁ?」
「順横サーブでバックサイドを切ったら、クロスに返ってくるかなぁ。」
「フォアにストップをしたら、バックにツッツキがくるかなぁ?」
「バックにフリックをしたら、クロスに繋いでくるかなぁ?」
など、とにかくいろいろ試して、イメージ通りになるものを見つけましょう。
大部隊と小部隊の任用、運用方法の違いを知ること
大部隊で攻めるのか。
小部隊を使って敵の目を別のところに向けさせるのか。
あるいは偵察をするのか。
兵の運用方法はいろいろあります。
卓球も、ひとつの技術に様々な運用方法があります。
例えば、バックハンドをストレートに打つとします。
「攻めるため」に打つのであれば、
まずは絶対にミスをしてはいけません。
その代わり、ミドル気味に多少コースが甘くなるのはオッケーです。
とにかくミスをしないことが優先で、その範囲内で強く打ちます。
これが、攻めるときに意識することです。
「相手にフォア側を意識させるため」に打つのであれば、
まずは絶対にコースが甘くなってはいけません。
ミドルに行ってしまえば、当然フォア側を意識させることはできません。
逆に、最悪ミスしてもオッケーです。
「フォア側を狙った」という事実は相手に残るので。
そして、必須ではありませんが、強く打った方が相手の印象に残るでしょう。
これが、相手の目を向けさせるときに意識することです。
「相手がフォア側をどう対応するのか確かめるため」に打つのであれば、
ミスは絶対に許されないし、コースがズレるのも許されません。
きっちりフォア側に打たないと、相手の対応を確認できません。
そして、強いボールを打つ必要は無く、多少甘くなってもオッケーです。
「あれ、甘いボールを送っちゃったのに、繋いできたぞ!?」
というのも立派な情報ですから。
これが、試合序盤で偵察するときに意識することです。
このように、その技術を使う目的によって、意識すべきことは変わります。
目的による運用方法の違いを知り、きっちり使い分けられるようになりましょう。
上下の情報共有と意思疎通ができていること
上司と部下の意思疎通ができていないといけません。
上司がちゃんと部下のことを把握しているかが問われます。
部下が足を負傷しているのに、
「敵陣まで走れー!」
なんて言っていたら、ブラック認定されてしまいます。
卓球も、あなた自身が、あなたの技術をちゃんと把握していないといけません。
「スマッシュを打てー!」
とあなたが叫んでも、そのボールをスマッシュするだけの技術力が無ければ、ミスをしてしまいます。
そのボールをスマッシュできるほど調子が良くなければ、ミスをしてしまいます。
同じミスが続いたら、あなたのスマッシュを見つめ直して、もっと確実性を重視して打つのか、あるいは打つのをやめるのか、何かしらの対策が必要になります。
このように、部下の状態に応じて作戦を立てるのが、上司の役目です。
「なんで入らないんだ!クソが!」
と怒りながら、闇雲にスマッシュを打ち続けていたら、ブラック認定されてしまいます。
事前の計画や段取りが周到で敵を待ち受ける準備ができていること
事前の計画とは、試合序盤での偵察のことです。
相手の癖を見つけましょう。
攻撃をするために必要だとは既に述べました。
ラリーや守備をするときも、相手の情報は必要です。
「ループドライブはバック側に来る」
「強打はクロスに来る」
「バックドライブをしたら回り込む」
「フォアドライブを打ったら、次はフォア側を待っている」
「こちらがドライブのバックスイングを取ると、相手は一歩下がる」
など、相手の傾向を掴めると、ラリーやブロックがやりやすくなります。
ブロックが得意な人は、敵を待ち受ける準備ができています。
敵が来るところに、先に現れるのです。
ブロックができない人は、敵がドライブを打ってから動き出します。
だから、ラケットを出した頃には、もうボールは後ろのフェンスに到達しているのです。
将軍が有能であって、君主が過剰な口出しをしないこと
選手自身が作戦を立てる能力があり、ベンチコーチは過剰にアドバイスを押し付けないように気を付けましょう。
まず、選手自身が頭を使えないといけません。
どんなにベンチコーチが優秀でも、アドバイスできるのはセット間とタイムアウト時のみ。
一球一球の組み立ては、状況に応じて選手自身で行わないといけません。
そして、ベンチコーチは自分の意見を押し付けてはいけません。
ベンチから見て感じることと、選手が現場で感じることは必ずしも一致しないからです。
「フォアドライブが全部フォア側に来てるから、それを待ってストレートにブロックしよう!」
とベンチコーチが言っても、選手が相手のドライブを嫌がっている可能性はあります。
嫌がっているのにこの作戦を実行したら、そりゃ失敗します。
ブロックできないんですから。
なので、
「あのドライブ、なんか合わないんスよー。」
と選手が言えるような風通しの良い関係性を、コーチが築く必要があります。
ベンチコーチは、現場の感覚をちゃんと考慮してあげましょう。
ベンチコーチが、
「相手のあのドライブ、さては取りづらいな!」
などと、現場の感覚を全て見通す神の眼を持っていれば最強ですが、そんな第六感持ちのベンチコーチはなかなかいません。
ベンチコーチの客観的な意見と、選手の主観的な意見を、話し合うことで上手に組み合わせましょう。
敵のことも自分のことも知りなさい!
「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」
敵の実情を知り、自分の実情も知っていれば、百回戦っても危険な状況にはならない。
孫子を代表する有名な言葉がここで出てきます。
相手と自分の実情を両方分かっていれば、最適な作戦を採れるので、何度戦っても危機的状況には陥りません。
自分はバックハンドが得意で、相手はバックハンドが苦手だと分かっていれば、バック対バックで勝負する。
こうやってベストな作戦を選択できるのです。
ただ、ここで孫子は「百戦殆うからず」と言っています。
「百戦百勝する」とまでは言っていません。
相手はバックハンドが苦手でも、球質が独特で、自分がそれに合わずにミスをしてしまう可能性もあります。
そういう相性の問題もありますし、あとは単純に、相手が明らかに強くて、有効な作戦が無い場合もあります。
なのであくまで「百戦殆うからず」としています。
彼を知らずして己を知らば、一勝一負す。
もし、自分の実情だけ分かっていて、相手の実情をよく分かっていなければ、勝ったり負けたりの五分五分になります。
自分はバックハンドが得意で、
「よっしゃ!バックハンドで攻めるぞー!」
と言っていても、相手の方がバックハンドが得意なら、厳しい戦いになります。
「おかしいなぁ。俺のバックハンドは、こんなもんじゃないはずだ!」
とか言って意気込んでも、勝つことは難しいです。
自分の方がバックハンドが強ければ勝つし、相手の方が強ければ負ける。
これはもはや卓球ではなく、確率50%のギャンブルです。
彼を知らず己を知らざれば、戦う毎に必ず殆うし。
自分の実情すら分かっていないと、何が起こるか分からず、戦うたびにピンチに陥ります。
たまたま勝つこともあるので「必ず負ける」とまでは言いませんが、良い戦い方では全くありません。
この「自分の実情」を知るのが意外と難しいんです。
「そんなの簡単じゃん!自分のことなんて、自分が一番よく分かってるよ!」
とか言っている人が危なかったりします。
人は、願望と事実がすり代わり、自分の実力を過信してしまうのです。
例えば、新しい技術が身に付き始めたときなんかは注意が必要です。
最近バックドライブを覚えたからといって、
「よっしゃー!バックドライブ食らわしてやるぜ!」
とか言って打ちまくると、大概は全く入りません。
これは、
「ちょっとだけ打てるようになった」
のが事実なのに、
「バックドライブが得意になった」
ような気がしてしまっているんです。
こうした過信が、大量のミスを生んでしまいます。
逆に、本当は得意なのに「得意じゃない」と思い込んでいると、大量の得点機会を失います。
本当はブロックが得意なのに、打たれることにビビってしまうのは、かなりもったいないです。
こういう損をしないためにも、
「己を知る」
ことは非常に重要です。
「そんなの簡単じゃん!自分のことなんて、自分が一番よく分かってるよ!」
なんて油断はせず、自分のことを冷静に慎重に客観的に分析しましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
