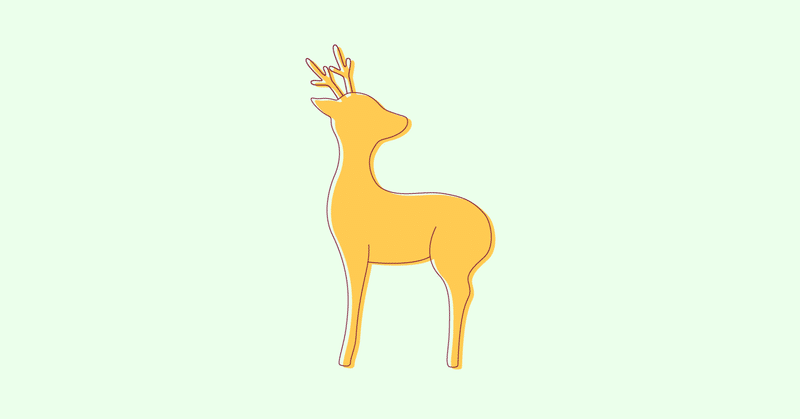
ジビエ料理の食レポは「臭みがあるかないか」しか語らない
どうも、ぺりかんです。こんにちは。
本日はmiyamiさんの「【透明世界】鹿」という作品をお借りしています。「ジビエ」に関してのおはなしをしようと思っていたので、ちょうどよいと思いまして。
ジビエ。フランス語ではgibierと書く。狩猟によって得られた野生鳥獣の肉を指す。シカやイノシシ、クマ、鳥類など多岐にわたる。
みなさんは鹿肉やイノシシ肉を食べたことはあるだろうか。ぼくは、ぼたん鍋はよく食べるし、実家に帰るたびに「鹿肉ビーフジャーキー」を自分用に買いだめしたりもする。ちょっと関係ないかもしれないが愛知県犬山市にある「リトルワールド」でワニ肉を食べたときの感動も忘れがたい。あれはさっぱりとした、魚で言えば白身魚のような軽やかさと、しっかりした歯ごたえが両立していて、本当に美味しかった。
ジビエについてテレビや雑誌で触れられる機会も、昔に比べればずっと増えた。とはいっても、15年前くらいからの動きだといえよう。背景には野生鳥獣による農林被害の深刻化が挙げられることはいうまでもない。安倍内閣によって鳥獣保護法が改正され、鳥獣捕獲事業者の認定制度が設けられたり、安全面が確保されれば夜間でも狩猟が認められるようになったりしたのは2014年のことだ(そこにおける「適正」「管理」のワードは興味深いものである。また、狩猟と鳥獣害対策をいっしょくたにしてしまうことも問題含みだったりする。このあたりについては、また別途掘り下げたい)。また、東日本大震災を契機にこれまでの自身の生活を見直そうとする動きが社会的に広がりを見せたことも、背景にあげられよう。
おおくは燃やされたり、埋められたりしていた「害獣」を食肉として価値づけていく動きも同時期のものだ。イノシシとシカ肉のレシピ集を作り、一般家庭におけるジビエ料理の消費を促そうとするような自治体規模の活動(たとえば下関市等5市からなる「県西部鳥獣被害広域対策協議会」)がはじまったり、害獣の食肉加工を行う「みのりの丘ジビエセンター」(豊田公園:下関市)が設立されたりした。
と、背景的な説明はこのあたりにして、話の本筋を書きたい。ぼくが違和感を抱いているのは、こうしたジビエ料理に対する「感想」の特定の言説化、ひらたく言うならば「食レポ」のあり方である。前々からずっと思ってはいたことなのだが、つい最近実家に帰省して久しぶりにテレビを見たときに偶然ジビエ料理の食レポを目にし、「いまでもこんな食レポをしているのか‥」とあきれたことで思い出した。
レポーターやタレントがジビエ料理を食べたときに何を言うか。これはほぼ決まっている。「臭みがない」ということである。いや、むしろそれしか説明されない。イノシシにせよシカにせよ、「○○肉を使っています」などと店員さんが説明し、それを聞いたレポーターはわざとらしく驚いてみせ、人によってはやや躊躇したそぶりをみせながら料理を口に運ぶ。そしてどうなるか。彼彼女はほぼ確実に、「臭みが全くないですね!」と驚き、店員さんかカメラに目線を向けるのだ。いつもこの流れだと言っていい。
臭みを処理することは、たしかに手のかかる作業だ。味付けや下処理に一工夫をしなければならない。一般的に食されている豚肉でさえ、酒を用いて臭みをとるひと手間を加えることはある。
それを差し引いたとしても、ジビエ料理の食肉化や専門料理店の普及が進んだ今日においてなお、料理の感想が「臭みが全くないですね!」だけというのはいかがなものなのだろうか、と思ってしまう。付け加えられる感想はせいぜい、「噛み応えがある」とか「肉肉しい」とか「味が濃い」とかであって、料理/調理の創意工夫やデザイン、食材のマリアージュに対するコメントがなされることはほとんどない。
臭みの磁場にとらわれているのである。臭みがあるかないかの二元論の枠組みでのみジビエ料理を語ってしまうこと/食してしまうことについて、そろそろ真面目に考えねばならないのではないか。食材の魅力をより豊かに語り、料理人の創意工夫をより適切に評価し、料理としてそれをより幸福に味わうために。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
