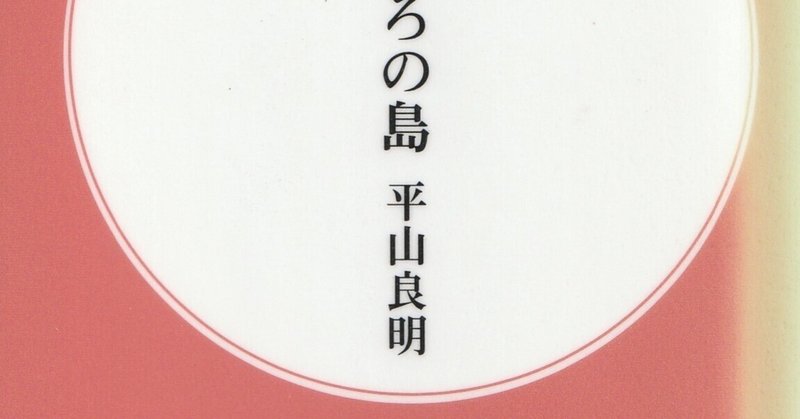
沖縄の短歌一首評③平山良明
人の世の深き悲しみくり返すあけもどろの花咲いわたる島
平山良明『歌集 あけもどろの島』《第一歌集文庫》令和三年二月
現在は沖縄短歌の重鎮である平山良明の代表歌(と思われる)歌です。簡明で難解な語もなく口誦にのりやすい短歌ではないでしょうか。
『歌集 あけもどろの島』は初版が1972年1月に刊行されました。この年5月15日に沖縄の本土復帰があります。文庫版あとがきによれば「二十代の作品が多い」といいます。年代的には1954~1963年、ちょうど昭和30年代となります。日本本土が高度経済成長へと向かう時期、アメリカの施政権下にある沖縄で生きる青年の熱情と、現状の不合理不条理への怒りと憤りを短詩へと昇華させようとする情熱を感じます。
十字架の接点に血は注がれてしたたり落ちるここは沖縄
「四月の炎」
死はかくも空しきものよB52頭上に飛ばして生ける群像
「悲しき民」
青空を手帳のひろさに書き写し心の憂さを飛ばしめん冬
「毒ガスの森」
それはまた人権と自治をもとめた沖縄に生きる人々の,時代への怒りの熱情でもありました。1970年代に青年期を過ごしたわたしにも平山の二十代の短歌は真直ぐに届きます。それはおそらく現代の沖縄にも届くものであり、沖縄を取り巻く状況は変わっていないのかもしれません。
そこに2021年に文庫版として復刻された意味があるのでしょう。
ただ、好みの問題かもしれませんが、30代以降とおもわれる後半の短歌群は読み込むのに少々疲れるものがあったことも、告白しておきます。
さて掲出歌です。おそらく二十代の作歌でしょう。初読の方が気になる「あけもどろの花~」について歌集中にも解説がありますが、ここでは外間守善先生の解説を引用します。
天に鳴響む大主
明けもどろの花の咲い渡り
あれよ 見れよ清らやよ
『おもろそうし』十三巻所収。太陽よ、明けもどろの花が咲き渡っていく。あれ、見ろ、美しいことよ。光が飛び散り炎が揺れて現れてくる太陽に、天地をどよもすような底鳴りの音が響き合っている。日の出の美観を讃えたオモロ。
ちなみに『おもろそうし』とは1531~1623年にかけて首里王府によって編纂された歌集です。ひどくあっさり言えば沖縄の『万葉集』といえるものです。
四方を海に囲まれている沖縄で境界の明確でなかった古代人にとっては、ソトから見れば小島であってもウチから見れば海原を抱く広い世界だったのではないか、そんな思いを感じさせます。
掲出歌において「深き悲しみくり返す」沖縄ですが、そこにはまた日々にあけもどろの希望の花が咲き続けているところです。いや、どの地に居ようとあけもどろの花は咲いわたっているはずです。二十代の平山良明は沖縄のウチから見る海と空の広さをソトへと、あけもどろの一片の花びらとなりえるかどうかを、自問しつつ沖縄で短歌を詠み続けたのではないか。
そのようなことを思わせる一首です。
拙作3首
懐かしきオキナワンロックの動画みる続く五十年目の憂鬱抱え
黒き雷身内にいだいて十七歳は復帰の夜抜けてライブハウスへ
身体ごとぶつかり踊るダンスフロアベトナム帰りの米兵は痛い
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
