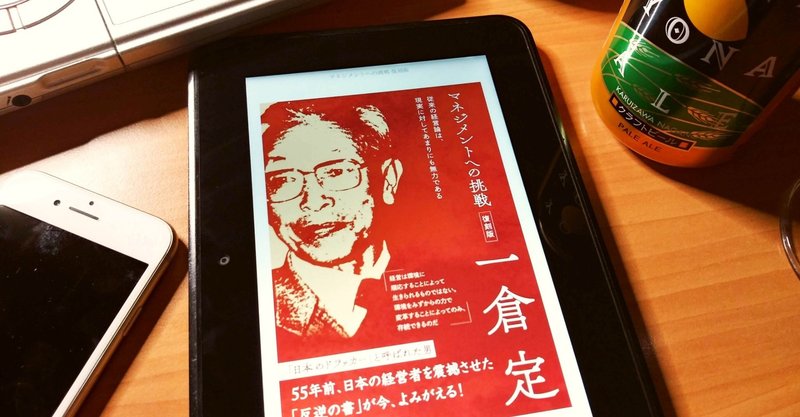
Back to Basics:一倉定「マネジメントへの挑戦」
父曰く:「ドラッカーなんか読んでたってしょうがない、当たり前のことしか書いてないじゃないか。」
基本に帰るのはときには大事だと思う。お父さんお母さんに叱ってもらおう、お爺さんに叱ってもらおう、というわけでもないだろうが、危機的な状況にあるとき、多くの人が思うことかもしれない。日本だけでなく、世界中の国々で政治が場当たり的対応ばかりで右往左往し混乱しているように感じられ、会社の経営も状況に振回されているように見え、そんな状況で、名著を復刻しようという動機も強かったのだろう。マネジメントの基本に帰ろう。
著者の一倉定(いちくら・さだむ)は、1918年生まれ、「社長の教祖」「日本のドラッカー」と呼ばれ、多くの経営者が支持し、指導した会社は大中小1万社ちかくに及ぶという。今から55年前の1965年に初版が出た著作を2020年6月に復刻した本書、なかなか評判だということで、読んでみた。
「序にかえて」とある最初の章は、次の文章で始まる。
これは挑戦の書であり、反逆の書である。ドロドロによごれた現実のなかで、汗と油とドロにまみれながら、真実を求めて苦しみもがいてきた一個の人間の、”きれい事のマネジメント論"への抗議なのである。
最近のスマートな語り口の翻訳本ばかり読んでいる人には少し刺激が強いかもしれない。
もう少し「序にかえて」から引用してみよう。
生きるための真剣勝負に、きれい事の公式論や観念論は通用しないのだ。(略)
自分で水にはいったこともない。おぼれた経験もない者が、果たしてマネジメントを云々する資格があるのだろうか。
(略)
そこにあるものは、空理空論であり、切っても血を噴かぬ死物である。その死物から出る毒が、われわれの精神をむしばみ、堕落させていく。
知識技術のみにおぼれ、枝葉末節のテクニックはもっともらしい。しかし、かんじんな精神を忘れ、魂ははいっていない。
マネジメントは、人間の行動の一つの指針である。人間に始まり、人間に終わる。従来のマネジメント論はその人間を忘れているのだ。いったい、なんのためのマネジメントなのだろうか。
これからのマネジメントは、しっかりと目標を見つめ、夢と希望をもちながら、きびしい現実に対処し、みにくさ、矛盾、混乱、その他いろいろの障害をのりこえていく勇気と知恵をあたえてくれるものでなければならないのだ。
このような序章のあと、1章から3章で、計画、実施、統制、それぞれのあるべき考え方や実践を説き、4章では、そのための組織のありかた・上司と部下のありようについて、5章で経営者の心構え、6章では財務の基礎を限界利益と付加価値から説き、7章では教育訓練、8章では人間関係について、そして9章で労務管理と賃金について、付加価値と賃金を一定の割合で連動させるラッカー・プランが紹介される。
資本主義の体制や仕組み、企業活動の根本が、当時から変わっているわけではないので、今でもコンセプトは通用すると思う。そして、いまだに私たちの大きな課題となっている生産性向上の議論などは、ここに書かれている以上の面倒なことは考える必要はないのではないか、と思った。
さて、マネジメントは経営管理という意味であり、「経営」を意識するか、「管理」を意識するかで大きくマネジメント論は異なるものとなり、人によって言うことが異なるのはよくある話である。本書では、マネジメントを経営として、社長・トップ・経営担当者がどう会社を経営すべきか、という視点で書かれていることに注意する必要があると思う。だから、単なる管理手法としてのマネジメント論に対しては、役に立たないうえ返って毒である、なぜならば、会社が生き残っていくためには、過去から現状の繰り返しを管理するだけではだめなのだ、と強く主張する。
そして、著者の熱い心は人間を見ている。批評家でも評論家でもない、なにより、その強い当事者意識だ。「マネジメントは人間に始まり、人間に終わる。」という言葉が美辞麗句でないことは、読むと伝わってくるだろう。

しかし、人によっては古臭く思えるかもしれない。サーバントリーダーシップ、自己組織化、マインドフルネス、といった方向に目が向いている人にとっては強い反発を感じるところが随所にあるかもしれない。
「マネジメントは人間に始まり、人間に終わる。」というなら、最新の行動科学の成果や情動の研究成果、脳科学、身体のリズムや食事など、そういったものが考慮されてしかるべきではないか、どこ読んだってそういう人間のことを科学的に書いてないじゃないか、結局は、人間を見ずに、トップが決めて部下が従う、オレンジ組織かアンバー組織だよね、今だにそんなこと言ってるの?そんなの古い、古い。変革はミドルマネジメントから、いやいや、これからは、トップもボトムもミドルもない、ティール組織さ。
などと思う人も多いかもしれない。
だが、一倉定が、「マネジメントへの挑戦」で対象にしているのは、主に、中小の企業であり、その経営者である。経営トップの夢を実現するために組織された会社が、いかに生きながらえるか、そのための経営手法を説いているのだ。
本書で書かれている言葉をつないでみると次のような感じだ。
会社は商品を生産し、または販売し、あるいはサービスを提供することが仕事であり、会社が倒産しないためには、少なくとも業界の成長率以上の成長率をもって事業を伸ばす以外に道はない。ということは、付加価値を生み出し、かつ大きくすること、生産性向上、これが企業の任務である。そのためには、革新的でかつ創造的なものが重要であり、過去に経験した標準的な事がらや、くり返し仕事は重要ではない。つまり、将来に向かって、高い目標を設定し、それを実現するために行動することが会社の活動の正しい姿であり、経営トップは常にそこに集中しなければならない。
すなわち「会社が”生き抜くため”には、不可能なものを可能なものに変質させること以外にないのだ。」
ということで、生き延びるためにどうするか、という執念、そこに役に立たない理論は無用である、というのが、随所に現れる「マネジメント論への挑戦・反逆」の主旨ではあるが、著者は単に批判するだけではない。一般論を展開して批評をするわけでもない。著者が対峙した事実と経験に基づいた理論や方法論を提示し、実践的である。

さて、考えてみれば当たり前のことだが、組織のありかた、私たちの働く現場のありよう、リーダーシップやフォロワーシップ、トップダウンかボトムアップ、あるいはミドルからの変革か、自由と規律、プロジェクト制か通常業務か、ラインかクロスファンクショナルチームか、etc etc.. 私たちが直面していることがらは、正解はない。自らの体格と体質、おかれた環境と、環境の変化、そういったことがらに応じて適不適は変わるもので、唯一究極の解はないだろう。
そういう意味では、本書を読んでも、今自分が直面している、個人個人の問題や、所属する組織の問題、社会の様々な課題の解決にすぐに役立つ処方箋が書いてあるわけではない。
しかし、大事なのは「うまくやる」手段 (*2) は必ずあるはずだ、と信じて追及して実践することだ。そのために、理論や概念は少なからず参考になるはずだ。わが社が生き延びるために、役に立たない理論はどうして役に立たないのか徹底して考え、役に立つ理論はどうあるかを導き適用する。役に立つ理論はとり入れる。一倉定の本書を読んで感じるのは、その執念と熱意だろう。
考え抜くとはどういうことか。私たちは、他者の成功事例に安易に飛びついてよしとしていないだろうか。ときには、統計、科学、哲学などといった言葉で簡単にだまされていないだろうか。早く何度も失敗することこそが、早く成功に結び付ける鍵である、とにかく回転を速くまわすことだ、などという言葉に甘えて安易に現実に妥協していないだろうか。逆に、理論や高い理想だけを振り回して、それに合わない不都合な現実を、安易に無視したり、批判するだけになっていないだろうか。
一寸先は闇、変化の激しい世の中で、会社が、国が、私が、”生き抜くため”には、不可能なものを可能なものに変質させること以外にないのだ。
「なんだ、当たり前のことしか書いてないじゃないか、そんなことを有難がって読んでいるようだから、世の中おかしくなるんだ。」
全編、父に、そして尊敬する会社の先輩方に叱られているような、そんな気がした。しかし、叱られたことで、良しとしてはいけない。叱られて人より賢くなったような気がしてたって、行動に結びつかなければ、そして、新らしい環境のもとで応用・発展させなければ意味がない。

Back to basics、困難なときこそ、当たり前の基本に帰るのがよいだろう。私たちはスマートなふりをしすぎているのかもしれない。
■ 補足
(*1) 冒頭でドラッカーを引き合いに出したが、一倉定は、「日本のドラッカー」と呼ばれ、実際、本書でもたびたびドラッカーの著作から引用しているし、一倉定の理論やノウハウの骨格には、ドラッカーがあることがよくわかる。それで思い出したのである。
(*2) このnoteを書き始めて、そもそもマネジメントってなんだったっけ、会社って何のためにあるんだっけ、経営と管理、リーダーシップ、組織や制度、働く意義や意味、動機、キャリア、人間の心理と行動、社会との関わり合い、いろいろ考えさせられた。結局、うまくまとめることができずにいて、モヤモヤしたので、私にとってのバイブル、中西晶の「マネジメントの心理学」にあたってみた。
世の中には、いろいろなマネジメント関連の本があってくらくらするけれど、この本にまとめられている大きな視点とこの100年の変遷の中で相対的に捉えなおすと、目の前の本が全てではなくなる。当たり前のことなのかもしれないけど。
まず、冒頭 1.1 が「マネジメントとは」とあり、その中の第一節が「マネジメントの歴史は人類の歴史」と題されている。
複数の人間が集まれば、集団や組織ができます。そうした組織や集団をうまく動かしていこうとする考え方や手法がマネジメントです。
第二節は、「マネジメントの基本」である。あまり長く引用するのはためらわれるが、上に書いたことがらを考え直すうえで、とても大事だと思うので、関連する部分をうまく抜き出してみたいと思う。
通常、「マネジメント」(management)は「経営管理」と訳されます。文脈によっては、「経営」の意味であったり、「管理」の意味であったりします。(略)
マネジメントの動詞形である「マネージ」(manage)は、「うまくやる」という意味です。1人では動かない大きな石もみんなが力を合わせれば動かすことができます。でも、1人ひとりがバラバラなことをやっているだけでは決してうまくいきません。「みんなでうまくやる」ためには何かが必要なのです。その「何か」こそが「マネジメント」であるといってもよいでしょう。
会社は、1人ではとてもできないことを、人を集めてできるようにする組織だ。別に行政組織だって、NGOだってNPOだってかまわない。集める人数は多いかもしれないし少ないかもしれない、1人の創業家の夢から始まったかもしれないし、何人かの問題意識を同じくする人たちの危機意識から始まるかもしれない。組織の社会的な意義や組織がおかれた環境も、組織の規模によっても異なるだろうし、時代や国によっても、大きくことなることになる。
また、マネジメントは「1人ひとりがバラバラに動く」のではなく「みんなでうまくやる」ための何かであるとするならば、マネジメントの対象は、組織を構成する人びとである。組織によっては近所の数人の集まりという場合もあるし、世界中の数万人もの人の場合もある。そして、それぞれ事情をかかえ、能力も異なり、感情を持つ人たちである。
力を合わせるためにどうするべきか、いろんなやり方があるだろう。しかし、間違いないのは、集まった多様な人の力を合わせるためにすべきこと、考えることは、人間に始まり人間に終わるということだ。
なんだ、当たり前じゃないですか。
しかし、みんなで力を合わせるために、より効果的な方法はないだろうか、と古今東西の理論と概念を学び、最新の科学の成果を調べ、としているうちに、学んだことや調べたことが第一になってしまい、さらには新しい発見をしたと思いこめば、それを売りこむのに必死になってしまい、人間を忘れ、そんな当たり前のことを忘れてしまう。多くのマネジメント論や経営論、組織論などで目にとまることである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
