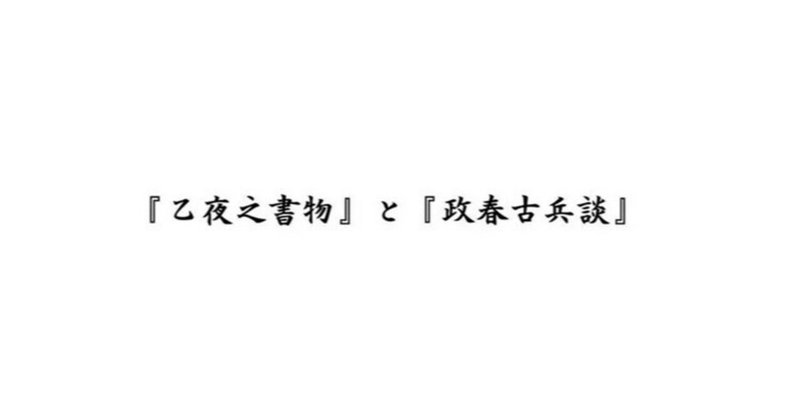
『乙夜之書物』にみる「本能寺の変」

■『乙夜之書物』(上)95条 ※Recoの翻刻
一、天正拾年の春より、中国毛利家為退治、羽柴筑前守秀吉、備中の国ゑ発向して、同国高松の城をかこむ。為後巻と、毛利右馬輝元五万余騎にて出張して秀吉に対陣す。依是、為加勢、惟任日向守光秀可下向旨被仰出、信長公も頓て御出勢可在と也。又、四国為退治と三七信孝を大将として織田七兵衛信澄、長岡越中守、筒井順慶、丹羽五郎左衛門、堀久太郎、池田勝入、以下各先、大坂迄下向す。然所に、日向守光秀、むほんを企、六月朔日、居城丹波の国亀山を打立、中国発向とひろうして数を亀山ゑあつむる。斎藤内蔵助は、同国笹山の城に居す。朔日の昼時分に亀山ゑ着す。其間、光秀、内蔵助を待兼、今や\/と云。昼時分に内蔵助まいりたると云。光秀、色代まて出むかい、内蔵助か手を執(『異聞 本能寺の変』では「取」)て奥ゑ入る。其外、侍大将同道在り。何も数奇屋ゑはいりて、光秀、座上に居て、各ぬむかい、しばし目をふさぎ、大息をつぎ、「我等は気がちがいたるは」と云。各きやうさめ、気はづんだり。其時、「むほんなるは」と云。内蔵助云。「唯今迄御延引なり御先は、我等可仕」と云。残る衆は、是に同ず。光秀、「扨は満足なり左馬助」といわれけれは、勝手の口に居たると見ゑて、数寄屋の内ゑはいる。「各同心なるは」と云。左馬助、「目出度奉存」と云。「扨、何もあつきに、何そ」といゑは、道明寺をひやして出し。其後、光秀、「左馬助、ソレ\/」といわれければ、硯箱に料紙と熊野の午玉を出す。各血判すみて、亀山の城を朔日の暮前に立て、大井の山を打越て、夜中に掛、桂川に至り、諸軍を「川原に座備て、兵粮つかゑ」と云。各、心得ぬ事哉。亀山を出て、やう\/三里斗(『異聞 本能寺の変』では「計」)来りて、「何事ぞ」と思いながら竹葉つかいける所に、物頭とも乗廻し、「本能寺ゑ執(『異聞 本能寺の変』では「取」)かくるぞ。各其心得可仕」と云。諸軍ふるいたるとなり。扨、本能寺ゑは、明知弥平次、斎藤内蔵、人数弐千余き指むけ、光秀は鳥羽にひかゑたり。
【現代語訳】
Reco
https://note.com/sz2020/n/n877e987204af
萩原大輔『異聞 本能寺の変』pp.43-44
菅野俊輔『真相解明「本能寺の変」』pp.64-65,68-69,70-71
■『乙夜之書物』(上)96条 ※Recoの翻刻
一、明知弥平次、斎藤内蔵助、弐千余騎にて本能寺ゑ押寄たれば、早、夜は、ほのぼのと明にけり。内より水吸の下郎、水桶をにない出けるが、敵の押寄たる体を見て、内ゑにけこみ、門を立る。「あの門たてさするな」とて押詰、門を打やぶり乱入る。当番の衆、「是は何事ぞ」とをきふためき、はしり出て見ければ、敵、早、門内ゑ込入たり。各、鑓を執(『異聞 本能寺の変』では「取」)て縁の上下にて攻合。信長公、白き御帷子をめし、みだれがみにて出させたまい、御弓にて庭の敵をさし取引つめ射たまう。御弓のつるきれたりと見ゑて、御弓をなけすてたまい、十文字の鑓を執(『異聞 本能寺の変』では「取」)て、せり合たまう。然所に御手を負はれたりと見ゑて、白き御帷子に血かヽって見ゆる。御鑓、御すて、奥ゑ御入、ほどなく奥の方より焼出たり。
【現代語訳】
萩原大輔『異聞 本能寺の変』p.62
菅野俊輔『真相解明「本能寺の変」』pp.74-76
■『乙夜之書物』(上)97条 ※Recoの翻刻
一、御番衆、ずいぶん働といゑとも、をもいよらぬ事なれば、何(いずれ)もすはだにて、わつかの人数。敵は具足、甲を着、弓、鑓、鉄炮備て大勢攻め込む。終に縁の上ゑをいあげ、つき伏、切り伏、首を執(『異聞 本能寺の変』では「取」)る。去とも、何としても首、不落、其時、可児才蔵、「下は板敷なるぞ。手をさげてすれ」と云ければ、何も早すり落したり。
右三ケ条、斎藤佐渡守殿物語の由、井上清左衛門語る。斎藤佐渡守殿は内蔵助子息、清左衛門は、内蔵助孫、佐渡守殿をいなり。
【現代語訳】
Reco
https://note.com/sz2020/n/n07a36ed2bb12
萩原大輔『異聞 本能寺の変』pp.62-63
菅野俊輔『真相解明「本能寺の変」』p.76
--------------------------------------------------------------------------------------
萩原大輔氏の翻刻とRecoの翻刻との違いは、
●「とる」は、「取る」か「執る」か。
●「ばかり」は、「計」か「斗」か。
だけ。
現代語訳の違いは、ほとんどない。あっても、文法的なことではなく、単語の意味の違いである。たとえば、95条で言えば、「色代」「道明寺」の解釈である。
●「光秀、色代まて出むかい、内蔵助か手を執て奥ゑ入る」
・(玄関の)式台まで出迎えて(菅野訳)
・出入り口まで出迎え(萩原訳)
・敷台(控えの間)まで迎えに行き(Reco訳)
※「手を取って」を「手を執って」と書く、「しきだい」を「色代」と書くのは、誤字というより、関屋政春の癖であろう。(ちなみに、「色代」とは「挨拶」のことであり、「色代なく」であれば、「挨拶を交わすこと無く(急いで、慌ただしく)」の意となる。)
明智光秀は、「斉藤利三が到着した」と聞いて出迎えに向ったのであって、斉藤利三がまだ玄関(色代=式台)にいたとは考えにくい。それに、「式台まで出迎え」を「玄関先に設けた板敷きの部分まで出迎え」と訳すのには無理があろう。もしそうであれば、「式台まで出迎え」ではなく、「玄関まで出迎え」と書くと思う。
斉藤利三は既に控え室(色代=敷台)に入っていたと思われる。明智光秀が控え室まで斉藤利三を迎えに行き、手を取って奥へ(数奇屋の方へ)連れて行くと、控え室にいた侍大将たちも後をついて数寄屋に向ったのであろう。
※しきだい
①【式台】玄関先に設けた板敷きの部分。
②【敷台】武家屋敷で、表座敷に接続し、家来の控える部屋。
③【色代】挨拶すること。
※式台:式台とは玄関の土間と床の段差が大きい場合に設置される板のこと。
式台の由来は武家屋敷にて、来客者が地面に降りることなく、 かごに乗れるように設けられた板の間でした。
https://polaris-hs.jp/zisyo_syosai/shikidai.html
●「道明寺をひやして出し」
・菅野訳:(左馬助は、用意してあった)道明寺(道明寺粉製の茶菓)を冷やして出した。
・萩原訳:(左馬助は)道明寺(粉を溶いた水)を冷やして出した。
・Reco訳:「道明寺」を冷やして出した。
明智光秀が「何か冷たい物はないか?」と言うと、明智左馬助は道明寺を冷やして出した。「道明寺」が何か分からないが、冷たい物でなければならない。
「道明寺」は、本来は「干し飯」(道明寺糒)であるが、後に道明寺粉=「新引粉(しんびきこ)」を指すようになった。現在、「道明寺」と聞けば「道明寺桜餅」が思い浮かぶ。場所が数寄屋(茶室)だけに、お茶菓子としての「道明寺桜餅」かもしれないが、「道明寺桜餅」は江戸時代に初めて作られたという。
※道明寺桜餅の「歴史や由来」
道明寺桜餅は、大阪にある道明寺が由来。江戸時代に道明寺で、もち米を水に浸しておき、これを蒸しあげて乾燥させ、粗く挽いた「道明寺粉」が作られました。江戸の桜餅の方が先にできたといわれていますが、それが関西地方に広まる前に、この道明寺粉を使った道明寺桜餅が、関西の人々の間に定着したと考えられています。
https://precious.jp/articles/-/17400
ここでいう「道明寺」の可能性としては、
①道明寺粉を溶いた水(萩原訳)
②道明寺粉製の茶菓(菅野訳)
③道明寺羹(Reco説)
があろう。
①私なら、「道明寺粉を溶いた水」ではなく、ストレートに井戸水とか、冷水を出すな。それに「道明寺粉を溶いた水」が出された時、「道明寺が出された」と書くだろうか? 私なら「水が出された」と書くよ。
②たとえば「道明寺桜餅」が出された時、「道明寺が出された」と書くだろうか? 私なら「桜餅が出された」と書くよ。それに和菓子を食べたら喉が渇かない?
③「道明寺が出された」と書くからには、
・一目で道明寺と分かる物
・「道明寺」と表現する以外に代替語(水、桜餅など)の無い物
・冷たく冷やすことが出来る物
が出されたのでは?
「冷たい物」といえば、蕨粉(蕨の根)で作った「蕨餅」とか、葛粉(葛の根)で作った「くずきり」、「心太(心天)」に「寒天」が思い浮かぶ。ここでは、「道明寺羹(みぞれ羹)」を作って冷しておいた物を出したのではないかと思う。
※「道明寺羹の作り方」
https://ws-plan.com/wagasi/kanntenn/domyojikan.html
※道明寺あれこれ
https://ukishimania.net/aboutdomyojiko/
※道明寺公式サイト
http://www.domyoji.jp/
逐語訳は難しい。
本なんて、その場の雰囲気が分かればいいんですよね。斉藤利三が到着すると、「待ってました!」と、明智光秀は、近習に「ここへ連れてこい」と指示するのではなく、自ら出迎えに行ったとか、暑かったので、冷たい物を出させたとか、その場の雰囲気が分かれば十分かと。
【解説】
『乙夜之書物』は、著者・関屋政春の「体験談」ではなく、「聞き書き」であるので、
・語り手の記憶間違いがある。
・関屋政春の記録間違いがある。
・語り手の解釈や、自分の祖先を誇る誇張が加えられている。
可能性がある。
95条に関していえば、大坂にいた四国遠征軍(長宗我部征伐軍)を「織田信孝を大将として、織田信澄、長岡忠興、筒井順慶、丹羽長秀、堀秀政、池田恒興」としているが、通説では、長岡忠興は丹後国、筒井順慶は大和国におり、堀秀政は既に備中国に遣わされていたとする。また、斉藤利三の居城は笹山城ではなく黒井城である。通説=史実とは限らないが、『乙夜之書物』は「聞き書き」であるので、上の3つの理由から「記述内容は100%史実である」とは考えられない。
とはいえ、「『乙夜之書物』には細かなミスはあっても、大きなミスはない」と思われ、明智光秀の決意表明は、伝承のように「篠村八幡宮」ではなく、「亀山城の数奇屋」で間違いないと思う。「篠村八幡宮」では、兵の集り具合を見て、複数に分けたり、進軍ルートを確認したりしたのであろう。
【95-97条の語り手・井上清左衛門重成】
斎藤内蔵助利三┬長男:斎藤利康
├次男:斎藤甚平
├三男:斎藤伊豆守利宗→斎藤佐渡守利光
├女子:柴田源左衛門勝定前室(享年23)
├四男:稲葉出雲守
├五男:斎藤与惣右衛門→斎藤助右衛門三存
├六男:斎藤七兵衛
├女子:柴田源左衛門勝定後室・寿院(享年65)
└女子:福(春日局) ├女子
柴田源左衛門勝定 ├井上清左衛門重成(重盛)
井上兵左衛門
「右三ケ条、斎藤佐渡守殿物語の由、井上清左衛門語る。斎藤佐渡守殿は内蔵助子息、清左衛門は、内蔵助孫、佐渡守殿をいなり」(以上の3ヶ条(95&96&97条)は、斎藤佐渡守利光が語った話を聞いた井上清左衛門が、私(関屋政春)に語った話である。話をした斎藤佐渡守利光は、斎藤内蔵助利三の子(三男)である。それを私に話した井上清左衛門重成は、斎藤内蔵助利三の孫で、斎藤佐渡守利光の甥である)とある。
しかし、系図によれば、井上清左衛門重成は、斎藤内蔵助利三の孫娘の子で、斎藤佐渡守利光の妹の孫(姪の子)である。自分に話をしてくれた人の素性を知らないとは・・・作り話ではないとすると、系図が間違っているのか?
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
