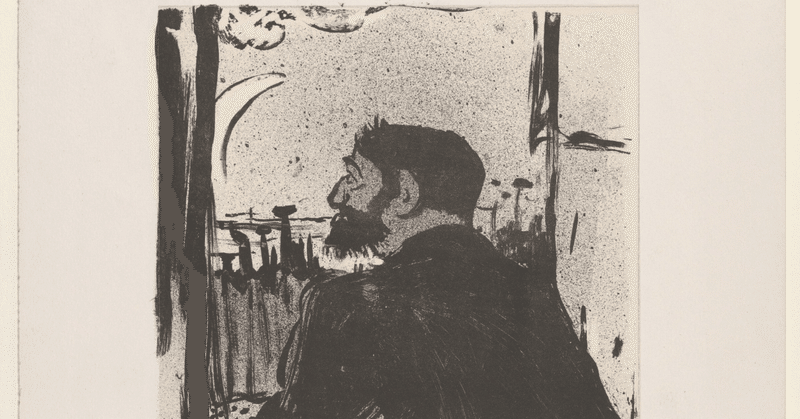
綾波レイ問答法、略してレイ問答
今から語ってゆくことは、映画「シン・エヴァンゲリオン劇場版𝄇」のネタバレを含んでいるのみならず真剣な戯言という奇々怪々な内容なので、くれぐれもご注意ねがいます。
また私は、「綾波レイ推し」「LRS<Love(×2) Rei Shinji>」と「綾波主義者」は若干ながら異なる派閥だと考えており、その中で私は「アヤナミスト」だと自認しています。
ですので、なるべく公平なる判断に基づいて、今回このことについて語っていきたいのですが、不偏不党とはやはり言い難いところも多々あると思いますので、その点もどうぞご了承ください。
綾波レイ問答法とは
さて、「このこと」とは、すなわち、題名にもある『綾波レイ問答法(略:レイ問答)』のことです。
シンエヴァを既にご視聴なさった方であれば、「そっくりさん」と題されるアヤナミレイが、以下のように様々なことを尋ねているシーンをよく記憶に残っている事と思います。
仕事って、何?
Twitterでは一部、構文と化しつつあるこの問いかけの仕方を、私は「レイ問答」と呼びたいのであり、さらには、私も含め、実践を視野に入れた一つの哲学的手法として再認識していきたいのです。
参考①ソクラテス
一般的に、「問答法」という用語を用いれば、それはソクラテスが古代ギリシアで行っていた哲学対話の手法を指していることが多いです。
これは、対話を重ね、相手の答えに含まれる矛盾を指摘して相手に無知を自覚させることにより、真理の認識に導く方法であり、「産婆術」という別名もあります。
しかしながら、この手法は言ってしまえば「質問を質問で返す」ようなものでもあり、私たちの現代感覚同様に、古代ギリシア社会の知識人たちの間でも問題となり、ソクラテスは「若者たちをたぶらかした」として死刑となりました。

参考②禅問答
こちらはお察しかと思われますが、略称である「レイ問答」の語呂の元ネタでもあります。
禅問答とは、座禅と同じように、禅の代表的な修行法の一つで、修行者が疑問を問い、師匠がこれに答えるというものです。
またそのことから現代では、わかったようなわからないようなやりとりや、かみあわない問答などにたとえていうこともあります。

禅語よろしく、各エピソードはなるほど含蓄に富んでおり、いろいろとみてみるのは面白いですが、いかんせん修行の一環ですので、禅僧ではない私たちが自分の身に置き換えてみると「わかったような、わからないような・・・」となることも少なくないです。
参考③デカルト・方法的懐疑
われ思う、ゆえに我あり。byデカルト
方法的懐疑とは、デカルト哲学の根底をなす方法で、少しでも疑いうるものはすべて偽りとみなしたうえで、まったく疑いえない絶対に確実なものが残らないかどうかを探る態度のことです。
重要なのは、すべてを偽りとしてから考える「懐疑論」とはまた一風異なる点でしょう。
デカルトはそうした方法によって、上記の考えに至ったのです。

再び「レイ問答」を問答する
このように、問答形式の哲学的手法は様々な時代で用いられてきました。
そしてこの三つには、それぞれの目的がまず第一にありました。
まずはソクラテス。
彼の弟子が、アポロンの神託所において、巫女に「ソクラテス以上の賢者はあるか」と尋ねてみたところ、「ソクラテス以上の賢者は一人もない」と答えられたことから全ては始まりました。
これを聞いたソクラテスは驚き、それが何を意味するのか自問しました。
さんざん悩んだ挙句、彼はその神託の反証を試みようと考え、世間で評判の賢者たちに会って問答することで、その人々が自分より賢明であることを明らかにして神託を反証するつもりでした。
しかし、実際に賢者と呼ばれる者(ソフィスト)と会って話してみると、彼らは自ら語っていることをよく理解しておらず、そのことを彼らに説明するはめになってしまいました。
こうした経験を経て、彼は神託の意味を“無知の知”であると解釈し、問答によって、各々の無知を悟らせていったのです。
次に禅問答は、このような長い説明は不要ですよね。つまり、禅宗における悟りのためです。デカルトも真理への到達という同様のものでした。
ではレイ問答は。
彼女は言葉を知ることによって、それまで以上に“自分らしく生きる”こととなりました。
それ以前は「そっくりさん」という名称からも分かるように、既に与えられていた「綾波レイ」の影を追っていました。しかし、第三村において、一つ一つを尋ね聞くことによって、ようやくそれを用いるか否かについて検討することが可能となったのです。
したがってレイ問答は、「零」の立場(無知・白紙)からすべてを尋ね、そして知ることで、ようやくそれらを理解し、実生活・実社会において用いることが可能となるという術であり主張なのです。
ソクラテスのように論破的なものでもなく、禅問答のように人によっては不可解な言葉の世界に迷い込むこともなく、努力の結果デカルトに勝るとも劣らない頭脳の持ち主のみが到達し得るものでもありません。
まさしくなぜなぜ期・命名期の自分がそうしていたように、素直に世界を問い直す。これが哲学への初歩であるのではないでしょうか。
綾波レイはそう私たちに囁いてくれたように感じます(?)
よろしければサポートお願いします!
