
再エネ発電、“植民地化”排する住民と経営者の矜持
※この記事は過去にシン・エナジーの公式ブログ「ミラトモ!」に公開された2019年7月の記事の再掲です。内容はすべて当時のものです
一般社団法人日本サステイナブルコミュニティ協会は2019年7月2~3日、岐阜県高山市の奥飛騨温泉郷の奥飛騨総合文化センターなどで「奥飛騨・高山フォーラム&ツアー」という催しを開催した。名古屋からJR特急「ひだ」で高山駅まで2時間20分、そこからバスを乗り継いで1時間余りのところだ。
奥飛騨温泉郷には、同協会の正会員であるシン・エナジーが地域の企業などと一体となって開設した発電所がある。地熱利用のバイナリー発電所が1カ所、木質バイオマス発電所が1カ所、さらに開設準備中のバイナリー発電所が1カ所と小水力発電所が3カ所ある。発電方式が異なる3種の再生可能エネルギー発電所が同じ地区に集積し、発電だけでなく熱も使って新しい産業の育成と地域創生を目指している点で、全国から注目されている地域である。事実、東京や大阪からも参加者が相次いだ。現地で再生可能エネルギーの将来性を肌で感じたい、との思いからだ。
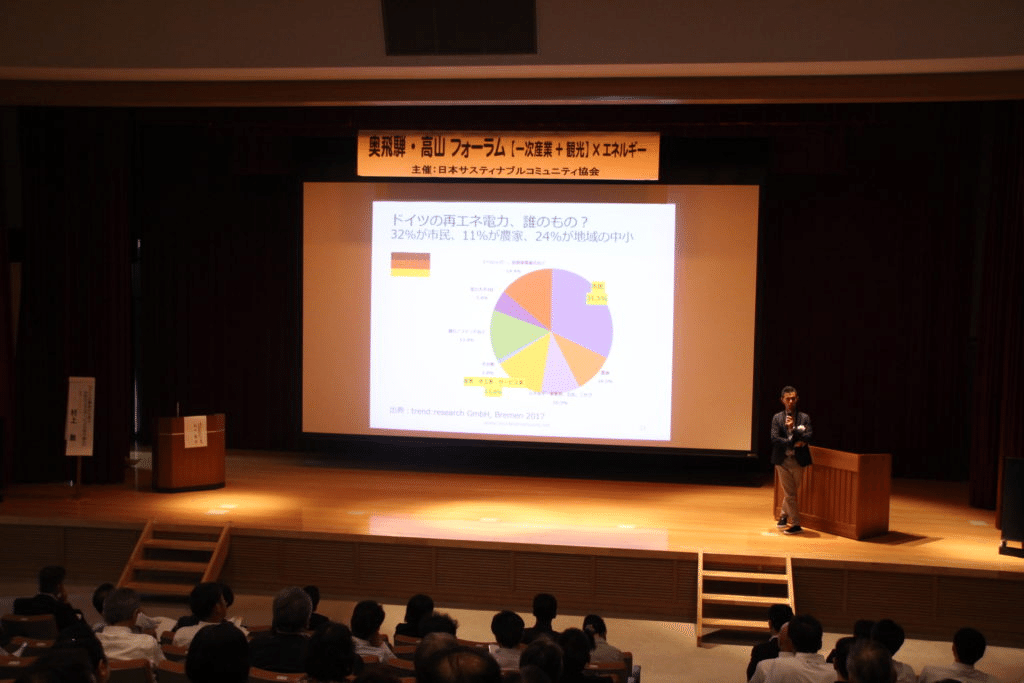

イベント初日に奥飛騨総合文化センターで開催されたフォーラムでは中部経済産業局の岩田則子・資源エネルギー環境部長と、高山市出身でドイツを中心に環境ジャーナリスト・コンサルタントとして活躍する村上敦さんが基調講演を行った。
村上さんの講演が強烈だった。「再生可能エネルギーは地熱や木材、水といった地域の資源を使った発電方式。都市部から来ている企業の“植民地”になってはいけない。植民地になれば収益が出ても大半は域外に流出する。そうさせないためにはその再エネ会社に地元からみんなが出資して、社員も地元から送り込んで技術も含めて地域の物にする必要がある」。
確かに資源にしろ、人材にしろ、都市部の資本力に吸引されながら地方の町や村はどんどん再生力を失っていった。このまま進んだら、自治体が消滅していくのは時間の問題かも知れない。
村上さんの「植民地になるな」という言葉は、その危機感を関係する行政や企業、住民がもっと自覚すべきではないか、と鋭く突き付けてきたものだった。
しかし、この奥飛騨の開発事例はそうした問題意識は杞憂だったかもしれない。早くから問題を意識し、地域との共存共栄を企業が目指していたのだ。シン・エナジーと地元の企業や住民が協力して同地域に設立した奥飛騨水力発電株式会社の清水満氏は、事例紹介資料の最初のところで「(当社は)適正ルールを遵守した水力開発を推進することで乱開発を防止するとともに『植民地型開発』から地域のための『地域貢献型開発』への転換を図りたいと考えております」と明確に地域との連携を宣言していた。
さらにフォーラムの後半に開かれたパネルディスカッションでは、「飛騨高山しぶきの湯バイオマス発電所」を運営する谷渕庸次・飛騨高山グリーンヒート合同会社社長が「当社の資本は地元資本が7割です。人材も地元を中心に雇い、発電機等の整備は自分たちでできるようにしました」と、設立当初から地元優先の自立型経営方針を取ってきたと胸を張った。
地域との信頼関係を築くのは一朝一夕にはできない。人と人との地道な付き合いがあって初めて成り立つ。フォーラムの事務局を務める地元関係者が住民の方などに参加を呼び掛けてくれたことが功を奏して、会場となった奥飛騨総合文化センターには130人もの方が当日参加してくれた。
その事務局の方々は、協会から頼まれたからではなく受付や会場整理、講師応対等に、自分たちの仕事として進んで取り組んでいた。
**********************
フォーラムの翌日、「奥飛騨・高山ツアー」という名称で現地を見学した。温泉を生かした錦鯉やスッポンの養殖場、そしてゴーという大きな音を出しながら勢いよく蒸気を噴き出す奥飛騨第2バイナリー発電所建設予定地、自然公園の景観を生かしながら発電する安房谷小水力発電所予定地など7カ所を訪問。蒸気は発電所が、温泉は地元に還元という共存共栄の姿に、地域創生のあるべき姿の一端を見ることができた。

 ■錦鯉の養殖場(上)、奥飛騨第2バイナリー発電所予定地(下)
■錦鯉の養殖場(上)、奥飛騨第2バイナリー発電所予定地(下)
地域の再生という日本の前途に立ちはだかる難しい問題は、外部の資本や技術をいたずらに排除するのではなく、それを地域に取り込んでしまう住民意識の向上と地域重視の姿勢を取る経営者の矜持が解決のカギを握っていると感じた。
(2019/7/18 シン・エナジー広報/元日本経済新聞記者 府川浩・記)
