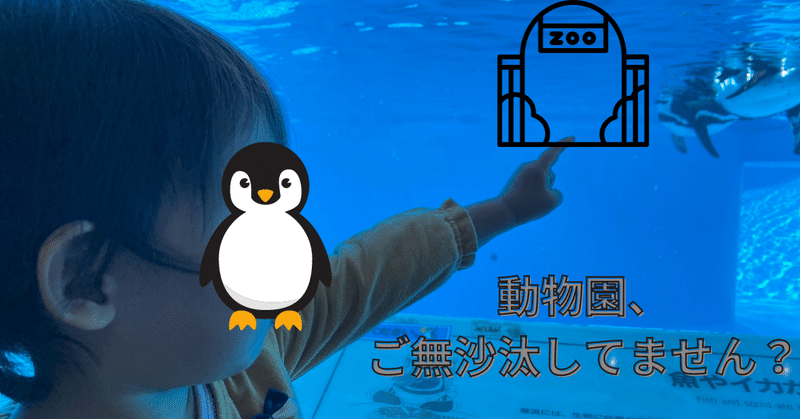
動物園に行ったら、すさまじく非日常な多様性の世界だった
秋のある晴れた日。
2歳になった娘と一緒に動物園にでかけた。
最後に動物園に行ったのは、たぶん中学一年の遠足のとき。
あれから20年。動物たちはどうしているのだろう。
車を駐車場に停め、入園ゲートで券を買う。
ベビーカーを借り娘を乗せたが10秒で降りたがったので、ベビーカーはそのあと園を出るまで荷物置きになった。
そして彼/彼女はいきなり現れた。
動物はうんと遠い存在になってしまった
象。

写真でもイラストでも、数えきれないくらいみたことがある。
もちろん実際に見たことも、これまで何度かあった。
象を頭に思い描けと言われたら、たやすく思い描けた。
けれど、目の前に現れた象のインパクトはすさまじかった。
こわい、違和感がある、なんだこれは。
私の直感は、象を歓迎してはいなかった。
まず、当たり前なのだが鼻が長い。
たしかにあの大きさだと、いちいちしゃがむよりは鼻でひょいと物を取ったほうが楽なのだということはわかる。
理屈ではわかる。
けれどなんだ、あの鼻の長さは。
耳もデカいじゃないか。
脳が目の前の光景を受け入れない。
それに、食べる量がすさまじい。
じゃがいも20kg、かぼちゃ20kg、草20kg…一日で200kg以上食べるらしい。
当然、横に転がっているウンコもでかい。
私はウンコのでかさには自信があったが、一気に自信喪失だ。
その後もクマ、コアラ、ヒョウ、キリン、カバを見る。
生身の肉体を持った彼らがそこにいるというだけで、なんだかどきどきした。
ちょくちょく見かけるヒツジや馬にはそこまでの違和感はなかったから、単に見慣れているかどうかなのだろう。
もちろん、日本由来の動物たちばかりではない。それでも、同じ地球で一緒に暮らしてきた動物たちは、私たちの生活からうんと遠い存在になっているのだなと感じた。
形態進化の多様性
象は鼻が長い。
キリンは首が長い。
アリクイはアリの巣を探すために、鼻や舌が独自の形に進化している。(細い舌が60cmもあって、正直ちょっと気持ち悪い)
それぞれの動物は、地球上のとある環境下で、有限な資源を確保して自分たちが生きて繁殖していけるように少しずつ形を変えてきた。
こんなにもたくさんの動物たちが、それぞれの形ややり方で生きていける居場所がある。
地球というのは、なんと器の広い場所なのだろうと思った。
人間社会のユニバーサルデザインなんて、逆立ちしても敵わない。
一方で、動物の進化にも物理的制約が当然ある。
象の体を支えるためにはどうしても太い足がいるし、目が一つの大型動物がいたら生存競争に不利だろう。
それとは逆に微生物は、あえて多細胞化・長寿命化しないメリットを取った。
制約のある環境下で、それぞれが自分の場所を見つけて生きている。
「どうするのが一番いいだろう」と、最適解をひとつ見つけようとしてしまう自分を振り返って、最適解って無数にあるんだなぁと感動した。
一方で、人が象牙を取るために象をどんどん殺していた時代があった。
そのような環境下では、牙を持つことは象たちにとって不利になってしまう。
その結果、牙を持たない象の割合が短期間で増える結果になった。
このように、人為的な形態変化(進化)が短期間で起こってしまうこともある。
教科書で学んでいるのと、実際に目で見て体感するのは全然違う。
そんな当たり前のことを知った。
地球上をヒトが覆う時代に思うこと
人新世(じんしんせい)という言葉を聞いたことがあるだろうか。
45億年の地球の歴史は、地質学的にはいくつかの時期に分けられる。
大きな区分で見ると、先カンブリア時代・古生代(その初めがカンブリア紀)・中生代・新生代があって、現代は新生代にあたる。
さらに「代(era)」の下には「紀(period)」「世(epoch)」「期(age)」の細かい区分があり、この「世」を新しい「人新世」と呼ぶことが提案されている。
人類の活動が、短いうちに地質を変えてしまったということだ。
地球上はヒトと、ヒトの活動の結果で覆われている。
そんな状況下では、多くの動物は動物園でしか見られない。
檻に入れられてかわいそうという見方もあるが、急速に絶滅の危機を迎えている動物を保護する役割も、動物園にはある。
物理的な個体数という意味でも、私たちヒトの意識の点でも。
科学は、ヒトの社会に役立てられるために為されることが多くある。
国の予算が出るのも、ヒトの病気を治すため、ヒトの暮らしを快適にするための研究に傾いている。
けれど、ヒト以外の生きものの住む環境の急激な変化をおだやかにするための研究がもっとされるべきなのかもしれない。
そもそもヒトも動物も環境も地球も、ぜんぶつながっているのだから。
短期的な成果ばかり追い求めていては、近い将来ヒト自身が消えるのではないだろうか。
まあ、地球はそれを求めているのかもしれないけれども。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
